今日は東京都庭園美術館へ。




奇想のモード-装うことへの狂気、またはシュルレアリスム-。
会期は1月15日~4月10日。
撮影は新館のみ可。
20世紀最大の芸術運動であったシュルレアリスムは芸術という枠を超えて人々の意識の奥深くまで影響を与えた。
モードの世界もしかり。
スキャパレリの創始者エルザ・スキャパレッリなどファッションデザイナーたちもモードに積極的にシュルレアリスムを取り込み、シュルレアリストたちもファッションアイテムを作品の中に取り込んでいった。
この展覧会は、16世紀の歴史的ファッションプレートから始まり、シュルレアリスムがモードの世界にもたらしたセンセーションな美の表現に迫る。
撮影禁止の本館。
Chapter1
有機物への偏愛
Chapter2
歴史にみる奇想のモード
Chapter3
髪へと向かう、狂気の愛
Chapter4
エルザ・スキャパレッリ
Chapter5
シュルレアリスムとモード
Chapter6
裏と表ー発想は覆す
Chapter7
和の奇想ー帯留と花魁の装い
そして新館へ。

Chapter8
ハイブリッドとモード-インスピレーションの奇想
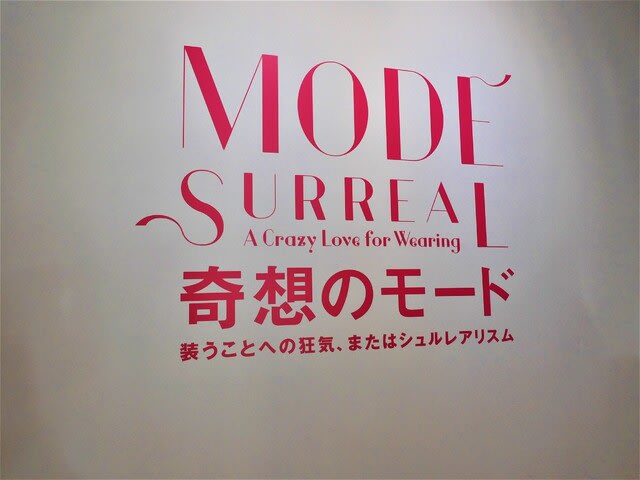
ユアサエボシ、舘鼻則孝、永澤陽一、串野真也の作品群に圧倒される。
















一見、現実離れした奇想にも見えるけど、今現在のモードも影響下にあるのは一目瞭然。来観者のほとんどが若い人。彼等は現実離れした作品を眺めているというより、特に女性からはこんな靴が欲しいという表情を感じた。
ブルトンが「シュルレアリスム宣言」を出したのは1924年。日本では大正ロマン華やかなりし頃。
今を生きる若い人は、どんな時代でも自分の親や祖父母は最初から年寄りだと思っている。私もそうだった。
でもどんな人にだって若い頃はある。そして若い頃はその時代の流行に身を包み肩で風を切って颯爽と闊歩していたのだ。
祖父母、あるいは曽祖父母世代が、意識するしないに関わらずシュルレアリスムに影響を受けた世代なら、その孫・ひ孫世代の美意識にも及ぶ。特にファッションの流行は繰り返す。

お洒落より足腰の不安が勝つようになると、特に装うことはどうでもよくなる。
でも、たまには少し気を使ってみようかな。。。

隣りの科博の自然教育園にはカワセミがいた。

人がいくら頑張ってもやっぱりあなたの装いには敵わないわ。
















