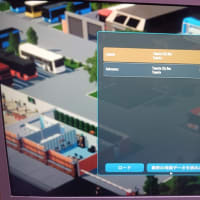前回の記事で神奈中バスの回数券を買った話から、pasmoでのバス利用時の割引き「バス利用特典サービス(バス特)」について簡単に紹介しました。
pasmo導入前に主流だった首都圏1都3県のバスで普及していたものに「共通バスカード」があります。さて、私の地元地域を走る富士急湘南バスでの変化を見ると・・
例えば小田急線新松田駅から山北町(西丹沢やアサヒビール工場など)方面への路線の主な利用者は西丹沢方面などへのハイキングや登山などの行楽客。5~10人以上の団体での利用も多いなど、「観光客の為の路線に数少ない地元など一般の利用者が相乗りさせてもらっている」という状態にです。
たまに私が行楽利用者が居ない時間帯・便に乗ると、乗客は自分だけというのもそう珍しい事でもなく・・よく地方の公共交通は地元の人のもの云々な話がありますが、ここでは「観光客のお陰で路線が維持できている」ような雰囲気。
さてpasmo導入以前はこれら行楽客はバスカードではなく現金払いが多かったです。しかしpasmo・suica導入以降はICカードでの支払いが当たり前に状況に。
首都圏内であってもバスという存在が「乗る人は乗るけど乗らない人は全然乗らない」という状態になっている実情を考えるとバスカードを持っている人は「日常でたまにでもバスに乗る人」
それが「電車で使えるsuica・pasmoでバスにも乗れる」ようになったことで、初めて乗るような路線のバスでも現金ではなくICカードで運賃を支払うことが出来ます。
私の場合は共通バスカード廃止で実質的な割引率が下がった上に、昼割カード(3000円で3900円利用可能)も廃止されて、これまた値上げ感が強く、明らかに以前に較べて乗る回数が減った。というのはともかく・・・
新松田駅から丹沢湖までで片道で900円近い金額、その奥終点の西丹沢まで行くと片道で1200円近い金額。pasmoなら片道1回乗るだけで100円得します。比較的短距離といえる、アサヒビール工場でも往復で700円強。
世の交通機関の割引制度は定期にしろフリーきっぷ類にしろ「利用者が最初に選択して購入して適用される」「存在を知らずに普通に払っていたら適用されない」ものが当たり前。
しかしバスの場合は「バス特」制度を知らなくても、知らず知らずのうちに割引が受けられるpasmoは不慣れな初見の利用者からすればとても便利なシステムです。
といった余談はさておき・・・
前回の記事の終盤で書いた、5000円で850円の割引(約15%)は本当に負担なのか??
という面ですが、ここでいくつか実例を見ていくと・・
 京急バスなど横浜駅や羽田空港からアクアライン経由で房総方面への高速バス
京急バスなど横浜駅や羽田空港からアクアライン経由で房総方面への高速バスpasmoが利用できますがバス特サービスの対象外
しかし多くの路線でその路線ごとの回数券が発売されています
例えば、横浜駅~木更津駅の路線
横浜駅から木更津駅まで片道1550円ですが、10000円で11750円分の回数券を発売していて割引率は約15%。8回の乗車で約15%割引は鉄道の回数券に較べても結構お得な金額です
また横浜駅~館山駅の路線では
片道2550円に対して、回数券は8000円で9600円分(約17%割引)
4回の乗車で約17%の割引が受けられます。
アクアライン系のバスは横浜駅~木更津駅は所定52分で1550円のように、走行距離や所要時間の割に元々の運賃が高い。というのもありますが、注目すべきは「pasmoバス特対象外にも関わらず独自回数券でそれ以上の割引を提供している」という点です。
4回で10%引きぐらいでもいいので、私が乗る羽田空港・横浜駅~御殿場箱根方面の高速バスも回数券を是非・・。
 神奈川県湘南地区の江ノ電バス回数券
神奈川県湘南地区の江ノ電バス回数券江ノ電バスでは4月の消費税増税による運賃値上げにあわせて、なんと回数券の割引率を引上げ
1000円券組で1100円利用可能(9.1%割引)→1160円利用可能(14%割引)
3000円券組で3360円利用可能(11.7%割引)→3530円利用可能(15%割引)
参考サイト>バス回数券情報(消費税5%時代)>江ノ電バス
http://ticket.wiki.fc2.com/wiki/%E6%B1%9F%E3%83%8E%E9%9B%BB%E3%83%90%E3%82%B9
と割引率を上げています。特に1000円券で14%の割引率は結構高いような。
「消費増税だからといって安易に運賃に転嫁していたら乗客が逃げるだけ」という危機感もあるのでしょうが・・・。
 ちばグリーンバスの深夜急行バス
ちばグリーンバスの深夜急行バスちょっと毛色が違う例ですが、新橋・有楽町駅から成田空港第2ターミナルや京成佐倉駅に向かう深夜急行バス。
終電後の足としてまたLCC航空会社の躍進で増えた成田早朝便利用者を狙っている路線ですが・・
こちらは去年12月2日からパスモバス特制度から脱退。
その代わりにICカードを使えば2000円以上の区間は200~300円その場で割引された運賃が引かれる。というシステムに変更
運賃2000円の区間では1800円(10%引)、3300円の区間では3000円(9.1%引)で乗れることに。
さて、思いついた実例を3つほど紹介しましたが、特に上で紹介したアクアラインや江ノ電バスの場合、pasmoバス特システムに拠らずに、15%程度の割引を付与しているのをみると「15%前後の割引が負担が大きく厳しい」と一概に言えるものではないと思います。
また有効期限もないので3~6ヶ月かけて割引を受けながら使い切るような使い方も出来ます。
このような会社や路線独自の割引とpasmoのバス特サービスの大きな違いは、独自の割引は基本的にそのバス会社や路線でのみ通用。バス特は対象の会社のバスなら全て割引が適用されるという点。
通勤通学などで同じバス会社の路線に月に何回も乗るならいいですが、自分の乗る区間が複数の会社が運行していたり、時々あちこちで乗るようなスタイルの場合。
バス特なら例えば月の利用額がA社500円B社300円C社200円とバラバラでも恩恵を受けられるのは乗客側からすれば大きなメリット。
しかし割引を提供するバス会社側からすれば、この自社内で完結しない割引サービスというのが実は結構な曲者なのでは?という感がします。その上、回数券など自社内で完結する割引券は「売った時点でまとまった額の売上になる」という点も見逃せません。
前回の記事でバス特サービスの概要を紹介しましたが、要するに言えば
「乗車するごとに金額に応じてポイントが付与」「ポイントが一定額貯まるとチケットをつける」というシステム
そしてバスポイントを付けた時点で「そのカードがチケット付与されるほど乗るかどうか分からない」という実態を考えると恐らくのところ割引額の負担の仕組みは
(1)月間のバスポイント付与額を会社ごとに集計し各社ごとの付与割合を算出
(2)この割合に応じて月間のバスチケット利用額を各社比例配分で負担
のような形になっているのではないかと推定します。
例えばあるカードで某月に以下の様にバスで利用したと仮定
1回目A社で500円乗車 2回目B社で300円乗車 3回目C社で200円乗車(ここでチケットが付く) 4回目C社で100円乗車(チケット利用)
月間のポイント付与:A社 500P B社300P C社200P→付与割合を算出すると50%:30%:20%
チケット利用:C社乗車時に100円
A社は50円 B社は30円 C社は20円の負担→A社は50円B社は30円、C社に払う
こういった計算を何十万・何百万枚??のカードの利用状況全てを集計した上で行っているとのではないかと思うわけですが、この例でも運賃が高額(ポイント付与が多い)A社は他社への支払額が多く持ち出しになっています。
実際にはチャージ手数料(チャージした会社の取り分)やpasmo社への上納金など色々あると思いますが、バス特システムの割引額の負担はこういう仕組みなのかなと・・。
このようなシステムだとすると
運賃が高い会社→ポイント付与が多い
普段バスに乗らない人の利用が多い会社→チケット利用額が低い
運賃が高く普段バスに乗らない人の利用が多い会社は不利なシステムになっているのではないかなと。
これはあくまで私の推測なので実際は分かりませんが、本当はどういうシステムになっているのか、信頼できる情報源で公表されているのを見たことがないので、実際が分からないのが残念ですが・・・
(友人の関係者の話とかそういう類のは、ネット上なら誰でも関係者になれる世界なので・・・)
Tポイントなど共通ポイントカードでも「ポイント付与分は持ち出し」「加盟側はポイントを使ってくれた方が嬉しい」「なので1ポイントから使えますのように積極的にアピールする」という話を聞いたことがありますが似ているような??
****************
ということで2回に渡りpasmoでのバス利用時の割引制度について見てみましたが・・・、首都圏の多くの会社が相乗りしているpasmoシステム。いくつかの事例をみるに参加各社は決して一枚岩ではなく、損得思惑が色々ありそうに見えてきます。
ここまで詳細を考えるに現状のバス特システムは、1回の運賃が200円前後、概ね5回乗れば100円割引、10回で200円割引(電車の普通回数券と同じぐらいの割引)が大半の、首都圏の中でも東京都区内や横浜など中心部の事業者に最適化して作られたシステムなのかなという気がしてきます。
上で紹介したように、バス特よりも高率な割引を適用した独自の割引を導入したり、バス特適用を終了する会社が増えてくるのか、それともバス特システム自体が改変されるのか??気になるところではあります。
「会社や路線独自の回数券のように先払いが必要だけど割引率が高いもの」と「pasmoバス特のように難しい事を考えずに普通に利用していれば一定の割引が受けられ、高額の先払いも必要ではない」のどちらが便利だといえるのか?
鉄道の回数券や定期券とpasmoどっちがいいのか?のような話にも共通してきますが・・・この辺りは利用頻度やその人自身の性格など人それぞれな部分も大きいでしょう。
例えば上で紹介したアクアラインバスの回数券も、1~2回しか乗らない訪問者や観光客なら、最初から回数券を買うという選択はないので、例え割引率が半分であってもpasmoバス特が適用された方が嬉しいでしょう。しかし回数券を買っても損しない程度乗る常連客からすれば、割引率の引き下げは嬉しくない人も多いでしょう。
「嬉しくない」と書けばソフトな表現ですが、この時代(実質的)値上な値上げは利用者減少にも直結します。
以前にも書いていますが私はsuica・pasmoのシステムはあまり信用していないので、積極的に使いたいほど好きではないですが、色々調べてみると面白いは面白い部分も色々ありますよね。
【広告】楽天市場で「pasmo」を検索
2104/6/8 1:42(JST)