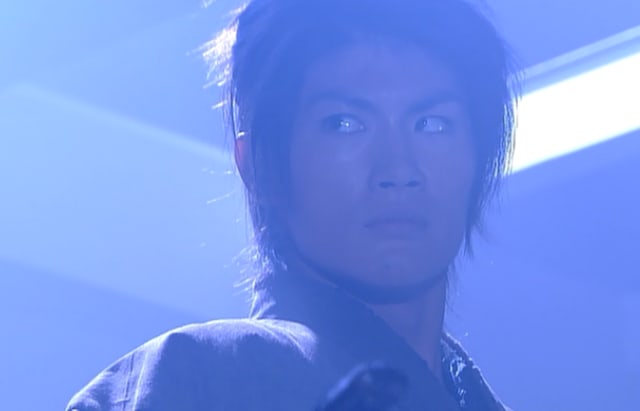第 十 章
「馬作……」
ばあちゃんが側に来て涙ぐんだ。
暖かな囲炉裏の焔でばあちゃんの顔も橙色に染まっている。
「たまたま、山で拾った林檎が井戸の中で
こんなに増えてしまうなんて」
村の者にも林檎が行き渡り、一段落したところで
馬作の村あばら家の前に一台の輿が到着した。

降り立ったのは姫りんご姫である。
村の者も煌びやかな輿に気が付き、何事かとわさわさ集まってきた。
「なんてえ天女みてえな姫さまじゃ」
「あのクマみてえなご領主の姫さまかね?」
「これ、お前さん、聞こえるよ、お付きの女中さまや
若い衆が見張っている」
「それにしてもヨカおなごじゃのう」
「これは姫様、こんなきたねえところへ」
馬作とばあちゃんは走り出て地面に膝をついた。
「おふたりとも顔をお上げください。
今日は改めてお礼を申し上げるつもりで参りました。
父も後日、参る所存でございます」
「ひぇっ!!」
「あ、あばら家ですが、とにかくお上がりくだせえまし」
姫は馬作の小さな小屋のようなあばら家の
囲炉裏の前に座った。
「馬作、そなたのおかげで村の者たちは餓えから救われ
わらわの命も救ってくれました。
なんとお礼を申してよいかわかりません」
「たまたま起ったことを、もったいないお言葉です」
「いいえ、そなたはこの村に続いた姥捨てという良くない
慣わしを断ち切ってくれました。
そのこともお礼申し上げなければなりません」
「そりゃ、オラもばあちゃんとずっと一緒に暮らせる
ことになって、こんなに嬉しいことはごぜえませんよ」
馬作とばあちゃんはにっこり笑って向き合った。
***********************************
第 十一 章
さて、井戸から湧き出た林檎の大群は十日ほどして
ようやく尽きたようだ。
後日、メリケンご一行が林檎をすべて井戸から
取り除きもう一度、調べに入った。
どうやら、井戸の底には植物の栄養源の
鉱物が眠っていたらしい。
一行の求めるものだったので、さっそく領主に
買いたいと申し出た。
これで領主もこの鉱物を使って林檎の栽培を
始めることにする。
**************************
何度春が来て、何度,
林檎の実る秋が過ぎたことか。

林の畑はすっかり林檎の樹で埋め尽くされている。
ある春の麗らかな陽射しの中、林檎の白い花が
咲き乱れ、ミツバチの飛翔が聞こえる日。
畑で梯子(はしご)をかついでいた馬作が
ふと手を止め立ち上がった。
白い衣の仙女が立っていた。
頭(こうべ)には金色のかんむり、
変わったカタチの透けるような打ち掛け、
ぬばたまの黒髪は華のように華麗に結い上げられてある。
言葉も失った馬作。

「わらわの見込んだ通り、よくぞ村を救った。誉めてとらすぞ」
神々しい声が響いた。
一陣の風が吹き、馬作は思わず目を覆った。
白い花がゴウ、と渦巻く。
次に目を向けた時、仙女の白い打ち掛けが
風に煽られて蒼穹に舞い上がるのが見えた。
****************************
後ろに立っていたのはあどけない顔立ちの領主の姫、
姫りんご姫だ。
「馬作、息災でおりましたか」
少女の声に戻っている。
「は、はい、姫さまも大きゅうなられて」
「村が平和になり嬉しゅう思います」
「オラもばあちゃんと一緒にいられて安心じゃ、
いや安心でございます」
「ほほほ。おばあ様孝行でおられますのう。
おばあ様は息災でおられますか?」
ちょうどその時、何本もの林檎の樹の向こうからばあちゃんが手を振った。
「お~~い、そろそろ、メシにすっか」
「両親の代わりにオラを育ててくれたばあちゃん、
ずっと見守ってやりたいと思いますで」
「ずっと?」姫がいたずらっぽく笑った。
「おばあ様は不死のお方ですよ。
永久に見守るということですか?」
「不死?」
「おばあ様ご自身は存じておられるかどうか
わかりませんが林檎の花の精でいらっしゃいます。
その力のためもあって、あんなに井戸から林檎が湧いたのです」
「何じゃと、いや、何ですとっ!?なんで姫さまがそんなことを」
「さあ、なにゆえでしょう」
背伸びして林檎の花を一輪つまむと
そのまま馬作の元に近づき、唇を重ねた。
ほのかに甘い花の蜜が、馬作を蕩けさせた。
<キャストイメージ>
馬作 ―――――三浦春馬
ばあちゃん――――草笛光子
姫りんご姫――― 幼い頃、 橋本環奈
大人になってから 石橋杏奈
★最後までご愛読くださいました読者さまに
厚く御礼申し上げます。
海道 遠
「馬作……」
ばあちゃんが側に来て涙ぐんだ。
暖かな囲炉裏の焔でばあちゃんの顔も橙色に染まっている。
「たまたま、山で拾った林檎が井戸の中で
こんなに増えてしまうなんて」
村の者にも林檎が行き渡り、一段落したところで
馬作の村あばら家の前に一台の輿が到着した。

降り立ったのは姫りんご姫である。
村の者も煌びやかな輿に気が付き、何事かとわさわさ集まってきた。
「なんてえ天女みてえな姫さまじゃ」
「あのクマみてえなご領主の姫さまかね?」
「これ、お前さん、聞こえるよ、お付きの女中さまや
若い衆が見張っている」
「それにしてもヨカおなごじゃのう」
「これは姫様、こんなきたねえところへ」
馬作とばあちゃんは走り出て地面に膝をついた。
「おふたりとも顔をお上げください。
今日は改めてお礼を申し上げるつもりで参りました。
父も後日、参る所存でございます」
「ひぇっ!!」
「あ、あばら家ですが、とにかくお上がりくだせえまし」
姫は馬作の小さな小屋のようなあばら家の
囲炉裏の前に座った。
「馬作、そなたのおかげで村の者たちは餓えから救われ
わらわの命も救ってくれました。
なんとお礼を申してよいかわかりません」
「たまたま起ったことを、もったいないお言葉です」
「いいえ、そなたはこの村に続いた姥捨てという良くない
慣わしを断ち切ってくれました。
そのこともお礼申し上げなければなりません」
「そりゃ、オラもばあちゃんとずっと一緒に暮らせる
ことになって、こんなに嬉しいことはごぜえませんよ」
馬作とばあちゃんはにっこり笑って向き合った。
***********************************
第 十一 章
さて、井戸から湧き出た林檎の大群は十日ほどして
ようやく尽きたようだ。
後日、メリケンご一行が林檎をすべて井戸から
取り除きもう一度、調べに入った。
どうやら、井戸の底には植物の栄養源の
鉱物が眠っていたらしい。
一行の求めるものだったので、さっそく領主に
買いたいと申し出た。
これで領主もこの鉱物を使って林檎の栽培を
始めることにする。
**************************
何度春が来て、何度,
林檎の実る秋が過ぎたことか。

林の畑はすっかり林檎の樹で埋め尽くされている。
ある春の麗らかな陽射しの中、林檎の白い花が
咲き乱れ、ミツバチの飛翔が聞こえる日。
畑で梯子(はしご)をかついでいた馬作が
ふと手を止め立ち上がった。
白い衣の仙女が立っていた。
頭(こうべ)には金色のかんむり、
変わったカタチの透けるような打ち掛け、
ぬばたまの黒髪は華のように華麗に結い上げられてある。
言葉も失った馬作。

「わらわの見込んだ通り、よくぞ村を救った。誉めてとらすぞ」
神々しい声が響いた。
一陣の風が吹き、馬作は思わず目を覆った。
白い花がゴウ、と渦巻く。
次に目を向けた時、仙女の白い打ち掛けが
風に煽られて蒼穹に舞い上がるのが見えた。
****************************
後ろに立っていたのはあどけない顔立ちの領主の姫、
姫りんご姫だ。
「馬作、息災でおりましたか」
少女の声に戻っている。
「は、はい、姫さまも大きゅうなられて」
「村が平和になり嬉しゅう思います」
「オラもばあちゃんと一緒にいられて安心じゃ、
いや安心でございます」
「ほほほ。おばあ様孝行でおられますのう。
おばあ様は息災でおられますか?」
ちょうどその時、何本もの林檎の樹の向こうからばあちゃんが手を振った。
「お~~い、そろそろ、メシにすっか」
「両親の代わりにオラを育ててくれたばあちゃん、
ずっと見守ってやりたいと思いますで」
「ずっと?」姫がいたずらっぽく笑った。
「おばあ様は不死のお方ですよ。
永久に見守るということですか?」
「不死?」
「おばあ様ご自身は存じておられるかどうか
わかりませんが林檎の花の精でいらっしゃいます。
その力のためもあって、あんなに井戸から林檎が湧いたのです」
「何じゃと、いや、何ですとっ!?なんで姫さまがそんなことを」
「さあ、なにゆえでしょう」
背伸びして林檎の花を一輪つまむと
そのまま馬作の元に近づき、唇を重ねた。
ほのかに甘い花の蜜が、馬作を蕩けさせた。
<キャストイメージ>
馬作 ―――――三浦春馬
ばあちゃん――――草笛光子
姫りんご姫――― 幼い頃、 橋本環奈
大人になってから 石橋杏奈
★最後までご愛読くださいました読者さまに
厚く御礼申し上げます。
海道 遠