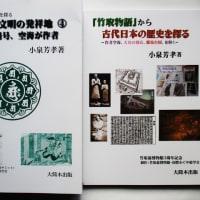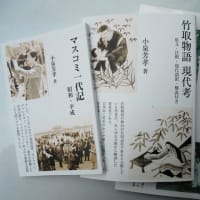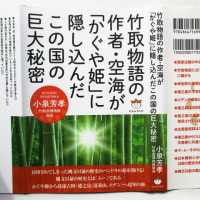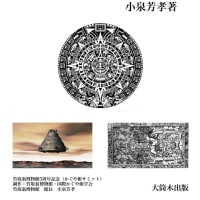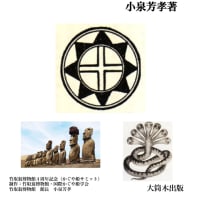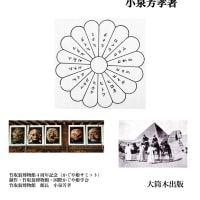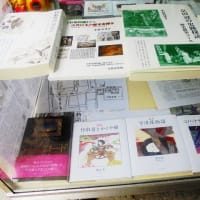竹取翁博物館にて竹取家「春の茶乃湯」を盛大に開催 (竹取翁博物館) 2013年4月14日
春の茶の湯には、竹取物語の「語り」と点心茶会という本格的な「山城かぐや流茶会」をすることになりました。茶席には、4月の季節にふさわしい古民家での囲炉裏(いろり)を使った釣り釜を準備しての「かぐや姫桜花茶会」
春の陽に 泉川ゆく 花いかだ を開催しました。


染色作家の玉井芳泉画伯が描いた竹取物語の襖絵の茶席には、天上から吊された自在鉤(じざいかぎ)が用意されました。この煤竹で出来た自在鉤は、竹取翁博物館の自慢の品であり煤竹の支柱と横木に鯉をあしらった年代物で風情あふれる古民家での「かぐや姫桜花茶会」となりました。
出席者には大阪や奈良から表千家の先生方、小堀遠州流の茶人ら10名が集まり本格的な点心茶会となりました。




開催日 2013年4月14日(日)
時間 10時半~竹取翁博物館の本館見学 小泉館長が展示説明
11時~ 〃 別館①「かぐや姫館」
竹取物語の「語り」言語造形家の村上恭仁子さん (銅鑼付)
「薄茶」 亭主は陶芸家の植村貞澄さん
12時半~ 「点心懐石」 料理家の堀敦子さん
14時~ 「濃茶」
15時半 終 席
主催…竹取翁博物館、恭仁陶芸 竹取家
茶会に先立ち10時半から開かれた竹取翁博物館本館の見学は、小泉館長から概略を説明したあと展示物を見ながら五人の貴公子などの説明を交えて作者空海説も述べられました。また、庭に特設された「かぐや姫神社」では、「子宝の神」と「多宝の神」「宝石の神」にあやかろうと竹筒に賽銭を入れて頂き願い事をしたためておられました。







11時からは、別館①「かぐや姫館」である竹取家において言語造形家の村上恭仁子さんによる竹取物語の語りを聞きました。
まず、開始の銅鑼が鳴り響いたあと竹林の襖絵が空けられ
今は昔、竹取の翁といふものありけり、
野山にまじりて、竹を取りつつ、萬の事に使ひけり…
から始められ、茶室の周囲に描かれた竹取物語にふさわしい幕開けとなりました。



このあと亭主の植村貞澄さん(陶芸家)の手前で薄茶を頂きました。御菓子は、加茂町の「小間安老舗」の「いづみ川」最中と「とうのう」干菓子でした。床の間には、青竹に「かぐや姫の誕生シーン」をあしらった人形が掲げられました。また、近代に生まれた線の探究者で “忘れられた巨匠”といわれる吉川麗華(きっかわ れいか)の『桜狩り』と近代日本画壇に燦然と輝く天才日本画家 菱田春草(ひしだ しゅんそう)の掛軸『黒猫』も掲げられました。



出席者のご婦人は、かぐや姫茶会なので「貴公子の描かれた帯」を締めた着物を着てこられ雰囲気を盛り上げていました。


あと一人の手前は、今年奈良女子大を卒業した小堀遠州流の村上さんに手前も披露して頂きました。 普段は表や裏千家の先生方でしたので「裏や表千家の手前とは全然違うね」と目を白黒して見つめておられました。


この後の点心には料理家の堀敦子さんが手作りした懐石点心を頂きました。
八寸、筍木の芽和え、胡麻豆腐、それに「かぐや姫桜花茶会」にふさわしい桜をあしらった「桜ご飯」など素材の味を生かした味付けで一品一品味わいながらいただきました。
その後、濃い茶席に移り、陶芸家の植村さん手作りの大仏茶碗などで濃い茶を頂き、一段と「桜花茶会」の風情をかもしだし優雅なひと時を過ごしました。
『追加』
近代に生まれた線の探究者で “忘れられた巨匠”といわれる吉川麗華(きっかわ れいか)の『桜狩り』。幼少より漢籍に親しんでいた霊華は、金鈴社の時代に引き続き、中国の詩や説話に題材をとった作品を描き続けています。幻の画家と言われ、徹底的に東洋芸術の古典を研究し、線描の美しさを追い求めた霊華の作品のクオリティーが圧巻です。
霊華は、絵と同等に書を好んだ画家で、余白に仮名文字の書を書き散らしているのが特色で、作品の特徴である細い線描の美しさを、より近くで見ないとその実感を鑑賞できない。この『桜狩り』という作品は、貴公子と思われる人物が馬に乗って桜狩りをしている様子が描かれています。作品は犯しがたい気品と高踏な雰囲気が醸成されています。
近代日本画壇に燦然と輝く天才日本画家 菱田春草(ひしだ しゅんそう)の掛軸『黒猫』
。
金に銅を混ぜた赤金と、金に銀を混ぜた青金の金泥を使って描いた光り輝く美しい色合いの柏の葉と、その幹に座る艶やかな黒猫が見事に調和した作品です。
黒猫はふわふわとした毛並みを見事に表現し丁寧に描かれています。重要文化財にも指定される菱田春草画伯の名作です。
黒猫 赤金と青金の金泥を使って描いた光り輝く美しい色合いの艶やかな黒猫を見事に描いた躍動的な作品です。「塗る」絵画ではなく、「描く」絵画特有の、生き生きした描線の動きが特色です。