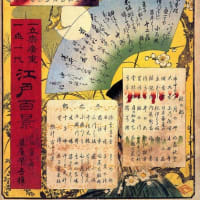名所江戸百景を訪ねて
名所江戸百景
第105景 「小梅堤」

本所の北、隅田川東岸にあった小梅村の風景を描いています。
曳舟川の始点近くの堤から北を望んでいます。
近景には色づいた葉をつけた榛の木(はんのき)が描かれています。その下では子どもたちと犬がじゃれ合って遊んでいます。
描かれている橋は手前から八反目橋、庚申橋、七本松橋です。
曳舟川


曳船川由来碑曳船川の由来曳船川は、徳川幕府が本所開拓に伴う上水として、万治二年(1659年)に開削したものです。当時は、本所上水、亀有上水などと呼ばれ、瓦曽根(現越谷市)の溜井から分水して、亀有から四ツ木をへて本所と深川の各地に配水されたようです。その後、享保七年(1722年)に上水としては利用されなくなりましたが、川筋の脇を四ツ木街道が通り水戸街道に接続しているため、次第に重要な交通路として利用されるようになりました。この川が「曳船川」と呼ばれるようになったのは、「サッパコ」と呼ばれる田舟のような舟に旅人を乗せ、岸から引かせたことによるものです。また、曳船川には古くから多くの橋がかけられており、薬師橋、鶴土手橋、地蔵橋、庚申橋などの名前が文献に見られますが、この付近(小梅児童遊園)にも八反目橋が架けられていました。このあたりの小梅という地名は、元は梅香原(うめがはら)と呼ばれる梅の木の多い地域だったことによるもので、八反目の名も八反梅(八十アールの梅林)からきているとの説があります。昭和二九年六月東京告示によって川としての役割は廃止され、昭和三十年代を中心に埋め立てられ、道路として整備されました。平成五年三月 墨田区
榛の木
(はんのき)

出典・Wikipedia
古名を榛(はり)といいます。
日本では、北海道から九州、沖縄まで分布します。
低地や湿地や低山の川沿いに生え、日本では全国の山野の低地や湿地、沼に自生します。
湿原のような過湿地において森林を形成する数少ない樹木です。
田の畔に植えられ、近年では水田耕作放棄地に繁殖する例が多く見られます。
水田の畔に稲のはざ掛け用に植栽されています。
描かれた場所は
現在どのようになっているのでしょうか?
訪ねてみました。


実際に描かれた場所は、現・小梅児童遊園のある辺りから曳船川を望んだ景色のようですが、とうきょうスカイツリー駅北の交差点から曳船通りを撮影しました。
曳船川は現在埋め立てられ、道路となっています。
現在は、ビルが建ち並び、江戸時代には見えていた向島秋葉神社は見えません。
木の代わりに電信柱、舟の代わりにトラックって所でしょうか。
最後に
江戸時代にはのどかな田園風景の広がっていた場所。
現在では川は埋め立てられ、ビルが建ち並んでいます。
緑が少なくなったこと、ちょっと残念に思いました。
参考
Wikipedia
太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅