
多様な生態系がバランスよく存在し、季節による変化が激しく、生物多様性に富んでいる、そんな理想の聖域を追い求めた写真集。
知床に残された手つかずの自然に身を置き、その激しい変化と光り輝く生命の営みを克明に撮影。
第1章 春―海と陸が出会う潮間帯
第2章 夏―ヒグマの楽園
第3章 秋―海から回帰する
第4章 冬―北半球南限の流氷
メス熊は特定の谷に居つく傾向があるのに対し、オス熊は、半島全体を行動圏にするほど広い範囲を歩きまわる。そうやって移動することで、あちこちにいる複数のメス熊と出会う機会を増やしている。
アイヌは、母熊が冬眠しているときに冬眠穴を見つけ、トリカブトを塗った矢でこれを獲った。中には生まれたばかりの赤ちゃん熊がいる。それを殺さずにコタンへ連れて帰り、1~2年、まるで家族の一員のように大事に育て、飼うのが危険になったころ、特別の儀式をして子熊をカムイの国に送り返した。この儀式がイオマンテである。アイヌ語では、イ(それ)オマンテ(送る)という意味だ。カムイのように尊いものの名はうかつに口にはできないので、あえてイ(それ)というのである。
卵を産むためとはいえ、わざわざ死ぬために戻ってくるのは、あまりにむなしいことのように思われたのである。確かに赤ちゃんのサケには、お腹に栄養を入れた袋がついていて、しばらくはそれで生きのびられるだろう。だが、そのあとは?--赤ちゃんサケが生まれた産卵床のまわりには、たくさんのプランクトンが生まれて、それが赤ちゃんサケの餌になってくれるのだ。そのプランクトンはどこから来たのか?産卵床のまわりで息絶えた、赤ちゃんサケのお父さん、お母さんの体から来たのだ。サケのお父さんやお母さんが、産卵床のまわりで死んでいくことには深い深い意味があったのである。それだけではなかった。雪に埋もれたサケたちの死骸を、冬には、キタキツネやオオワシ、オジロワシが食べにくるのである。
産卵を終えてその場所で死ぬことは、無意味でもむなしいことでもなく、そのこと自体が、自然の生態系を支える重要な行為だったのだ。
確かに










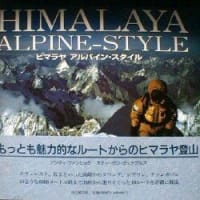
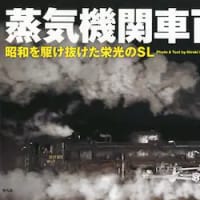
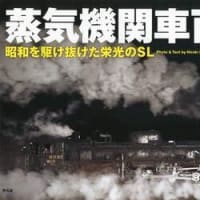
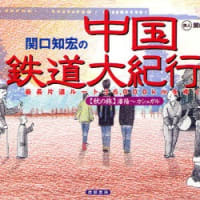
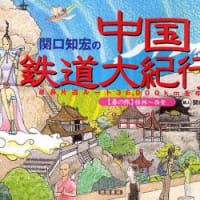
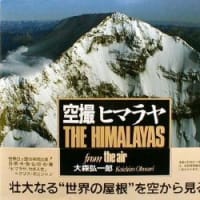

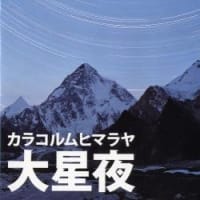
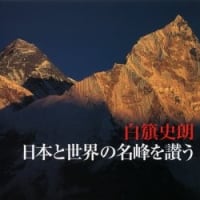
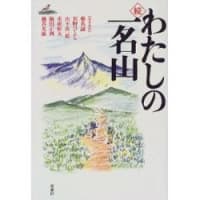
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます