楽しみにしていた映画「道~白磁の人」 を公開初日の9日に見に行った。林業技師として朝鮮半島の荒れた山林を生き返らせた浅川巧の生涯を描いた高橋伴明監督の作品である。江宮隆之著『白磁の人』(河出書房新社、1997)にもとづいて林民雄が脚本を書いた。
1891年に山梨県で生まれた浅川巧は、1914年に23歳で母や兄(伯教)のいる朝鮮半島に渡って朝鮮総督府農商工部山林課に就職、同僚の職員チョンリムとともに多くの山林を緑化復元に取り組む。当時の朝鮮半島は日本統治下にあったが、浅川は朝鮮語を覚えるなどして自分から進んで現地の人々に溶け込もうとする。だが、さまざまな差別と弾圧を受けていた朝鮮の人々は日本人にたいして心を許すことはなかった。朝鮮独立運動が高まるなか、日常生活で普通に用いられていた白磁に魅かれ、無名の職人が作った朝鮮工藝の美しさを高く評価した浅川は、1924年、柳宗悦らとともに朝鮮民族美術館を設立する。自らの信条にしたがって朝鮮の人々と共に生き、その山林と文化を守った浅川に多くの人が感銘を受け、白磁のような人と讃えた。1931年、肺炎のために41歳の若さで亡くなった浅川の葬儀には、その死を悼む朝鮮の人々がつめかけ、競ってその棺を担いだといわれる。1931年、今からほぼ80年前のことである。彼のお墓は今もソウル市忘憂里(マンウリ)の共同墓地にある。
映画を見て、あらためて浅川巧の純粋さと民族を超えた友情の深さに打たれた。だが、それだけで終わってはいけないと思った。政治によって否応なく引き裂かれた民族どうしの人間的なつながりという重い課題を自ら引き受けた浅川巧の生き方。そこには、政治体制、芸術(生活に根ざした美的感性)、自然との共生といったテーマが、一つの軸でつながって相互に関連しあう問題として提起されている。
山梨県北杜市高根にある「浅川伯教・巧兄弟記念資料館」を私が最初に訪れたのは、2006年のことだった。そこで、ふと目に留まった椙村彩著『日韓交流のさきがけ 浅川巧』(揺藍社、2004)という本を手に取ったことが、浅川巧についてもっと知りたいと思うきっかけになった。中学生だった椙村さんが、母校の高根西小学校の先輩である浅川巧について、文献だけでなく実際に韓国を訪問して足跡をたどって書いた自由研究のレポートが出版されたもので、永六輔さんも推薦文を書いておられる。ひとりの中学生をここまでひきつけた浅川巧の魅力とは何か? それを探りたくて『白磁の人』や高崎宗司著『朝鮮の土となった日本人―浅川巧の生涯』(草風館、増補三版2002)などを読んだ。
(資料館のある高根ふれあい交流センターで浅川巧シンポジウムが行われると聞いて、なんとか参加したいと思っていたが、6月13日から配布された360人分の整理券が当日のうちに定員に達し、終了したそうだ。残念!)
 |
日韓交流のさきがけ-浅川巧 |
| クリエーター情報なし | |
| 揺籃社 |
 |
白磁の人 (河出文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 河出書房新社 |
 |
朝鮮の土となった日本人―浅川巧の生涯 |
| クリエーター情報なし | |
| 草風館 |
前に書いたブログ記事「中学生の著書」










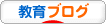

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます