白内障で両眼を受けてから間もなく2週間になる。これといった自覚症状もなく順調に回復しているようだ。老人にはありふれた、リスクの低い手術らしいが、手術を決意するまでにはかなりの時間がかかった。もう、この年齢では進行しないと思っていた視力が1年以上前から急激に落ちていった。反射防止の眼鏡をかけていても、まぶしい。今年に入って受けた健康診断で、黒目が小さくて眼圧が測れないので専門医に行くように勧められたのがきっかけだった。医師から「生活に不便だったら手術を考えてもいいでしょう」といわれたとき、残り少ない人生を、これからどういう生きていくかを問われているように感じた。遠い風景はもちろん手元の文字も面と向かって話している相手の顔も滲んでみえる状況は、他の身体機能と裡から湧き上がってくる意欲にくらべて、きわめてバランスが悪く、日々の活動や思考も制限されている。そこに「緑内障の疑いもありますね」という医師の言葉が追い打ちをかけた。「近視」と「視野狭窄」って、最近の自分の言動を象徴的に言い当てていないか。それが、これからも進行するのを放置したくないと思った。
軽い手術で2泊3日の病院生活は、ある意味で快適だった。頭をやすめ、ゆったりとした規則正しい生活を送る状況に自らをおく。質素な病院食は美味ではないが、栄養バランスはとれている。それで物足りなければ、コンビニはもちろん、おしゃれなカフェやレストランもある。移転して間もない真新しい神戸市民病院には、一人でくつろいだり人と話ができるスペースが、あちこちに設けてある。(こうした設備は、もちろん入院患者だけでなく、すべての来院者に開放されていて、これまでも検査に来たついでにホールで行われていたミニコンサートを楽しんで帰ることもあった)
手術をしたからといって視力が完全に回復したわけではない。読み書きがしやすいように比較的短い距離で焦点が合うようにしてもらったので、遠方の風景はぼやけたままだ。それでも、多少の不便を我慢すれば眼鏡をかけないまま外出できるようになった。世界はこんなにも大きく色鮮やかだったのか! 裸眼で見るモノや活字は、これまで見慣れていたのより一回り以上も大きかった。色彩感覚にも変化があった。これまで私を虜にしていた緑のグラデーションが後退し、青系統の色、とりわけコバルトブルーが強烈に飛び込んでくる。気がつくと、普段使いの洋食器の大半がコバルトブルーで、いつも利用するJRの駅前には淡路島と明石海峡大橋を望む海と空が広がっていた。
退院するとき、ずっと気になっていたことを医師に尋ねてみた。「この手術で視力はどこまで回復しますか?」返ってきた答えは単純明快だった。「視力は、その人の見る力なので、同じ手術をしても人によって異なります」。なるほど、1.0とか1.2といった数値は指標であって視力そのものではないということか。私が気にしていたことは、「学力」は「学ぶ力」なのに、指標にすぎない成績(点数)にこだわるのに似ている。火事場の馬鹿力の喩えを引き合いに出すまでもなく、人の「力」は諸条件によって常に変動することを私たちは経験的に知っているではないか。
退院後はじめての講義で学生から「メガネのない先生はなんだかヘン」の声。自分でもそう思う。見慣れていないからだけではない。子どもの頃から眼鏡に合わせて自分の顔がつくられてきたのだろう。
こうしてさまざまなことに気付かされた術後の2週間だったが、退院のときには新鮮だった風景も自分の顔も、しだいにありふれたものになろうとしている。それでも1日4回の点眼のときや就寝前には、きまって片手を目の近くにもっていって眼鏡を外すしぐさをしてしまう。
【追記】
自分の視力の話を書いているうちに、ふと、首相には、いま、この国がどんなふうに見えているのだろう? と思った。8日に行われた記者会見で野田総理は稼働停止中の原発について「国民の生活を守るために再稼働を」と訴えたが、その内容は、まるで「再稼働が必要だ」という題で書いた作文だった。「電力が足りない」「原発は安い」といった不確かな情報、40年も繰り返されてきた「安全」という言葉も空虚に響く。理屈は何とでもつけられるが、福島で起こっていることは大飯やその他の場所では起こらない(起こさない)と、どうして断言できるのか。国論が二分されているわけではない。多くのアンケート結果やメディアの論調をみても、いま再稼働に踏み切るのは反対あるいは慎重であるべきという意見が大半をしめる。記者会見で訴えるべきは、中長期的なエネルギー政策の方向を明らかにして、国民とともに眼前の不安と苦境を克服していこうという気概ではなかったか。
この首相の視界には、自分を取り巻いている官僚と経団連の人たちだけしか入っていないのだろうか。その向こうにいる国民一人一人は遠景にかすんでしまっているらしい。福島の現実をこの国全体の(そして人類全体の)問題と受け止められない想像力の欠如が怖い。
(では、これからの日本は、どのような方向に進むべきか。2012年04月19日に放送された、報道ステーション「原発再稼動わたしはこう思う」最終回でのエコノミスト・浜矩子さんの指摘を、あらためてかみしめてみたい。どこか平川克美氏の『移行期的混乱』や『小商いのすすめ』にも通じる話だ)
 |
移行期的混乱: 経済成長神話の終わり (ちくま文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 筑摩書房 |
 |
小商いのすすめ 「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ |
| クリエーター情報なし | |
| ミシマ社 |














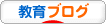
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます