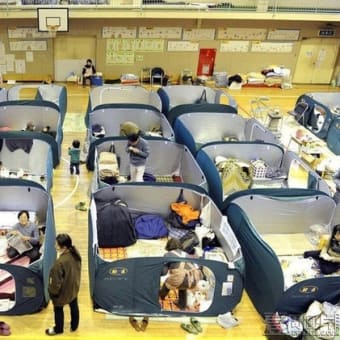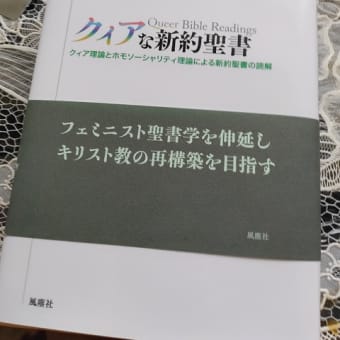病院勤務していた頃の話。
その時は請負での仕事であった。ある日文書が回ってきた。こんな感じの内容だった。
「当直帯に入る際、ミーティングを行うことになった。当直の看護師、検査技師、薬剤師、事務は、16:45に救急室前に集合すること。」
加えて「16:45に集合不可能な場合は当日の当直以外が代理で参加すること。」こんな感じであった。
僕が勤務していた当直事務の勤務時間は17:00からであったので、16:45に参加することは不可能であった。「代理が参加」ともなっていたし、この文書を渡してきた病院スタッフも「そういうことだと思います」と伝えてきた。
僕が行っていた病院当直事務は業務形態として、請負であった。だから、当然時間前の業務をする必要はないので、当直事務にはほぼ関係ないと受け取っていた。
そのため、なんとはなしにこの文書を受け取っていた。僕自身が当直事務のリーダー、正式には**マネージャーとなっていた。**はなんだったか忘れてしまった(笑)。
請負は組織の命令系統に入らない。この場合、病院の中にある命令系統に入らないで、独自に仕事を行うのである。これは請負を選択した雇用主(この場合は病院)、そして請負業者(この場合、我々が所属する会社)との間での契約である。だから、病院は当直事務を病院の命令系統に入らないこと、この場合は病院事務の命令系統には入らないことを自ら選択したのである。
ちょうど小泉政権が派遣法の改正を行い、事務業務が請負に適していないのではないかと議論になったが、当時の政府が「日本人は節度を持てるから、問題は起きない」程度に答えていた。適当なもんだよ、いつも。ちなみに派遣は勤務先の命令系統に入ることになるので、両者は異なる業態になる。
例えばマンション建築をする場合、水道管の工事を請負が行う。建築を行う施工会社は、さすがに水道管の工事自体はできないので、水道管工事の専門の会社に請け負ってもらう。事前に図面や工費などの相談はするが、現場では施工会社が水道管の請負業者にいちいち工事方法を指示することはない。当たり前だ。そのような知識も技術もないのだから。
この場合、請負業者は水道管工事以外はもちろん関係ない。もし施工に関して問題があれば、事前の相談がなされる。もちろん同じ現場で仕事をするので、顔見知になったり、話をしたりはするであろう。そういう中で、工事についての話もあるに違いない。ただ、それぞれ仕事の指示をしたり、されたりはない。それがプロってもんであろう。
僕たち病院当直事務も契約先の病院スタッフともうまくやっていた。ただ、彼らに請負とはなんであるのかを知る者は少なかった。そこでは経営に携わる部署の人たちは、請負が命令系統に入らないことを認識していた。ただ現場の人間はそうではなかった。命令系統などという”子面倒臭い”こととは別に、命令っぽいことを言ってくる者はいた。その場合、僕が防波堤になって「当直の仕事じゃないでしょう」などと誤魔化していた。まあどうにかやりくりしていたわけだ。
ところが、16:45の当直のミーティングの件でトラブルが発生した。
(つづく)