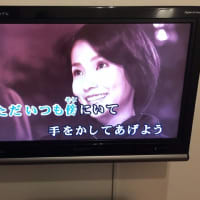夜中の2時過ぎにスマホの警報音で目が覚めました。石川県で大きな地震があったようですね。被害の状況はわかりませんが、特に能登方面の方々、どうかお気をつけください。
さて、13日の金曜日ですが、仏教系の我が家では関係なく😅 、今日は祖父の月逮夜(つきたいや)です。祖父は、30年前の4月14日に亡くなったんですが、亡くなった日である14日の前日13日の朝に、毎月住職さんがお参りに来てくださいます(なぜ前日なのかは知りません。そういえばこういう法事関係はだいたい前日とか前年にやりますね。また訊いておきます)。
我が家では、祖父、祖母、父、曾祖母の4人の月逮夜参りがあるんですが、毎回お金を払ってますので、あんまり回数が増えるとお金もかかるので、住職さんが「近い日の二人をまとめて一緒にしたりして少なめに」と言ってくださって、月3回の逮夜参りをしてもらってます。

まだ40代のお若い住職さんです。お父さんがガンで手術をしてからお寺の仕事ができなくなったので、一般企業をやめて、お寺を継いでいらっしゃいます。話がしやすいので、お参りのあと、お茶を出して、お家族の話などしながら、いろいろと思うところを毎回聞いたりしています。
お参りは、短いお経を読み上げてもらい、一緒に手を合わせて「南無阿弥陀仏」を唱え、そのあと「御文書」(「おふみ」ともいって蓮如上人(だったかな?)の手紙(だったかな?))を読み上げて、終わり。
そのお経というのが、だいたい毎回、「こうげんぎぃぎぃ~」と始まるのです。なんか錆びた扉を開けるような(笑)と思ってたので、それは何か訊いてみました。
それによると、「嘆仏偈」(たんぶつげ)という、元は「大無量寿経」の一節らしいのですが、「こうげんぎぃぎぃ」は「光顔巍巍」という字で、お釈迦さんが光り輝いていいらっしゃるようすなんだそうです。まぁ、「我々には思い及ばない素晴らしいお釈迦さんの教えがあるから、心配せんとそれに身を預けたら救われるよ」という感じでしょうか。浄土真宗であげられるお経って、だいたいそんな感じなのかな?(間違ってたらすみません)
で、住職さんがおもむろに経机(きょうづくえ)の下に置いてある「在家勤行集」という小さな本を取り上げてページを開き、「ここにあるんですよ」とニッコリして見せてくださいました。おお、この本のこと、ずっとあるのは知ってたけど、「コーゲンギーギー」は知らなかった! いやはや、よくわかっていないものですな。😓
というわけで、今朝は一つ勉強いたしました。いっぺんあげてみてもええかもな。

月逮夜のたびにお花とお供え物を整えるんですが、お供えは果物とお菓子。今日のお菓子は、隣町の信貴山の名物「虎饅頭」です。顔はコワいですが、古風な味で美味しいです♪😋
一つ疑問が解けました、というお話でした。😊