タイトルに2桁の番号をふってしまったが、果たしてそんなに続くだろうか。
1000年アーキテクチャーを考えるに当たって、まずは1000年残っているものは何か考えてみたい。
例えば奈良の法隆寺。1000年以上前に立てられた寺で、今も多くの人が訪れている。これは正に活きている遺産だと思う。これを人との関わりで整理したいと思う。まずはお坊さんがいる。お寺の主である。次に参拝者がいる。訪れる人がいるからこそ活き続けるのだと思う。そして火災などによって壊れた場合でも修復する宮大工がいる。システムとして考えた場合、建物と言う器があって守る人がいて、訪れる人がいて、修理する人がいる。どうやらこの3種類の人との関わりが器を1000年持たせるのに重要な役割をしているのではないかと思う。建物は器であって、本来の価値はそこにいるお坊さんの説法だったり目に見えないものが価値なのではないかと思う。しかし、時が経つにつれ建物自身も価値があがって、今ではただ見てみたいと言う理由で訪れる人が大半なのではないかと思う。僕たちSEからすると古い=負の資産と言う感覚なので、古くなって価値が上がると言う仕組みは興味深い。










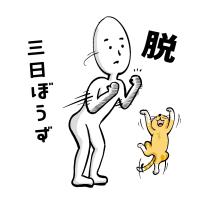
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます