
〘 年末年始は贈り物の季節。大切な人へのプレゼントは丁寧に包んで渡したいと思う人は少なくないでしょう。そこで考えてみたいのが風呂敷。日本国内の歴史的資料や芸術作品にも頻繁に登場してきたこの布は、実用品や贈答品として、さまざまな用途で使われてきました。この伝統文化は時代に合わせて変化しており、今日ではその価値が国内外で見直されているのです。
そもそも日本人は古くから包み物を大切にしてきました。勅撰の歴史書『続日本紀』には「天下百姓右襟」とあり、養老3年(719年)に衣服の袷の方向が法令で定められたのです。着物の着方が法律で定まり、それを基にしながら、包みの方向が慶事は右包み、弔事は左包みと定着していきました。縁起を重視した日本人の伝統や風習は、無言の志として相手を思いやる気持ちが表現されていますが、慶弔や贈答における包み方の作法は現代でも受け継がれています。
「風呂敷」の名称は、戦国から江戸時代にかけて、特に銭湯における湯具としての風呂敷包みから広まったと言われています。江戸時代の文学人、井原西鶴 の作品にも度々登場していますが、当時の木綿風呂敷は、徳川家康の遺産目録にも(包み物ではなく風呂の敷物として)含まれていた高級品でした。大名をはじめとする限られた人々に愛用された風呂敷は、この時代に大衆の間でも爆発的に普及していきます。その後、明治時代に平民が苗字や家紋を持つことを許されてからは、各家の紋章デザイン文化が隆盛し、さらに長寿や子孫繁栄の象徴とされる唐草文様の風呂敷が大衆に人気を博しました。… 〙
〘 …『世間胸算用』
[せけんむねさんよう]
元禄5(1692)年に書かれた西鶴晩年の作品で、5巻20章の短編集です。副題は「大晦日は一攫千金なり」
『日本永代蔵』では商家を紹介し町人の心得的なものを面白おかしく描いていたのに対し、この『胸算用』は、大晦日の一日に焦点を合わせて、借金取りから逃れるために手を尽くす借家人とそれを追いかける借金取りの駆け引きを描いた切実なテーマです。
江戸時代の商取引は、つけ払いが一般的で取引相手とは各月の最後の日(晦日 みそか)に集金人が店に来る形で支払いをしていました。12月31日はその年の晦日の最終日なので大晦日となります。
主な作品
作品は「世の常は大晦日は闇なること」の一説から始まります。大晦日は旧暦で闇夜にあたることと、支払いの締め日で憂鬱な気持ちとを重ねています。
正月のお飾りには伊勢海老がないと始まらないという商家の話(巻1の3「伊勢海老は春のも栬」)、持っていくものが何もないなら、柱をもっていくという強者の借金取り払わなくてもお縄にはならないと開き直っている借り手の話(巻2の4「門柱も皆かりの世」)、ぐうたら亭主と亭主のために仕方なく乳母として働く妻の話(巻3の3「小判は寝姿の夢」)
内容と対照人物
なかでも「小判は寝姿の夢」はぐうたら亭主でありながら、妻の勤め先のご主人が妻のような女が好みかといううわさを聞いて、引き戻してしまうという、ほろりとさせる内容です。
描かれているのは商人だけでなく、つけ払いでも買い物ができないような階層の人々にもスポットを当てています。
大晦日が今よりももっと大変な日だったこと、江戸時代の町人のたくましさを感じさせる作品です。… 〙
〘 …『新釈諸国噺』とは、12編の短編から成る太宰治の作品集のことで、江戸時代の浮世草子・人形浄瑠璃作者であった井原西鶴の著作の中から、太宰自身がお気に入りの作品を選んで現代語訳をし、独特の趣向を凝らして描かれた作品集となっています。
太宰は冒頭の「凡例」で次のように述べています。
西鶴は、世界で一ばん偉い作家である。メリメ、モオパッサンの諸秀才も遠く及ばぬ。私のこのような仕事に依よって、西鶴のその偉さが、さらに深く皆に信用されるようになったら、私のまずしい仕事も無意義ではないと思われる。
ちなみに『貧の意地』の元になっているのは、(井原西鶴『諸国はなし』巻一の三、大晦日おほつごもりはあはぬ算用)です。… 〙













![【浮世草子】町人の生活を描いた小説!井原西鶴の代表作品を紹介[簡単解説]](https://watsunagi.jp/wp-content/uploads/2019/01/ihara_00.jpg)

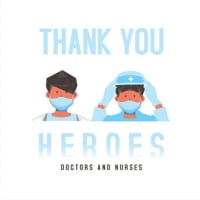













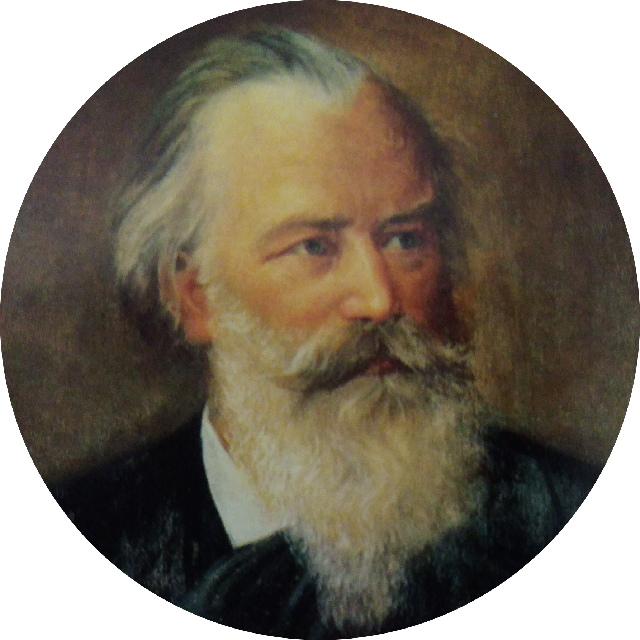

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます