バスを降りて室生寺へ。
室生寺前とはいうものの、室生寺までは徒歩5分くらい。
土産物屋がならぶ道路を歩いてゆきます。
室生寺は役の行者が開き、その後弘法大師が中興した、と思っていたのですが、
お寺でいただいたパンフレットによると、奈良時代の末期に山部親王(後の桓武天皇)の病気平癒の祈願が、
この地で興福寺の高僧賢憬らによって行われ、
これに卓効があったことから勅命によって国家の為に創建された、とあります。
以来、室生寺は山林修行の道場として、また法相・真言・天台など、各宗兼学の寺院として、
独特の仏教文化を形成したようです。
中学校の時に「弘仁貞観文化」としてこの室生寺を知ったのを覚えています。
さて、室生川にかかる太鼓橋の向こうに雪を載せた室生寺表門の屋根が見えてきます。


拝観は、右に曲がって赤門の奥にあるところで拝観料を払って。
仁王門が見えてきます。




仁王門をくぐると左手に梵字池があって、その先には鎧坂。
鎧坂の向こうに金堂が見えてきます。
金堂自体が国宝で、屋根はこけら葺き。
今日は雪が積もっているので、その屋根の様子ははっきりとしません。
この金堂の中には国宝の本尊、釈迦如来立像、
これまた国宝の十一面観音菩薩像や、重文の薬師如来像、地蔵菩薩像、文殊菩薩像。
そして横一列にこれまた重文の十二神将像が並んでいます。
十二神将像の二体は現在奈良国立博物館のなら仏像館でみることができます。
これだけ揃うと壮観です。






金堂の左側には弥勒堂。
内部の趣味壇には本尊の弥勒菩薩立像(重文)、その向かって右側の脇壇には釈迦如来坐像(国宝)。
どちらも遠くにしか見えないのが残念。
金堂といい、弥勒堂といい、オペラグラスを持ってゆけばよかったと後悔。


弥勒堂からまた石の階段を昇ったところにあるのが本堂である灌頂堂。
ここに、五重塔の内部に安置されている五智如来像が特別公開されていました。
ここは特別拝観料が必要です。
拝観料を払うとここに飾られている金剛界曼荼羅、胎蔵界曼荼羅がプリントされたクリアファイルがもらえます。





さて、金堂に続いてのメインともいえる五重塔。
五重塔は灌頂堂からすぐ。
奈良市内には海龍王寺を代表とする、建物のなかにある小塔何基かあるのですが、
この五重塔は屋外に建つ問うとしては最小のもので、16.1m。
興福寺や薬師寺、長谷寺などの塔と比べると、本当に小さな、
でも、その桧皮葺の屋根と丹塗りの柱のバランスはすばらしいものです。




この塔の初層が開窓されていました。
柱に何か描かれているあるかと思ったのですが、何も描かれていませんでした。


さて、ここから奥ノ院へ向かいます。
高野山の奥ノ院には現在でも弘法大師が生きておられるということですが、
さすがにここではそんな事はないようです。
奥ノ院へ向かう階段からの五重塔。















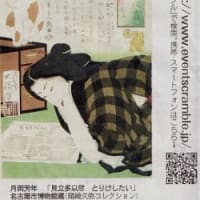
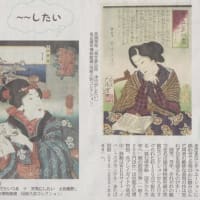





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます