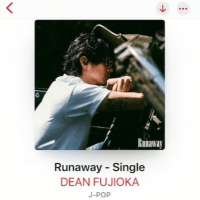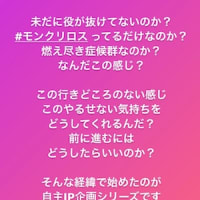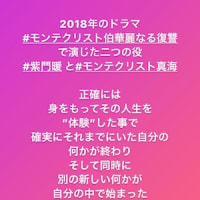深田監督のインタビューを受けたディーンさんのTweetが素敵

インタビュー後編の方ですけど、ディーンさんファンについて語ったインタビューなんて初めて。たしかに皆さん、熱心だし研究者だと思います。それはディーンさんの表面だけではなく、内面に惹かれている部分が大きいから。ディーンさんを入り口に世界の視野がどんどん広がっていく。考え方、生き方に影響を受ける。そういうところもディーンさんの魅力なんですよね。
一部を引用させていただきます。質問は要約。
******
●SWAMP
『海を駆ける』深田晃司監督インタビュー前編 深田監督が語る「演劇詐欺」とは?
--ディーンさんが一つのセリフを日本語とインドネシア語と英語で一度試してみた、と。監督としてはどういう意図が?
深田:実はあれはけっこう昔のことで、そんなに正確には覚えていないんです。率直に言うと、ディーンさんとは今回初めてご一緒したので、まずはディーンさんのしゃべり方の傾向をさぐるために、いろんな言語でしゃべってもらったということは、あると思いますね。
もともとディーンさんの役は無国籍なキャラクターで考えていたんですが、それについては、既にこれまでのディーンさんの生き方自体が裏打ちしているので、あまり心配していなかったんです。
言葉ということに関していえば、自分は日本語以外のことは正確にはわからないんですけど、ただ、どの国の俳優の演技でもベースは一緒だと思っています。
--最近の世の中の風潮って、自分がよくわからないものを、「つまらない」という一言で片づけてしまう人が多い
深田:「わからないから、つまらない」って言われた途端、シャットダウンになってしまうので、確かに不安なところではあるんですけれど……。
ただ、ラウというのは、やっぱりわからない存在なんです。基本的に、私たち人間にとって、この世の中ってわからないことだらけですよね。死んだ先に何があるかなんてわからないし、まぁ多分、何もないんだろうけど。でも、結局誰も経験したことがないから、わからないっていう。
そういう、自然に代表されるような、「わからないもの」を「わからないまま」描こうっていうのが、今回の作品のひとつの挑戦でもあって。
がわからないものを見たときに、思うことは人それぞれじゃないですか。例えば、自然を見てスピリチュアルなものを感じたりとか、そこに対して自然のメカニズムを感じたりとか、幽霊を見たりとか。だから、その人それぞれの想像力を邪魔しないように、とにかく気を付けるっていうことを、心掛けて作ったつもりです。
●SWAMP
『海を駆ける』深田晃司監督インタビュー後編 「いい映画とは、鏡のような映画」
--舞台挨拶の空気感
ディーンさん自ら開口一番「映画では全裸で出ていますが、今日は服を着てきました!」って言っていましたからね。やっぱり、ちゃんとファン心理がわかっているな~って。
--深田監督には、ディーンさんの熱狂的なファンの方たちって、どんな風に映っているんですか?
もともと自分はどの映画であっても、「この映画は誰に見てもらおう」とかっていうのは、あまり想定して作っていないんです。でも、今回は確かに『海を駆ける』にディーンさんが出てくれたことによって、自分の映画に興味を持ってくれる人の層が広がったなとは思っています。
これはほかの、いわゆるアイドル的な人気を持っている俳優さんのファンにも共通する傾向なのか、ディーンさんのファンならではなのかは、わからないんですけれど……いやぁ、研究熱心ですね。
最近はもう「ディーンさんのファンって、研究者だな」って思っていて。「ディーン・フジオカっていう研究対象への探究心が半端ない研究者」みたいな感じで。
まず今回『海を駆ける』の公開が発表された途端に、公式Twitterのフォロワー数が、わずか1時間くらいで300人くらいパーンって増えたんだけど、それからもコンスタントに増え続けていて、フォローしてくれた人のプロフィールを見てみると、みんなディーンさんのファンの方なんですね。
さらに去年「KAWASAKIしんゆり映画祭」で『淵に立つ』を上映したときに、ディーンさんのファンが何人か観に来てくれたんですよ。
で、「今度ディーンさんが主演する映画を撮っている監督の映画を観てきた」ってツイッターでつぶやいてくれるんですよ。ディーンさんは、その映画に出てもいないのに(笑)
今度は「文學界」に小説版の『海を駆ける』が掲載されるって発表したら、発売後に「文學界」もちゃんと買って、「読みました!」ってリプライとかを結構送ってくれて。
本当にありがたいですよね。中でも一番衝撃的だったのは、「独立映画鍋」というNPOに参加していて、月に1回、勉強会をやっているんですけれど、この前ちょうど「大阪アジアン映画祭」と提携して、シンポジウムを開催したんですよ。
「映画の東京一極集中について考える」みたいな、超お堅い内容のシンポジウムで、ゲストも関西のミニシアターの支配人とかだったんですけれど、なんとそこにもディーンさんのファンが、駆け付けてくれたんですよ!
しかもそのあと、ツイッターを介して「ああいう話、初めて聞きましたけど、勉強になりました」ってコメントまで送ってくれて、もう「研究者」だな!って(笑)。
(このエピソードに、取材に立ち会っていたSWAMP編集長からも、思わず「ディーン・フジオカ沼、凄いですね!」と感嘆の声が)
ディーンさんのファンの方って、ディーンさんが香港や台湾でもグローバルに活動しているという生き方や、ディーンさん自身の背景にある文化とかもひっくるめて好きだから、視野が広いというか、興味の対象が広いんじゃないかっていう話を、昨日も「文學界」の方としていたんです。
--正直、ここまでの反響って、予想されていました?
いや、まったく想定していなかったんです。そもそも、ディーンさんの生き方と、お姿がラウにピッタリだからオファーしただけなので(笑)
--「映画が鏡である」というお話
「鏡のような映画がいい映画だ」っていうのは、そもそも青年団を主宰している平田オリザさんが「リトマス試験紙みたいなものだ」という言い方を、確か以前にしていたんです。健康状態がわかるっていうか、健康診断みたいなものだって。その人の心の状態がわかる、みたいな言い方をしていて。で、自分は「鏡」という言い方をしているんですが、でもそれって、実はすごく重要なことだと思っているんです。
自分が映画っていうものを考えるときに、プロパガンダっていうことは、どうしても避けて通れないことだと思っていて。やっぱり映画はすごく強い力を持ったメディアであり、表現であり、しかもその上、複製芸術でもある。いわば何万人をも一気に同じ色に塗りつぶすこともその気になれば可能な表現であり、力強い作品であればある程そういったことができてしまうリスクを伴っているんです。
だからこそ、戦争中は散々政治的なプロパガンダに利用されてきて、もう日本もナチスもアメリカもフランスもみんなそれをやってきたわけで。そういう時代を経て、いま映画を作ろうとするときに、やっぱり表現の持つプロパガンダ性みたいなものには、ものすごく気を付けなければいけないと思うんですよね。
つまり自分の中にこれといった答えがあるわけではなくて、そういった表現が抱えているプロパガンダの危うさから、全力で距離を置くための一番ベターな方法が、観客の想像力に委ねることである。観客自身の思想や見方があぶり出されるような作品にすることだと思っているんですね。そういった意味で「いい映画とは鏡のような作品である」という言い方をよくしています。
--今回『海を駆ける』の主演にディーンさんを起用するにあたっては、役柄のイメージということ以外にも、やはり戦略的な部分も
それはディーンさんに限らず、ある程度の数千万円以上の予算で映画を作った時に、誰をキャスティングするのかというのは、確かにすごく重要なので、いつもせめぎ合いですね。そもそも主演クラスになると選択肢が減るので、そこはプロデューサーとの話し合いの中で決めることが多いんです。でも、ディーンさんの場合はちょっと特殊で……。
実は、ディーンさんがこんなに有名人だって知らなかったんです。単純にディーンさんの顔写真を見て「あ! この人いいじゃん!!」って思って選んだので(笑)。今回はプロデューサーがずいぶん物分かりがいいなあと思ったら、もうとっくにブレイクしていた……みたいな感じで(笑)。自分としては無邪気に決めたつもりだったんですけどね。
基本的にはお金を集めるために、どんな娯楽性を入れないといけないというのは、最後に考えることだと思っていて。まずは自分のやりたいことを実現するために、どうやってお金を集めていくかということの方が、まずは重要かなとは思っていますね。
今回登場するほんわかした若者4人の関係性について言うと、当初は若者たちの連帯というか、友情を描くことが、この映画の目的ではなかったんですね。
あくまでラウっていう、いわば自然の象徴のような、全く理由もなく気まぐれに人を殺めたりする自然そのもののような存在と、貧富の差であったり、将来の夢であったり、津波であったり、ものすごく人間的な葛藤を抱えた若者たちの、他愛もない恋愛物語とを対比させたかったんです。そして最後に一気に自然の存在が立ち上がってきて、自然の中に放り出されて終わる……といったようなものにしたいと思っていたので、その対比のために若者たち4人が描かれているんです。
ただ、その連帯というものに関しては、皆問題を抱えているんだけど、その問題が脚本上の障壁にならないようにしたいと思っていたんですね。主人公に障がいを与えて、それを乗り越えたからハッピーエンドになるというわけではなくて、それぞれの状況は何ひとつ解決していないんだけど、それとは関係なく、とりあえず今は仲良くもなれるっていう風にはしたかったんです。
もともとはラウとの対比を際立たせるための存在から、4人の関係性がちょっと強くなったのは、俳優の力なんです。彼らは本当に仲が良かったんですよ。もう、まるで青春映画を観ているかのような感じでしたね。そもそも4人で一緒に歌う場面も、当初は無かったので。
脚本上は、ただ4人がデッキに普通に座って、海を眺めているというシーンだったんですが、思わず「これはもう歌わせたい!」という気分になってしまって(笑)。その結果として、4人の連帯性が、少し強く出るようになったんだと思います。

インタビュー後編の方ですけど、ディーンさんファンについて語ったインタビューなんて初めて。たしかに皆さん、熱心だし研究者だと思います。それはディーンさんの表面だけではなく、内面に惹かれている部分が大きいから。ディーンさんを入り口に世界の視野がどんどん広がっていく。考え方、生き方に影響を受ける。そういうところもディーンさんの魅力なんですよね。
一部を引用させていただきます。質問は要約。
******
●SWAMP
『海を駆ける』深田晃司監督インタビュー前編 深田監督が語る「演劇詐欺」とは?
--ディーンさんが一つのセリフを日本語とインドネシア語と英語で一度試してみた、と。監督としてはどういう意図が?
深田:実はあれはけっこう昔のことで、そんなに正確には覚えていないんです。率直に言うと、ディーンさんとは今回初めてご一緒したので、まずはディーンさんのしゃべり方の傾向をさぐるために、いろんな言語でしゃべってもらったということは、あると思いますね。
もともとディーンさんの役は無国籍なキャラクターで考えていたんですが、それについては、既にこれまでのディーンさんの生き方自体が裏打ちしているので、あまり心配していなかったんです。
言葉ということに関していえば、自分は日本語以外のことは正確にはわからないんですけど、ただ、どの国の俳優の演技でもベースは一緒だと思っています。
--最近の世の中の風潮って、自分がよくわからないものを、「つまらない」という一言で片づけてしまう人が多い
深田:「わからないから、つまらない」って言われた途端、シャットダウンになってしまうので、確かに不安なところではあるんですけれど……。
ただ、ラウというのは、やっぱりわからない存在なんです。基本的に、私たち人間にとって、この世の中ってわからないことだらけですよね。死んだ先に何があるかなんてわからないし、まぁ多分、何もないんだろうけど。でも、結局誰も経験したことがないから、わからないっていう。
そういう、自然に代表されるような、「わからないもの」を「わからないまま」描こうっていうのが、今回の作品のひとつの挑戦でもあって。
がわからないものを見たときに、思うことは人それぞれじゃないですか。例えば、自然を見てスピリチュアルなものを感じたりとか、そこに対して自然のメカニズムを感じたりとか、幽霊を見たりとか。だから、その人それぞれの想像力を邪魔しないように、とにかく気を付けるっていうことを、心掛けて作ったつもりです。
●SWAMP
『海を駆ける』深田晃司監督インタビュー後編 「いい映画とは、鏡のような映画」
--舞台挨拶の空気感
ディーンさん自ら開口一番「映画では全裸で出ていますが、今日は服を着てきました!」って言っていましたからね。やっぱり、ちゃんとファン心理がわかっているな~って。
--深田監督には、ディーンさんの熱狂的なファンの方たちって、どんな風に映っているんですか?
もともと自分はどの映画であっても、「この映画は誰に見てもらおう」とかっていうのは、あまり想定して作っていないんです。でも、今回は確かに『海を駆ける』にディーンさんが出てくれたことによって、自分の映画に興味を持ってくれる人の層が広がったなとは思っています。
これはほかの、いわゆるアイドル的な人気を持っている俳優さんのファンにも共通する傾向なのか、ディーンさんのファンならではなのかは、わからないんですけれど……いやぁ、研究熱心ですね。
最近はもう「ディーンさんのファンって、研究者だな」って思っていて。「ディーン・フジオカっていう研究対象への探究心が半端ない研究者」みたいな感じで。
まず今回『海を駆ける』の公開が発表された途端に、公式Twitterのフォロワー数が、わずか1時間くらいで300人くらいパーンって増えたんだけど、それからもコンスタントに増え続けていて、フォローしてくれた人のプロフィールを見てみると、みんなディーンさんのファンの方なんですね。
さらに去年「KAWASAKIしんゆり映画祭」で『淵に立つ』を上映したときに、ディーンさんのファンが何人か観に来てくれたんですよ。
で、「今度ディーンさんが主演する映画を撮っている監督の映画を観てきた」ってツイッターでつぶやいてくれるんですよ。ディーンさんは、その映画に出てもいないのに(笑)
今度は「文學界」に小説版の『海を駆ける』が掲載されるって発表したら、発売後に「文學界」もちゃんと買って、「読みました!」ってリプライとかを結構送ってくれて。
本当にありがたいですよね。中でも一番衝撃的だったのは、「独立映画鍋」というNPOに参加していて、月に1回、勉強会をやっているんですけれど、この前ちょうど「大阪アジアン映画祭」と提携して、シンポジウムを開催したんですよ。
「映画の東京一極集中について考える」みたいな、超お堅い内容のシンポジウムで、ゲストも関西のミニシアターの支配人とかだったんですけれど、なんとそこにもディーンさんのファンが、駆け付けてくれたんですよ!
しかもそのあと、ツイッターを介して「ああいう話、初めて聞きましたけど、勉強になりました」ってコメントまで送ってくれて、もう「研究者」だな!って(笑)。
(このエピソードに、取材に立ち会っていたSWAMP編集長からも、思わず「ディーン・フジオカ沼、凄いですね!」と感嘆の声が)
ディーンさんのファンの方って、ディーンさんが香港や台湾でもグローバルに活動しているという生き方や、ディーンさん自身の背景にある文化とかもひっくるめて好きだから、視野が広いというか、興味の対象が広いんじゃないかっていう話を、昨日も「文學界」の方としていたんです。
--正直、ここまでの反響って、予想されていました?
いや、まったく想定していなかったんです。そもそも、ディーンさんの生き方と、お姿がラウにピッタリだからオファーしただけなので(笑)
--「映画が鏡である」というお話
「鏡のような映画がいい映画だ」っていうのは、そもそも青年団を主宰している平田オリザさんが「リトマス試験紙みたいなものだ」という言い方を、確か以前にしていたんです。健康状態がわかるっていうか、健康診断みたいなものだって。その人の心の状態がわかる、みたいな言い方をしていて。で、自分は「鏡」という言い方をしているんですが、でもそれって、実はすごく重要なことだと思っているんです。
自分が映画っていうものを考えるときに、プロパガンダっていうことは、どうしても避けて通れないことだと思っていて。やっぱり映画はすごく強い力を持ったメディアであり、表現であり、しかもその上、複製芸術でもある。いわば何万人をも一気に同じ色に塗りつぶすこともその気になれば可能な表現であり、力強い作品であればある程そういったことができてしまうリスクを伴っているんです。
だからこそ、戦争中は散々政治的なプロパガンダに利用されてきて、もう日本もナチスもアメリカもフランスもみんなそれをやってきたわけで。そういう時代を経て、いま映画を作ろうとするときに、やっぱり表現の持つプロパガンダ性みたいなものには、ものすごく気を付けなければいけないと思うんですよね。
つまり自分の中にこれといった答えがあるわけではなくて、そういった表現が抱えているプロパガンダの危うさから、全力で距離を置くための一番ベターな方法が、観客の想像力に委ねることである。観客自身の思想や見方があぶり出されるような作品にすることだと思っているんですね。そういった意味で「いい映画とは鏡のような作品である」という言い方をよくしています。
--今回『海を駆ける』の主演にディーンさんを起用するにあたっては、役柄のイメージということ以外にも、やはり戦略的な部分も
それはディーンさんに限らず、ある程度の数千万円以上の予算で映画を作った時に、誰をキャスティングするのかというのは、確かにすごく重要なので、いつもせめぎ合いですね。そもそも主演クラスになると選択肢が減るので、そこはプロデューサーとの話し合いの中で決めることが多いんです。でも、ディーンさんの場合はちょっと特殊で……。
実は、ディーンさんがこんなに有名人だって知らなかったんです。単純にディーンさんの顔写真を見て「あ! この人いいじゃん!!」って思って選んだので(笑)。今回はプロデューサーがずいぶん物分かりがいいなあと思ったら、もうとっくにブレイクしていた……みたいな感じで(笑)。自分としては無邪気に決めたつもりだったんですけどね。
基本的にはお金を集めるために、どんな娯楽性を入れないといけないというのは、最後に考えることだと思っていて。まずは自分のやりたいことを実現するために、どうやってお金を集めていくかということの方が、まずは重要かなとは思っていますね。
今回登場するほんわかした若者4人の関係性について言うと、当初は若者たちの連帯というか、友情を描くことが、この映画の目的ではなかったんですね。
あくまでラウっていう、いわば自然の象徴のような、全く理由もなく気まぐれに人を殺めたりする自然そのもののような存在と、貧富の差であったり、将来の夢であったり、津波であったり、ものすごく人間的な葛藤を抱えた若者たちの、他愛もない恋愛物語とを対比させたかったんです。そして最後に一気に自然の存在が立ち上がってきて、自然の中に放り出されて終わる……といったようなものにしたいと思っていたので、その対比のために若者たち4人が描かれているんです。
ただ、その連帯というものに関しては、皆問題を抱えているんだけど、その問題が脚本上の障壁にならないようにしたいと思っていたんですね。主人公に障がいを与えて、それを乗り越えたからハッピーエンドになるというわけではなくて、それぞれの状況は何ひとつ解決していないんだけど、それとは関係なく、とりあえず今は仲良くもなれるっていう風にはしたかったんです。
もともとはラウとの対比を際立たせるための存在から、4人の関係性がちょっと強くなったのは、俳優の力なんです。彼らは本当に仲が良かったんですよ。もう、まるで青春映画を観ているかのような感じでしたね。そもそも4人で一緒に歌う場面も、当初は無かったので。
脚本上は、ただ4人がデッキに普通に座って、海を眺めているというシーンだったんですが、思わず「これはもう歌わせたい!」という気分になってしまって(笑)。その結果として、4人の連帯性が、少し強く出るようになったんだと思います。