1月の3連休。
足を痛めてどこにも出かけられずに見た1本のビデオ。見てよかった~。
かしまし娘さんのおかげでございます。ありがとうございます♪
●かしまし娘さんが書かれた「女の一生」紹介記事はこちらに。
「女の一生」
文学座の森本薫が当時、杉村春子のために書いた作品で、上演回数947回。
演劇史に大きな足跡を残す、杉村春子の代表作。
リアリズム演劇・・・とかいうらしいのですが、実はその辺りのこと、私
には全くわかりません。
ただ、キャピキャピした少女の頃から、恋する乙女時代、女実業家として
の風格を見せる熟年、落ち着いた風情の老女までを、何通りもの声と仕草、
台詞の言い回し等で、イキイキとめまぐるしく演じ分ける杉村春子さんの
演技は本当に見事です。
細かいことですが、役の年齢に合わせて瞼の開き具合まで作り込んでいる
のには驚きました。
どの瞬間にも布引けい、という女性がそこにいると思わせてくれます。
そしてやっぱり脚本、台詞がいいんです。
冒頭の場面を少し書き出してみると・・・・・・。
戦後の焼け跡。
何もかも失った街の一角、老女に声をかける老人が一人。
女はこの家を守ってきた主らしい。(家とおぼしき建物はないが。)
男は長い歳月を経てある一軒の家を訪ねてきたが、見つからないと話す。
二人、たわいのない会話を交わした後、男がその場を去ろうとする。
とその時。
老女が焚き火にあたりながらふと口ずさむ歌が「アニーローリー」。
ハッとする男。ふりむきざまに老女にいう。
「けいさん?」
あーん。いいよねー。杉村春子が歌う「アニーローリー」。
日本語の歌詞なのがね。なんか、こう、きゅん。
この歌が二人をどんなふうに結びつけているんだろう?
ガゼン気になってしまうじゃないのぉ~。
------物語はこんなふう------
明治42年。
日露戦争によって孤児となった布引けいは、ある一軒の家の庭に迷い込む。
家の中から聴こえてきたのは、オルガンの伴奏に合わせ皆が歌う「アニー
ローリー」。そこでふとした出来事をきっかけに、けいは自分とは縁もゆ
かりもなかったこの裕福な家庭に拾われ女中となる。
やがて、けいはその気性と才覚を女主人に見込まれ、長男の嫁となり、夫
に代わって事業と家を切り盛りしていく。
ひとりの女性の一生の物語。
そこには恋があり、ビジネスがあり、戦争もある。
商家が舞台だけに、明治から昭和にかけての日本の政局、戦局、経済問題、
思想等が色濃く反映され、登場人物たちがいやでもそうした出来事に飲み
込まれていってしまう。
そんな中、先代の女主人(夫の母)の言いつけに従い、ひたすら「家」と
家業の「仕事」を守り抜こうとする主人公けい。
ときには冷徹とさえ思えるけいのやり方は周囲には受け入れられず、いつ
しか夫や娘との感情の行き違いや、かつて好きだった人(次男、永二)と
の別れ等を経験することに。
そして、昭和20年。
別居していた夫が和解した直後に息を引き取り、ようやく娘も帰ってくる
ことになった矢先に空襲に遭う。
何もかも失った東京の空の下。堤家の屋敷跡で再会する、けいと永二。
長い歳月を経て、ようやく打ち解け合った二人の台詞が心に沁みる。
-----------------------
女性の華やかなサクセスストーリー?
と見る前は思っていたけれど、かなり違っていました。
あの時。
先代から「この家の人間になってほしい。息子の嫁に」と請われ、願って
もない自分の強運に今風に言えばガッツポーズまで見せたけい。
見方によっては、憎々しいまでにふてぶてしく、たくましく生き抜く女。
でも、そこに透けて見えるのは、何があろうとこの家だけはと死守し続け
る律儀で健気な女の姿でした。
それはたぶん、先代である義母もたどって来た道。
けいは堤家のオモワクの犠牲になったともいえるけれど、それを承知の上
での選択だったと思うし、けいにはそれしかなかったのだと思う。
ただ、「家」を守ろうとするがゆえの、家族や身内との確執までは予想は
していなかったとは思うけれど。いつも鎧を着たけいの心の内側は繊細で
柔らかく、つねにたくさんの血を流していたのかも。
何もかも完璧にこなすスーパーウーマンけいに、伯父(義母の弟)が言う。
おや、けいさんでも間違えることがあるのかい?
それに毅然と胸を張って答えるけいの言葉。
とても有名な台詞なのだそう。
「自分で選んで歩いて来た道ですもの。間違いだと気づいたら間違いじゃ
ないようにしなくっちゃ。」
ふう~。
志というものを一度でも抱いたことのある女性ならば、飛びついてすがり
たくなる言葉ではないですか。
あるいは、二度と引き返せない人生という道を、ただ前向きに生きてゆく
ための超極意のような言葉。
そこには女優業という一本道をゆく、杉村春子という人の背筋の伸びた姿
が重なって見えるから、よけいに共感と感動を呼んだのでしょうね。
物語はこの台詞で終わるわけではなく、先のほうが長いんですけどね。
中盤は割愛させて頂くとして。
お話は冒頭の場面にもどります。
老人というのは堤家の次男、栄二。
老女は堤家の長男の妻となった、けい。
好きどうしだったはずの二人が結ばれることはなく。
さらに戦時中、共産党の活動に打ち込む永二を警察に差し出すという苦渋
の決断を余儀なくされた、けい。
それも、これも、すべては堤家を守るために・・・。
そして今、戦後の瓦礫の中で再会した二人。
けいが言う。
「私の一生ってものはいったい何だったんだろう。小さい時分から人様の
ために働き、人様からああしろと言われればそのようにし、今度はそれが
いけないと身近な人から背いていかれる。やっとみんな帰ってきたと思っ
たら何もかもめちゃくちゃにされる。いったい私ってものがどこにあるん
だか」
永二が返す。
「今までの日本の女の人にはそういうことが多すぎたんです。これからの
女の人はまた違った一生を送ることになるでしょう」
再び、けい。
「でも、私の一生はこれからという気がするんです。・・・・・・」
そして、永二が外国の短編小説を思い出したと言い、二人でカドリール
(ダンスの一種)を踊ろうと提案するんですね。
「私たちの老年にも1つや2つの想い出があろうというもんです。」
やや間があって「踊りましょうか」と答えるけいの顔が、笑顔から一瞬泣
き顔になって、もうどっちだかわからなくなる。そんなラストシーン。
この作品を観て、ひとつ思い出した映画がありました。
『風と共に去りぬ』です。
人生の紆余曲折を経て、ふと気づいたら目の前には大地があった。
自分の人生を全面的に受け入れた瞬間に言うスカーレットの台詞が、
「明日また考えよう」(明日は明日の風が吹く)。
スカーレットには大地があったように、けいには家がある。
焼け跡に建物はなくても、その場所には、けいがいる。
それはやっぱり、間違いじゃないようにして歩いてきた人の、地に足着い
た美しい姿なのだと。
昔の女性は家の犠牲になって可哀想、などという想いではなく、一人の人
間が家や大地に等しい存在になれる。
布引けいという女性にそんな強い希望を感じたラストシーンでした。
うーん、これは見る度に感想が変わりそうな気がする。
●文学座の「女の一生」上演情報はこちら
足を痛めてどこにも出かけられずに見た1本のビデオ。見てよかった~。
かしまし娘さんのおかげでございます。ありがとうございます♪
●かしまし娘さんが書かれた「女の一生」紹介記事はこちらに。
「女の一生」
文学座の森本薫が当時、杉村春子のために書いた作品で、上演回数947回。
演劇史に大きな足跡を残す、杉村春子の代表作。
リアリズム演劇・・・とかいうらしいのですが、実はその辺りのこと、私
には全くわかりません。
ただ、キャピキャピした少女の頃から、恋する乙女時代、女実業家として
の風格を見せる熟年、落ち着いた風情の老女までを、何通りもの声と仕草、
台詞の言い回し等で、イキイキとめまぐるしく演じ分ける杉村春子さんの
演技は本当に見事です。
細かいことですが、役の年齢に合わせて瞼の開き具合まで作り込んでいる
のには驚きました。
どの瞬間にも布引けい、という女性がそこにいると思わせてくれます。
そしてやっぱり脚本、台詞がいいんです。
冒頭の場面を少し書き出してみると・・・・・・。
戦後の焼け跡。
何もかも失った街の一角、老女に声をかける老人が一人。
女はこの家を守ってきた主らしい。(家とおぼしき建物はないが。)
男は長い歳月を経てある一軒の家を訪ねてきたが、見つからないと話す。
二人、たわいのない会話を交わした後、男がその場を去ろうとする。
とその時。
老女が焚き火にあたりながらふと口ずさむ歌が「アニーローリー」。
ハッとする男。ふりむきざまに老女にいう。
「けいさん?」
あーん。いいよねー。杉村春子が歌う「アニーローリー」。
日本語の歌詞なのがね。なんか、こう、きゅん。
この歌が二人をどんなふうに結びつけているんだろう?
ガゼン気になってしまうじゃないのぉ~。
------物語はこんなふう------
明治42年。
日露戦争によって孤児となった布引けいは、ある一軒の家の庭に迷い込む。
家の中から聴こえてきたのは、オルガンの伴奏に合わせ皆が歌う「アニー
ローリー」。そこでふとした出来事をきっかけに、けいは自分とは縁もゆ
かりもなかったこの裕福な家庭に拾われ女中となる。
やがて、けいはその気性と才覚を女主人に見込まれ、長男の嫁となり、夫
に代わって事業と家を切り盛りしていく。
ひとりの女性の一生の物語。
そこには恋があり、ビジネスがあり、戦争もある。
商家が舞台だけに、明治から昭和にかけての日本の政局、戦局、経済問題、
思想等が色濃く反映され、登場人物たちがいやでもそうした出来事に飲み
込まれていってしまう。
そんな中、先代の女主人(夫の母)の言いつけに従い、ひたすら「家」と
家業の「仕事」を守り抜こうとする主人公けい。
ときには冷徹とさえ思えるけいのやり方は周囲には受け入れられず、いつ
しか夫や娘との感情の行き違いや、かつて好きだった人(次男、永二)と
の別れ等を経験することに。
そして、昭和20年。
別居していた夫が和解した直後に息を引き取り、ようやく娘も帰ってくる
ことになった矢先に空襲に遭う。
何もかも失った東京の空の下。堤家の屋敷跡で再会する、けいと永二。
長い歳月を経て、ようやく打ち解け合った二人の台詞が心に沁みる。
-----------------------
女性の華やかなサクセスストーリー?
と見る前は思っていたけれど、かなり違っていました。
あの時。
先代から「この家の人間になってほしい。息子の嫁に」と請われ、願って
もない自分の強運に今風に言えばガッツポーズまで見せたけい。
見方によっては、憎々しいまでにふてぶてしく、たくましく生き抜く女。
でも、そこに透けて見えるのは、何があろうとこの家だけはと死守し続け
る律儀で健気な女の姿でした。
それはたぶん、先代である義母もたどって来た道。
けいは堤家のオモワクの犠牲になったともいえるけれど、それを承知の上
での選択だったと思うし、けいにはそれしかなかったのだと思う。
ただ、「家」を守ろうとするがゆえの、家族や身内との確執までは予想は
していなかったとは思うけれど。いつも鎧を着たけいの心の内側は繊細で
柔らかく、つねにたくさんの血を流していたのかも。
何もかも完璧にこなすスーパーウーマンけいに、伯父(義母の弟)が言う。
おや、けいさんでも間違えることがあるのかい?
それに毅然と胸を張って答えるけいの言葉。
とても有名な台詞なのだそう。
「自分で選んで歩いて来た道ですもの。間違いだと気づいたら間違いじゃ
ないようにしなくっちゃ。」
ふう~。
志というものを一度でも抱いたことのある女性ならば、飛びついてすがり
たくなる言葉ではないですか。
あるいは、二度と引き返せない人生という道を、ただ前向きに生きてゆく
ための超極意のような言葉。
そこには女優業という一本道をゆく、杉村春子という人の背筋の伸びた姿
が重なって見えるから、よけいに共感と感動を呼んだのでしょうね。
物語はこの台詞で終わるわけではなく、先のほうが長いんですけどね。
中盤は割愛させて頂くとして。
お話は冒頭の場面にもどります。
老人というのは堤家の次男、栄二。
老女は堤家の長男の妻となった、けい。
好きどうしだったはずの二人が結ばれることはなく。
さらに戦時中、共産党の活動に打ち込む永二を警察に差し出すという苦渋
の決断を余儀なくされた、けい。
それも、これも、すべては堤家を守るために・・・。
そして今、戦後の瓦礫の中で再会した二人。
けいが言う。
「私の一生ってものはいったい何だったんだろう。小さい時分から人様の
ために働き、人様からああしろと言われればそのようにし、今度はそれが
いけないと身近な人から背いていかれる。やっとみんな帰ってきたと思っ
たら何もかもめちゃくちゃにされる。いったい私ってものがどこにあるん
だか」
永二が返す。
「今までの日本の女の人にはそういうことが多すぎたんです。これからの
女の人はまた違った一生を送ることになるでしょう」
再び、けい。
「でも、私の一生はこれからという気がするんです。・・・・・・」
そして、永二が外国の短編小説を思い出したと言い、二人でカドリール
(ダンスの一種)を踊ろうと提案するんですね。
「私たちの老年にも1つや2つの想い出があろうというもんです。」
やや間があって「踊りましょうか」と答えるけいの顔が、笑顔から一瞬泣
き顔になって、もうどっちだかわからなくなる。そんなラストシーン。
この作品を観て、ひとつ思い出した映画がありました。
『風と共に去りぬ』です。
人生の紆余曲折を経て、ふと気づいたら目の前には大地があった。
自分の人生を全面的に受け入れた瞬間に言うスカーレットの台詞が、
「明日また考えよう」(明日は明日の風が吹く)。
スカーレットには大地があったように、けいには家がある。
焼け跡に建物はなくても、その場所には、けいがいる。
それはやっぱり、間違いじゃないようにして歩いてきた人の、地に足着い
た美しい姿なのだと。
昔の女性は家の犠牲になって可哀想、などという想いではなく、一人の人
間が家や大地に等しい存在になれる。
布引けいという女性にそんな強い希望を感じたラストシーンでした。
うーん、これは見る度に感想が変わりそうな気がする。
●文学座の「女の一生」上演情報はこちら














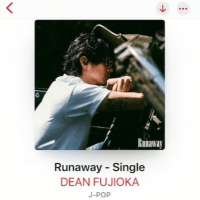
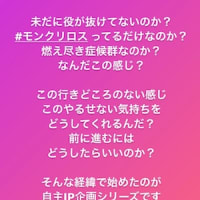
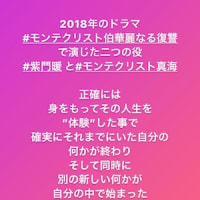


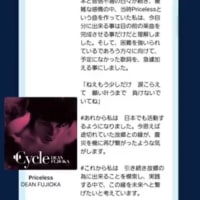












紹介ありがとうございます。
「女の一生」を久しぶりに観返したくなりましたぁ…。
こちらの観る年齢によっても感想が変わりますよね、きっと。
私が初観劇(最初で最後だったのだけど…)したのが20代だったし、
夢もいっぱい持っていたので
「自分で選んで歩いて来た道ですもの。間違いだと気づいたら間違いじゃ
ないようにしなくっちゃ。」
この台詞も自分の背中を押されるようでキラキラ輝いていましたヨ。
実は時々口ずさんだりする台詞です。今はホロリ…ときてしまうのですが(笑)
この作品は森本薫が杉村春子のために書いたんです。
だから絶品と言ってもいいキャストなんでしょうね。
今は代替わりをして平淑恵が演っています。文学座の財産です。
残念なことに「新劇」という存在が希薄になって久しいのですが
…まだ現役の俳優もいるし。
「ドライビング・ミス・デイジー」などオススメっすよ♪
3/4~8 サンケイホールブリーゼ
> こちらの観る年齢によっても感想が変わりますよね、きっと。
わあっ。それ泣いてしまいそう~。
そうなんですよねー。今は老女のけいの心境のほうが
よくわかったりしてね(爆)。
ちょっと歌舞伎の「ぢいさん ばあさん」に似た台詞も
あったりするし。(これからの人生は余生ではない。)
あの毅然とした台詞が似合う背筋の伸びた女優さん、
可愛らしさもあって、昭和・大正の古きよき佇まいを
もった女優さん。
そんな人がいまも文学座にいるんですね。
新派の舞台でも同じことを思ったけれど、その劇団の財産
である作品はやはり頑張って上演し続けてほしいですね。
時代感覚が多少古くても、その背景が伝わってくる演技力
があれば、今でもじゅうぶん共感できますからね。
次、文学座の「女の一生」が関西でかかったら、
ぜひナマで見てみたいです。
ここで脚本を見つけました。↓
http://www.aozora.gr.jp/cards/000827/files/4332_21415.html
第三幕の終わりにあの台詞が。
「誰が選んでくれたのでもない、自分で選んで
歩きだした道ですもの。間違いと知ったら
自分で間違いでないようにしなくちゃ。」