(1)からの続きです。
<特別出演>
この後は、他の流派の家元、舞踊家の方々の特別出演が続く。
まずは、若柳吉蔵さん、若柳吉金吾さんによる「猩々」。
獅子のような赤い髪をつけて夫婦の猩々を演じ、襲名を祝っておられた。
続いて、上方舞山村流宗家の六世山村若さんによる「蓬莱」。
祝儀の飾り物を綴りつつ、郭の正月の情景を優雅に表現されていた。
「由縁の月」を舞われたのは京舞井上流五世家元の井上八千代さん。
夕霧伊左衛門に材をとったものだが、井上流では独自の舞とのこと。
すごく大きなお名前の方ばかり。
この場にいること自体がどう考えても不思議だ。
いよいよ最後の演目へ。
<地唄 荒れ鼠>
出演/楳茂都扇性 山村若 若柳吉蔵 藤間豊宏 藤間勘世
吉村古ゆう 花柳源九郎
地唄のなかで滑稽な詞章なものを「作物」といい、その代表的な演目が
これだそう。鼠の大将が鼠たちを引き連れて家中を荒し回る様子を擬人
化したもので、最後に猫が出てきて逃げ出すまでを描いている。
各流派の人たちが参加しての群舞というのが珍しく、またおめでたい。
ユーモラスな歌詞とそれに合った振付に、ときどき笑いが起こり、なご
やかで晴れやかな雰囲気になった。
以下、また思い出せる箇所だけ。間違いがあったらおゆるしをば!
前後して置かれた数枚の金屏風の間から、一匹、また一匹と鼠が登場。
そのたびに大きな拍手が。全員集合すると愛嬌があってカワイイ。
全員が黒の紋付き袴姿の素踊り。
なので、鼠っぽさは動きや扇子で表現することになる。たとえば、
扇子を頭にかざし、少し開いて黒い要を先に向けると鼠の顔になる。
扇子は体の後ろに出せば尻尾にもなる。
しゃがんだままちょこちょこ歩いたり。(源九郎狐みたいに。)
ムカデのように前の人の腰をもって連なって動いたりもする。
大将は扇性さん演じる鼠。
扇子を前に置き、腹ばいになって膝を曲げ、頬杖をついている。
(いやん。与兵衛のあのポーズやん♪)
ここは天井裏。大将が板の隙間から下の様子をうかがっているのだ。
後ろにいるのは子分の鼠たち。
だれもいないことを確認して、いざ、台所へと向かう。
あ、こんな書き方だけど、ちゃんと踊りになっていますから(笑)。
機敏でコミカル。ときにはゆっくりそろそろ・・・。
お前はあっち、お前はこっち、ここでは何をかじって、ここではこれ
を取ってこい、行け-!と、大将がめざす方向に右手を伸ばして采配
をふるう姿は、まるで忠臣蔵の大石内蔵助みたい。
あ、鼠には名前もあるんだった。
一人一人自己紹介するように次々(一人複数役)現れる。
チュウの守、チュウ左衛門、チュウ一、チュウ次郎、チュウ兵衛、
チュウ七、チュウ八・・・(みたいな名前が延々と続く。ふう~。)
命令だけじゃなく、注意事項も言い渡す。
わさびおろしに近づくな! 柱の水壺には気をつけろ!(だった?)
飯炊きおばばを起こすな!など。
あっちこっちで好き勝手放題、かじりまくる鼠たち。
個人的にウケたのは、山村若さん子分鼠に注意する、扇性さん大将鼠。
子分鼠の横で扇子を立ててコン、コン、コンッ!
お前は・・・だから・・・するように気をつけなさい(内容失念)、
みたいに説教をした後(←地唄の歌詞)、頭をパンって。
2~3匹の鼠が説教されてた(笑)。
ネコイラズを見つけてパニック。扇子をパッと投げ捨てる振付。
さすが大黒様のお使いだけあって(笑)つねづね大黒様を信心してい
るから大丈夫、とそれぞれ一斉に拝み始める。
(鼠さんたち、カワイイやら可笑しいやら。ここ、観客が一番わいた♪)
そうこうしているうちに、ごチュウ進、ごチュウ進。
猫が来たー。
知らせた鼠、これがまことの忠チュウ、うんぬん。
だれが先頭になるか、ジャンケンで決める。
(↑ ジャンケンはここだと思うが、その様子にまたまた会場大ウケ。)
ダダダダダ・・・。
一目散に逃げ出してゆく鼠たち。(完。)
きゃー、なんてクリエイティブなんだ~!
場内大きな拍手が起こる。
関西の舞踊家の皆さん、大変楽しかったです。
2007年に見た時は、猫も蛙もたしかに面白かったけど。
荒れ鼠の群舞は、今まで見たことのない楽しさだった。
はんなりした優雅な舞と「作物」のえもいわれぬ味わい。
どちらも楳茂都流なんですね。
この日はお父様の秀太郎さんも客席で見守っておられた。
記念すべき公演ですから。いわずもがな。
流派の家元として新しくスタートを切った扇性さん。
あと数時間でお誕生日を迎える愛之助さん。
おめでとうございます~♪
(はずかしながら、ついでにそっとお祝いしてみました。)
四代目楳茂都流家元披露舞踊公演(1)(このブログ内の関連記事)
「狐忠信再度の旅」観劇メモ(このブログ内の関連記事)
<特別出演>
この後は、他の流派の家元、舞踊家の方々の特別出演が続く。
まずは、若柳吉蔵さん、若柳吉金吾さんによる「猩々」。
獅子のような赤い髪をつけて夫婦の猩々を演じ、襲名を祝っておられた。
続いて、上方舞山村流宗家の六世山村若さんによる「蓬莱」。
祝儀の飾り物を綴りつつ、郭の正月の情景を優雅に表現されていた。
「由縁の月」を舞われたのは京舞井上流五世家元の井上八千代さん。
夕霧伊左衛門に材をとったものだが、井上流では独自の舞とのこと。
すごく大きなお名前の方ばかり。
この場にいること自体がどう考えても不思議だ。
いよいよ最後の演目へ。
 |
<地唄 荒れ鼠>
出演/楳茂都扇性 山村若 若柳吉蔵 藤間豊宏 藤間勘世
吉村古ゆう 花柳源九郎
地唄のなかで滑稽な詞章なものを「作物」といい、その代表的な演目が
これだそう。鼠の大将が鼠たちを引き連れて家中を荒し回る様子を擬人
化したもので、最後に猫が出てきて逃げ出すまでを描いている。
各流派の人たちが参加しての群舞というのが珍しく、またおめでたい。
ユーモラスな歌詞とそれに合った振付に、ときどき笑いが起こり、なご
やかで晴れやかな雰囲気になった。
以下、また思い出せる箇所だけ。間違いがあったらおゆるしをば!
前後して置かれた数枚の金屏風の間から、一匹、また一匹と鼠が登場。
そのたびに大きな拍手が。全員集合すると愛嬌があってカワイイ。
全員が黒の紋付き袴姿の素踊り。
なので、鼠っぽさは動きや扇子で表現することになる。たとえば、
扇子を頭にかざし、少し開いて黒い要を先に向けると鼠の顔になる。
扇子は体の後ろに出せば尻尾にもなる。
しゃがんだままちょこちょこ歩いたり。(源九郎狐みたいに。)
ムカデのように前の人の腰をもって連なって動いたりもする。
大将は扇性さん演じる鼠。
扇子を前に置き、腹ばいになって膝を曲げ、頬杖をついている。
(いやん。与兵衛のあのポーズやん♪)
ここは天井裏。大将が板の隙間から下の様子をうかがっているのだ。
後ろにいるのは子分の鼠たち。
だれもいないことを確認して、いざ、台所へと向かう。
あ、こんな書き方だけど、ちゃんと踊りになっていますから(笑)。
機敏でコミカル。ときにはゆっくりそろそろ・・・。
お前はあっち、お前はこっち、ここでは何をかじって、ここではこれ
を取ってこい、行け-!と、大将がめざす方向に右手を伸ばして采配
をふるう姿は、まるで忠臣蔵の大石内蔵助みたい。
あ、鼠には名前もあるんだった。
一人一人自己紹介するように次々(一人複数役)現れる。
チュウの守、チュウ左衛門、チュウ一、チュウ次郎、チュウ兵衛、
チュウ七、チュウ八・・・(みたいな名前が延々と続く。ふう~。)
命令だけじゃなく、注意事項も言い渡す。
わさびおろしに近づくな! 柱の水壺には気をつけろ!(だった?)
飯炊きおばばを起こすな!など。
あっちこっちで好き勝手放題、かじりまくる鼠たち。
個人的にウケたのは、山村若さん子分鼠に注意する、扇性さん大将鼠。
子分鼠の横で扇子を立ててコン、コン、コンッ!
お前は・・・だから・・・するように気をつけなさい(内容失念)、
みたいに説教をした後(←地唄の歌詞)、頭をパンって。
2~3匹の鼠が説教されてた(笑)。
ネコイラズを見つけてパニック。扇子をパッと投げ捨てる振付。
さすが大黒様のお使いだけあって(笑)つねづね大黒様を信心してい
るから大丈夫、とそれぞれ一斉に拝み始める。
(鼠さんたち、カワイイやら可笑しいやら。ここ、観客が一番わいた♪)
そうこうしているうちに、ごチュウ進、ごチュウ進。
猫が来たー。
知らせた鼠、これがまことの忠チュウ、うんぬん。
だれが先頭になるか、ジャンケンで決める。
(↑ ジャンケンはここだと思うが、その様子にまたまた会場大ウケ。)
ダダダダダ・・・。
一目散に逃げ出してゆく鼠たち。(完。)
きゃー、なんてクリエイティブなんだ~!
場内大きな拍手が起こる。
関西の舞踊家の皆さん、大変楽しかったです。
2007年に見た時は、猫も蛙もたしかに面白かったけど。
荒れ鼠の群舞は、今まで見たことのない楽しさだった。
はんなりした優雅な舞と「作物」のえもいわれぬ味わい。
どちらも楳茂都流なんですね。
この日はお父様の秀太郎さんも客席で見守っておられた。
記念すべき公演ですから。いわずもがな。
流派の家元として新しくスタートを切った扇性さん。
あと数時間でお誕生日を迎える愛之助さん。
おめでとうございます~♪
(はずかしながら、ついでにそっとお祝いしてみました。)
四代目楳茂都流家元披露舞踊公演(1)(このブログ内の関連記事)
「狐忠信再度の旅」観劇メモ(このブログ内の関連記事)














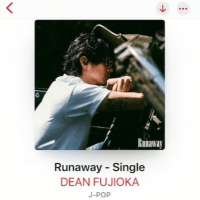
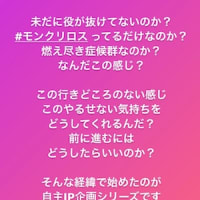
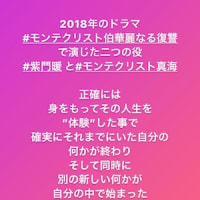


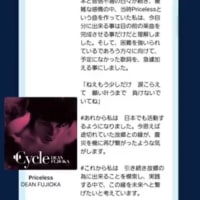












「荒れ鼠」は変わってて面白かったのに細部を忘れてしまい、ここを拝見して、「わさびおろしに近づくな」と言ってたな、と思い出しました。引っ込むとき、愛之助さんの袴の裾がちょっとまくれてたの、気づきましたか?
プログラムの表紙のアメノウズメみたいな舞を新しい扇性さんが振付けて、ご自分で舞われるのも良いのでは、と思いました。
はい、素踊りがこんなに素敵だとは意外でした♪
お顔が見えると感情をこめているところもわかりますし、
それに小首を動かす時にプチ見得っぽく見えるとことか、
好きです~♪
> 愛之助さんの袴の裾がちょっとまくれてた
へええ~。
私の席からは人垣が多くて、ぐっと伸び上がらないと
裾のほうまでは見えなかったんです。
> アメノウズメ
あはは。私は吉祥天かと思いましたよ。いい絵ですよね。
とみたさんのヒラメキに一票!
あ、でもこの衣装で舞うんですよね~~~~♪♪♪
いらっしゃるのかなと思ってました。
四代目のお家元は、腰を落としてからの股割が、上半身全く動かずで、
流石だなと思いました。
あんなふうに衣装を付けず、素で舞うのは、
男の舞い手の醍醐味かなと私は思います。
お家元として流を立てていかねばならないでしょうから、色々大変なこともあると思いますが、
ムンバリ様のようなファンもいらっしゃることだし、
力強いのではないでしょうか。
これからは歌舞伎だけでなく、楳茂都の舞の会も見に行かねばなりませんね♪
こちらこそ、ごぶさたしております。
踊り・舞の観劇はまだまだ慣れませんが、あのような場に
いられたことがただただ幸運に思いました。
また一つ、舞の見方をお教え頂きありがとうございます。
腰を落としてからの動き、ですね♪
素踊りは、歌舞伎ではなかなか見られませんから、
とても新鮮に映りました。
舞も歌舞伎と同じように、見ているうちに少しずつ
わかるようになっていけばいいなと思っています。
山村若伸紀様のサイトとブログ、これからも楽しみに
拝見させて頂きますね♪