平安初期の木簡に“米作りカレンダー” (読売新聞) - goo ニュース
平安期の田植えに関する記述がみつかったという。
田植えと生き物の関係について調べている。このところ、田植えの時期が早くなったことが生き物の生活にも影響しているのでは、と考えていた。
平安時代も種蒔きは旧暦で早稲種は3月8日、新暦で4月5日、苗が育って田植えをするのは、およそ7週間後なので、田植えは5月の23日ぐらいということになるだろうか。晩成種ならばもうすこし遅いかも知れない。
やはり今よりも一月ちかく遅かったということになる。
暦 太陰太陽暦 国立図書館HP
お月様とも仲良く 太陰太陽暦
★テキスト版
平安初期の木簡に“米作りカレンダー”
2006年 4月 7日 (金) 03:15
奈良県香芝市の下田東遺跡で出土した平安時代初期(9世紀初め)の木簡に、春の種まきから秋の稲刈りや販売まで、米作りの作業手順などが詳しく書かれていることがわかった。
いわば、古代の“農業カレンダー”で、男女で作業を分担した様子も記されており、稲作の具体的な作業の流れを記述した最古の木簡となる。荘園の管理者が書いたとみられ、貴重な資料になりそうだ。
この木簡は長さ36・8センチ、幅11・1センチで、墨書は表裏両面にあった。種まきに関しては「種蒔(ま)く日 和世(わせ)種三月六日 小須弥女(こすみめ)十一日に蒔く」とあり、女性が苗代に早生(わせ)種の種をまいた様子がうかがえる。
また、収穫については「小支石(おきいし)という男性が七月□、十二、十四、十七、□日の5日間出勤して稲を刈った」と記載。「二百八十」の稲やわらの束などを、2回に分けて売ったとも記されていた。
平安期の田植えに関する記述がみつかったという。
田植えと生き物の関係について調べている。このところ、田植えの時期が早くなったことが生き物の生活にも影響しているのでは、と考えていた。
平安時代も種蒔きは旧暦で早稲種は3月8日、新暦で4月5日、苗が育って田植えをするのは、およそ7週間後なので、田植えは5月の23日ぐらいということになるだろうか。晩成種ならばもうすこし遅いかも知れない。
やはり今よりも一月ちかく遅かったということになる。
暦 太陰太陽暦 国立図書館HP
お月様とも仲良く 太陰太陽暦
★テキスト版
平安初期の木簡に“米作りカレンダー”
2006年 4月 7日 (金) 03:15
奈良県香芝市の下田東遺跡で出土した平安時代初期(9世紀初め)の木簡に、春の種まきから秋の稲刈りや販売まで、米作りの作業手順などが詳しく書かれていることがわかった。
いわば、古代の“農業カレンダー”で、男女で作業を分担した様子も記されており、稲作の具体的な作業の流れを記述した最古の木簡となる。荘園の管理者が書いたとみられ、貴重な資料になりそうだ。
この木簡は長さ36・8センチ、幅11・1センチで、墨書は表裏両面にあった。種まきに関しては「種蒔(ま)く日 和世(わせ)種三月六日 小須弥女(こすみめ)十一日に蒔く」とあり、女性が苗代に早生(わせ)種の種をまいた様子がうかがえる。
また、収穫については「小支石(おきいし)という男性が七月□、十二、十四、十七、□日の5日間出勤して稲を刈った」と記載。「二百八十」の稲やわらの束などを、2回に分けて売ったとも記されていた。











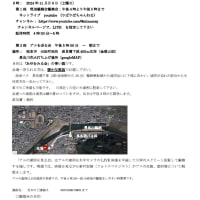














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます