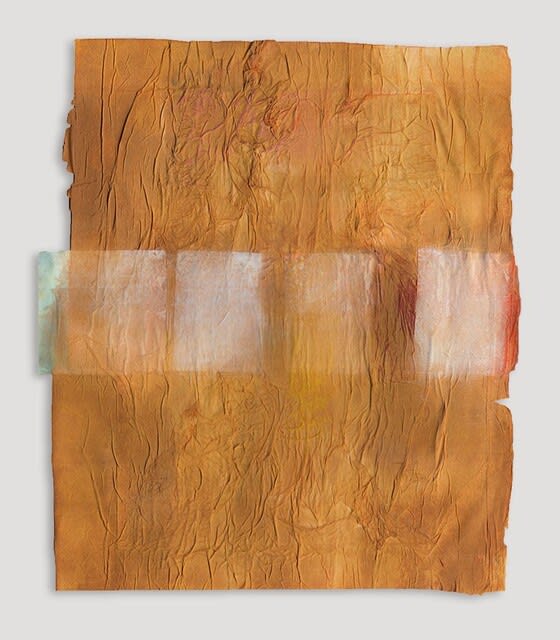
https://yykubo.tumblr.com/
愛することしかしないということ。 イスラエル-パレスチナ問題
報道ステーションで3人の娘たちを殺されたガザ地区のアブラエーシュという医師が、それでも憎まないと言っているのを見た。ネガティブにネガティブで対応しても解決しない。 復讐を選ぶことで墓穴を掘ることになると言う。
一方のイスラエルに住む歴史の教師は、パレスチナの子供が殺されている写真をSNSに掲げ、停戦を訴えたが、当局に拘束され、学校では教え子たちから追い出され、教職を解かれた。彼は裏切り者になった。 (「NHKスペシャル」で放映) 彼も、このガザ地区の医者と同じように「憎しみ」を選択しなかった。
「愛」はキリスト教が教えている最も大切な教えだが、ここに人は条件を付けた。 自国の正義に反する者は愛するに値しない。 それはユダヤ教も、イスラム教も同じ。 イスラエルも、合衆国も、他のどの国も強力な軍隊を持ち、核武装をし、国民を守るというお墨付きによって、自国の正義に反することには裁きを下し、戦い、報復する。
でも、この医師は「愛すること」しかしない。 正義の鉄槌を下す人々からすれば、なんとも情けなく、弱弱しく、現実を見ない愚か者か夢想者だ。
しかしもし、神がたった一つ、「愛」だけ、であるとしたら、二元的な愛と憎しみ、善と悪のの壮絶なバトルが続く(これはごく普通の人気映画のテーマだ。)世界に神は関わらないとしたら、神が憎しみや懲罰や攻撃や虐待をまったくこれっぽっちも持たないし、知りもしないとしたら、どうだろう。
これに対して、旧約聖書の神は、裁く神だ。 懲罰も、復讐も、破壊も、収奪もみな知っている。
「わたしは裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の御名はほめたたえられよ。」…ヨブ記1章13節~21節
旧約聖書に登場する神は恐ろしい。バベルの塔、ノアの箱舟、ソドムとゴモラも、人間の行いに神は天罰を下す。 ダビデに力を与え、敵を打ち滅ぼす。皆殺しにする。 偶像崇拝をするユダヤ人にも辛い試練を与える。 世の終わりには裁きを下す。
神がそうなのだから、その神を信奉する民もそのようになるのはごく自然なことではないだろうか。 彼らもやっぱり神に代わって正義の鉄槌を下す。 彼らは神の僕(しもべ)だからだ。 このことにほとんどの人は異を唱えない。 今、イスラエルが行っている戦いは、一朝一夕で始められたものではない。 彼らの行為には思想的にユダヤの伝統が重厚な後ろ盾として存在している。 それはユダヤ人の歴史を見ればわかる。 イスラエルはアッシリア、バビロニア、ペルシア、マケドニア、ローマに蹂躙されてきた。 実に紀元前6世紀から国を守るために、彼らの祖先は戦い、死んでいっているのだ。 我々外野が「仲良くしてね。」なんて言っても簡単に受け入れられるものではない。
→「イスラエルパレスチナ問題」 https://www.youtube.com/watch?v=T9L7ExUgEi0
ここで脱線するようだが、「正義」について、述べておかなければならない。 「正義」という言葉は、相対化されてしまった。 国同士が戦争を起こすとき、政治家はなんて言うかと言うと、凡そ「国民の命を守らなければならない」ということと、「正義を貫かねばならない」という、この2点だ。我々はお互いの国がこの同じ2点を掲げて、戦いに突き進んでいる様子を見ている。 どちらの正義なのかは勝敗が付くまで相対化され、決着がついた時に「勝てば官軍」、「歴史は強者によって作られる」と言われるように絶対化される。 これらを冷静に見た人はもう「正義」という言葉はただの飾りだと思うようになる。
もし、国として敗北しても、挫けずに「正義」を貫こうとするなら、テロをおこすしかなくなる。 もちろんテロという言葉は勝利した方が使う言葉だ。 彼らにとってはそれは「聖戦」である。
でも、本当の「正義」というものが、本来あるはずなのだ。 奇跡のコースはそれを以下のように説明する。
***********************************
愛は罪人にとっては理解不可能です。
なぜなら、罪人は、正義は愛から切り離されたものであり、何か他のものを表していると考えているからです。こうして、愛は弱いものであり、復讐は強いものであると知覚されます。なぜなら、審判が愛に味方しなくなった時に愛は敗北したのであり、罰から救い出してもらうには、愛は弱すぎるという事になるからです。しかし、愛がなくなった復讐は、愛から分離し隔離される事で強力になったことになります。愛が正義と活力を奪われ、打つ手もなく救い出す力もなく弱々しくたたずんでいる時、復讐以外に何がその人達を助け、救う事が出来るでしょう。…Text-25-8-8
***********************************
愛に満ちた正義が、神の子に受け取る権利があると知っているものを神の子が受け取る時、神は喜びます。
なぜなら、愛と正義には何の違いもないからです。その二つが同じものであるからこそ、慈悲が神の右に立ち、神の子に自らの罪を赦す力を与えるのです。
…Text-25-8-9
***********************************
本題に戻るが、実は、先述のユダヤ人の歴史の教師の選択にも、旧約聖書の後ろ盾があることを忘れてはならない。 それはまず、下記の箇所がある。
「復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。わたしは主である。」(レビ19:18)
「復讐と報いとは、わたしのもの、それは、彼らの足がよろめくときのため。彼らのわざわいの日は近く、来るべきことが、すみやかに来るからだ。」(申命記32:35)
さらにもっとも注目すべきなのが第2イザヤ書である。
なぜ第2というのかというと、このイザヤ書は3人の作者がいるとされ、バビロン捕囚の解放時に書かれた第2イザヤは、他のイザヤとまったく異なるからだ。 第2イザヤは、後にこの箇所はキリスト教によってイエスを予言するものとして重要視されることになる。
その中の第4詩は「苦難の僕」と呼ばれるもので、度重なる自分の民族に降りかかった苦難に対して、一般常識的な対応とは全く違う姿勢を説いた。 その部分を丸ごと下記に掲げる。
*****************************************
わたしたちの聞いたことを、誰が信じえようか。主は御腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。
見るべき面影はなく輝かしい風格も、好ましい容姿もない。
彼は軽蔑され、人々に見捨てられ多くの痛みを負い、病を知っている。
彼はわたしたちに顔を隠しわたしたちは彼を軽蔑し、無視していた。
彼が担ったのはわたしたちの病。彼が負ったのはわたしたちの痛みであったのに。
わたしたちは思っていた神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだ、と。
彼が刺し貫かれたのはわたしたちの背きのためであり彼が打ち砕かれたのはわたしたちの咎のためであった。
彼の受けた懲らしめによってわたしたちに平和が与えられ
彼の受けた傷によって、わたしたちはいやされた。
わたしたちは羊の群れ
道を誤り、それぞれの方角に向かって行った。そのわたしたちの罪をすべて主は彼に負わせられた。
苦役を課せられて、かがみ込み彼は口を開かなかった。
屠り場に引かれる小羊のように毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。
捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか
わたしの民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり命ある者の地から断たれたことを。
彼は不法を働かずその口に偽りもなかったのにその墓は神に逆らう者と共にされ富める者と共に葬られた。
病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ彼は自らを償いの献げ物とした。
彼は、子孫が末永く続くのを見る。 主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。
彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。 わたしの僕は、多くの人が正しい者とされるために彼らの罪を自ら負った。
それゆえ、わたしは多くの人を彼の取り分とし彼は戦利品としておびただしい人を受ける。
彼が自らをなげうち、死んで罪人のひとりに数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために執り成しをしたのはこの人であった。…イザヤ53章
**************************
岩田靖男という哲学者はこう言う。 「ここには悪業を裁き、悪業に報いる、という発想は全くない。 ただ、苦しみを引き受け続けるだけである。現代のユダヤ人哲学者レヴィナスの思想で言えばそういう受動性の極限の姿が神の栄光の現れである、ということになるだろう。」 (西洋思想史入門)
ただ、苦しみを引き受け続けるだけなのか? もし我々がご利益、家内安全、商売繁盛のために、神を信仰するのなら、その対価を得ることによって完結してしまう。 言わば取引成立ということだ。 それは他人に対しても同じである。 イエスが「お前たちに善くしてもらう者に善くしてたからと言ってお前たちにどんな善意があるのか。 罪人もまた同じものをお返しとして受け取るために罪人に貸すのである。」…ルカ6-33 と言ったことだ。 これをレヴィナスは「善行とは自分自身に還帰しない業」と言う。 人間はこの聖性をこの世に輝かせるために生まれ出た。
ユダヤの思想はここまで深まっていたのだ。
イエスの生涯はまさにこの「苦難の僕」であった。
イエスの弟子のパウロはこう言った。
「だれに対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。 あなたがたは、できる限りすべての人と平和に過ごしなさい。 愛する者たちよ。自分で復讐をしないで、むしろ、神の怒りに任せなさい。なぜなら、『主が言われる。復讐はわたしのすることである。わたし自身が報復する』と書いてあるからである。」…ローマ人への手紙 12:17-19
そしてイエスの生き方はさらに徹底したものだった。 たぶん、イエス自身は「神が復讐をする」なんてことも言わなかったはずだ。 言ったとしたら他のイエスが言った箇所と矛盾を起こしてしまう。 イエスはどこまでも愛の人だった。 パリサイ人たちの間違いを手厳しく指摘し、神殿境内では商売人を追い出したけれど、けっして剣に対して剣で対抗しなかった。 ゲッセマネの園でペテロは捕えに来た大祭司の手下の耳を切って抵抗したが、イエスはそれを止めさせた。そして、結局はむごたらしく殺されてしまった。 これはイエスの父である神が「愛」であり、復讐と裁きの神ではなかったからだ。 ここに第2イザヤ書が反映される。 イエスが生まれた時のエルサレムはもうすでに、入れ代わり立ち代わり、様々な国から蹂躙され、暴力の下にあった。 今と何も変わらない。
イエスの有名な言葉、「右の頬を打たれたら、左の頬も差し出しなさい」…マタイ 5章39節は、その後、換骨奪胎されてしまった。
前述のガザ地区の医者はイエスと同じ、常識外れの弱っちい馬鹿者だ。 ただ、この人はイエスと同じように「愛」しか知ろうとしなかった。 もちろん、彼は「憎しみ」を選ぶこともできた。 しかし選択肢は「愛」と決断した。 この人は「神の国」にしか住まないことを選んだ。 最愛の娘3人を殺されてどれほど苦しんだことだろうか。 それでも決断したのだ。 それは「それでも人生にYESと言う(trotzdem Ja zum Leben sagen)」とフランクルが言ったことに一致する。 フランクルも戦後、ナチの親衛隊だった人ともいっしょに山に登り、カトリックの信者と再婚して、同じユダヤ人から弾劾された。 彼も、このガザ地区の医者と同じように「憎しみ」を選択しなかった。
愛は本質的に拡張していく。 民族の壁を飛び越える。
そんな生き方もあるのだ。 愛だけ。 愛だけしか見ない生き方もあるのだ。
もし明らかな犯罪が行われ、被害を受けたとしても、愛が足らなくて、愛が欲しくてやってしまった間違いなのだと理解することもできるのだ。 正義の鉄槌を下す常識人にはこれはまるで馬鹿に見えるかもしれない。 でも馬鹿でいい。 ただ、一つのこと、憎しみの連鎖に入るよりはいい。
「あなたが愛だけを望むのなら、他には何も見ないでしょう。」 Text12-8-1
檸檬
高校時代に梶井基次郎という人が書いた「檸檬」という小説を読んだ。 日本の小説はいつもジメジメしていて、スケールが小さくて好きになれなかったが、これは別だった。 妙に気に入った。 それから半世紀が経ってしまったが、どういうわけか、今朝再び読むことになった。
この短編はこのように始まる。
「えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧さえつけていた。焦躁と言おうか、嫌悪と言おうか――酒を飲んだあとに宿酔があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。」
どういうわけか、ここ2,3日、これとそっくりそのままで、梶井基次郎の言い方を借りれば、私の不吉な塊は、以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。お気に入りの音楽を聴いても、最初の二三小節で止めてしまう。何かが私を居堪らずさせた。
何かが欠落してしまった。 どんな感動的な映画を観ても、本を読んでも、自然の中を散歩しても、欠落感が無くならなかった。 もちろんこの作家と同じ心境であったと言いたいのではない。 この作家はたぶん、実物のクオリア(質感)とイメージとしてのクオリア(質感)の違いに注目したのだろうが、私はクオリア以前の「もの自体」に著しく刺激された。 ジャック・ラカンは現実界を「不可能なもの」と定義している。 それは想像することが 不可能であり、象徴に統合することが不可能であり、到達することが不可能だからである。この象徴化への抵抗こそが、現実界にトラウマ的な質を与えていると言う。
それは「もの自体」の不可思議さである。 この小説の場合は、「檸檬」だった。 朝の坐禅中にこんなことが頭に浮かんだ。 この作者が丸善にしかけた「檸檬爆弾」は、そのデパートに溢れていた「色彩のガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた。」
私にはこれはイメージ(象徴)という情報の洪水の中に、「もの自体」がポンと爆弾のように投げ込まれたように思われた。 「もの自体」とは言わずと知れたカントの言葉だ。 全ては私たちの心(主観)にしか存在しない。 もの自体は認識できない。もの自体が現象として現れる。 心に像を結んだものが現象だとされる。
我々は五感によって世界を感知し、それを脳の中で、今までの過去の記憶や日本人としての生まれついた傾向、さらにもっと基本的な人間としての様々なフィルターを通して、再構築する。 この時、クオリアが生じる。または以前経験したクオリアがリコールされる。
クオリアとは広辞苑では「感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」のことだ。
昆虫や魚にクオリアは無いとする学者は多い。 彼らにはクオリアが必要ないからだ。 彼らは高性能な機械のように、ある情報が入力されれば、必ず一定の出力をする。そこにタイムラグはない。 瞬間的に危険を回避できる。 その点で人間よりはるかに優秀だ。 ところが人間の場合、入力と出力の間にクオリアがある。 人は過去の記憶や、それに伴うクオリアを思い出して、様々な予想をしたり、迷ったりする。 クオリアはその選択の背中を押す。 熱い薬缶に触ったら、まず最初に手を瞬間的にひっこめる。 その後に、ジンジンと痛みというクオリアがやってくる。 そして次にどういった行動をとるかの選択を迫る。 流水で冷やそうか、氷の方がいいかな。でも氷は冷凍庫にあったかな?、大したことはないかも、放っておこうか、なんて考える。
ここで覚えておいていいのは、クオリアの目的は我々の行動と選択を促すことだから、行動と選択がなされれば、お役目終了と考えていいということだ。 後で予想と違うようになってクオリアが戻ってきたら、またその時改めて考えればいい。 クオリアがずっと居座るのはよろしくない。 それはネガティブなクオリアだけでなく、ポジティブなクオリアについても言える。 夕陽を見て美しいと感動しても、それも痛みと同じように過ぎ去っていくのがよい。 なぜならばクオリア自体は本質ではないからだ。
ここで言いたいのは、生物には昆虫や魚のように必ずしも「感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」が必須のものではないということだ。 「もの自体」が現象として私たちの心に像を結ぶ。 それに伴って様々なクオリアが生まれるかリコールされる。 でもそれはもうすでにモニターVR画面を見ているのと変わらないのではないか。 つまり将来、映画「マトリックス」のようなモニターとしての脳のみの存在なんてことが可能になるのではないか?
逆にこう考えたらどうだろう。 もし本当に我々が水槽に入っている脳だったとしたら、現実だと思っている世界に我々を繋ぐのは、クオリアのみとなる。 脳の神経回路の反応だ。 改めてこう問いかけてみる。 水槽の外には何があるのだろうか?
坐禅を続けていると、目の前の感覚的体験、一時も止まらない、絶えず動いて変化しているこの感覚的体験に伴う質感、現れては消えていく思考、エピソード記憶と、この現実界、ジャック・ラカンの言った想像することが 不可能であり、象徴に統合することが不可能であり、到達することが不可能な「何ものか」、「もの自体」がバラける瞬間がくる。
縛り付けられていた感覚的体験に伴う質感が「もの自体」から離されるとき、世界は一つになる。 もはや目の前の花瓶と窓の区別がつかなくなる。 そして花瓶と自分の区別もつかなくなる。 名前を持たなくなる。 もちろん、それは何もかもが混ざったごった煮のようになるのではない。 感覚的体験はそのままある。 しかしそれは想像することも、象徴に統合することも、到達することもできないものとなる。 まさに「何ものか」があることがわかってくる。 「何ものか」を見ている自分はいない。
その先のことはまだ駆け出しの私にはわからない。 少しワクワクする。
白隠禅師和讃に次のような言葉がある。
「三昧無碍の空ひろく四智円明の月さえん」
訳:世界と自己が一体になった三昧の世界のひろやかさ。その三昧の大空には仏の智慧の光が、月のように光り輝いている。
東京の田舎、秋川渓谷にカトリックの坐禅堂がある。 ここで指導をしているアメリカ人の80歳を越えたシスターキャサリンは、このような白隠禅師和讃の境地に一瞬入ったことがあると言う。 でも自分は、まだまだだと言うのだそうだ。(ついさっき、娘から聞いた話)
いい話だ。 自分にはまだまだ知らない、体験していないものがある。 これって素晴らしいことだと思う。 ホンモノはいつも謙虚だ。
自己距離化と自己超越
何か自分の意図に反することが起きている時、心がザワザワしたり、嫉妬したり、恐怖が襲ってきたり、鬱になったり、絶望的になったり、不安になったりするのは、自我がやっていることであり、その自我との距離を取ることが大事。そうすれば、客観視し、笑い飛ばせるようになると言われる。
これをフランクルは「自己距離化」と言う。 自己距離化には「逆説志向」という方法がとられる。 吃音の少年が学芸会で吃音の役を与えられ、意図してどもりながらセリフを話そうとしたところ、ちっともどもることができず、ついにその役から降ろされてしまったというエピソードがある。 自分の話し方に過度に志向し、過度に反応することによって生じてしまった吃音が、逆にどもろうと逆説的に志向したら、どもらなくなったのだ。これは逆説志向によって自己距離化が可能になり、効果を生んだ例だ。。
それでは身体的な苦痛はどうだろうか? これについてはフランクルはこう言う。
「…ガンの痛みは自我ではなくむしろ確実に視床に属している。しかし…故人を失った悲しみは、確かに人間に属しているのであり、視床に属しているのではない。」
私は数週間前まで歯痛があり、この身体的な苦痛にどう対処すればいいか、試行錯誤していた。 何かスピリチュアルな方法で、それをすると痛みが無くなるような特別な方法があるのではないかなんて思った。 でも結局のところ、一番いいのは、なんてことはない、単純に、ちゃんとした歯医者に行くことだった。 神経を抜いてもらったら一発で歯痛は収まった。 当たり前の話。 これはフランクルが言うように脳の視床の話だった。
ただし、「自己距離化」は、この身体的な痛みが、例えば、歯医者がお盆休暇だったり、またはヤブ医者だったとして我慢しなければならない状況に陥った時には、やはり有効になる。 もちろん、痛みは変わらない。 しかしここの身体的苦痛が引き金になって、自我による未来への不安や恐れに堕ちこんでいくのを防いでくれる。 この時、痛みで「ある」のではなく、痛みを対象化して「持つ」ということになる。 これは身体的な苦痛から、日常的な苦悩にまで適用される。 距離を作って対象化することで笑い飛ばせるようになる。 ジョーン・トリフソンが言ったように、「ああ、またジョーンが二元のダンスを踊っているな」と言うことができるようになる。
快川和尚の「心頭滅却すれば火もまた涼し」という言葉は、無念無想の境地に至ったら火さえも涼しく感じられるということだと言われるが、確かに厳冬のヒマラヤで真裸で生活して、凍傷にもならないヨーギのような人も実際にいる。 つまり自在に身体的反応を制御することが可能らしいが、私のようなナマクラにはあまりにもハードルが高い。
これと同時にもう一つのことが言われる。 それは自己超越だ。
私たちは通常、自己を意識していない。 自分の身体維持に脅威を及ぼされるような情報を得た時に自己を意識し始める。 例えば、私たちは熱いストーブに触ってしまった時に「アチッ」と手を瞬間的にひっこめる。その時、手を引っ込める身体的な反応が先に来て、そのすぐ後から痛みを感じる。 痛みを感じ始めてから自己を強烈に意識し始める。 そしてこれは身体的なものではなく、家賃が上がりそうだなんていう情報だけであっても、同じように作用する。 つまり実際に自分の身体維持に脅威がおこった瞬間は自己を意識する前に身体の方で反応するが、将来に脅威が起こりそうな場合に自己を意識し始める。
その時、恐怖や不安がおき、自己を意識する。 それは人間に予めプログラムされているのであり、だからこそ、私たち人間は来年、不作が起こる予想を立てて、備えるということができるようになったわけだ。 ここで起きる恐怖や不安は、行動するための原動力となる。恐怖や不安(クオリア)は我々の行動の背中を押すのであり、私たちの生命維持には欠かせないものなのだ。
しかしこれが過剰に発動されるとき、我々は自分で自分の首を絞めることになる。 実はまったく実際には脅威が起こっていないのに、我々は絶えず恐怖と不安におびえることになる。
すべての人にこの恐怖と不安がある。 そして身体の最大脅威としてすべての人に死がある。 これからは誰も逃れられない。 この恐怖と不安に対処するために、我々はそのことを、いつか、知らない、特定できないこと、そして周りの人はみなそうなっているが、自分には例外として死が来ないかもしれない、少なくとも今日、明日ではないと、自分で自分を騙している。 そして現在だけを生きようとしている。
ハイデガーはこれを「頽落」と呼び、好奇心、世間話、曖昧さを示していると言った。 例えばYoutubeやTikTokは次から次へと新しい動画が流れ、思わず時間を忘れて見てしまう。1つの動画を見ても、また面白い動画が待ってるかもしれないという予期がある。 街に出ると、ほとんどの人がスマホとにらめっこをしている。 ゲーム、ライン、そして様々なゴシップ、動画、それらはみな、死への不安と恐怖から逃れる絶好の道具となっている。 これらは世話話のレベルであり、曖昧さは許容される。 好奇心、世間話、曖昧さは道具に対応する配慮的な気遣いや人間関係に対応する顧慮的な気遣いから解放され、責任や重荷を忘れることができる。
自己超越は、自己忘却ではない。 ハイデガーの言う頽落は自己忘却であり、実存から逃避している。 これに対して、フランクルの言う自己超越は、逃避ではなく、逆に自己を見つめていく。 自分の苦悩、逆境を見つめていく。 その点で、自己距離化の逆方向に進んでいるように見える。
フランクルは先にこう言った。 「故人を失った悲しみは、確かに人間に属しているのであり、視床に属しているのではない。」 自分の妻が病気の苦痛の中で亡くなったという現実があった時、先ほどと同じように自己距離化をして、客観化し、笑い飛ばしていいのだろうか? これは幻想であり、夢なんだと思い込んで、離れていいのだろうか? フランクルはニーチェの「生きるべき『何故』を知っている者は、ほとんどすべての『いかに』に耐える」という言葉を類繁に引用する。 つまり、われわれは苦悩そのものに苦しむのではなく、苦悩に意味がないことに苦しむ。 逆に言えば、意味のある苦悩というものがあるとフランクルは強調するのだ。
もし非二元の人たちが、目の前で起こっている悲惨な出来事、紛争や虐殺、それらはみな幻想であり、夢なんだと片づけて、意味のある苦悩から逃避しているのなら、その先の真の自己超越にまでは至らないように思う。 彼らは結局、彼らの好みの別の幻想、夢、桃源郷、信念をこしらえて見ているに過ぎない。
自己超越は苦悩を受け止めて、自分を見つめていった先にたどり着く反転だと思う。 別の言葉で言えば、「降参」のことだ。 もうお手上げ。 もうダメ。 その時、「脱反省」が起こる。 エゴから離れ、過剰な反省を止める。 反省とは自己を省みて、自己の負い目を確認し、自分で矯正しようとすることだ。 自分の負い目を確認し、自分で矯正することもあきらめた時、「脱反省」が可能になる。 自己超越が起こる。 自分を超えた大いなる存在に自分を預けてしまう瞬間だ。
自己超越(非対象化)は自己距離化(対象化)と矛盾するように思えるが、実は自己距離化をして、対象化している時の、対象を見ている主体は、非対象化した大いなる存在なのであり、矛盾はしない。 これを非二元の人は「気づき」と言う。