年末から読んだ本のことを書きます! 何故か白石一文と乙川優三郎の二人の作品!
12月27日(日) 「ほかならぬ人へ」(白石一文著)

「ベストの相手が見つかったときは、この人に間違いないっていう明らかな証拠があるんだ」…妻のなずなに裏切られ、失意のうちにいた明生。半ば自暴自棄の彼はふと、ある女性が発していた不思議な“徴”に気づき、徐々に惹かれていく…。様々な愛のかたちとその本質を描いて第一四二回直木賞を受賞した、もっとも純粋な恋愛小説。
12月30日(水) 「私という運命について」(白石一文著)

大手メーカーの営業部に総合職として勤務する冬木亜紀は、元恋人・佐藤康の結婚式の招待状に出欠の返事を出しかねていた。康との別離後、彼の母親から手紙をもらったことを思い出した亜紀は、2年の年月を経て、その手紙を読むことになり…。―女性にとって、恋愛、結婚、出産、家族、そして死とは?一人の女性の29歳から40歳までの“揺れる10年”を描き、運命の不可思議を鮮やかに映し出す、感動と圧巻の大傑作長編小説。
白石一文作品としてはなかなか良いできの作品でした。3人の手紙形式の構成が効果的でした。
1月4日(月) 「脊梁山脈」(乙川優三郎著)

物語が始まるのは1946(昭和21)年。上海へ留学中に応召し、復員してきた23歳の矢田部信幸は、故郷へ向かう列車のなかで小椋康造に助けられる。その後、小椋を探すうちに木地師だとわかる。ろくろを回して、木で椀(わん)や盆、こけしなどを作る古代からの職人だ。矢田部は、かつて漂泊の民だった木地師の源流を求めて、各地の山間を旅する。それは、戦争で失ってしまった生の実感を取りもどす旅でもあった。
歴史には残らない下級武士や町人、芸に生きる女性らの人生の哀歓を、端正な文体で描いてきた時代小説の名手が、初めての現代小説に取りくんだ。
乙川優三郎の世界にのめり込みそう!?
1月6日(水) 「一瞬の光」(白石一文著)

橋田浩介は一流企業に勤めるエリートサラリーマン。38歳という異例の若さで人事課長に抜擢され、社長派の中核として忙しい毎日を送っていた。そんなある日、彼はトラウマを抱えた短大生の香折と出会い、その陰うつな過去と傷ついた魂に心を動かされ、彼女から目が離せなくなる。派閥間の争いや陰謀、信じていた人の裏切りですべてを失う中、浩介は香折の中に家族や恋人を超えた愛の形を見出していく。
著者はデビュー作である本書で、「人は何のために生きるのか」「人を愛するとはどういうことか」という大きな問題に取り組んでいる。観念的になりがちなテーマを軸にしながらも、背景となる企業社会を残酷なまでにリアルに描くことで、地に足着いた存在感のある物語を作り上げた。無慈悲な現実の渦に見え隠れする感動、生きる喜び。そうした一瞬の光を求めてがむしゃらに生きる一人の男の姿が、そこにはある。
1月9日(土) 「霧の橋」(乙川優三郎著)

刀を捨て、紅を扱う紅屋の主人となった惣兵衛だったが、大店の陰謀、父親の仇の出現を契機に武士魂が蘇った。妻は夫が武士に戻ってしまうのではと不安を感じ、心のすれ違いに思い悩む。夫婦の愛のあり方、感情の機微を叙情豊かに描き、鮮やかなラストシーンが感動的な傑作長編。第七回時代小説大賞受賞作。
1月11日(日) 「五年の梅」(乙川優三郎著)

友を助けるため、主君へ諌言をした近習の村上助之丞。蟄居を命ぜられ、ただ時の過ぎる日々を生きていたが、ある日、友の妹で妻にとも思っていた弥生が、頼れる者もない不幸な境遇にあると耳にし―「五年の梅」。表題作の他、病の夫を抱えた小間物屋の内儀、結婚を二度もしくじった末に小禄の下士に嫁いだ女など、人生に追われる市井の人々の転機を鮮やかに描く。生きる力が湧く全五篇。
1月13日(水) 「麗しき花実」(乙川優三郎著)

蒔絵師の兄を手伝うため、江戸に出てきた理野。 しかし、兄が突然帰らぬ人となり、女の蒔絵師として原羊遊斎に師事することになってしまう。彼女は、女の情念を込めた、この世に一つとない蒔絵を完成させるために、人生の全てを蒔絵に注ぐが……。
酒井抱一、鈴木其一など、実在の人物を絡めて蒔絵職人の世界を描いた傑作。
「題名にある花実には外観と実質という意味もあり、江戸工芸の素晴らしさと内実を掘り下げながら、美とともに自立して生きようとする女性を描いたつもりである。理野のような女性が堂々と生きてゆける世の中であってほしいという願いもあった。蒔絵の限らず、人の手が創り出す美しいものには優しさと生命力があると思う。多難な時代だからこそ、進歩即ち豊かさという幻想は捨てて、何が人を本当に豊かにするかを探らなければならない」(連載小説『麗しき花実』を終えて) 朝日新聞2009/9/15


















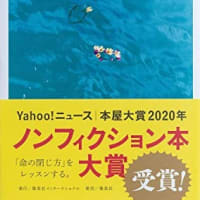

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます