1月16日(月) 「また、桜の国で」 (須賀しのぶ著)
 「戦争の悲しみ 民族超えて共有」 朝日新聞(12/4) *1
「戦争の悲しみ 民族超えて共有」 朝日新聞(12/4) *1
1937年10月1日、外務書記生棚倉慎はワルシャワの在ポーランド日本大使館に着任した。ロシア人の父を持つ彼には、ロシア革命の被害者で、シベリアで保護され来日したポーランド人孤児の一人カミルとの思い出があった。先の大戦から僅か二十年、世界が平和を渇望する中、ヒトラー率いるナチス・ドイツは周辺国への野心を露わにし始め、緊張が高まっていた。慎は祖国に帰った孤児たちが作った極東青年会と協力し戦争回避に向け奔走、やがてアメリカ人記者レイと知り合う。だが、遂にドイツがポーランドに侵攻、戦争が勃発すると、慎は「一人の人間として」生きる決意を固めてゆくが。
この練習曲は11月蜂起における1831年のロシアによるワルシャワ侵攻にほぼ同じくして公表された。ショパンは肉体的もろさのため暴動に参加することはできず、その怒りの感情を代わりにそのとき作曲した多くの作品にぶつけたとされる。その中で最も注目に値するのが、この革命のエチュードであり、失敗に終わったポーランドのロシアに対する革命が終結したとき、ショパンは「これは私に多くの痛みを残した。それを分かっていたのかもしれない!」と泣いたと伝えられている。が、伝記作家モーリッツ・カラソフスキーによる作り話から出たものだそうです。
「日本でそれほど知られていないこの時期のワルシャワを舞台に、一人の在ポーランド日本大使館外務書記生の運命を描いた小説が本書である。難しい外国語や資料の制約など幾重もの壁を乗り越え、これだけのスケールをもった小説に仕立て上げた著者の構想力に心を動かされる」(*1 原武史)
「革命前夜」も印象的だったが、他の作品も読みたくなった!
1月20日(金) 「みかづき」 (森 絵都著)

「私、学校教育が太陽だとしたら、塾は月のような存在になると思うんです」昭和36年。人生を教えることに捧げた、塾教師たちの物語が始まる。胸を打つ確かな感動。著者5年ぶり、渾身の大長編。
小学校用務員の大島吾郎は、勉強を教えていた児童の母親、赤坂千明に誘われ、ともに学習塾を立ち上げる。女手ひとつで娘を育てる千明と結婚し、家族になった吾郎。ベビーブームと経済成長を背景に、塾も順調に成長してゆくが、予期せぬ波瀾がふたりを襲い――。
「みかづき」の由来に触れられたシーンに納得。読み終えて爽やかな気分になった。
1月23日(月) 「ハリネズミの願い」 (トーン・テヘレン著)
 「人づきあいをそっと後押し」 朝日新聞(1/8)*1 売れてる本から
「人づきあいをそっと後押し」 朝日新聞(1/8)*1 売れてる本から
親愛なるどうぶつたちへ。きみたちみんなをぼくの家に招待します。……でも、誰も来なくてもだいじょうぶです。ある日、自分のハリが大嫌いで、つきあいの苦手なハリネズミが、誰かを招待しようと思いたつ。さっそく招待状を書き始めるが、手紙を送る勇気が出ない。もしクマがきたら? カエルがきたら? フクロウがきたら? ――臆病で気難しいハリネズミに友だちはできるのか? オランダで最も敬愛される作家による大人のための物語。
「贈ったり贈られたりして読者が増えている。友だちと仲直りできた人もいるとか。みんな中身に惹かれているのだ。… ケニアでマサイ族の医師を務めたとき、娘にせがまれて物語をつくり始めたにが作家になるきっかけで、ご本人もたいそう恥ずかしがり屋だそうだ。… 本当は友だちがほしい。そんな人の背中をそっと押してくれるあたたかい本。挿画も装丁も可愛くて、うん、誰かにプレゼントしたくなった。」(*1 最相葉月)
1月23日(月) 「帰郷」 (浅田 次郎著)
 「もう二度と帰れない、遠きふるさと」第43回大佛次郎賞受賞
「もう二度と帰れない、遠きふるさと」第43回大佛次郎賞受賞
学生、商人、エンジニア、それぞれの人生を抱えた男たちの運命は「戦争」によって引き裂かれた――。戦争小説をライフワークとして書く著者が、「いまこそ読んでほしい」との覚悟を持って書いた反戦小説集。戦後の闇市で、家を失くした帰還兵と娼婦が出会う「帰郷」、ニューギニアで高射砲の修理にあたる職工を主人公にした「鉄の沈黙」、開業直後の後楽園ゆうえんちを舞台に、戦争の後ろ姿を描く「夜の遊園地」、南方戦線の生き残り兵の戦後の生き方を見つめる「金鵄のもとに」など、全6編。
1月29日(日) 「オリーヴ・キタリッジの生活」 (エリザベス・ストラウド著)
 「すべての人生が、いとしく、切ない」 ピュリッツァー賞を受賞した珠玉の連作短篇集。
「すべての人生が、いとしく、切ない」 ピュリッツァー賞を受賞した珠玉の連作短篇集。
アメリカ北東部の小さな港町クロズビー。一見静かな町の暮らしだが、そこに生きる人々の心では、まれに嵐も吹き荒れて、生々しい傷跡を残す――。穏やかな中年男性が、息苦しい家庭からの救いを若い女性店員に見いだす「薬局」。自殺を考える青年と恩師との思いがけない再会を描いた「上げ潮」。過去を振り切れない女性がある決断をする「ピアノ弾き」。13篇すべてに姿を見せる傍若無人な数学教師オリーヴ・キタリッジは、ときには激しく、ときにはささやかに、周囲を揺りうごかしていく。
「メイン州の田舎町に住んで、まれにニューヨークへ出ることもあったが、あくまで臨時に滞在しただけで、生活の基盤は小さな町にある。この町を、読者はオリーヴの目を通してながめる。あるいは他のマイナーな主役とでもいうべき地元住民の目から見ることもあるが、いずれにせよ、いわば町の中から町を見る。その視点が交錯して、さまざまな角度から町の住人を見るのが大きな魅力になっている」と、下の本の訳者あとがきのある。短編集の不思議な魅力に接することができた作品でした。
1月31日(火) 「バージェス家の出来事」 (エリザベス・ストラウド著)

息子が事件を起こした、助けてほしい――妹からの電話をきっかけに、ニューヨークに住む兄弟は久しぶりに帰郷する。それは家族さえも揺れ動くことになる一年の始まりだった。
やり手の企業弁護士ジムと、ばかにされながらもジムを慕う、温厚な弟ボブ。ニューヨークで暮らす二人のもとに、ある日、故郷のメイン州に残ったボブの双子スーザンから電話がかかってきた。一人息子ザックが事件を起こして逮捕されるというのだ。助けを求めるスーザンに応じて、久しぶりに生まれ育った町に赴いたジムとボブ。しかしそれをきっかけに、三人きょうだいのそれぞれの生活は、少しずつ揺らいでいく。 じぇす
ジムとボブという兄弟の過去にあった古傷が物語の発生源になって、バージェス家の人々が変わっていくという意味で<バージェス家の出来事>なのである。ソマリ人移民のことも多く書かれてるが中身も意味も良く分からなかった!


















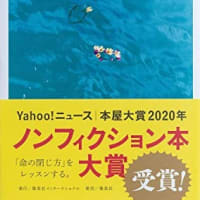

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます