
|
行徳河岸の『常夜灯』
市川市教育委員会の説明によれば、文化9(1812)年に日本橋界隈の成田参詣の講中が成田山新勝寺へ寄進したものだそうだ。 |

|
行徳河岸の『常夜灯』
市川市教育委員会の説明によれば、文化9(1812)年に日本橋界隈の成田参詣の講中が成田山新勝寺へ寄進したものだそうだ。 |
 どちらがお好き?
8年前
どちらがお好き?
8年前
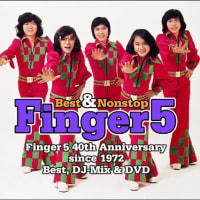 どちらがお好き?
8年前
どちらがお好き?
8年前
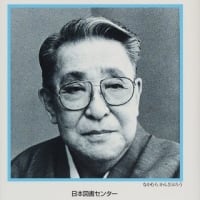 落語家;三代目 桂 三木助
8年前
落語家;三代目 桂 三木助
8年前
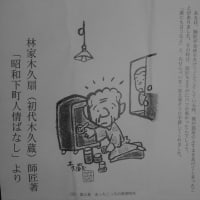 落語家;三代目 桂 三木助
8年前
落語家;三代目 桂 三木助
8年前
 寒夜
8年前
寒夜
8年前
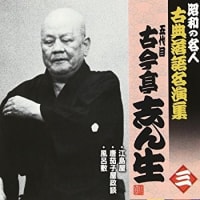 寒夜
8年前
寒夜
8年前
 寒夜
8年前
寒夜
8年前
 ナンタ
8年前
ナンタ
8年前
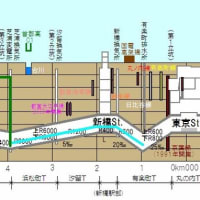 総武快速・横須賀線1 : 総武・東京トンネル
8年前
総武快速・横須賀線1 : 総武・東京トンネル
8年前
 季節(とき)知らず
8年前
季節(とき)知らず
8年前