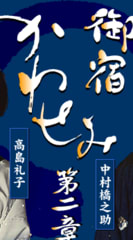どうしたら勝てるか
実に深刻な悩みを抱えています。と申しますのは、あるガキにどうしても勝てないからです。
何度も、チャレンジしました。手を変え品を替えて挑みましたが、その度にはねつけられ負けました。歯が立たないのです。悔しくって仕方ありません。どうぞ、皆様方のお知恵を拝借して、捲土重来を期したいものと念じおる次第です。
相手は“小便小僧”です。どのように頑張ってみても、あれだけの長い時間に渡 . . . 本文を読む
老々介護と学生時代の落研慰問旅行「ドサ廻り」
数日間に渡る関西への旅を終えて帰京した。観光の旅ではなく、墓参りのためと重篤な病人二人を見舞うためだ。はしゃぐことの許されない気の重い旅だった。
墓は樹木の剪定や草むしりなど、炎天下にはキツイ労働だった。二年間も放置しておいた罰だ。
病人はご夫婦だが、別々の施設に収容されている。ご主人の方は病のため惚けが進行し、この種の老人専門のケアー施設 . . . 本文を読む
礫(つぶて)
(イラスト:「御宿かわせみ」)
平岩弓枝の「御宿かわせみ」シリーズの拾巻目に『星の降る夜』という作品がある。ご存知の方も多いと思う。
この作品には、石礫が登場する。昼夜を問わず、突然地鳴りのような大音響とともに、石礫が飛来する。家具調度品が空中を飛び回り、ひどい場合には人間が死傷することもある怪奇現象だ。今流行の言葉で表現すると、超常現象ということになるのかも知れない。
. . . 本文を読む
末摘花初編(2)
①蚊帳一重 でも夜ばいには きつい邪魔
②誰が来る ものかと下女は 口説かれる
③抜くときに 舌打ちをする 大年増
④猿ぐつわ はめてと子守 泣いている
⑤ふんどしを はずす処へ てい主くる
⑥はないきの 出るとき抜いて 喰つかれ
⑦茶うすとは 美食のうえの 道具なり
⑧恋のやみ とは火を消して するのなり
⑨後家 . . . 本文を読む
末摘花
艶笑・川柳として名高い「末摘花」から10点選んでみた。
①蛤は 初手赤貝は 夜中なり
②女房に 茶臼引かせりゃ 引っ外づし
③孕んでも 己は知らぬと むごい奴
④十六で 娘は道具 そろうなり
⑤まだ伸びも せぬにもう来る 麦畑
⑥女房の 寝耳に下女の よがり声
⑦手を取ると 下女鼻息を 荒くする
⑧いたい事 ないと娘を 口説くなり
⑨き . . . 本文を読む
★本稿は、「江戸の都市政策」という観点から、「享保の改革」「寛政の改革」「天保の改革」の三大改革に関する代表的な議論を、本稿筆者が纏めたものである。しかし、筆者は、三大改革の歴史的性格を必ずしもこのようには考えない。それは極々大まかに云えば、「享保の改革」は「家康の頃に戻す改革」、「寛政の改革」は「享保の改革後の弛緩を正す改革」、「天保の改革」は幕府にとってどれだけ好ましくなくても、「近代日本」 . . . 本文を読む
童謡:赤い帽子 白い帽子
ご存知の童謡:赤い帽子 白い帽子 である。
(本歌)
赤い帽子 白い帽子 仲良しさん
いつも通るよ 女の子
ランドセル背負って おテテを振って
いつも通るよ 仲良しさん
(音羽ゆりかご会)*脚注参照
話は右往左往するが、近頃は「エイズ検診」が盛んになってきた。というわけで、童謡:赤い帽子 白い帽子 のパロ唄をおひとつ参ります。何方か二番を . . . 本文を読む
「セントレア空港」in海老フリャア:考
追加記事:★セントレア君に、ノーだって
中部国際空港が開港した。それに伴い、地元の町が合併後の市名候補である「南セントレア市」の適否を巡って争いが起きている。
その真因は何かというと、名古屋人には「セントレア」という発語・発音は無理なのだというところにある。名古屋人の意識の上では、「セントレア」と発語・発音しているつもりでも、吾人が聴くと「セントレャ . . . 本文を読む
浅草の楽しみ
(写真:360億年前〈洒落!)の岩塩)
久しぶりに旧友と逢って、浅草で会食した。このblogの1月21日のページでご紹介した「桜鍋・中江」で、【桜づくしコース】を楽しんだ。お値打ちのコースである。
「中江」のホームページからメールで頼むと、簡単で安心。その際、メールに「中江のホームページを見た」と付け加えておくと、帰りに浅草散策には便利なMAPまでくれる。
旧友も大いに満 . . . 本文を読む
天気と弁当屋
と言えば、勘の良い方なら直ぐ気が付かれるだろう。行楽に弁当は付き物だ。ましてプロ野球の球場に弁当やお摘み類を納品している業者なら、天気が死活問題になる。もっともこのお話は、我が国にドーム球場なるものが初めて出来たばかりの頃のことである。ビッグエッグ以外は未だドーム球場はなかった。当然、輩もサリーマン現役であった。
取引先に、西武球場をはじめ首都圏の複数の球場に弁当を納めている弁 . . . 本文を読む
江戸探訪「八丁堀」●八丁堀与力・同心と小伝馬町牢獄 その2
3.同心
町奉行に属し、与力の支配をうけた足軽身分の者で、享保4年(1719)に2人の町奉行のもとに100人宛、合計200人というように、南北両奉行に各100人から120人、合計200人から240人の時期が長い。
同心の役格は年寄役、増年寄役、年寄並、物書役、物書役格、添物書役、添物書役格、本勤・本勤並、見習い、無足見習いの11に分かれ . . . 本文を読む
江戸探訪「八丁堀」●八丁堀与力・同心と小伝馬町牢獄 その1
1.町奉行所
江戸幕府の職名。幕府の重要都市(江戸、大坂、長崎、駿河など)の民政をつかさどるためにおかれた。その名称は戦国大名家からはじまり、永禄年間(1558-69)のころよりみられるが、江戸時代には単に町奉行という場合は、江戸の町奉行のことをいう。
町奉行所は御番所(ごばんしょ)とも呼ばれ、役所と同時に役宅であって、表が役所、奥が . . . 本文を読む
江戸探訪「八丁堀」●八丁堀の七不思議
(イラスト:八丁堀の旦那)
八丁堀の七不思議には諸説がある。ここでは三説を取り上げた。まず、安藤菊二著の「八町堀襍記(ざっき)」から紹介してみる。(編者が現代文に置き換えるなど、抄訳した)
★(出典)「八町堀襍記」安藤菊二著、郷土史だより、第43号、1984.3.31京橋図書館発行
(前文略)…八丁堀の方は、ねっから不思議でないところに話の落をつけて . . . 本文を読む