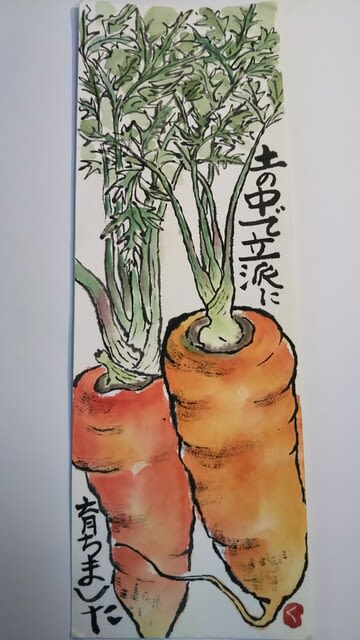広島駅北口から徒歩圏内の二葉の里に鎮座する「広島東照宮(広島市南区二葉の里2丁目)」へ参拝しました。徳川家康公を御祭神にお祀りした神社です。

徳川家康公薨去(こうきょ)後三十三年忌に当たる1648年(慶安元年)、広島東照宮は、時の広島藩主浅野光晟(みつあきら)公(浅野家第四代)により、広島城の鬼門(北東)の方向に当たる二葉山の山麓に造営されました。
 1945年(昭和20年)8月6日の原子爆弾の熱風により、檜皮葺(ひわだぶき)本殿、中門、瑞垣、拝殿は焼失しました。現在の社殿は、1965年(昭和40年)、徳川家康公薨去後三百五十年祭を記念して再建されたものです。
1945年(昭和20年)8月6日の原子爆弾の熱風により、檜皮葺(ひわだぶき)本殿、中門、瑞垣、拝殿は焼失しました。現在の社殿は、1965年(昭和40年)、徳川家康公薨去後三百五十年祭を記念して再建されたものです。

徳川家康公は、1542年(天文11年)12月26日、三河国(愛知県)岡崎城で誕生。当時は戦国時代で、幼少から大変苦労をしましたが、よく困難に耐え、時節の到来を待ち、関ヶ原の戦いに勝利。混乱の世に新たな秩序をつくり、学問をすすめ、産業を興し、生活の安定を図り、江戸時代二百六十余年にわたる平和と文化の礎を確立し、近世日本の発展に偉大な寄与をしました。1616年(元和2年)4月17日、75才をもって駿府城で薨去。
 「東照公御遺訓」(慶長九年一月十五日)は、徳川家康公の体験による処世の秘訣を示しており、今日においても一段と深い意義を有しています。
「東照公御遺訓」(慶長九年一月十五日)は、徳川家康公の体験による処世の秘訣を示しており、今日においても一段と深い意義を有しています。

東照公御遺訓…
人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し、急ぐべからず。
不自由を常と思えば不足なし。
心に望おこらば、困窮したる時を思ひ出すべし。
堪忍は無事長久の基、いかりは敵とおもへ。
勝事ばかり知てまくる事をしらざれば害其身にいたる。
己を責て人をせむるな。
及ばざるは過ぎたるよりまされり。
 唐門・翼廊・手水舎・本地堂・御供所・脇門・神輿および麒麟獅子頭は、広島市の重要文化財に指定。いずれも創建の頃より存在するもので、広島の歴史・文化上価値が高いものです。
唐門・翼廊・手水舎・本地堂・御供所・脇門・神輿および麒麟獅子頭は、広島市の重要文化財に指定。いずれも創建の頃より存在するもので、広島の歴史・文化上価値が高いものです。
唐門・翼廊…



本地堂…

神輿(収納庫)…

金光稲荷神社(境内社)…三百年以上前、元禄の頃よりこの二葉山山頂に祀られる。商売繁盛、家内平安等、所願成就の大神として、金光稲荷大神と称えられてきました。山頂の奥宮までの階段約五百段、朱塗鳥居百二十数基。






































 広島北IC(広島市安佐北区安佐町飯室)から国道261号線を北上し、鈴張(広島市安佐北区安佐町)と北広島町(広島県山県郡)との境にある明神峠へと……鈴張から明神峠付近までの2kmで見られる純白の凛とした棚田の雪景色です。
広島北IC(広島市安佐北区安佐町飯室)から国道261号線を北上し、鈴張(広島市安佐北区安佐町)と北広島町(広島県山県郡)との境にある明神峠へと……鈴張から明神峠付近までの2kmで見られる純白の凛とした棚田の雪景色です。 ペルーの遺跡になぞられる「鈴張のマチュピチュ」の棚田の冬景色が広がっています。
ペルーの遺跡になぞられる「鈴張のマチュピチュ」の棚田の冬景色が広がっています。