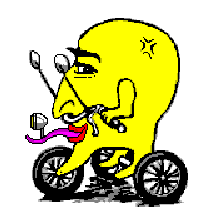六本木アートナイト2013
アートナイトに行かナイト!ということで4回目のナイト見物。初回の日記を見たら、「アートナイトというなんだかよくわからないイベント」と書いてあった。4回目だけに、何をやりたいイベントなのかはわかったつもり。今回のアーティスティックディレクターはダンボール大好きな日比野克彦氏。毎回ディレクターが変わるので、イベントの色合いや面白さも当然変わってくる。面白く感じるかどうかは参加者次第。
今回は17:00頃から11人集まってぞろぞろ見物。六本木の人混み暗がりで何度も行方不明者を出しながら、初めての徹夜に挑戦。結局朝まで残ったのは8人という好成績で幕を下ろした。
アートナイト中は美術館も遅くまで開いていて、国立新美術館の展示は観覧無料だったので、「アーティスト・ファイル2013」、「カリフォルニア・デザイン1930-1965」、「第66回 日本アンデパンダン展」をまとめて見てしまった。無料でホントに大助かりである。サントリー美術館では観覧料1300円のところ割引価格500円だったので「歌舞伎 江戸の芝居小屋」を観覧。森美術館は24:00~06:00が1000円に割引されていたようだ。やたら評判の良い「デザインあ展」は(超満員なう)とかツィートしている人が居たので、近づきもしなかった。
もちろん六本木アートトライアングル界隈の道端にはいろいろなアーティストの作品やパフォーマンスが点在していて、ブラブラ歩きながらそれらを見て回るのがいちばんの楽しみでもある。
徹夜とはいえ、歩きっぱなしというわけでもなく、夜中に2時間以上喫茶店であーでもないこーでもないそーでもないなんでもないとウダウダ過ごしたりしていたので時間が長く感じることもなかったし、気温も意外と安定していて、真夜中にうろうろしていても寒さに震えることもなく過ごせた。
ヒルズアリーナの灯台

志村信裕 《hundreds of boots》

ミッドタウンの桜ライトアップ

柴田祐輔 《クリーニング・ディスコ》

日比野克彦 《動きたい水灯台・動かない土灯台》

六本木アートナイト2012のブログ
六本木アートナイト2010のブログ
六本木アートナイト2009のブログ
アートナイトに行かナイト!ということで4回目のナイト見物。初回の日記を見たら、「アートナイトというなんだかよくわからないイベント」と書いてあった。4回目だけに、何をやりたいイベントなのかはわかったつもり。今回のアーティスティックディレクターはダンボール大好きな日比野克彦氏。毎回ディレクターが変わるので、イベントの色合いや面白さも当然変わってくる。面白く感じるかどうかは参加者次第。
今回は17:00頃から11人集まってぞろぞろ見物。六本木の人混み暗がりで何度も行方不明者を出しながら、初めての徹夜に挑戦。結局朝まで残ったのは8人という好成績で幕を下ろした。
アートナイト中は美術館も遅くまで開いていて、国立新美術館の展示は観覧無料だったので、「アーティスト・ファイル2013」、「カリフォルニア・デザイン1930-1965」、「第66回 日本アンデパンダン展」をまとめて見てしまった。無料でホントに大助かりである。サントリー美術館では観覧料1300円のところ割引価格500円だったので「歌舞伎 江戸の芝居小屋」を観覧。森美術館は24:00~06:00が1000円に割引されていたようだ。やたら評判の良い「デザインあ展」は(超満員なう)とかツィートしている人が居たので、近づきもしなかった。
もちろん六本木アートトライアングル界隈の道端にはいろいろなアーティストの作品やパフォーマンスが点在していて、ブラブラ歩きながらそれらを見て回るのがいちばんの楽しみでもある。
徹夜とはいえ、歩きっぱなしというわけでもなく、夜中に2時間以上喫茶店であーでもないこーでもないそーでもないなんでもないとウダウダ過ごしたりしていたので時間が長く感じることもなかったし、気温も意外と安定していて、真夜中にうろうろしていても寒さに震えることもなく過ごせた。
ヒルズアリーナの灯台

志村信裕 《hundreds of boots》

ミッドタウンの桜ライトアップ

柴田祐輔 《クリーニング・ディスコ》

日比野克彦 《動きたい水灯台・動かない土灯台》

六本木アートナイト2012のブログ
六本木アートナイト2010のブログ
六本木アートナイト2009のブログ