下記の記事は東洋経済様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。
「なんだか眠れない……」「なんとなく胃の調子が悪い……」「なぜか胸が苦しい……」こういった不調は、自律神経乱れが原因かもしれません。自律神経の乱れは、長引くとうつ病をはじめとするさまざまな疾患を引き起こすおそれがあります。本稿では、『忙しいビジネスパーソンのための自律神経整え方BOOK』から抜粋し、自律神経を整える「考え方」の習慣を紹介します。
ストレスを感じたときは、脳を意識的に切り替える
自律神経失調の症状がある方の多くは、そもそもストレスを抱えていて、悩みが頭の中でグルグルと回っています。あなたも、ふと気がつくとストレスになっている仕事や人間関係などで頭がいっぱい――そんな経験はありませんか?
どうせなら、楽しいこと、好きなこと、リラックスできることを思い浮かべる癖をつけましょう。ストレスになることが頭に思い浮かんできたら「よくないことを思い浮かべているな」と思い、楽しいこと、好きなこと、リラックスできることを頭に思い浮かべてください。
普段からでも、楽しいことや好きなこと、リラックスできることを思い浮かべていいのです。
こう言うと、皆さんはそんなにすぐに楽しいことなんて考えられないし、考えたって楽しくなんてならない、と思うかもしれませんが、このエクササイズは無理矢理考えても大丈夫です。
これにはしっかりとした理由があるのです。というのも、脳は見ているものを自分の実体験だと勘違いする性質があるからです。
自分の頭の中で、楽しい情景や、リラックスできることをなるべく鮮明に思い浮かべると、しだいに自分が今、実際にやっているのだと勘違いしてくれます。
楽しいこと、好きなこと、リラックスできることというのは、副交感神経を働かせてくれる状況なので、考え方を変えるだけで、体をリラックスする状況に切り替えることができるのです。
「認知の歪み」という言葉をご存じですか?
これは、ストレスを溜めやすい方が陥りがちな考え方のパターンを表しているもので、アメリカの精神科医デビッド・D・バーンズ博士が提唱している新しい認知療法です。これをビジネスパーソンでストレスを溜めやすい方の考え方のパターンに当てはめると、2つに分けられます。
1つ目は、完璧主義の考え方で、100点を取らないと気が済まない、「〜しなければならない、といった思考」がその典型です。
2つ目は、ネガティブな考え方で、小さな失敗を大きなミスだと思う、これで全てが台無しだと考える、悪いことばかりに視点を向けてしまう、根拠もないのに未来はきっと悪くなると考えるなどがその典型です。
ビジネスの現場でこのような考え方をしていると、同じことが起きていても、ほかの人はストレスに感じていないのに、自分はストレスに感じてしまうということになりやすいのです。
すると、何をやってもストレスになって、いつも交感神経を活発に働かせてしまう状況をつくりだしてしまうのです。
ビジネスの現場に合わせた「脳の切り替え方」
では、実際にビジネスの現場に合わせた「脳の切り替え方」を見ていきましょう。
① 完璧主義をやめてみる 物事を白か黒か、ゼロか100かという視点でしか見ることができず、白黒つけなければ納得できないという思考パターンです。
ビジネスの現場の例では、任された仕事は何としてでも高い評価を取らないといけないと考え、「ミスをすることは許されない」と、過度に自分を追い込んでしまう、というものです。
また、上司があいまいだったり間違った指示をしてくると怒りが込み上げてきたり、好きか嫌いかだけで分けてしまう……なども当てはまります。
対処法としては、あいまいさを許容する気持ちを持つことです。
世の中のほとんどは、あいまいなことなので、許して受けいれるということができれば、このストレスの負担を大きく減らすことができます。
人の意見が変わったり、間違ったことをしたりしたとしても同じ人間なんだから当たり前と考えたり、無理して100点取るよりも、無理をしないで90点取れればいいという考え方に切り替えましょう。
② よくない出来事が起こり続けると考えない 一度よくない出来事があったら、いつもよくないことばかりだと思ってしまったり、たった1人に嫌われただけなのに、みんな私のことが嫌いなのだと思ってしまうような思考パターンがあります。
ビジネスの現場の例では、1週間のうちで6日間は、うまく仕事ができていたのに、1日でも失敗があると「いつも自分は失敗ばかりだ。出世することもできない」と思ってしまうなど、悪い状況を一般的なものだと考えてしまうような状態です。
対処法としては、全体を客観的に考えることです。
先ほどの失敗例でいえば、1週間を7日と考えて、7分の6はうまくいっている。失敗したのは7分の1だから、たった1日うまくいかなかっただけだと思うようにするのです。
たった1度の最下位なんてどうでもいい
一度起きたよくない出来事を、たまたま起きただけだ、いつもではない、と考えて冷静に見ることができれば、この思考パターンによるストレスを減らすことができます。
③ 悪いことだけを見ない 全体の中の1つのよくないことだけに目が向いて、よいことが見えなくなり、悪いことばかりが見えてしまうという状態に陥ることがあります。
たとえば仕事をしているとき、長らく営業でよい成績を取っていたのに、一度だけ最下位の営業成績になったとします。このとき、最下位になったことばかりが気になって、このままクビになるのではないかと思ってしまう、というような状況です。これは、最下位になったショックがあまりに大きく、仕事全体に対して不安感を抱いてしまっているのです。
対処法としては、よいことに目が向いていない状態なので、視点を悪いことからよいことに切り替える必要があります。
たった1度の最下位なんてどうでもよく、ずっとよい成績を残し続けていることのほうがすごいことなのです。
④ マイナスにとらえすぎない マイナス化思考とは、プラスの経験を「マイナス化」してしまったり、よいことを悪いことにすり替えてしまったりする考え方のことです。
せっかく成功したことを、「どうせ、まぐれだ」と考えがちなあなたは要注意。うまくいったことを、偶然だとか、たまたまだというふうにとらえていると、成功したことを素直に喜べなくなり、よかったとかうれしいとか思うことがなくなってしまいます。つまり、成功体験そのものを感じられなくなってしまうのです。
そうすると、何をやってもうまくいかないとか、うまくいっていることもうまくいっていないと勘違いしてしまうことが起きるのです。このようにマイナス化してとらえていたら、何をやっても楽しくなく、やる気も起きなくなってしまいます。
仕事でうまくいった、成功したということがあれば、成功を成功として素直にとらえることが必要です。また、まぐれではなく、努力の結果なのだと、客観的にとらえることが必要となります。できたことは、素直に喜ぶようにする習慣をつけていきましょう。
⑤ 根拠のない結論を出さない 根拠もないのに、悪い結論を勝手に予測する考え方をやめましょう。
1つ目は、人に対しての考え方で、「心の読みすぎ」というものがあります。本当のことは本人から聞かなければわからないのに、他人の行動を勝手に決めつけてしまう……という思考パターンです。
他人が黙っているのを見て、怒っているのだろうと決めつけたり、そっけない態度をされたら嫌われていると思い込んだりなど、他人の顔色を気にしすぎてしまう方が、このタイプに当てはまります。
2つ目は、物事に対しての考え方で、「先読みの誤り」というものがあります。結論を悪く決めつけてしまう思考パターンです。
「私はこのまま出世することができない」「私は一生、平社員のままだ」など、と、先を悪いほうに読んで考えています。
2つのケースとも、根拠のない結論を出さないことが必要です。
根拠がないのなら、よい結論を出すことも自由です。勝手に悪い結論に決めつけて悩み苦しむよりも、よい結論に決めつけて明るく希望を持って行動しよう、と考えてみましょう。
成功は成功、失敗は失敗
⑥ 拡大解釈や過小評価をしない 失敗や悪いことを大きく考え、成功やよいことを小さく考えるという思考パターンがあります。
こういった思考に陥ると、小さなミスが大失敗に感じられ、社会人として最低だ、この会社を辞めたほうがいいと、自分で勝手にことを大きくしてしまいます。
小さなミスは、小さなミスであり、台なしではないと考えましょう。
失敗は成功のもとという言葉があるとおり、小さなミスは、大きな成功のもとかもしれません。ミスは行動した結果です。どんどんチャレンジして、ミスをたくさんしたほうが、後でいろいろなことに気配りができ、大成功することができるかもしれません。
私もうつ病を克服した方法を基にこの整体院を開業し、皆さんのお役に立つことができています。成功は成功。失敗は失敗。いいことはいいこと。悪いことは悪いこと、という客観的な視点を持つことが必要です。
⑦ 感情的に物事を決めつけない 自分の感情が現実であると思い込んでしまうという思考パターンがあります。
自分が不安を感じている → だから失敗する
自分の気分が落ち込んでいる → だからこのままやらないほうがいい
など、自分の感情によって世の中の正しさを決めたりしていませんか?
時間があまりとれなかったために不安に陥り、仕事はすべて失敗だと考えてしまったりなど、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。
やみくもに時間を費やしたからといって、必ずうまくいくとは限りません。
少なくても正確に準備ができたほうがうまくいくこともありますし、それ以外の堂々とした受け答えなどによる要因でうまくいくことだってあります。
気分や感情は、一過性のことが多く、いつまでも続くわけではないですし、次の瞬間には楽しくなるかもしれません。
この状況の対策としては、気分をよくしたり、いいことを探したりすることがいちばんです。
帰りにおいしいものを食べて帰ろうとか、次の休みに旅行に行くことを思い浮かべるなど、とにかく楽しいことを頭に思い浮かべるようにしましょう。
⑧ 「すべき」思考をやめる 「〜すべき」「〜すべきでない」「〜しなければならない」と、つい考えていませんか?
期限があるものではないのに、いつまでにやらなければならないと思い込み、結果的に自分自身を追い込んで、プレッシャーを感じた経験はありませんか?
この思考パターンの厄介なところは、自分だけでなく、他人に対しても同様に当たってしまうことにあります。
『忙しいビジネスパーソンのための自律神経整え方BOOK』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)
たとえば他人を見て、もっと頑張るべきだとか、自分より早く帰るべきではないと考えてしまったことはありませんか?
人はそれぞれ持っている常識が違います。もしかしたら相手から見ると、自分のほうが間違っているのかもしれません。
こんな状況には「上下に目線をずらす」という考え方が有効です。
まずは、「上」の目線。
たとえば自分が「すべきだ」と考えていることに対して的外れなことを言ってきたら、悪い言い方ですが、少し斜に構えて上から目線になってみましょう。小さな子どもに接するように、まともにぶつからず、よしよしかわいそうな人だと上から目線で見れば、他人を許せる余裕が生まれます。
また、逆に相手の言うことは絶対だ、どんなことでも「はい」と言おうと、「下」から目線でいるのも有効です。どちらもアプローチは違いますが、自分の「すべき」という思考パターンから無理やり離れることができます。
うまくいかなくても、次はうまくいくこともある
⑨ レッテル貼りをやめる うまくいかなかったときや、失敗をしてしまったときに、ネガティブなレッテルを貼ってしまうことはありませんか?
うまくいかなくても、次はうまくいくこともある。努力をすれば状況は変わると考え、決めつけをできるかぎり排除していきましょう。
⑩ 何もかもを自分に関連づけない 悪いことが起こったときに、自分に責任がない場合でも、自分のせいにしてしまう思考パターンがあります。
ほかの人が仕事で失敗しているのを見て、自分が助けてあげられなかったから失敗してしまったんだというように、他人の失敗を自分のせいにしてしまうことがありますが、他人がやってしまったことに責任を感じすぎてはいけません。
他人に100%の影響を与えることはできないのですから、助けなかったから失敗をしたと決めつけてしまうのは飛躍した論理なのです。
原田 賢 : 「自律神経専門」整体師










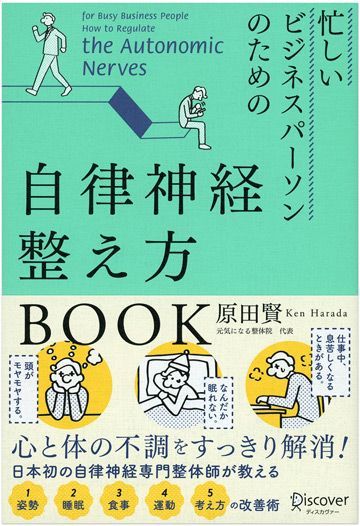
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます