ここ数日、このブログにしては真面目な記事が続いていまして、すっかりお笑いキャラであったことを、忘れかけてた代表管理人ございます。(笑)
私は看護師でございまして、日々、物心がついてからというもの、「何か、楽しいことはないかいな?」と思って生きておりますが、看護学生の実習病院の教官から、「医療職としては、はなはだ性格が明るすぎる。」と、通っていた看護学校クレームがついたりしたこともありますし(笑)、どうも「高田純次さんに似てるよね。」と言われることも多いです。(爆笑)
こういうガチャガチャした性格で、心を扱う宗教の信者として、また在家の布教を担うというのは、誠にもって、「日々是修行(笑)」でございますね。
しかし笑いというのは、大切でございます。
なんと言っても、健康にとても良いです。
かつて、吉本興業と、とある大学との共同研究で、笑うことで人体の免疫機能が、極端に上昇することがわかっています。
人間にはナチュラルキラー細胞、通称NK細胞という、とても強い免疫細胞があり、ガン細胞を消し去る強さを持ちますが、NK細胞を活性化させるものこそ、「笑い」なんですね。
こういう生理的な背景もあって、笑いで免疫力は跳ね上がるのですけれども、この力は、たとえ作り笑いでも効果が出るそうですから、なにかと大変で、つらいことの多い人生ではありますが、やはり時折は、「がーははははははははは 。」と、大声で笑うことが大切だなぁと思う次第です。
天国は、とにかく楽しい世界です。
そりゃぁそうでしょう。(笑)
楽しくない天国ならば、それは看板が違っちゃっているでしょう。(爆笑)
天国が楽しいところであるならば、話は簡単ですね。
あなたが天国に行きたいのならば、楽しい人になればよいですし、この地上を天国のようにしたいならば、楽しい世界にすればよいということですよね。
笑うと体が、ポカポカと暖かくなりますね。
これは、天国の光、神仏の光が、心に入ってくるからなんです。
それでリラックスできて、血管も開いて、血流も良くなるんですね。
ただ、知らなければならないことがあります。
もちろん天使は、楽しくって笑いっぱなし(失礼)な方ばかりですけれども、地獄の悪魔という方も笑うんですよ。
しかしこの笑いには、明らかな差があるんです。
笑いにも、天国的な笑いと、地獄的な笑いが存在するんです。
その天国と地獄を分けるものは、「人が幸福になって笑う」のか、それとも、「人が不幸になって笑う」のかです。
これだけです。
つまり、笑いの対象と基準が、天国と地獄を分けるんです。
天国の笑いは、とにかく開けっぴろげで、屈託のないものです。
天真爛漫なんですね。
一方地獄の笑いは、そう、「人の不幸は蜜の味」の方ですね。
策略を張り巡らし、人が不幸の沼に陥るのを見て、「ホ~レ、してやったぜ。」的な感じですね。
私は個人的には「悟りとは、自分自身の当たり前」だと、思っております。
つまり、たとえば、私なんぞは神様がいるのは当たり前だし、人間が神様の子というのは当たり前ですし、死後の世界があって、転生輪廻しているというのが、人生を生きる判断をする上で、もはや前提になっていますが、そうでない「当たり前」を持っている人も数多くいます。
自分は「どういう当たり前なのか」を知ろうとすれば、色んな人生観を持つ人たちや、好きな人や嫌いな人との出会いがなければ、絶対にわからないことで、そういう意味で、人間関係中心の人生修行があるのではないかと思います。
つまりその理論で言うならば、何を見て笑えるかで、その方自身の悟りが一目瞭然なんです。

通常、笑いの常識からですと、「笑いは国境を越えることは難しい」と言われますが、笑いと悟りの関係は、これは全世界共通、人類共通なのではないかと思います。
地獄的な方が大笑いしていることは、「天国的な方」つまり、今死んだら天国に行くような方から見れば、ただただ「かわいそうに。」としか思えない事柄なんですね。
因果の理法、つまり、原因結果の法則は、たとえ如来と言われるような、格の高い方でもくらませませんが、この笑いと悟りの法則もくらませないんです。
つまり、「何を見て笑えるか?」が、自分自身であるし、自分の現在の心境が、神の世界の、どの位置に属しているかを如実に現してしまうんですね。
ああ、なんだか、うかつに笑えなくなってきましたね。(爆笑)
本日は、経典『幸福の道標』(幸福の科学出版)より、大川隆法幸福の科学グループ総裁が、講話におけるユーモアについて語った説法をご紹介いたします。
(ばく)
「幸福の科学とは何か」抜粋 大川隆法総裁1989年第1回講演会
映画『心霊喫茶「エクストラ」の秘密-The Real Exorcist-』予告編【5月15日(金)ロードショー!】
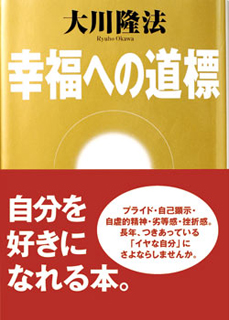 https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=200
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=200
やはりそういう失敗や、あるいは性格上のマイナスや、能力の不足など、いろいろなものがあったとしても、それを打ち消すだけの成功をどこかでおさめていることがだいじなことのように思えます。
何か成功体験があって、それは確固としたものだという感覚が自分自身にあると、その劣等感の部分が、ユーモアに消し込めるようになるのです。
笑い話にもできるようになり、「私もこんな失敗をしているんだよ。」ということが人に言えるようになります。
単に劣等感に悩んでいる人を見て、「私もそういう悩みがありましたよ。」と過去形で言えるようになる、これがだいじなことです。
このように、劣等感の処方箋としては、最初はそれをバネに使って成功への道を歩むということもあるのですが、その次はその成功の感覚を実感として持つことだと思います。これを持たなければだめだと思います。
この実感は、自分が確認できるということもありますが、できうるならば、他の人にも確認してもらえるようなものになっていく必要があります。それが安心感となって自分に返ってきます。
次にどうするかというと、そういう劣等感などを味わって苦しんできた道程を他の人にも同じように歩ませ、苦しませようとするのではなくて、また、「おまえも少しは苦労したほうがよい。」などといったり、あるいは心の傷口に刃を突き刺すようなことはしないで、その道程をひとつの自分の体験として、ユーモアとして、人に話ができて、同じ苦しみにある人たちのその苦しみをやわらげてあげ、生きる道を教えてあげる、これがだいじなことだと私は思うのです。そこまでいかなければいけないと思います。
こうしてみると、私はとくに年輩の方、壮年や実年の方に申し上げたいのですが、この年代になって、自己顕示で頑張っている人がいるとやはり気の毒に感じるのです。
そういう年代の人はむしろ自分の失敗談を、他の人に対する、若い人たちに対する、処方箋として出してあげなければいけないと思います。
人間は、歳をとると自慢話をしたくなりますけれども、自慢話ばかりしているのではなくて、自分の過去の失敗体験や、挫折体験を、上手に話してあげて、いろいろな人の悩みを緩和する、そういうところまでいかなければいけないのです。
ですから、実年の方は、過去の失敗は隠蔽し、現状の自慢ばかりに走るのではなくて、どうか蓋を開けてください。
蓋を開けて、これを出して、ユーモラスに話ができるところまでいってほしいのです。これをどうか目標にしていただきたいのです。
「おれは失敗なんかしたことはないわ。」とか「自分が若いときはそんなじゃなかった。」とか、こういうことは言わないで、ご自分もいろいろ経験されているはずですから、そういう失敗の部分などを、どんどん出して言えるぐらいにならなければいけないと思います。
『幸福の道標』(大川隆法著 幸福の科学出版)P41~43
原作・小説・楽曲解説『心霊喫茶「エクストラ」の秘密』のご紹介
























桜師匠に、コメントさせていただきました。
本当にお疲れ様でした。
桜咲くやさんの御主人が、
帰天したらしい。
ブログに、書いてあった。