 昨日、以前お世話になった先生から、少年少女合唱団の定期コンサートに奥様が招待された。奥様の合唱コンサートに来てもらっている事から断るわけにもいかず、私が隣の町のコンサートホールまで送って行く事にした。さて私もそのコンサートを聞かせてもらっても良かったのだが、せっかくの休日なので、このコンサートの開催時間中を自分の読書時間にする事にした。
昨日、以前お世話になった先生から、少年少女合唱団の定期コンサートに奥様が招待された。奥様の合唱コンサートに来てもらっている事から断るわけにもいかず、私が隣の町のコンサートホールまで送って行く事にした。さて私もそのコンサートを聞かせてもらっても良かったのだが、せっかくの休日なので、このコンサートの開催時間中を自分の読書時間にする事にした。
以前、学研大人の科学について掲載したが、昨年この付録つき雑誌を何冊か購入したが、購入したばかりでその後放っておいた中の一冊を取り出して、その雑誌をざっと読んだ。この雑誌は、昨年12月17日発売「大人の科学Vol.26ふろくアンプ/スピーカー内蔵ミニエレキ」であり、購入して4.5ヶ月も放っておいた事になる。しかも正月休みと言う長い休みがあったにもかかわらず・・・。
この雑誌の目的はと言うともちろんふろくだった。このふろくと言うのがミニエレキである。このミニエレキが欲しくてこの雑誌を買ったと言うのが正解だった。
昨年の夏に入門者用アコギの中古を購入したが、実はその後全く練習していない。なぜか?休職中を含めて、アルトサックス、ポケットサックス、フルート、ブルースハープ等と楽器を購入してきたが、アコギも含めて気安く家で弾けないと言う事が最大の原因だろうと思っている。そうどの楽器でも音がうるさくて、家で弾こうものなら、近所迷惑の前に家族から猛反対される為だ。これは卵と鶏の話ではないが、外で練習する為にある程度うまくなってからと考えるといつまでたっても練習できないと言う事になる。この為、休職期間中のアルトサックスの練習は、普通の日に近くの府民の森に行って、誰もいない山の中で吹いた。さすがに復帰後はこれもできなくなった。仕事優先となり億劫になるし、普通の日の休みが殆ど無いからだ。と言う事で、目をつけたのがこのミニエレキだ。要は私にとっての楽器は、人の為ではない。自分のストレス発散ができればよい。その為にはいろいろ面白い物を試したい。高価な物である必要はない。聞き分ける耳も音楽センスも持っていないし、もちろん腕もだが・・・。更に継続するかもわからない。
と言う事で、このミニエレキはこの私の欲求を満たしてくれそうだったからだ。しかもプラモデル同様に自分で組み立てなければならないおまけまで付いて。
| 1 | 音量をコントロールできる | 家で練習できる | 結果的に電子楽器となる。 |
| 2 | めずらしい。おもしろい。 | 外で練習しても恥ずかしくない。注目される可能性あり。 | メジャーとはならないが、あそびならよいのでは・・・。 |
| 3 | 小さい。 | どこへでも持っていける。 | 楽器として小さい事は、音量や音質的に不利であるが、これもあそびならよいのでは・・・。 |
| 4 | 高価でない。 | ダメもと。続かなくても後悔しない。 | うまくなってから良い物は買えばよいのでは。 |
と言ってもコンサート開催時間中の車の中で組み立てるわけにはいかず、ふろくではなく雑誌そのものを読む事にした。通常はこっちの方が正しい順番なのだろうが、この雑誌の位置づけ上、付録が主で雑誌が付録の様な感じだが、ドッチでも良いのだろう。
さて内容に期待はしないでこの雑誌を読んだが、久しぶりにおもしろかった。と同時になぜこのミニエレキが大人の科学のネタになったのかを理解した。つまり私は、エレキギターの音がでる仕組みを全く理解していなかったと言う事になる。おそらく大半の方はそうだと思うが。
エレキギターは、内蔵マイクの様な物でギターの弦の音を拾い、アンプを使ってスピーカーに出力しているのだろうぐらいにしか思っていなかった。
今回この雑誌を読んで、且つミニエレキを実際に自分で組み立てて見て、初めてエレキの音のでる原理を理解した。
エレキギターは、スティールの弦の振動を、ピックアップ(磁石とコイル)と言うパーツで、電気信号に変えてアンプとスピーカーに出力していた。つまりマイクの様に音から電気信号に変換するのではなく、磁石の上で振動する金属により変化した磁界をコイルで電気に変えていたと言う事だ。これなら大人の科学のネタに十分なる。
と言うか、この金属、磁界(磁石)、コイルを使った面白い実験と言う意味では、このミニエレキは最高の材料ではないかと思う。原理を理解しながら、実際の音がでる楽しみを知る事ができるのだから・・・。
本来、科学とはこういうものではないかと思う。素晴らしい題材を提供してもらったと言う気がする。学研の皆様には感謝したい。今回は楽器と音楽と言うより、楽器と科学を学べたような気がした。イヤー奥が深い。
それにしてもこのエレキギター(ピックアップ)を発明したジョージ・ビーチャムという人は凄い。自らがスティールギターの演奏者だったとの事だが、深夜学校に通ってこの理論を学んで開発したされたらしい。当時でも最新の技術だったはずであり、私も高校の物理でこの理論を学んだ時には、チンプンカンプンだった。実際の利用例等と切り離し、学問としてだけ科学を学ぶとそうなるのだろう。目的があって初めてその意味があるのだろうと思う。
















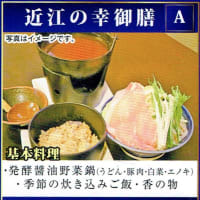
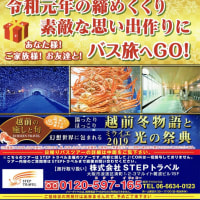


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます