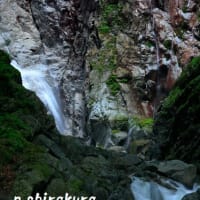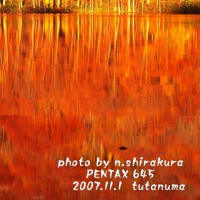神社の境内に囲矢倉を組み、さまざまな仕掛け花火が奉納される。準備は、煙火師の免許をとった者が夏頃から取りかかる。
資料によると、江戸時代、清内路では煙草が作られ三河へ行商に行った人々が花火の製法を教わって持ち帰ったのが始まりであり、享保16年(1731)に竜勢を打ち上げた記録が残っているとしている。(龍勢(りゅうせい)とは筒に黒色火薬を詰め、竹竿を結んだ花火である。上空で傘が開き、様々な仕掛けが作動する。)
<ここの手づくり花火は、神社対岸の山と境内をつなぐナイアガラをはじめ、ブドウ棚やチョウ、ハチなどの珍しい形をした花火が特徴とのことである。>
花火:ブドウ棚

点火

見事に色ずく

花火2:巴車前半






次回:巴車続き