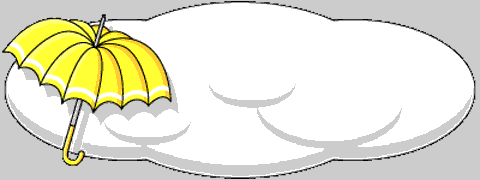6月、梅雨時期の気まぐれな天気。
変わりやすい天気でも、山へ行こうと すれば 今日では WEBサイトなどで いろいろな最新 気象データを いとも簡単に手に入れることができる。
高層の天気図、予報支援図など や 航空用の気象データも 見てみると とても参考になる。
船舶向け天気図提供ページ (放送スケジュール)
船舶向け天気図 (画種別)
専門天気図
専門気象情報
もっとも 気象の専門家でない 素人の範囲では 気象プロが それらの多くのデータから様々な情報を関連づけて 的確に うまく読み解くようなことは とてもできない。
私など 正直にいって ようするに ウェブサイトの膨大な データを ただ単に ぼんやり眺めているだけに過ぎない。

今 私のような素人が できることは 照る照る坊主か、 下駄を投げるような 気象占い 程度のことか。
更にできることは
先人の知恵袋としての 天気の諺は 過去の気象データベースの集大成であり、これなど 謙虚に 紐解いて先人に教訓を学ぶこと。
観天望気

そして 山の中に入ったら
危険な 気象現象を避けるよう 常に空を見て、雲の動きをみて、 風の向きを見て、 寒いか暖かいか 感じること。
さらに いつも 心得ておかねばならないのは 山で危険な気象を避ける努力は大事だが それでも 山では 時には 人智を超えた 突発的な気象現象にであうことがあるということ。
その場合。
どんな事態に陥ってしまったとしても 最後まで あきらめずに なんとか無事に下山できるよう 最善の努力をつくすことができるようにと 少々の悪天にも 耐えうるように 常に 備え 鍛えておくこと。
そんな ことしかできない。

高松空港
徳島空港
高知空港
松山空港
山域の地形 地質と 気象
梅雨時期
よもやま話