いよいよ、明日の真田丸第10回「妙手」で上田城の築城が開始されます。
その前に私見はでありますがまとめてみました。
改めて整理し直し記しました。
古図や郷土史を参考にして描いてみました。
上田城築城前の様子

丸数字は環境依存する為、一部で正確に表示されないので
使用しませんでした。数字は図中の丸数字に対応しています。
1、小泉曲輪と呼ばれている場所で小泉氏の古城館があったとされる場所。
2、現在、上田高校がある場所には常田氏の御屋敷があった場所。
3、尼ヶ淵
4、千曲川
5、旧矢出沢川が流れていた広谷
6、旧矢出沢川
7、旧蛭沢川
8、上州道(どうではなくみちと呼ぶ)
9、川中島道(東山道)当時はそう呼んでいたものと思われる
10、保福寺道(東山道)当時はそう呼んでいたものと思われる
11、川中島道、当時はそう呼んでいたものと思われる
この場所に選定した理由には
○武田信玄の家臣であった真田幸隆(幸綱)が対岸の諏訪形を信玄より宛行われ、のちに幸隆に伴って昌幸も諏訪形から尼ヶ淵を眺めていたのではと思われる事
○尼ヶ淵周辺の地も宛行われており「小泉ノ城破却御祝着ノ由被仰出候」と記された文書から、小泉曲輪の地も支配していた事
○現上田高校の場所に常田氏の御屋敷があり、幸隆の弟の隆永が常田氏の養子となり、真田氏の勢力が及んでいた事
○盆地の北側であるが盆地一帯を望むことができ、小県郡平定の為には絶好の地であった事
等々が挙げられる。
天正12~13年(1584~85年)頃の上田城の様子

丸数字は環境依存する為、一部で正確に表示されないので
使用しませんでした。数字は図中の丸数字に対応しています。
1、本丸
2、二の丸
3、作事場、第一次上田合戦時には横曲輪になったか?
4、常田氏御屋敷、第一次上田合戦時には横曲輪になったか?
5、広谷を堰き止めた広堀
6、尼ヶ淵
7、蛭沢川を北に向けて分流
8、矢出沢川を外堀のような筋に変更
9、堀への導水路に付した排水路
10、二の丸と小泉曲輪間に設置した空堀
11、小泉曲輪
12、小泉曲輪の一部で捨曲輪としその間には堀を兼ねる排水路を通した
13、城下町(この時は小規模)
14、東の大手口(城下町との行き来や町人・村人衆を戦の時に傭兵として連れ込むため)
15、北の大手口(上杉勢が侵入して来るであろうと想定)
16、千曲川
17、上州道
18、北へ寄せた川中島道
19、川中島道
20、保福寺道
北の上杉勢に対する為の縄張りになっています。
北西方向は上杉勢の領地となっている北信濃との境目になっています。
上田城自身が境目の役割を持つ最前線基地である。
なので西側は堅固な構えになっています。
東側の防御力はそれほど高くはない。また規模が小さいが城下町が整備されました。
城の鬼門となる方向には海野郷より寺社を移築しました。
本丸の構えは
天正12年(1584年)頃の様子を描いたとされる絵図を、のちに松代藩士の佐久間象山が模写した上田古図を参考にしました。江戸時代後期に模写されたものなので約260年の時を経ているので信ぴょう性・正確性には?がつきます。
徳川の援助の下、必要最低限なものは作ったと言われています。
第一次上田合戦時の上田城の様子を「天守も無き小城」と山鹿素行の「武家事記」にはそう記されています。
本丸の構えは
土塁(虎口部分は石垣であったか?)を巡らし、
その上に櫓(平櫓?)・塀(おそらく木塀)を築き、そして屋敷を構えた。
本丸堀に木橋を架け北虎口を経て本丸へ。
二の丸の構えは
西側の二の丸は狭い。
土塁を巡らせその上に木柵を築いた。
北の大手口も同様の作りで木橋を広堀に架けた。いざという時に壊せば侵入を防げる。
東側の二の丸は家臣の屋敷を配置し、家臣の本丸との往来用に虎口を設け
南東の虎口へ誘導するような配置になっていたのでは。
東の大手口にも土塁・木柵を築いた。
東の大手口から東に小規模の城下町を配し、そこから北に向けても町を配した。
蛭沢川(導水路・排水路)を惣構えにし、矢出沢川もそれに付随したものとなっていたのではと思います。
全体的に中世城郭の色が出ていた最初の上田城だったのだと思います。
築城は徳川の援助で始まり、上杉の援助で一応の完成に至りました。
築城の背景

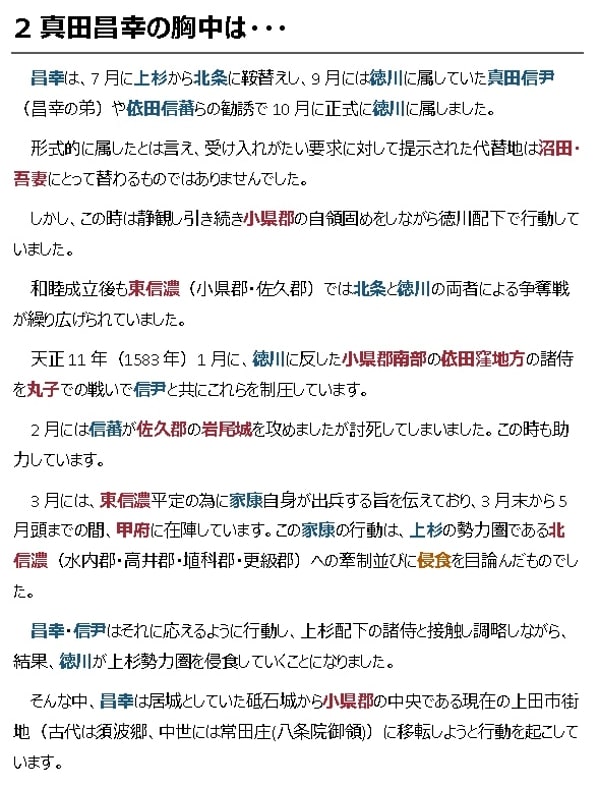

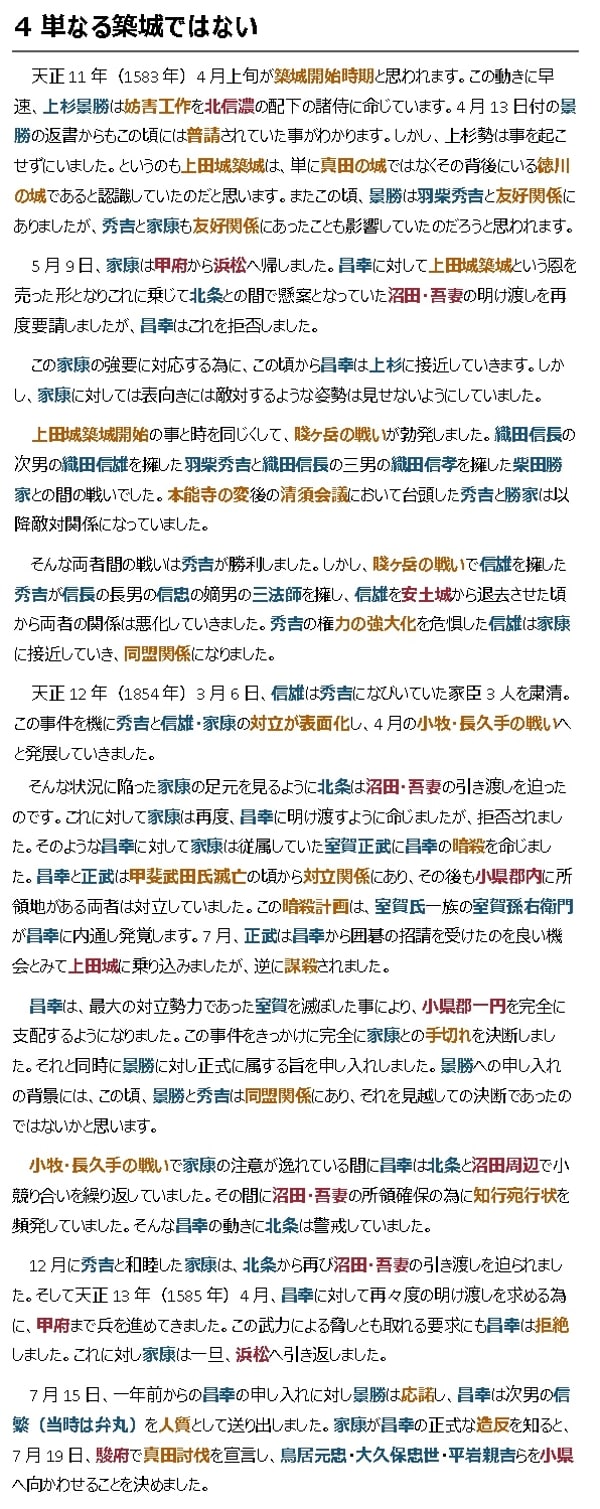


以上、上田城築城とその背景でした。
その前に私見はでありますがまとめてみました。
改めて整理し直し記しました。
古図や郷土史を参考にして描いてみました。
上田城築城前の様子

丸数字は環境依存する為、一部で正確に表示されないので
使用しませんでした。数字は図中の丸数字に対応しています。
1、小泉曲輪と呼ばれている場所で小泉氏の古城館があったとされる場所。
2、現在、上田高校がある場所には常田氏の御屋敷があった場所。
3、尼ヶ淵
4、千曲川
5、旧矢出沢川が流れていた広谷
6、旧矢出沢川
7、旧蛭沢川
8、上州道(どうではなくみちと呼ぶ)
9、川中島道(東山道)当時はそう呼んでいたものと思われる
10、保福寺道(東山道)当時はそう呼んでいたものと思われる
11、川中島道、当時はそう呼んでいたものと思われる
この場所に選定した理由には
○武田信玄の家臣であった真田幸隆(幸綱)が対岸の諏訪形を信玄より宛行われ、のちに幸隆に伴って昌幸も諏訪形から尼ヶ淵を眺めていたのではと思われる事
○尼ヶ淵周辺の地も宛行われており「小泉ノ城破却御祝着ノ由被仰出候」と記された文書から、小泉曲輪の地も支配していた事
○現上田高校の場所に常田氏の御屋敷があり、幸隆の弟の隆永が常田氏の養子となり、真田氏の勢力が及んでいた事
○盆地の北側であるが盆地一帯を望むことができ、小県郡平定の為には絶好の地であった事
等々が挙げられる。
天正12~13年(1584~85年)頃の上田城の様子

丸数字は環境依存する為、一部で正確に表示されないので
使用しませんでした。数字は図中の丸数字に対応しています。
1、本丸
2、二の丸
3、作事場、第一次上田合戦時には横曲輪になったか?
4、常田氏御屋敷、第一次上田合戦時には横曲輪になったか?
5、広谷を堰き止めた広堀
6、尼ヶ淵
7、蛭沢川を北に向けて分流
8、矢出沢川を外堀のような筋に変更
9、堀への導水路に付した排水路
10、二の丸と小泉曲輪間に設置した空堀
11、小泉曲輪
12、小泉曲輪の一部で捨曲輪としその間には堀を兼ねる排水路を通した
13、城下町(この時は小規模)
14、東の大手口(城下町との行き来や町人・村人衆を戦の時に傭兵として連れ込むため)
15、北の大手口(上杉勢が侵入して来るであろうと想定)
16、千曲川
17、上州道
18、北へ寄せた川中島道
19、川中島道
20、保福寺道
北の上杉勢に対する為の縄張りになっています。
北西方向は上杉勢の領地となっている北信濃との境目になっています。
上田城自身が境目の役割を持つ最前線基地である。
なので西側は堅固な構えになっています。
東側の防御力はそれほど高くはない。また規模が小さいが城下町が整備されました。
城の鬼門となる方向には海野郷より寺社を移築しました。
本丸の構えは
天正12年(1584年)頃の様子を描いたとされる絵図を、のちに松代藩士の佐久間象山が模写した上田古図を参考にしました。江戸時代後期に模写されたものなので約260年の時を経ているので信ぴょう性・正確性には?がつきます。
徳川の援助の下、必要最低限なものは作ったと言われています。
第一次上田合戦時の上田城の様子を「天守も無き小城」と山鹿素行の「武家事記」にはそう記されています。
本丸の構えは
土塁(虎口部分は石垣であったか?)を巡らし、
その上に櫓(平櫓?)・塀(おそらく木塀)を築き、そして屋敷を構えた。
本丸堀に木橋を架け北虎口を経て本丸へ。
二の丸の構えは
西側の二の丸は狭い。
土塁を巡らせその上に木柵を築いた。
北の大手口も同様の作りで木橋を広堀に架けた。いざという時に壊せば侵入を防げる。
東側の二の丸は家臣の屋敷を配置し、家臣の本丸との往来用に虎口を設け
南東の虎口へ誘導するような配置になっていたのでは。
東の大手口にも土塁・木柵を築いた。
東の大手口から東に小規模の城下町を配し、そこから北に向けても町を配した。
蛭沢川(導水路・排水路)を惣構えにし、矢出沢川もそれに付随したものとなっていたのではと思います。
全体的に中世城郭の色が出ていた最初の上田城だったのだと思います。
築城は徳川の援助で始まり、上杉の援助で一応の完成に至りました。
築城の背景

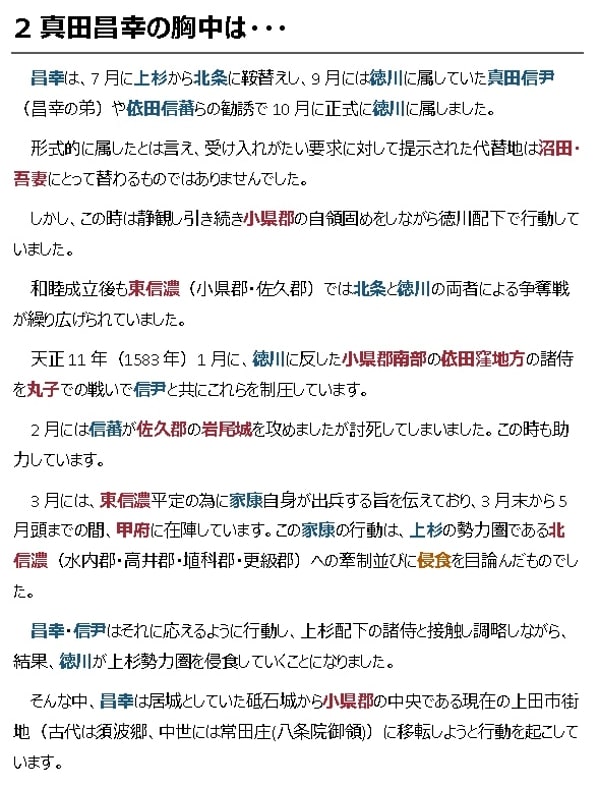

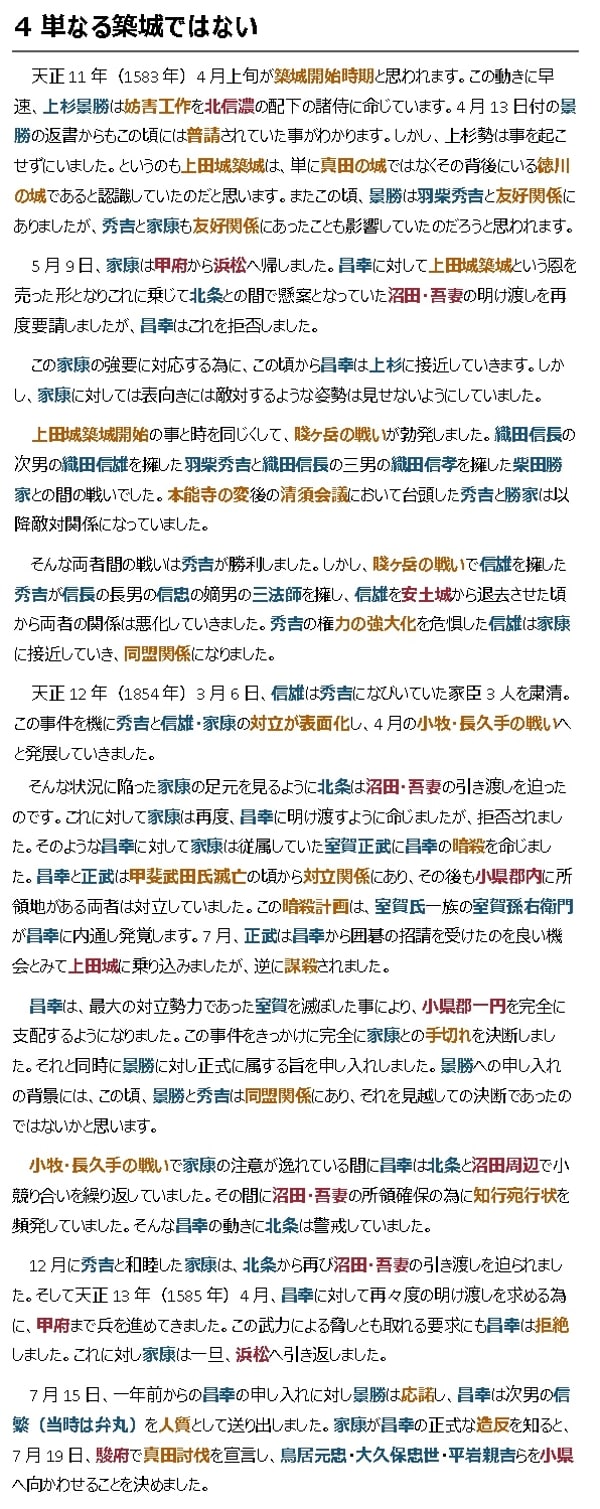


以上、上田城築城とその背景でした。






































