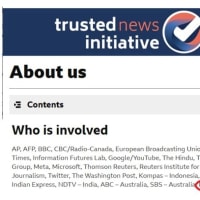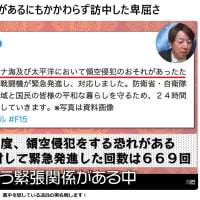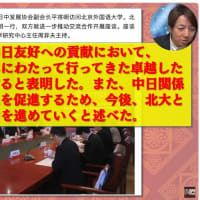中国軍艦2隻が尖閣に最接近 今月中旬、島まで70キロ
朝日新聞DIGITAL 機動特派員・峯村健司2014年12月30日05時23分
中国の軍艦2隻が12月中旬、沖縄県・尖閣諸島沖で、通関などの行政手続きが沿岸国に認められる「接続水域」まで約27キロ、沿岸から約70キロに迫ったことがわかった。自衛隊関係者によると、8月に島から北に200キロ前後の海域に常駐しているのが確認されており、今回は把握している限りで近年尖閣に最も近づいたという。日本側は示威や挑発と受け止め、海上自衛隊の護衛艦が監視活動にあたっている。
中国軍艦の尖閣接近、習主席の意向か 直属新組織が指示
日米中の軍事・防衛関係者が明らかにした。日本政府が尖閣を国有化した2012年9月以降、中国政府の監視船が領海侵犯を繰り返している。軍艦も一時派遣されたことがあったが、尖閣からの距離を保っていた。13年に中国軍艦が海自艦に射撃用管制レーダーを照射したのは、北に約180キロの海上だったという。
公海上の動きで国際法には抵触しないが、尖閣に近い海域で海自艦と中国軍艦が近距離で向き合うことで、衝突が起きかねない。
中国軍艦の尖閣接近、習主席の意向か 直属新組織が指示
朝日新聞デジタル 12月30日(火)8時43分配信
中国軍が尖閣諸島(沖縄県石垣市)沖に軍艦を派遣していることで、日本側の警戒感が高まっている。その動きは外交に連動しているように見える。複数の中国軍関係者は、軍トップでもある習近平国家主席の意向が働いている可能性を示唆する。
日米中の軍事・防衛関係者によると、尖閣沖に常駐している中国軍の2隻は、ふだんは離れた海域を航行している。発進したかと思うと、突然、船首の方向を90度以上変え、尖閣沖に向けてピッチをあげる。中国海軍を研究する米海軍大学のトシ・ヨシハラ教授は「日本に領土問題の存在を認めるように迫る強いシグナル」と指摘する。
複数の中国軍関係者は、共産党内にできた組織が、軍艦や監視船に直接指示を出している、と指摘する。正式発表されていないが、日本政府が尖閣国有化を決めた直後の2012年9月、党は東シナ海や南シナ海の領有権問題に対処する「党中央海洋権益維持工作指導小組」を新設した。
トップには習氏が就いた。外交を総括する楊潔篪(ヤンチエチー)・国務委員(副首相級)のほか、監視船を管理する国家海洋局長や軍総参謀部の幹部らで構成されている。メンバーが、無線やテレビ電話を使って現場の軍艦や監視船に指示を出すという。トップの意向を素早く現場に伝え、効率的に監視活動を展開する狙いがあるようだ。
中国軍4隻が日本一周…対馬海峡から東シナ海へ
YOMIURI ONLINE 2014年12月28日 20時19分
防衛省は28日、中国海軍の艦艇4隻が対馬海峡を通過して日本海から東シナ海の方向に進むのを確認したと発表した。
領海には侵入しなかった。これらの艦艇は、今月4日に大隅海峡を通過して太平洋に出た後、同25日には宗谷海峡を通過し、日本をほぼ1周する動きを見せており、同省で動向を注視している。
同省統合幕僚監部によると、28日午前5時頃、駆逐艦やフリゲート艦、補給艦の計4隻が、対馬海峡を通過した。これらの艦艇は太平洋で洋上補給の訓練などを行っていたという。中国海軍の艦艇は昨年7月、日本を1周する形で航行したことが初めて確認されている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
敵情地形の偵知に怠りなく励む中国軍
第47回衆議院議員総選挙は、11月21日衆議院解散、12月2日公示、12月14日に施行された12月26日に安倍改造内閣が発足した。先のAPEC における日中首脳会談を受けて経済界等民間では日中友好の動きが活発化し、世の中、年越しの話題で持ち切りである。中国軍はこの間の日本側の警備体制やマスコミ動向等をチェックするとともに、中国軍艦艇の動きによって日本周辺海域を制圧しうることを示し、今後は第二列島線及びハワイ以西の太平洋を支配下に置く動きを強化するとの意思表示をしたものと観察される。
『孫子』 虚実篇に
「故策之而知得失之計、作之而知動静之理、
形之而知死生之地、角之而知有余不足之虚」
策りて・・・・・・策は算と同じ。戦闘の前に目算すること。
角れて・・・・・・角は触の意。敵軍に小部隊で当たってみること。
「故に之を策りて得失の計を知り、之を作して動静の理を知り、
之に形して死生の地を知り、之に触れて有余不足の処を知る。」
「そこで、戦いの前に敵の虚実を知るためには、敵情を目算してみて利害損得の見積りを知り、敵軍を刺戟して動かせてみてその行動の規準を知り、敵軍のはっきりした態勢を把握してその敗死すべき地勢と敗れない地勢とを知り、敵軍と小ぜりあいをしてみて優勢な所と手薄な所とを知るのである。」
「これを策(はか)りて得失の計を知る」の策は、謀策で、戦争開始前の廟算すなわち、七計を比較秤量し、彼我の得失を知る、の策を意味する。それで、わが廟算にして不利であるなら「守るは足らざるなり」で、一時静閑を持し、機の到るを待つべきであり、これに反し有利であるなら、「攻むるは余り有るなり」・・・・・すぐ攻守に出るべきである。
そしていよいよ開戦に決したなら「これを作して動静の理を知る」・・・・間諜、軍使、遊士、外交機関を利用するなど、各種の手段で敵の動静を探知する。
その探知し得た敵の動静を基礎とし、推考し、詳言するなら敵情を推考判断し、敵の動静、態度の根底を測定する。ここにおいてわが作戦方針が決定するのである。
その方針に従って出陣し、敵と対向するに至ったなら、まず斥候、偵察隊、間諜等の探知機関を動かして敵の部署、配置を知ると同時に、敵の地形の険易、行動、近接の便否など地形的死生を偵知し考察の後、わが攻防、部署を決定するのである。
いよいよ戦闘開始となったなら「これに触れて」すなわち実力をもって敵に触接し、われ「有余」で敵の「不足」の方前、地点を判知し、ここで本攻撃実行となり勝を制するのである。
この際、敵が「有余」でわれ「不足」の方面、地点において敵に乗ぜられないようにしなけれぼならないが、退嬰に失してはいけない。敵を敗ることを失してはならないことは多くいうまでもない。
(ベトナムの懐柔に動く)
中国序列4位が訪越…南シナ海、対話で解決主張
YOMIURI ONNLINE 2014年12月27日 22時31分
【北京=五十嵐文】中国国営新華社通信は27日、中国共産党序列4位の兪正声ユージョンション・人民政治協商会議主席が25日から27日までベトナムを訪問し、チュオン・タン・サン国家主席ら指導部と会談した、と伝えた。
一連の会談で兪氏は、南シナ海をめぐるベトナムとの対立について、「海上の問題は高度に複雑で、敏感だ。話し合いで対立や矛盾をコントロールしなければならない」と述べ、対話を通じた解決を主張した。
中国は5月、ベトナムの反対を無視してパラセル(西沙)諸島周辺で一方的に石油掘削を行った。だが、その後は友好的な「周辺外交」を掲げ、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の首脳らと個別に会談する懐柔策を進めている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
来年は力を背景とした現状変更の試みが増大
フィリピンが南シナ海の領有権問題を巡り昨年仲裁裁判所に提訴していることに対し、中国は仲裁には応じない姿勢を示している。ベトナム外務省報道官は12月11日、中国が独自に設定し、南シナ海で領有権を主張する根拠としている「九段線」について「一方的な主張は断固拒否する」と強調した。その上で、「(仲裁)裁判所に自国の見解を伝え、ベトナムの法的権利と利益に正当な配慮を払うよう要請した」と述べた。裁判の当事者ではないが、国際社会に訴える狙いがあるとみられる。
中国は海洋における利害が対立する問題をめぐっては、力を背景とした現状変更の試みなど、高圧的とも言える対応を示している。わが国周辺海空域においては、中国は、海上法執行機関所属の公船や航空機によるわが国領海への断続的な侵入や領空の侵犯のほか、海軍艦艇による海自護衛艦に対する火器管制レーダーの照射や戦闘機による自衛隊機への異常な接近、独自の主張に基づく「東シナ海防空識別区」の設定といった公海上空における飛行の自由を妨げるような動きを含む、不測の事態を招きかねない危険な行為に及んでいる。
中国は、軍事力の強化の目的や目標を明確にしておらず、軍事や安全保障に関する意思決定プロセスの透明性も十分確保されていない。また、中国は、東シナ海や南シナ海をはじめとする海空域などにおいて活動を急速に拡大・活発化させている。
南シナ海で地歩を確立したので中国はベトナムを懐柔し、南シナ海方面で地歩を固め、今後は太平洋への進出に注力するのであろう。今夏の小笠原および伊豆諸島近海へ200隻を超す“サンゴ密漁船”を動員したのはその前触れで、第一列島線支配下におくだけでなく、第二列島線を支配下に置くための布石であろう。今年は西太平洋制圧のための予行演習を実施、来年以降その動きが本格化すると予期しなければならない。
「勝敗は戦う前に歴然たり」
『孫子』 計篇に
「夫未戦而廟算勝者、得算多也、未戦而廟算不勝者、得算少也、
多算勝、少算不勝 而況於無算乎、
吾以此観之、勝負見矣、」
夫れ未だ戦わずして廟算して勝つ者は、算を得ること多ければなり。
未だ戦わずして廟算して勝たざる者は、算を得ること少なければなり。
算多きは勝ち、算少なきは勝たず。而るを況んや算なきに於いてをや。
吾れ此れを以てこれを観るに、勝負見(あら)わる。
廟算・・・・開戦出兵に際しては、祖先の霊廟で画策し、儀式を行なうのが、古代の習慣であった。
廟算の廟は廟堂のそれで調停を指す。その朝廷の御前会議で、戦前早くも勝敗の数が分かるというのである。つまり敵を知り己を知れば、係数の多寡によって勝敗が判然する。
共産党独裁で軍事力と経済力を背景に領土や権益の一方的な拡大を狙う中国は、継続的に高い水準で国防費を増加させ、軍事力を広範かつ急速に強化している。そして、一端日本と戦うことがあれば「其の不意に出ず」。兵に常道なし、意表を衝くのである。
集団自衛権に関する憲法解釈や特定秘密保護法反対、「海外で戦争できる国」反対など姦しい見せかけ平和に浮かれる日本、虎視眈々と獲物を狙う中国、心耳を澄まして周囲を見れば中国軍の軍靴の音が聞こえる。
「勝敗は戦う前に歴然たり」である。