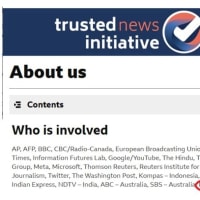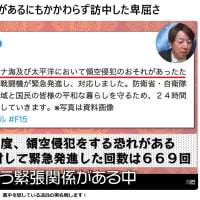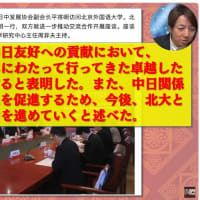【防衛大臣会見概要】
平成27年2月24日(09時28分~09時57分)
1 発表事項
なし。
2 質疑応答
Q: エボラ出血熱を巡っての件について伺います。一部報道で、防衛省が検討していたシエラレオネへの部隊派遣について、当面の必要性が低くなったことなどから、派遣の見送りを決定したという報道がありますが、事実関係について伺えますでしょうか。
A: このエボラ出血熱の対応につきましては、政府全体で取り組むこととしておりますが、現在、自衛隊の部隊派遣に関して、具体的に検討を行い、何らかの方針をまとめたという事実はありません。防衛省としましては、平素から、各国との意見交換を行い、部内でも様々な検討はしておりますが、その具体的、また個別的な内容については、お答えすることは差し控えたいと思います。いずれにせよ、防衛省・自衛隊としては、自衛隊の能力を活用して、国際緊急援助活動、また、PKO活動に積極的に取り組み、アジア太平洋地域の安定化、グローバルな安全保障環境の改善に一層努めてまいりたいと考えております。
Q: 現在のところ、部隊を送る考えというのは、当面のところはないと。
A: そういうことを決定したということはありません。
Q: 防衛省設置法12条の改正について、省内の内局では、局長級や次官級の幹部からも異論がいっぱい聞かれますが、大臣はそれについて、どう思われますか。
A: これは、長年、防衛省改革の一環で議論をされておりました。実際の部隊運用に関する業務の統合幕僚監部への一元化に伴う、統幕の改編及び運用企画局の廃止、また、省内の装備取得の関連部門を集約・統合した防衛装備庁、これの新設といった組織改編。
これは、長年、議論をして結論を得たところでございまして、これの決定をする際に、御指摘の防衛省設置法の12条、これの趣旨について、これも従来から、「政策的見地からの大臣の補佐と軍事専門的見地からの大臣の補佐の調整・吻合」、これを行っていくために改正をいたしますが、キーワードは「相まって」ということでありまして、この改編後の仕事のやり方、これを規定する場合に、政策的見地からの大臣の補佐と軍事専門的見地の大臣の補佐を相まって行うと、より一層シビリアンコントロール、いわゆる文民統制、それが強化をされるのではないかという結論に至ったと思っています。
Q: いわゆる「文官統制」をなくすことに、局長級や次官級の幹部からも異論がいっぱい出ていますが、それについてどう考えられるかということを端的に伺いたい。
A: これは、既に私が就任する前に、議論をして結論を得たことでございますが、私の就任以降、この問題について、そのような意見を直接聞いたこともございませんし、また、確認する際の業務においても、そのような発言が私のところまで来ているというふうに認識はしておりません。
Q: まさに制服出身の大臣がいる時に、こういった改革をすることは非常に問題があるということを言う幹部がいっぱいいますが、どうでしょうか。
A: 私は、12年前に防衛庁長官を経験したものでございますが、シビリアンコントロールによって選挙で選ばれた政治家として、この大臣の職を務めておりますので、こういった国民の代表であるという見地で仕事をする際に、先程言いましたけれども、軍事専門的見地からの意見も、また政策的な見地からの意見も、それぞれその背広組、また制服組、双方から意見を聞いて判断をしていきますので、私としてはあるべき姿ではないかと思っております。
Q: 制服から文官を通さずに、制服OBの大臣に直接運用計画が上がるのは問題ないと。
A: これはオペレーションですね。部隊運用に関しては、統幕を通じてということになっております。実際のオペレーションや部隊の運用等については、迅速性が求められるわけでありまして、そういう観点で、直接オペレーションを行う者から聞いて判断をするということは、私はより必要なことであると思います。
Q: 先の大戦の反省から「文官統制」の制度ができたと考えていますけれども、そういった「文官統制」の制度は一切いらないとお考えでしょうか。
A: 一切いらないという内容ではございません。「相まって」ということで、お互いに協力をして、防衛省としての総合的な意見を大臣として判断をするということですから、何ら支障はないと私は思います。
Q: 関連して、10年前にも長官をお務めになっているのでその観点からお聞きしたいのですが、これまで運用企画局と統合幕僚監部が2つあることによって、報告を受ける側として、例えばスピードが遅いとか、何か情報が錯綜するとか、そういったことをお感じになったことはありましたでしょうか。
A: 非常に大臣に上がっていくスピードや、ものの判断といたしまして、実例としてはふさわしくないかもしれませんが、民主党政権時代に、3.11東日本大震災が起こりました。当時は、東京電力の被災もあって、まさに東京電力の社長が本社に戻って指示しなければならなかったのですが、その当時は、東京電力の社長が名古屋付近におられまして、急に本社に帰る必要があるということで、これは官邸からの要請もあって、防衛省として検討をいたしましたが、こういった緊急を要する場合の物事の判断等においても、結局大臣まで上がってくる過程で非常に時間がかかりまして、結局、その日のうちに帰れないという状況が発生をいたしております。やはりこういった緊急事態においての対応なども、そういった過程を経てこなければならないような例もありますが、やはりこのすぐにやるべきことにおいては、すぐに防衛大臣が判断すべきようにしておくべきだと思います。
Q: 安保法制担当大臣としてお伺いしたいのですが、今の与党協議を見ておりますと政府が出してくる案が、去年の閣議決定の範囲から逸脱しているように見受けられる部分がかなりあるのですけれども、法制の案を作る政府側の担当大臣として、どうご覧になっておられるのでしょうか。
A: 政府としては、閣議決定にも書かれておりますけれども、「あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とすること」が重要であるということでございますので、それは一体何なのか。
これについて現在、与党で審議をしていただいているわけでございます。国会の質疑でも言われておりますが、非常に安全保障環境というのが激変しておりまして、もはやどの国も一国のみで平和を守るということができないということ、
そしていかなる事態においても、国民の命と幸せな暮らしを守っていくということで、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献をしていくという観点で、
この「あらゆる事態に切れ目のない対応」の安全保障法制を作ろうということで協議をいたしておりまして、今、精力的に与党協議において御議論をいただきながら検討しておりますが、政府としては、この与党の議論の中で要求されたこととか要望されたことに、精力的に意見や提案を行っているということでございます。
以下、略
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内局の官僚にとって、制服組が内局の官僚と対等に扱われることは、青天の霹靂であろう。彼らは不勉強で現場を知らない、自衛隊の部隊・基地等所在地の住民との交流も、米軍など外国の軍人との交流もない。
制服を押さえつけることによって存在してきたが、今後は、内局官僚も真面目に国防に取り組まないと国防環境が厳しくなる中で、内局の存在理由は益々無くなっていく。人事を餌で制服組を押さえつける時代は去った。
【関連記事】
制服組と背広組、対等に 内なる敵、警察官僚の自衛官抑制体質の打破、背景にある急を要する危機!
防衛省「文官統制」廃止へ 健全な国防論議が高まらない背景にある歪んだ国防認識と過度の文官優位
ああー暢気だね! 泥縄式の憲法解釈の見直し、三流政治からの脱皮と自衛官トップの事なかれ主義を排せ!