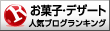友達の親戚のおばさんが作った首里織の作品、イタジイと化学染料を使った帯地が、うるま市長賞に入賞して展示されていました。彼女の作品は去年もおととしも沖展に出ていて、入賞するのが恒例になっているの。
他に、『天国への階段』と題した棚田を描いた絵画、グラフィックデザイン部門では動物愛護団体「ケルビム」の殺処分をなくそうと訴えた広告や『今、電子書籍が熱い!』、写真部門では『ブルームーン』(去年の7月31日のブルームーンを撮ったもので、月の周りに青い光の輪があった)、『不条理』と題した普天間と辺野古の写真を貼った作品、『メタルヒージャー』と題した前身が金属のヤギの彫刻、書芸部門では聖書の『第一コリント十三章』の一節を引用した書(去年も出て今年も出ていた)が印象に残った。
沖展を見た後は、カラオケに行きました。
私が歌った曲は
『風の旅人』、『長崎物語』
一人暮らしをしたいという気持ちを高めようと思って「旅人」にまつわる歌を歌った。一人暮らしをすることに時々不安にかられながらもあこがれがあるから、旅人気分になれば一人暮らしをしたいという気持ちがわいてくるし、旅人気分で一人暮らしをしたいという思いもあってね。
『長崎物語』はインドネシアからはるばる日本にやって来た「じゃがたらお春」が歌詞に出てくる。私は王制反対派なので、(オランダは王制、中国は共和制だから)「オランダ屋敷」は「中国屋敷」に替えて歌った。中華街の家をイメージして。ちょうどその時中華街の映像が映ってたからぴったりだった。
『Guantanamera(グァンタナメラ)』
ひさーしぶりに歌った。収容所の閉鎖や米軍基地の返還の兆しが見えてきたことでキューバのグァンタナモがニュースで話題になってる今、歌ってみようと思った。
『花宴(はなまつり)』
私はこの歌を4月8日のお釈迦様の誕生日の「花祭り」の歌だと思って歌っている。実際にそれと関係あるかどうかはわからないけど、歌詞が仏教の精神に通じるところを感じるの。
『東京天空樹之歌』(『東京スカイツリーの歌』の中国語版)
地名が出てくる歌で、地名は日本語読みでカタカナでふりがなが振られてたけど、私は中国語読みで歌ったよ。たとえば「台東」は「Taidong タイドン」、「押上」は「Yashang ヤーシャン」、「向島」は「Xiangdao シアンダオ」、という具合に。中国語読みにして歌ってみるのも面白いと思ってね。
『Wa! 輪!! ワールド音頭』
ヘタリアの歌。国名や国のものに関する言葉で語呂合わせした歌詞が特徴。
『恋とはどんなものかしら(Voi Che Sapete)』
モーツァルトが作曲し、オペラ『フィガロの結婚』に出てくる曲。今モーツァルトを取り上げた映画『アマデウス』が上映されていて、その映画の中にもこの曲が出てくるかもしれないね。
広告
天皇制批判の常識で検索
ライカム ポケモンで検索
Reborn 沖縄県立博物館・美術館で検索
最新の画像もっと見る
最近の「沖縄の話題」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事