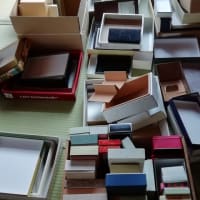1988年出版当時は、(知名度的に?)まだ写真家の増田彰久さんが著者1。
というよりむしろ、写真がメインの本で、藤森さんが書いている文章なんて
ものすごく少ない分量だから、藤森さんが著者2なのは当然かな。
大判と書いてあったが、図書館で実物を見て思わず「……そう来たか」と呟く。
いや、でかい、相当に。立派な装丁。後で知ったが3冊組で当時売価が11万円だそうだ。
予約していたので「すみません、次の機会に」ということも出来ず。
家に持って帰っても読まなそうなので(ねっころがって読める本じゃないと多分読まない)、
閲覧席でその場読みをしてきました。ほとんど全部が写真(1ページ、あるいは
見開き2ページのでかい写真)なので、じっくり眺めて30分程度かな。
読むんじゃなくて眺める本。
この第1巻を見て驚いたのは、何よりも天井のデザインの完成度。
日本にある西洋館の外観のデザインは、完成度を感じることがあまりない。
まあ材料にも建築家にも、資金にも不自由することが多かったんだろうから当然だが、
「ああ、やっぱりモノマネ」というような。そのマガイモノ感も味だったりするわけだが。
でも天井のパートはね。和風テイストを加味するにせよ、モノマネ感、マガイモノ感がなかった。
むしろ和洋の見事な融合を感じた。ここまで出来てるのはなぜだろう。
天井デザインというのは自由度も高く、ある程度こじんまりしているがゆえに
デザインしやすいのだろうか。
正統的ロココ調、正統的ゴシック、ステンドグラスを使ったヌーボー調、和風格天井っぽいのとか。
個人的な好みとしては、みんな美味しい、好きなデザインだった。
照明デザインは前から好き。特にヌーボー、デコ系の照明は味がある。
豪華なだけのシャンデリアより好きだ。もっとも赤坂離宮のこれでもか!というべき
シャンデリアくらいになると、恐れ入りましたと頭を下げるしかないけど。
照明にもうちょっとページを割いても良かったかもしれない。
各部屋で照明器具は変えていることが多いから、物はいくらでもあったろうから。
本のテーマとしては大変良い。
でもここまで豪華本に作る必要はあったか?と思う。
廉価版にしてもっと普及させた方が良かったのにねえ。内容がいいからこそ。
高価で重くて図書館にしか置けない本じゃなく、個人で愛蔵出来る本にするべきじゃなかったか。