アイランド■第1回
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
●第1回
「ママ、このあたりだね」
私ビィーは,すっかり年老いた、かたわらにいる母に言った。
眼下にはきれいな海が見えている。
「そうだよ、ビィー、サンチェス島はこのあたりにあったんだ」
「じゃ、母さんが、花束をおとしてよ」
私はママに、大きな花束を渡した。
「そうだね、ビィー。お父さんも、喜ぶだろうさ。
お前がこんなにりっぱになったのだから」
花束は、私達の乗っている「円盤」から、吸い込まれる様に海へ落下
していった。
「さようなら、バパ、そしてありがとう」
海面を見つめるママの目には涙が浮んでいだ。
私は母の手をにぎりしめていた。
かつて、この海に、「サンチェス島」という島があった。
そして、今は、跡形もないのだ。
それこそ サンチェス島は悲しみの島だった、「哀ランド」だった。
さて、 私ビィーが、その島の話を、始めようか。
■
潜望鏡がアラフラ海に突出していた。
その潜望鏡が、始まりだった。
やがて、水上にゆっくり艦橋があらわれ、ゆっくりと航行し始める。
甲板を波が洗い始めた。海の色はインディコブルーで、海の底はな
いようにすら見える。
潜水艦のハッチが開かれ、数人の男がはいあがってくる。
やがて、ゴムボートがひきずり出され、I人の男がそれに乗り込んだ。
「頼んだぞ、ボーン」
ゴムボートの男に、潜水艦から1人の男が叫んでいた。ゴムボート
の男は巨大な体で、答える。
「わかりました、チーフ」
ゴムボートは遠くに見える島をめがけ、エンジン音をあげていた。
数十分後、ゴムボートはその島の海岸線にたどりつく。
夕闇がせまっていた。男はゴムボートを岸へのりあげた。
突然、光が男を襲う。どこかに仕掛けられたサーチライトが男を
照らす。
瞬間男は体を伏せた。
■ポート=サンチェスの町。
かつてここは美しい海岸を見渡す町だった。
今はただの石くれの町。
この風景のありようは、暗号名「コロラド」の判断ミスがまねいた結果だった。
その男「コロラド」は孤独だった。過去のあやまちをさいなむ心が、この場所を歩かせるのだ。
大いなるあやまちをどうやってつぐなえばいいのか。
コロラドは思わず頭を抱え、傍らの石のかたまりに腰かけた。
彼の心臓は高なっていた。
天候は、彼の心とはうらはらで、とびきりの晴天だった。
そしてこの町あとから腿える海の風景はあまりに青かった。
この町の跡と対照的だった。
ポート=サンチェスのあった場所は、陰うつで耐えようがない。
とても気分が滅入る。
ああ、神よ。
コロラドは独りごちた。
ほほを涙がつたい、その涙が大地をぬらしていた。思わず大地に
口づけをしていた。
「許してくれ、皆。私が、私が悪いのだ」
何かの気配がした。
「プルトゥー」が来ていた。
この機械は大の形をしている。この島の防禦システム「エデイ」の一つの端子だった。
「どうしたプルトゥー、何かあったのか」
できる限り平静をよそおってコロラドは言った。
機械相手に平静を装うだと、私も老いたものだ。コロラドは思う。
世界でも名うてのヒットマンのこの私が、その前は連邦軍の………
やめておこう。過去にこだわるのは、老いた証拠だろう。
「何者かが、この島に近づこうとしています」
「わかった、いつもの手で、追いはらえ」
が、プルトゥーは首をたてに振らなかった。
「しかし、御主人のお知り合いの様ですが」
プルトゥーの胴体に、上空の衛星から撮影された映像が出てくる。
「こいつは、…」
二の句が告げない。
「よし、ブルトゥー、渚で待っていようか」
「わかりました。御主人さま」
プルトゥーはあとにしたがった。
「コロラド、俺だ、射つな」
なじみのある声が叫んでいた。私のコードネームは、アメリカの州名。つまり選ばれし特殊工作員。
「ボーン、お前だとはわかっていた。警告しておいたろう。何人も
この島に近づく事は許さないとな」
彼の名は、有名な小説の主人公から取られている。つまりは、有名な工作員指導官
いわゆるハンドラ-の一人の証明だ。
ボーンはスピーカーを通して叫んだ。彼らの行動はすべておみ
とおしなのだ。なぜなら、この島の防禦システムには1ケ国の国家
予算をつぎこんでいた。上空五千mには監視衛星まで飛ばしている。
「コロラド、お前に役に立つ情報を持って来てやったんだ」
聞きなじんだボーンの声が遠くから聞こえていた。
「静かにしろ、ボーン。お前も知っているだろう。俺が他人にこの
島へ入ってこられることを強度にいやがっている事を」
「いいか、コロラド。お前の島と言っているが、この島はもう地図
上は存在しない」
「何だと、という事は、俺の島は」
「そう、もう地球上にはないって事だ」
「どういう事だ、ボーン」
「いいか、思い出してみろ、コロラド、二、三日前、島に星が落ち
てこなかったか」
「そういえば、二日前」
この島、サンチェス島はコロラドの島だ。いや今のホーンの話では
とっくに地球上から消滅していらしい。
彼、暗号名ボーンは、地球連邦軍暗殺チーム「レインツリー」
に属する暗殺者である。
コロラドは考える。
私の手で幾度、歴史の運命が変わったか。
それを述べるのはやぶさかではない。しかし、
この話とは別の問題だ。ともかくも、コロラドの手は他人の血で汚
れていた。
しかし、そのおかげて普通の人間がI生かかっても手に入れるこ
とができない財産を得ていた。その汚染されたお金を、浄化させよ
うとした。
この島サンチェス島にすべてを注ぎ込んだのだ。この島はコロラ
ドにとっては、いわばエルドラド。楽園だった。
気候は温暖で、日々は過ごしやすかった。海の色はエメラルドグリーンで、渚は
遠浅だった。生活信条として、何人も、この島へ立ち入る事も許さ
なかったのだ。あの事件以来。
そこにあらわれたのがボーン。コロラドと同じく「レインツリー」
に属するヒットマンだった。まったく思いもかけぬ閑人者だった。
確かにコロラドは二日前に、島の山間部に、いん石が堕ちた事を知っていた。
が、屋敷にセットされている防禦システムSDIIはその物体
に対して、何らの危険性を警告していなかった。生命反応もなく、
ましてや危険物質の存在も告げてはいなかった。
「それがどうかしたのか、ボーン」
「とにかく、会って話をしてくれないか、コロラド、俺は何も武器
を持っちゃいない」
「OK、少しはお前さんの言う事を信じよう。同じレインツリーの
仲間としてな」
「用心深いお前さんの事さ、そんな事くらいはとっくにおみとおし
だろう」
そう、確かにおみとおしだった。ボーンの体やゴムボートの解析写
真はこの島の防禦機構SD11が何枚も撮影していた。ボーンの言
葉どおりに、彼はクリーンだった。武器は一つも持っていない。が、
油断はできない。彼の技がいかなる殺人技か、レインツリーの幹部
しか知らないのだから。彼は立ち上り、まわりの風景を見渡してい
る。
(続く)
最新の画像[もっと見る]
-
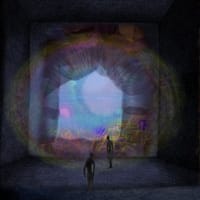 東京地下道1949第2回■アメリカ軍占領軍情報部(OSS)乾公介は窓下、東京分断壁を見ている。彼にMGB(在日占領軍ソ連保安省)のエージェントからの地図入手失敗の報告が。
3年前
東京地下道1949第2回■アメリカ軍占領軍情報部(OSS)乾公介は窓下、東京分断壁を見ている。彼にMGB(在日占領軍ソ連保安省)のエージェントからの地図入手失敗の報告が。
3年前
-
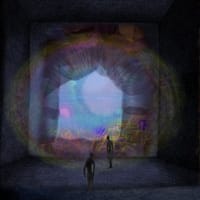 消滅の光景 第9回地球に向かう調査船エクスの中で、情報省のチヒロや超能力少女ラミーに守られて、カド博士は、地球での行方不明者の共通因子を探ろうとするが、祖先霊が邪魔をする。
3年前
消滅の光景 第9回地球に向かう調査船エクスの中で、情報省のチヒロや超能力少女ラミーに守られて、カド博士は、地球での行方不明者の共通因子を探ろうとするが、祖先霊が邪魔をする。
3年前
-
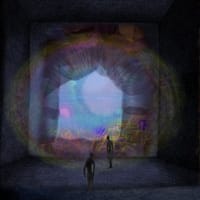 東京地下道1949■第1回1949年 日本は敗戦、分割占領。トウキョウ市アメリカ軍占領地区。浮浪児が、男たちの争いをみる。少年はカバンとトカレフ挙銃を手に入れ。「竜」のアジトヘ向かう。
3年前
東京地下道1949■第1回1949年 日本は敗戦、分割占領。トウキョウ市アメリカ軍占領地区。浮浪児が、男たちの争いをみる。少年はカバンとトカレフ挙銃を手に入れ。「竜」のアジトヘ向かう。
3年前
-
 源義経黄金伝説■第72回■最終回★源義経の存在が日本の統一を可能とした。 源頼朝は日本全国に守護地頭を置く。律法の世、貴族の世である日本を、革命においこんだ。
3年前
源義経黄金伝説■第72回■最終回★源義経の存在が日本の統一を可能とした。 源頼朝は日本全国に守護地頭を置く。律法の世、貴族の世である日本を、革命においこんだ。
3年前
-
 源義経黄金伝説■第71回京都神護寺にて 西行の宿敵、文覚は巨木に向かう。 「天下落居(てんからっきょ)」の時。師匠の彫像を、弟子の夢見、今は「明恵(みょうえ)」は微笑んで眺めている。
3年前
源義経黄金伝説■第71回京都神護寺にて 西行の宿敵、文覚は巨木に向かう。 「天下落居(てんからっきょ)」の時。師匠の彫像を、弟子の夢見、今は「明恵(みょうえ)」は微笑んで眺めている。
3年前
-
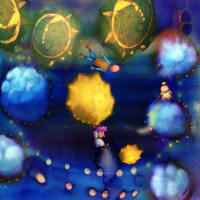 「支配者たち」短編(ハーモナイザーBIGIN)世界樹ハーモナイザーが支配する宇宙、2人の宇宙飛行士の物語。
3年前
「支配者たち」短編(ハーモナイザーBIGIN)世界樹ハーモナイザーが支配する宇宙、2人の宇宙飛行士の物語。
3年前
-
 源義経黄金伝説■第70回鎌倉、大江広元の前に静の母親、磯禅師が現れて、秘密を打ちあける。その秘密とは、源義経の遺児は。
3年前
源義経黄金伝説■第70回鎌倉、大江広元の前に静の母親、磯禅師が現れて、秘密を打ちあける。その秘密とは、源義経の遺児は。
3年前
-
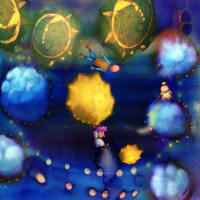 封印惑星)第12回■最終回 地球意志は大球(地球)と結ぶ小球(月)に、星の武器を集め自爆にアーヘブンを 巻きこむ。アーヘブンは新地球の創造をユニコーン、北の詩人、ゴーストトレインが実体化。
3年前
封印惑星)第12回■最終回 地球意志は大球(地球)と結ぶ小球(月)に、星の武器を集め自爆にアーヘブンを 巻きこむ。アーヘブンは新地球の創造をユニコーン、北の詩人、ゴーストトレインが実体化。
3年前
-
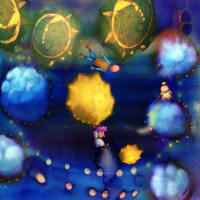 封印惑星)第11回アーヘブンは、「天宮」と対峙。「天宮」は、ハーモナイザーと同化を拒み、地球・思想本図書館とイメージコーダーの合成体が 破壊された。地球思想書が、粉々に吹き飛ぶ。
3年前
封印惑星)第11回アーヘブンは、「天宮」と対峙。「天宮」は、ハーモナイザーと同化を拒み、地球・思想本図書館とイメージコーダーの合成体が 破壊された。地球思想書が、粉々に吹き飛ぶ。
3年前
-
 源義経黄金伝説■第69回鬼一方眼との死闘のため、頭や顔は朱に染まり、足取りもおぼつかぬ文覚は、大江広元屋敷の元を訪れている。
3年前
源義経黄金伝説■第69回鬼一方眼との死闘のため、頭や顔は朱に染まり、足取りもおぼつかぬ文覚は、大江広元屋敷の元を訪れている。
3年前









