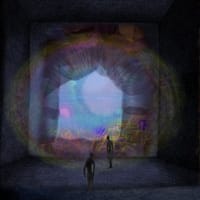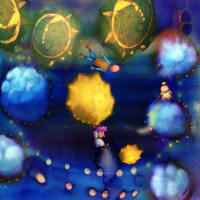染み入れ、我が涙、巌にーなみだ石の伝説」第3回
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
「ええ」僕は答える。
「そうですか.僕、この路線走るのは始めてですねん。ふだんでも,このバスは,ほとんど頭屋村までいかんのですわ。
最近は、客が、よういってるようだけど。本当は、これより先はいかんのなあ。いやだなあ」
「バス停には、頭屋村まで通じてますの地図と張り紙がったぜ」
滝がいいかえす。
「ここからは道が、えろう悪くなるし、つづらおりの坂ばかりですわ。あまり行き
たくないんですわ。頭屋村まで、まだ40分ほどかかるという話だし、途中には全然停まるとこないんで
すわ。」
「バスで40分もかかるところ、歩いてはいけないよ」
滝がいう。
「わかりました。では、こうしましょう。このバス停から先は特別料金をいただきますよ」
「ボリョルナ。タタシーみたいだな」
「残念ながら、ここにはタクシーはないんです。1000円余分にいりますけれど、このパスしか
ないんです」運転手は言い返す。
「そんなこと、一言もバス停の掲示板には、書いてなかったけれどな。まあいいわ、いってよ」
「すごいところだな。日待。1000円分の風景を楽しむとするか」
が、僕は滝の言葉に注意を払わず、僕は彼女のことを考え始めていた。
もうすぐ、あえるかもしれない。
心臓がなみうち始める。汗がでる、待てよ。記憶が、、そうだ。
彼女を。、、かなり昔から
ずっーとずっと前のことだ。僕が子供だった時よりも?、、、昔からだ?
変だ。僕が子供だったことより前。。、彼女を知っていた?。
どういうことだ。 僕が彼女を思うあまりに、そんな気がしたのだろうか。
いや、まちがいない。僕は彼女を大昔から知っている。
移り変わる新緑の山々、その外の景色に気をとられていた滝が、僕の思いつめた青い顔に気がつく。
「どうしたんだい、日待ひまち、まっさおだぜ、お前の顔」
突然、バスが横に激しくゆれた。
窓の景色がひと回りした。
体が車体に勢いよく打ちつけられ、失神しそうになる。
突熱、僕の体を、緑色の光が包み込む。光は神立山の神腹からきていた。体の重さがなくな
り、空間に浮いている。すべてのしがらみから解きはなされ、ほんとうに自由にたったような気がした。’
僕は、緑の光につつまれ、バスが大きく回転しながら、谷間へかちていくのを、他人事のようにぼんやりとなが
めている。
僕の名前が呼ばれたような気がした。それも遠くの方から。
いつのまにか僕の体は、道路そば側の草の上でよこたわっている。
滝のことを気づかい、起きあがり、谷の方をのぞいてみた。
パスは車体がグシャとなり、崖下20mくらいで火に包まれていた。
ころばないように気をつけながら、まったく無傷の僕は、バスまで降りていった。
燃えあがるバスの残骸までたどりつき、しばらくの間呆然とながめていた。
第5回
バスのとびちった部品の影に、滝が倒れていた。
「滝,しっかりしろ」
滝は目をあけた。
服がやぶれ、血がにじんでいた。すこし焼けこげてもいた。
一、二度、頭を振って、滝は上体をおこした。
不思議そうな顔をして、滝は僕をみつめていたが、ポケットに手をつっこんでから、ゆっくりといった。
「日待、君はケガをしなかったのか」
「ああ、そうさ、運転手は?」
あたりをしばらく見渡してみた。
「どうやら、ダメなようだな」
ポツリといった。
滝は、僕の目をじっとみつめ、口を開いた。
「日待、どうだ、ここらでもうはっきりさせないか」
その表情は、これまでの饒舌な滝のものではなかった。別人のようだった。
「何のことだ。何のことを言っているのだ」
僕は体をこわばらせる。
「日待、いや、君の本当の名前まではわからないが、、
まだ、しらばくれる気なのか。君と君の仲間のことさ」
「僕の仲間?」
滝は立ちあがり、少しよろけたが、僕の肩に手をかけた。
「はっきりいえよ、日待。それとも」
「まってくれ、滝、一体お前、どうしたんだ」
その時だ。隣にあるバスの残骸が爆発した。
おもわず僕達は体をふせた。
「そうだ。滝、はやく頭屋村へいこう。むこうで、君のケガをみてもらおう」
「ふっつ、どうやら、頭屋村までは、君が、案内してくれるつもりらしいな」
と皮肉っぽく言う。
いったい、この滝の変心は、なんだ。
僕は
バスの転落、
体を包み込んだ緑色の光、
滝の豹変、
わずかの間に起こった事で混乱している。
それにしても、あの緑色の光は、涙岩の色に似ている。と僕は思った。
頭屋村までは、まだかなりの距離があった。
僕は、滝、彼も、いや彼こそ本当の名前は何だ、、もう話をする気がしなかった。
冷たい沈黙が、僕達の間にあった。
が、二人は村へ向って歩きだす。
滝に肩をかしていた。
バスの通り道へあがり、夕ぐれの中を歩きだした。
村までの風景は、僕が出かける前と、少しも変わっていなかった。
おぼろげな記憶だった
けれども、はっきりと一致していた。
ようやく村へたどりついた時、
来てはいけないところへ来た、そんな気がした。
僕をよよつけない何物かがあった。
体がぞくっとした。
最初に滝の傷をみてもらもらおうと思った。
しかし急に「彼女」のことも思いだし、どうしても会いたいと思った。
彼女の姿を浮べ、不安を振り払おうとした。
手近かの家からは光がもれている。
「ごめんください。」
答えはない。
「誰もいないんですか」
無断で家にはいっていく。人の気配がない。
隣の家家にも、同じように走っていって声をかける。
やはり誰もいない。
そして、
不思議だが、村じゅう、物音一つしない。
誰もいないのか?
滝は、ポケットからタバコ箱くらいの小さな機械をとりだし操作していた。
さっきから滝が触っていたのは、これだったのか。
「滝、村には一人もいない。おかしい」
「やっぱりな、思った通りだな」
滝は、傷のせいか、疲れた顔をしていたが、不思議に目眼だけは、
力があった。
獲物を前にしたハンターの眼だ。
「いいか、もう、はっきりしたらどうなんだ、日待よ」
「何のことをいっていろんだ。滝、君はバスが転落した時から、何をいいたいんだ。人が変ったみたいだよ」
「ふう、簡単な話じゃないか。日待、最近、この田舎の、頭屋村へ来る人々が増えていたこと。
パスの中で老人が言ったこと。そして、今現在、この頭屋村にはな、人っ子一人いないこと。すなわち、今日が。涙岩のくずれる日だ。今日は涙岩伝説の日だ」
僕はその意味するところに、打ちのめされる。
そうか。今日が、涙岩がこわれる日に違いない。
すなわち、数百年に一度の日なのだ。
(続く)