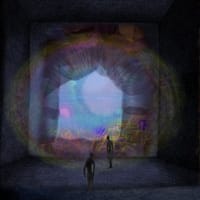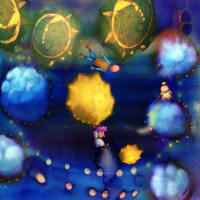●前説ー
太陽の光を受けて、頼朝の眼をいる輝きが焼け跡にあった。
これは…。
頼朝は、その土を触ってみた。何かが土中から姿を現す。
それは、猛火にも拘わらず、溶け掛けた銀作りの猫の像だった。見覚えがあった。
「大殿様、その像は…」
広元が不審な顔をしている頼朝に尋ねた。頼朝は3年前の、鎌倉での西行法師の顔と話を思い起こしていた。
「西行め、こんなところに…、やはり」
頼朝は悔しげに呟いている。
源義経黄金伝説■第57回★
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
Manga Agency山田企画事務所
●http://www.yamada-kikaku.com/
yamadakikaku2009-youtube
■ 1189年文治5年 平泉王国
平泉王国の焼け跡を馬で見回る二人の姿があった。
源頼朝と大江広元である。
文治五年(一一九六)八月二二日、頼朝の「奥州成敗」で、実質上日本統一がなったといえる。大和朝廷の成立後も奥州は異国であり、異国であり続けた。
二人は、中尊寺のところに来ていた。この寺跡は焼け残っている。見上げる頼朝は、感動していた。
「おお、広元、この平泉王国の富、さすがというべきか」
「ははっ、聞きしに勝る都城でございます」
西行がいった通りだと頼朝は考えていた。
平泉は仏教王国だった。
なにしろ、源頼朝は、伊豆に流されて以来、毎日毎日読経ばかりだったのである。心根に仏教教典が染み付いている。空で経文がいくらでもいえるのだ。
奥州藤原氏に対するやっかみの心が、頼朝に擡げてきた。
(こやつら奥州藤原氏にだけは、負けたくない。私が日本の統一者だからだ。
私が日本一の武者の大将なのだ。それならば、私の町鎌倉にもこのような寺が必要だ。)
「このような寺を鎌倉に作るのじゃ。鎌倉が、都や平泉に劣ることあれば、われらが坂東武者、源氏の恥じぞ。この平泉におる職人共をすべて鎌倉に連れ帰り、寺を建てるのじゃ」
「心得ました。この平泉にある寺の縁起、すべて書き出し、我が手に提出致しますよう命じてございます」
頼朝の願いどおり『鎌倉には、平泉の寺院を模倣した寺が建てられた』が、
それは平泉には及ばない。所詮は、平泉の寺院のコピーでしかないのだ。コピーは本物をこえることはできない。
やがて、頼朝は、目下気になっていることを聞いた。
「泰衡が弟、忠衡、発見できぬか」
「いまだ発見できませぬ」広元は残念そうに答えた。
「ええい、忠衡がおらねば、黄金の秘密一切わからぬとは」
古代東北の地、中でも気仙地方は、世界でも最大級の豊かな金鉱を有していた。今出山金山、氷上山の玉山金山、雪沢金山、馬越金山、世田米の蛭子館金山などである』
頼朝はいらついている。
(この国を攻めたは、実は奥州黄金を手に入れることぞ。この国の王には黄金が必要なのだ、あの京都を凋落するのは黄金が一番なのだ)
「国衡も見つからぬのか」
「いまだに姿が見えませぬ」
「ええい、国衡もいないとならば、奥州の金を手に入れたことにはならぬ。されば何のための奥州征伐ぞ」
怒りの目で、頼朝はあちこちを見回している。その時、何かがキラリと光り頼朝の目をいた。
「あれは…」
頼朝が、小高い台地にある焼け跡に目を移した。あきらかに何ヵ月か前の焼け跡である。
二人は高館の跡まで馬を走らす。
「この場所が、義経殿が最期を遂げた場所でございます」
広元が冷静に告げていた。
「義経が死に場所か……よし、少しばかり見て行くとするか」
その頼朝の目には、涙がにじんでいる。頼朝は馬を、その台地に乗り上げ、ゆっくりと馬から降りた。その場所から崖が北上川へと急に落ち込んでいて、東稲山も間近に見える。頼朝はその風景を見ながら思った。
「目の前のあの山が東稲山でございます。西行殿が愛でた桜山です」
(義経、なぜ私の言うことを聞かなんだ。俺は武士の世を作ろうとしたのだ。それを後白河法皇などという京都の天狗に操られよって…。我が兄の心根、わからなんだか。やはり母親の血は争えぬか)
頼朝は母常盤の血を引いていた、やさしい、さびしげな義経の顔を思い浮かべていた。
(あのばか者めが…)
太陽の光を受けて、頼朝の眼をいる輝きが焼け跡にあった。
これは…。
頼朝は、その土を触ってみた。何かが土中から姿を現す。
それは、猛火にも拘わらず、溶け掛けた銀作りの猫の像だった。見覚えがあった。
「大殿様、その像は…」
広元が不審な顔をしている頼朝に尋ねた。頼朝は3年前の、鎌倉での西行法師の顔と話を思い起こしていた。
「西行め、こんなところに…、やはり」
頼朝は悔しげに呟いている。
「では、その猫の像は、あのおり西行にお渡しなされたものではございますか」
「そうだ」
「やはり、西行は後白河法皇様のために…」
「いや、違うだろう。西行は義経を愛していたのであろう。まるで自分の子供
のようにな…」
頼朝は遠くを思いやるようにぽつり述べた。広元はその答えに首をかしげて
いた。
思い出したように源頼朝が告げた。
「平泉中尊寺の寺領を安堵せよ」源頼朝は急に大江広元に命令を下していた。
源頼朝は信心深い性格だった。三二歳で伊豆で旗を揚げるまで、行っていたことと言えば、源氏の祖先を祭り、お経を唱えることだけだった。
まさに、日々、お経しか許されていなかった。毎日十時間の勤行は、頼朝の心に清冷な一瞬を与えていた。神、仏が見えたと思う一瞬があるのだった。この一瞬、頼朝は思索家と思えるものになっていた。
頼朝は、自らの行っている幕府作りが日本の歴史上、大きな転換点になるとは考えてもいる。
板東の新王、ついに平将門以上の存在になった。
源氏の長者が、何世紀にもわたって成敗できなかった奥州も我が手にした。
彼の考えていたのは、武家が住みやすい世の中を作ることのみであった。
■7 1189年文治5年京都
京都の後白河法皇御殿にも平泉落城の知らせが届く。
「頼朝、ついに平泉へ入りました」
関白,藤原(九条)兼実が後白河法皇に悲しげに報告した。
「そうか、しかたがないのう。平泉を第二の京都にする計画潰えたか。残念だのう」
「せっかく夢を西行に託しましたが、無駄に終わりました」
「が、兼実、まだ方法はあろう」
後白河は、また、にやりとする。
「と、おっしゃいますと…」
不思議そうに、兼実は問い返す。
(いやはや、この殿には…、裏には裏が、天下一の策謀家よのう。平泉を第二の京都にできなかったは残念だが、次なる方策は)
「鎌倉を第二の京都にすることだ。源氏の血が絶えさえすれば、京に願いをすることは必定。まずは頼朝を籠絡させよう。さらに頼朝が言うことを聞かぬ場合は…」
後白河法皇の目は野望に潤んでいる。
「いかがなさいます」
「義経が子、生きていると聞くが、誠か」
「は、どうやら、西行が手筈整えましたような」
「その子を使い、頼朝を握り潰せ。また、北条の方が操りやすいやもしれぬ。兼実、よいか鬼一法眼に、朕が意を伝えるのだ」
笑いながら、後白河は部屋に引き込んだ。兼実は後に残って呟く。
「恐ろしいお方だ」
兼実は背筋がぞくっとした。
20131016改訂(続く)
Manga Agency山田企画事務所
●http://www.yamada-kikaku.com/
yamadakikaku2009-youtube