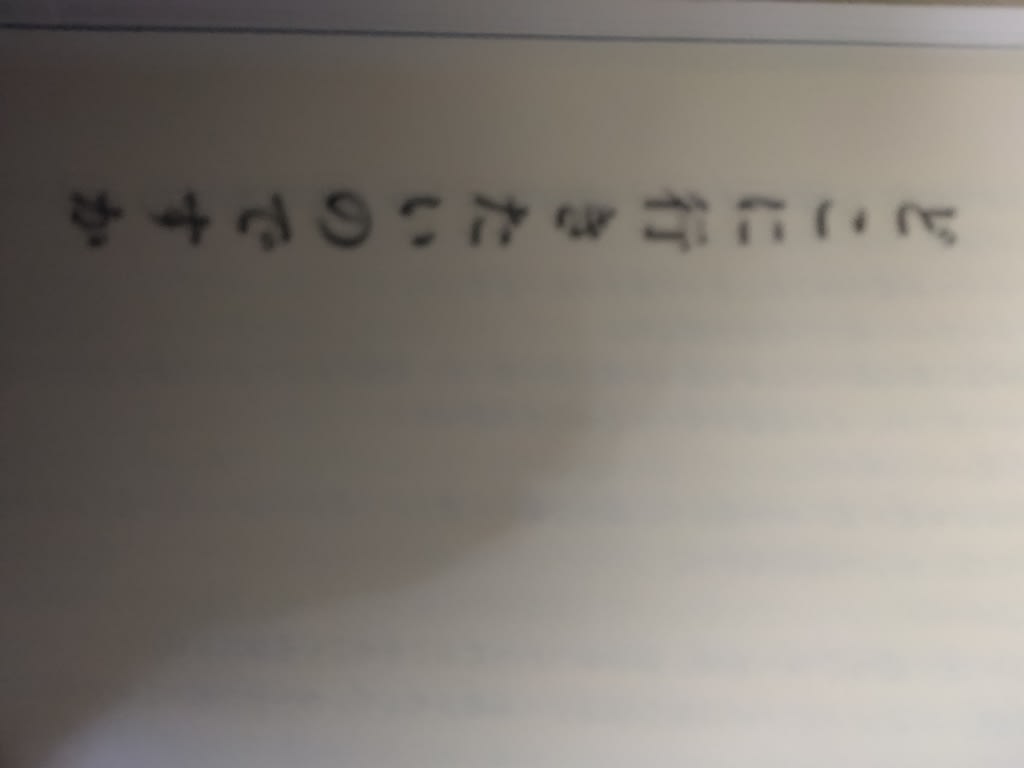
梶井基次郎の『檸檬』の主人公は、現代社会においては、
「健康」にも「裕福」にも、そして「正常」にも分類されないであろう。
貧乏学生で、借金持ち、友人の自宅を泊まり歩いている。
さらに、神経症で肺病とされており、かつアルコール中毒的な描写も在る。
しかし、主人公は、その状況を改善しようと躍起になっておらず、少しも気にしていないようにみえる。
たとえ「憂鬱」で「苦しい」と外部に規定されるような日々を送っているとしても、
彼自身は自分の生を「悪い」もの、または「否定的な」ものと思っていないから、絶望していないのであろう。
私には、むしろ彼が非常に堂々と日々を送っているように見える。
現代では(当時でも)
「多くの問題を抱えて未来もない駄目な男」
のレッテルを貼られるであろう彼は、どのように自己を肯定しているのだろうか。
私の解釈では、その理由として彼は、
外的(≒社会的)な評価よりも、自己の裡に強固な内面世界を持っているからではないであろか。
さらに、着目したいのは、彼が、彼自身の「美しいもの≒芸術」と一貫して関わることで、外的評価にとらわれない自己を完成させている。
彼の意識が、その美しさに耽溺することで、彼は、外的な社会的規範から離脱し、「純粋経験」をしているようにすらみえる。
『檸檬』が発表されたのは、1924年である。
人もモノも情報も容易に海を越えることが出来なかった時代だ。
「彼」にとっては、丸善の棚に並ぶ、舶来品の数々は、便利、高品質といった日常的な意味を超えて、非日常的で非現実的な、もしかしたら、「神聖な」輝きを放っていたかもしれない。
しかし彼は、それらを無批判に受け入れ、賛美するのではなく、「自己が満足する美」を模索し、手に入れる。
模索の過程で、幼少期の想い出、お祭りの夜の出店のような「身近に在って安っぽくて愛おしい、色、光、興奮」に「自分が満足する美」を感じる。
彼が最後に手に入れた「自己が満足する美」は舶来品に比べては「劣る」と外的な評価を受けかねない。
ある日散歩の途中、主人公は檸檬を買う。
食べるためではなく、檸檬自体の色や形や重さを味わうため、「美しさを感じるため」に手に取ったのだ。
確かに、主人公は、外的(社会的概念的)な世界内での時間を暗く重い気持ちで過ごしている描写もある。
しかし、内的な自己の時間では、主人公は対象との美に出会い、対象を内的な描写もある。
しかし、内的な自己の時間では、主人公は対象としての美に出会い、対象を内的な世界で昇華し美しい時間を生きている。
そのとき、自分が生きている外的(社会概念的な)世界は相対化され、遠く退いていくような不思議な意識状態を経験する。
彼は、この美的体験に、単なるおもしろさ楽しさではなく、それ以上の価値を見出している。
この体験によって、彼は、生と世界を肯定するのである。
(→次回に→→続く→→→)











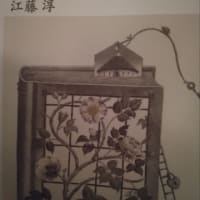
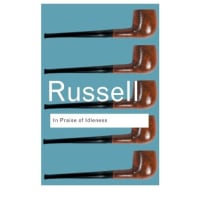


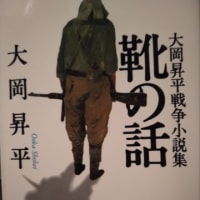


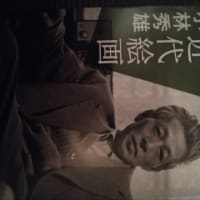

レモン🍋檸檬>なんでこんな難しい字にするんでしょうかね?(^O^)
「木編に丁寧な蒙驁将軍」これで暗記しました!
『薔薇』なんて、いまだに覚えてるつもりでも、暫くすると自信がなくなります!(#^.^#)
高校時代でしたかに、檸檬という漢字に惹かれて読みましたが、すっかり内容を忘れていました。
懐かしく思い出させて頂きました。
コメントありがとうございます( ^_^)
お返事遅れてしまいました。
数日間体調を崩していました。
寒い日が続きますが、ikenaijoniさんも体調にはお気をつけてくださいね( ^_^)
こんにちは。
コメントありがとうございます( ^_^)
お返事遅れてしまいました。
数日間体調を崩していました。
寒い日が続きますが、ピエリナさんも体調にはお気をつけてくださいね( ^_^)