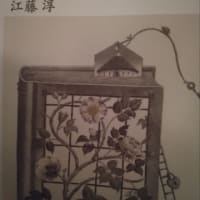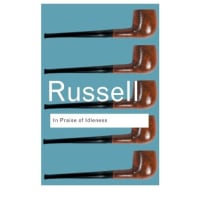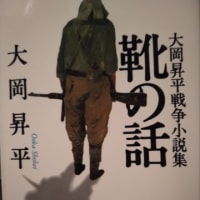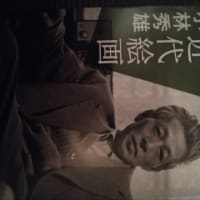植は可哀想かもしれない。
持つものは持っている、兄の曹丕(魏の文王)に武や文の才能を妬まれ、
「七歩歩くうちに詩を作れ、さもなくば処刑だ」
と言われ、哀しいながら考えた。
「煮豆持作羹
漉鼓以為汁
萁在釜下燃*
豆在釜中泣**
本是同根生***
相煎何太急****」
(→
*豆がらは釜の下で燃え
**豆は釜の中で泣く
***豆も豆がらも同じ根から育ったものなのに
****豆がらは豆を煮るのにどうしてそんなに激しく煮るのか)
何でだよ兄さん!?
この詩の哀しさを教えてくれた恩師をみているうちに、
原因において自由な行為(刑法39条)を想い起こした。
「(泥酔状態に仮になったとしても)泥酔状態で行った殺人や障害などは、心神喪失注(≒自分が何もわからない状態で)の行為だから罰せられない」
というものだ。
しかし、自ら責任能力のない泥酔状態をわざと作り出し、その状態を「利用し」て人殺しなどの犯罪を引き起こした場合でも無罪だと、はできないであろう。
そこで、「計画的に責任無能力」になった場合は罰する」という理論を
原因において自由な行為
というのである。
泥酔状態を作ることが予見され、作り出そうとして酒を飲む原因を設定した行為の当時には、自分をコントロールする能力が十分に働いていたわけであるから、危害を加えたなら、
加えたあなたにも責任能力はあるだろう、と、いう理屈である。
この泥酔状態で起こした事故と、高齢者が高齢だと認識していても運転した末に起こした事故をどう考えるのか、と、の問いが横たわる。
誰にでも背景が在るので、すべてはわからない。
(しかし、泥酔状態の背景もさまざまであるが......。)
さて、兄の曹丕と曹植の考えをみるに、『七歩詩』の兄もさまざまな原因で、精神的な泥酔状態かもしれない。
そんな意味で、私を救ってくれようとしている恩師を理会するため、彼が拘っていた
『七歩詩』を
考えてみたいと思う。