
現在、アラブ首長国連邦(UAE)でCOP28が行われている。
2日のCOP28会合で、南スーダン共和国のキール大統領は、
「地球温暖化の影響で、多くの国で、多くの人が避難民になっっている」
と述べた。
気候変動問題に拠る難民問題、それに附随して起きる領土・食料問題、そしてその結果としての紛争や戦争......私たちはどうして、問題たちに掛けた現実否認や願望的思考のベールを取り払おうとせず、さらには願望に満ちた都合の良い、しかしながら危険な幻想を作り上げようとしてしまうのだろうか。
精神医学において「妄想」とは、
「強固に維持された揺るぎない誤った信念であり、決定的な証拠や理性的議論による修正にも抵抗するもの」
と、定義されている。
また、動詞として「妄想させる」と使われる場合は、誤ったことを相手に信じさせるという意味になる。
(以下、「妄想」は上記の意味で用いることとする。)
人間はみな、大きな不安に直面すると、自らを安心させるような不正確な説明を作り上げてしまう性質を持っている。
人類が世界についてほとんど知識を持たなかった古代に作られた神話が、多くの知識を獲得した現代にまでも、延々と語り継がれているし、今も私たちは、今在る不安と将来に対する恐怖に向き合えるように、と、せっせと新たな神話を作り出している最中なのかもしれない。
私たちの社会も(私たち個人がそれぞれ構成員なので)、私たち個人に起きる妄想とよく似た妄想に悩まされている。
社会が抱く妄想により、私たちはリスクが見えなくなり、意図せぬ結果に無頓着になってしまう。
しかし、さまざまな重大な危機に対して消極的な態度を取り、現時点で厳しい決断をすることなく、将来なんとかなるという誤った信念に依存することは、
今在る世界をめちゃくちゃし、その世界を元どおりにするのに大きな犠牲を払わなければならない、と、いうつらい現実からのただの逃避である。
妄想はなかなか無くなってはくれない。
イデオロギーや利己主義、怒り、恐怖も、現実が非常に不安定で満足のいかないものであろうとも、現状を協力に守ろうとする。
私たちが、自ら深い墓穴を掘っていたのだ、と、理解することが、その墓穴から這い上がるために、まず必要なステップであろう。
シェークスピアの『リア王』は、「疎外」の小説だという人もいるが、私は、精神医学の定義での「妄想」に囚われた/絡め捕られたひとの姿を描いた小説だ、と、思う。
繰り返しになるが、精神医学において「妄想」とは、
「強固に維持された揺るぎない誤った信念であり、決定的な証拠や理性的議論による修正にも抵抗するもの」と、定義されている。
リア王前半でよくそれが表れているシーンがある。
三女のコーディリアの真意を理解しなかったリア王が、100人のお供を連れて長女のゴネリルのところへ行き、そこで受け入れ条件に「お供を半分(50人)にしろ」と言われ激怒し、とんでもない台詞(暴言)を浴びせかけた後に、次女のリーガンの元に行くものの、リーガンに受け入れ条件として「お供を半分(25人)にしろ」と言われ、激怒し、50人と25人のどちらがマシかを考えてしまう。
都合良くゴネリルに言ってしまったことを忘れたリアは、ゴネリルの元に戻るのだが、覆水盆に返らず......受け入れ条件は「お供をなし(0人)」となってしまう。
この一気のリアの立場の瓦解に愕然とするのだが、リア王(King Lear)と三女のコーディリア(Cordelia)の名前にシェークスピアの洒落っ気を感じる。
コーディリアはCordeliaと表記される。
Cor-de-liaと分解してみると、LearとLiaは発音(どちらもリアと読めるので)から、Lear≒Liaとすると、
さらにdeはラテン語で~からに由来するとして、
corは同じくラテン語から心臓や心といった意味であり、意訳と解釈を進めると根源とか中心となる(無理があるかもしれない)。
Cordeliaはリア(Lear)を源にする、またはリアを受け継ぐ者となる。
だから、本当の意味での子どもはコーディリアであったのに、リアは強固(頑固?)に維持された揺るぎない誤った信念のなか、修正に抵抗して、悲劇に直進している、ように思えてならないのである。
揺るぎない誤った信念を頑固に維持することは、愚かである、と『リア王』教えてくれる気がしてならない。
しかも、解決する手段は己の裡にしかないのだとコーディリア(Cordelia)を通じてシェークスピアが指摘しているようにも私は感じるし、そんな解釈をしている。
あとは、明日までのCOP28の成果にも、期待し過ぎず、期待をしている。少なくとも
将来世代に
「2023年のCOP28のときに、なぜ何もしなかったんだ、しようとしなかったんだ」
と言われない成果を望んでいる。
ここまで、読んでくださり、ありがとうございます。
見出し画像は、最近、あるお店の前で撮ったものです。
宮沢賢治さんの「注文の多い料理店」を想い起こしました。
「注文の多い料理店」は、料理を作ってもらえて食べるのが「アタリマエ」だった2人の、まさか、自分たちが料理の下準備をさせられていて、かつ、自分たちが山猫たちに料理される食材だった......!!と立場が入れ替わる驚き、恐怖、そこから安堵や学んだことなどを素敵な世界観で教えてくれますね。
それとともに、身近にある「アタリマエ」は本当に「アタリマエ」か、と、立ち止まって考えることの大切さをはじめて読んだ子どものときから教えてくれる本です。
30代になった今では、なんだか一層怖い気すらする本です......(;^_^A
今日も頑張り過ぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。











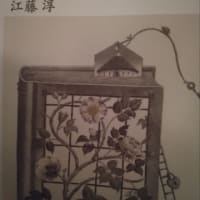
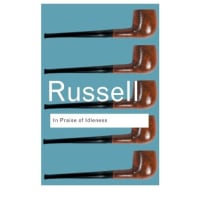


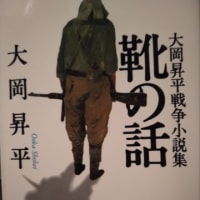


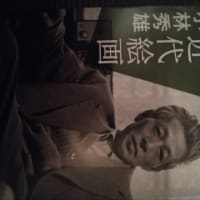

初めてコメントします。
いつも暖かいリアクションありがとうございます。
僕は高校しかでていない無学な人間で、僕みたいな無学な人間が、ようこさんのような高学歴の方のブログにコメントしてよいか戸惑いながら書きます。
いつも面白い記事を読ませていただいてありがとうございます。
さて、今日の記事で最後の方にアタリマエという語が出てきて、この間のとあるイタリアの大学が主催する伊語の検定試験の問題の1つを思い出しました。その問題に、この新聞記者はどう思ったか、という問題があり、最初”新聞記者?誰のことをいっているのだろう?”と思ったり問題文中の1人称単数で書かれていた文章を”誰が思っているのだろう?”と思いながら考えて、ふと、その問題文が新聞記事だということに気づきました。そして初めて、その分の著者が新聞記者だということに気づきました。
前置きが長くなりましたが、僕はようこさんの記事を見て、まさに人間の思い込みというのは怖いな、と思いました。自分の頭の中で客観的に物事を捕らえることができなければ、本当の意味や状態を知ることができずに、危ない崖に突っ込んでしまうな、僕の場合は試験の合否だったんだな、と思いました。こんな調子だったので、多分試験の結果はよくないだろうな、と思っていますが、とにかくおっしゃる通り、アタリマエが本当にアタリマエか考えるさせる注文の多い料理店は重要な本だと思います。
上手くかけなく無駄に長くコメントを書いてしまいましたが、ご容赦下さい。
何せ高卒出の無学な人間の書いたことなので笑って許して下さい。
はじめまして。
いつも読んで下さりありがとうございます。
いつもamocla91さんは、イタリア語をしっかり勉強されていて、努力家な方なのだなあと思っていました。
仰る通り、「アタリマエ」のことを、
なぜ「アタリマエ」なのか、考えたり証明したりしようとしなくなるので人間の思い込みは怖いですね。
私も思い込みにとらわれないように頑張って描こうとしていますがまだまだです^_^;
読んでくださりありがとうございます。
これからも努力しながら前に進もうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
明日の夜には復帰できそうです
おざわ様のブログ 私には難解で3度は閲覧を繰り返して理解した気になります
私は神楽坂の化学科卒なので未知の分野は
頭の体操にもなります
また、いつも読んでくださりありがとうございます。
まずは、お身体を大事になさって下さいね( ^_^)