今回は、竹人形の里&永平寺を紹介させていただきます 「越前竹人形の里」  越前竹人形の生産拠点 職人たちの手技を実感し 代表作や名作を展示した創作竹人形館が 見学できる日本で唯一の施設です  竹林の道 風情を感じませんか?  竹人形作家 勝生(かつみ)さんの、実演を拝見しました 竹人形の何が大変か?それは何を作るのではなくて どの竹でどうやって作るかを考える事 人形のしなやかさを、どの竹で表現するかが難しい と・・・おっしゃってました  竹を割いて作られる髪の毛 一本一本を丁寧に作られてて 本当に竹でできてるの?って思ったほどです 繊細でとても綺麗でした       「越前おろし蕎麦」  お昼にいただきました 腰があってさっぱりしてて とても美味しかったです ↑これで1人前です(食べすぎ?) 時は今から約400年前の慶長6年(1601年) 本多富正公が京都伏見から越前府中(現・生市)へ赴任してきたおり 金子権左衛門なる「そば職人」を連れてきました 家老本多富正公は府中藩主として 水利や(今でも武生の街の中央を用水が流れています) 産業など街の発展に尽力しました そして城下の人々に非常食として蕎麦の栽培や 大根おろしを蕎麦にかけて食べることを奨励し これが「福井のおろしそば」の発端であると言われています。 大根おろしを蕎麦にかけて食べる同様の食風習は 全国にもあちらこちらにありますが 領主が、飢饉や災害の非常食にと栽培を奨励したのは 全国でも非常に珍しいことで 現在に至るるまで営々として受け継がれてきました       「永平寺」  仏殿(ぶつでん)  永平寺中雀門  大晦日、行く年来る年で鳴らされる除夜の鐘です 曹洞宗大本山永平寺は 今から約750年前の寛元2年(1244年) 道元禅師によって開創建された出家参禅の道場です。 室町時代には天皇から「曹洞宗第1道場」の勅額を贈られ 日本の禅修行の場として歴史を刻んできました 33万平方メートルにも及ぶ広大な敷地には 山門・仏殿・法堂・僧堂・大庫院・浴室・東司などの 修行の中心となる「七堂伽藍」 など、70余棟の建物が 樹齢600年を越える老杉の巨木に囲まれながら 静かにたたずんでいます。 50名の雲水たちによって、荘厳な雰囲気の中、 今も750年前に道元によって定められた 厳しい作法に従って禅の修行が営まれています。 福井への旅、お付き合いいただきありがとうございました 今回は欲張ってあちこち見て回って へとへとになりましたが 初めて行く場所ばかりで、いい思い出がたくさん出来ました       「人を見て、表情が違う猫」  玄関先で寛ぐ猫ドンです ペロペロ毛繕い中  はっと!!写真を撮ってる管理人に気づきました  おい・・・猫ドン、舌を仕舞い忘れてるよ(汗) めちゃ、「ぶ○○く」なんですけど(爆)  今度はちゃんと可愛い横顔です ばっちりね  実はこのとき何を見てたのか?って申しますと 娘が玄関から出てきたんですよ 愛しい者を見る表情、優しい目で見てますね  管理人の時は、舌を仕舞い忘れた? いや・・・もしかして「べーだ」ってしてたのか?! こうも違うと、う~~ん悔しい   「ベーだ」から 「ベーだ」から愛しい目になった猫ドンに クリックお願いします
|














 恒例 「にゃんこに会ったよ~~」のコーナー
恒例 「にゃんこに会ったよ~~」のコーナー






















 )
)
































 >
>







 の時期が遅いて言われてますが
の時期が遅いて言われてますが




 」
」









 いらっしゃ~い、いらっしゃ~い
いらっしゃ~い、いらっしゃ~い 」
」


















































 エイ
エイ
 ユニット誕生にゃ~~
ユニット誕生にゃ~~



 >
> >
> >
>








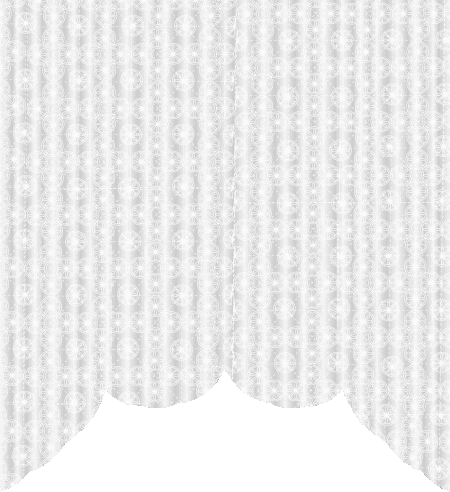
 右端下の「▽」部分をクリックし続けてください
右端下の「▽」部分をクリックし続けてください







 」
」









