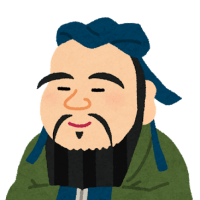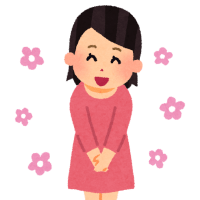論語を現代語訳してみました。
学而 第一
《原文》
有子曰、禮之用、和爲貴。先王之道斯爲美。小大由之、有所不行。知和而和、不以禮節之、亦不可行也。
《翻訳》
有子〔ゆうし〕 曰〔い〕わく、礼〔れい〕の用〔よう〕は、和もて貴〔たっと〕しと為〔な〕す。先王〔せんおう〕の道〔みち〕は斯〔これ〕を美〔び〕と為す。小大〔しょうだい〕 之〔これ〕に由〔よ〕れば、行なわれざる所〔ところ〕 有〔あ〕り。和を知りて和すれども、礼を以〔もっ〕て之を節〔せつ〕せざれば、亦〔また〕 行なう可〔べ〕かざる。
有子〔ゆうし〕 曰〔い〕わく、礼〔れい〕の用〔よう〕は、和もて貴〔たっと〕しと為〔な〕す。先王〔せんおう〕の道〔みち〕は斯〔これ〕を美〔び〕と為す。小大〔しょうだい〕 之〔これ〕に由〔よ〕れば、行なわれざる所〔ところ〕 有〔あ〕り。和を知りて和すれども、礼を以〔もっ〕て之を節〔せつ〕せざれば、亦〔また〕 行なう可〔べ〕かざる。
《現代語訳》
つづいて、有若〔ゆうじゃく〕先生が、『三年の喪に服す』ことについて、次のように述べられました。
それぞれの礼式・礼法を用いるにあたっては、堅苦しくならないように、和〔なご〕やかに用いることが肝心です。古代先王も、この和やかさをひとつの美徳として考えられていたようです。
それでも、三年の喪でさえも、大事に思わない人が多くなり、和やかさの度がこえてしまい、礼式・礼法を乱してしまうこともあるようです。
堅苦しくてもいけませんが、和やかすぎてもいけません。なにごとも、節度をもって行うべきではないですか、と。

〈つづく〉
※ 三年の喪とは、日本仏教でいうところの三回忌にあたるとされている
※ 原文・翻訳の出典は、加地伸行大阪大学名誉教授の『論語 増補版 全訳註』より
※ 現代語訳については、同出典本と伊與田學氏の『論語 一日一言』から参考としている
※ 孔先生とは、孔子のことで、名は孔丘〔こうきゅう〕といい、子は、先生という意味
※ イラストは『かわいいフリー素材集 いらすとや』さんより