やる気はあるんですよ。
ええ。
決してサボってるわけじゃないんですよ。
ええ。
やってはいませんけど、
それはやる気がないわけじゃないですし、
やろうと思ってることは確かなわけです。
そういう意味では、
毎日やっている、
いや、
やろうとしていると表現してもいいわけで、
つまり、
決してやってないというわけでもない、
というのが正しい現状でして、
全体的な視点と言いますか、
総合的に見てですね、
その結果として、
やってなかったというだけであって、
決してですよ、
サボってたわけじゃないと、
まぁそういうことなわけですよええ。
ええ、
そういうことなんです。
ん?
なにか?

そんな今日この頃、
ご無沙汰しておりました、
悠です。
来週ですね、
よ~やく休みがとれそうなんで、
本格的に仕込みの方を始めていこうかと思っています。
前から考えていた仮説が幾つかあり、
それを一つ一つやるには効率が悪いので、
時間短縮のため、
幾つかのグループに分けて、
同時進行で検証を行っていこうと思います。
一応、
新たな栽培方法にも着手する予定ですが、
時間的に見て難しそうなので、
そちらは準備だけ進めていく予定です。
で、
今回の実験の一番の目玉なんですが、
もうズバリ言っちゃいましょう。
それはですね、
なんと、
肥料

なんですね~。
またですか

さんざん失敗こいてきたじゃないですか、
という意見も、
当然あるでしょう。
学習能力がないんですか、
という声も、
当然あるでしょう。
だがしかし!
普及委員会では、
極秘裏に、
とある実験を行っていたんですね。
その実験とは、
袋をつけさせたネペンテスと、
袋が出来る前にカットして、
葉だけで育てたネペンテス、
その成長の違いをですね、
ずっと観察を続けていたわけです。
どうですかこれ。
ちょっとどうなるか興味はあっても、
実際に試したことある方、
ほとんどいないんじゃないですかこれ。
普及委員会はですね、
誰もが思うけど、
誰もやらない実験が得意でして。
どうですか、
結果が気になるんじゃないですかこれ。
まぁぶっちゃけ、
ネペンテスは成長自体が非常に遅いので、
検証中ではあるんですが、
いつも栽培記をご覧頂いてる方のために、
特別、
本当に特別ですが、
途中経過の様子をお伝えしましょう。
ええ、
写真はめんどいので撮りませんがね。
結論から言いますと、
袋があってもなくても、
生長はさほど変わらないと、
そういう状態が続いております。
吸水の感じも大差なく、
葉の出る速さや大きさも同じくらい。
調子の良しあしも、
特段あるようには見えません。
なんでしょうか、
わけがわかりません。
色々とご意見があると思いますので、
補足いたしますが、
袋にはどっちゃり虫が入っており、
栄養も十分に取れてるはずです。
これまで普及委員会では、
袋の役割は、
生命維持装置であるとか、
葉の寿命を長くするブースター装置であるとか、
数々のとんでも理論を展開してきましたが、
現段階の実験結果を見るに、
どの仮説もイマイチな感じです。
じゃあ逆にですよ、
生長速度やサイズ、
葉の寿命に影響がないのなら、
袋はいったいなんのためについてるのか。
この疑問を解消するべく、
普及委員会ではこの度、
新たな仮説を立ち上げました。
それはズバリ、
子孫繁栄説

そう、
袋の真の役割とは、
ネペンテスの生長などの、
短期的なスパンのためではなく、
もっと長い目で見た、
我々の想像を遥かに超えた、
遺伝子レベルの超重要器官なのではないか、
ということです。
つまりですよ、
どういうことかと言いますと、
人間や個人の価値観などはいったん置いといて、
生物学的に見た場合、
生き物の一番の使命は、
いったい何であるかという、
もっとも単純な、
生物のもっとも基本的な本質を問う問題なわけです。
そう、
それは、
子孫を残すということです。
じゃあ、
植物が子孫を残すには、
何をしなければならないのか。
種類によって方法の違いはありますが、
もっとも一般的なのは、
花を咲かせることなわけですね。
花を咲かせ、
花粉を作り、
受粉させ、
種を作る。
このサイクルが、
植物にとって一番重要な活動なわけですね。
思えばですよ、
なぜネペンテスは、
雄株と雌株に分かれているという、
一見すると非効率な生態で生き残ってきたのか。
効率で考えれば、
一本で花粉を作り、
受粉も済ませ、
種を作った方が、
種が存続しやすいように思えるわけですよ。
じゃあなぜ二つに分かれていた方が、
ネペンテスにとって都合がいいのか。
まぁおそらくですけど、
ネペンテスの住む地域は、
我々が想像する以上に、
貧栄養地帯だったということです。
そして、
花を咲かせるということが、
想像以上に、
エネルギーと養分を消費するということです。
つまり、
一本で行うにはあまりにも条件が悪く、
途中で力尽きてしまうリスクをとるよりも、
開花時期などの機会損失はありますが、
二本でそれぞれ分担し、
種の存続を賭けた方が、
可能性が高かったのではないか、
という仮説なわけです。
袋は成長のためではなく、
開花に使うエネルギーを蓄えるためのもの、
というのが、
今のところ、
普及委員会の見解です。
じゃあそれと肥料が、
いったい何の関係があるのか。
それはもう企業秘密ですね。
これはプロジェクトですから、
そうホイホイと公開するわけにはですね、
ええ、
いや、
もったいぶってるわけじゃないんですよ。
ただですよ、
また失敗しますと、
また皆様から、
ほれ見たことかと非難が噴出
厳しいお言葉を頂戴してしまうかもしれませんので、
成功した場合だけ大々的に公開する、
これが大人の処世術というものですから、
ええ、
つまりはそういうことなわけです。
ではでは、
今日はこの辺で。
また次回、
お会いしましょう。
ええ。
決してサボってるわけじゃないんですよ。
ええ。
やってはいませんけど、
それはやる気がないわけじゃないですし、
やろうと思ってることは確かなわけです。
そういう意味では、
毎日やっている、
いや、
やろうとしていると表現してもいいわけで、
つまり、
決してやってないというわけでもない、
というのが正しい現状でして、
全体的な視点と言いますか、
総合的に見てですね、
その結果として、
やってなかったというだけであって、
決してですよ、
サボってたわけじゃないと、
まぁそういうことなわけですよええ。
ええ、
そういうことなんです。
ん?
なにか?

そんな今日この頃、
ご無沙汰しておりました、
悠です。
来週ですね、
よ~やく休みがとれそうなんで、
本格的に仕込みの方を始めていこうかと思っています。
前から考えていた仮説が幾つかあり、
それを一つ一つやるには効率が悪いので、
時間短縮のため、
幾つかのグループに分けて、
同時進行で検証を行っていこうと思います。
一応、
新たな栽培方法にも着手する予定ですが、
時間的に見て難しそうなので、
そちらは準備だけ進めていく予定です。
で、
今回の実験の一番の目玉なんですが、
もうズバリ言っちゃいましょう。
それはですね、
なんと、
肥料

なんですね~。
またですか

さんざん失敗こいてきたじゃないですか、
という意見も、
当然あるでしょう。
学習能力がないんですか、
という声も、
当然あるでしょう。
だがしかし!
普及委員会では、
極秘裏に、
とある実験を行っていたんですね。
その実験とは、
袋をつけさせたネペンテスと、
袋が出来る前にカットして、
葉だけで育てたネペンテス、
その成長の違いをですね、
ずっと観察を続けていたわけです。
どうですかこれ。
ちょっとどうなるか興味はあっても、
実際に試したことある方、
ほとんどいないんじゃないですかこれ。
普及委員会はですね、
誰もが思うけど、
誰もやらない実験が得意でして。
どうですか、
結果が気になるんじゃないですかこれ。
まぁぶっちゃけ、
ネペンテスは成長自体が非常に遅いので、
検証中ではあるんですが、
いつも栽培記をご覧頂いてる方のために、
特別、
本当に特別ですが、
途中経過の様子をお伝えしましょう。
ええ、
写真はめんどいので撮りませんがね。
結論から言いますと、
袋があってもなくても、
生長はさほど変わらないと、
そういう状態が続いております。
吸水の感じも大差なく、
葉の出る速さや大きさも同じくらい。
調子の良しあしも、
特段あるようには見えません。
なんでしょうか、
わけがわかりません。
色々とご意見があると思いますので、
補足いたしますが、
袋にはどっちゃり虫が入っており、
栄養も十分に取れてるはずです。
これまで普及委員会では、
袋の役割は、
生命維持装置であるとか、
葉の寿命を長くするブースター装置であるとか、
数々のとんでも理論を展開してきましたが、
現段階の実験結果を見るに、
どの仮説もイマイチな感じです。
じゃあ逆にですよ、
生長速度やサイズ、
葉の寿命に影響がないのなら、
袋はいったいなんのためについてるのか。
この疑問を解消するべく、
普及委員会ではこの度、
新たな仮説を立ち上げました。
それはズバリ、
子孫繁栄説

そう、
袋の真の役割とは、
ネペンテスの生長などの、
短期的なスパンのためではなく、
もっと長い目で見た、
我々の想像を遥かに超えた、
遺伝子レベルの超重要器官なのではないか、
ということです。
つまりですよ、
どういうことかと言いますと、
人間や個人の価値観などはいったん置いといて、
生物学的に見た場合、
生き物の一番の使命は、
いったい何であるかという、
もっとも単純な、
生物のもっとも基本的な本質を問う問題なわけです。
そう、
それは、
子孫を残すということです。
じゃあ、
植物が子孫を残すには、
何をしなければならないのか。
種類によって方法の違いはありますが、
もっとも一般的なのは、
花を咲かせることなわけですね。
花を咲かせ、
花粉を作り、
受粉させ、
種を作る。
このサイクルが、
植物にとって一番重要な活動なわけですね。
思えばですよ、
なぜネペンテスは、
雄株と雌株に分かれているという、
一見すると非効率な生態で生き残ってきたのか。
効率で考えれば、
一本で花粉を作り、
受粉も済ませ、
種を作った方が、
種が存続しやすいように思えるわけですよ。
じゃあなぜ二つに分かれていた方が、
ネペンテスにとって都合がいいのか。
まぁおそらくですけど、
ネペンテスの住む地域は、
我々が想像する以上に、
貧栄養地帯だったということです。
そして、
花を咲かせるということが、
想像以上に、
エネルギーと養分を消費するということです。
つまり、
一本で行うにはあまりにも条件が悪く、
途中で力尽きてしまうリスクをとるよりも、
開花時期などの機会損失はありますが、
二本でそれぞれ分担し、
種の存続を賭けた方が、
可能性が高かったのではないか、
という仮説なわけです。
袋は成長のためではなく、
開花に使うエネルギーを蓄えるためのもの、
というのが、
今のところ、
普及委員会の見解です。
じゃあそれと肥料が、
いったい何の関係があるのか。
それはもう企業秘密ですね。
これはプロジェクトですから、
そうホイホイと公開するわけにはですね、
ええ、
いや、
もったいぶってるわけじゃないんですよ。
ただですよ、
また失敗しますと、
また皆様から、
厳しいお言葉を頂戴してしまうかもしれませんので、
成功した場合だけ大々的に公開する、
これが大人の処世術というものですから、
ええ、
つまりはそういうことなわけです。
ではでは、
今日はこの辺で。
また次回、
お会いしましょう。
















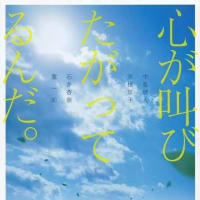






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます