「一般競争入札の導入率65% 市区町村の公共工事」という見出しの昨日発信のニュース(共同通信様)を目にしました。
常日頃考えていたことなのですが、雑感として今日は記させていただこうと思います。
総務省、国土交通省、財務省の3省によって、公共工事の入札実態調査の結果についてを発表されました。
2009年9月1日時点の政令指定都市を除く1779市区町村のうち、談合防止に効果があるとされる一般競争入札を導入(試行段階を含む)していたのは、65・0%の1157にとどまっているのが現状のようです。
『公共工事の入札は、地方自治法で一般競争入札が原則とされているようですが、導入率は前年同期から4・5ポイント増え、都道府県や政令市が100%なのに比べ、入札改革の遅れが明らかとなっている。』と、そのニュースには書かれていましたが、一般競争入札でないと遅れているとは必ずしも言えないと考えます。
そのニュースの中でも、「小規模市町村は一般競争入札の担当職員の確保が難しく、総務省は「結果を分析し、支援策などを検討する。」とあり、「一方で都道府県でも、ほぼすべての公共工事が一般競争入札となるよう対象の予定価格を「250万円超」としていたのは福島、大阪、宮崎など13府県だけで、東京(9億円以上)、沖縄(3億円以上)、新潟(1億2千万円以上)など高額なケースもあった。」とも書かれていました。
「ムダをなくす」、「ムダを減らす」ということは重要ではありますが、その「耳障り」が良いがゆえになおさら、本当の「ムダ」を見極める判定力が必要となるはずです。
本当にムダなことにはメスを入れるべきだとは思いますが、札を入れて、工事を請け負う建設会社も、この社会を構成する一員です。そこには従業員がおり、下請け等の関わり合う人々が大勢います。
工事を受注する場面では建設会社は「生産者」のポジションですが、場面が変われば「生活者」「市民」のポジションであるわけです。
公共の役割として、「生産者」と「生活者」「市民」のポジションの調整弁としての機能も期待されているところですから、(敢えて使いますが)「適当な」水準で工事を発注している限りにおいては、公共工事の発注価格を過度に抑制させる動きに出るのは、社会として適切なことではないと強く感じる次第です。
同じ日の毎日新聞様発信のニュースで、『県:公共工事入札、最低価格引き上げ 知事「改革後退ではない」/宮崎』というのがありました。
宮崎県は、公共事業の入札で建設工事の最低制限価格を、現行の85~90%から約90%に引き上げると発表した。発注量の減少や景気低迷による建設業界の厳しい経営環境に配慮した、というのです。
もともと宮崎県の東国原英夫知事は、「宮崎は変わらんといかんが」宣言!「過去」からのしがらみの一掃の政策の一環として、入札改革に関して、
①業者と知事の癒着を防ぐために指名競争入札の縮小及び廃止を検討し、一般競争入札の活用や現行の条件付き一般競争入札の拡大を検討
②落札率の常時チェック(チェック組織の検討)を行い、日本一高い落札率の低下を促進
などを掲げておられます。
官製談合事件の反省から入札制度改革を進めるのは結構なことですが、それはFairnessが確保されないことが問題の本質であって、入札制度の改革によって、中小、零細建設業者が犠牲になるのは遺憾なことです。
弊センターも出版・情報提供を通じて、建設業に深く関わっており、上記のような雑感をもった次第です。
【ご参考】
全日本土木建築情報センター(春日書房)のHPはこちら
常日頃考えていたことなのですが、雑感として今日は記させていただこうと思います。
総務省、国土交通省、財務省の3省によって、公共工事の入札実態調査の結果についてを発表されました。
2009年9月1日時点の政令指定都市を除く1779市区町村のうち、談合防止に効果があるとされる一般競争入札を導入(試行段階を含む)していたのは、65・0%の1157にとどまっているのが現状のようです。
『公共工事の入札は、地方自治法で一般競争入札が原則とされているようですが、導入率は前年同期から4・5ポイント増え、都道府県や政令市が100%なのに比べ、入札改革の遅れが明らかとなっている。』と、そのニュースには書かれていましたが、一般競争入札でないと遅れているとは必ずしも言えないと考えます。
そのニュースの中でも、「小規模市町村は一般競争入札の担当職員の確保が難しく、総務省は「結果を分析し、支援策などを検討する。」とあり、「一方で都道府県でも、ほぼすべての公共工事が一般競争入札となるよう対象の予定価格を「250万円超」としていたのは福島、大阪、宮崎など13府県だけで、東京(9億円以上)、沖縄(3億円以上)、新潟(1億2千万円以上)など高額なケースもあった。」とも書かれていました。
「ムダをなくす」、「ムダを減らす」ということは重要ではありますが、その「耳障り」が良いがゆえになおさら、本当の「ムダ」を見極める判定力が必要となるはずです。
本当にムダなことにはメスを入れるべきだとは思いますが、札を入れて、工事を請け負う建設会社も、この社会を構成する一員です。そこには従業員がおり、下請け等の関わり合う人々が大勢います。
工事を受注する場面では建設会社は「生産者」のポジションですが、場面が変われば「生活者」「市民」のポジションであるわけです。
公共の役割として、「生産者」と「生活者」「市民」のポジションの調整弁としての機能も期待されているところですから、(敢えて使いますが)「適当な」水準で工事を発注している限りにおいては、公共工事の発注価格を過度に抑制させる動きに出るのは、社会として適切なことではないと強く感じる次第です。
同じ日の毎日新聞様発信のニュースで、『県:公共工事入札、最低価格引き上げ 知事「改革後退ではない」/宮崎』というのがありました。
宮崎県は、公共事業の入札で建設工事の最低制限価格を、現行の85~90%から約90%に引き上げると発表した。発注量の減少や景気低迷による建設業界の厳しい経営環境に配慮した、というのです。
もともと宮崎県の東国原英夫知事は、「宮崎は変わらんといかんが」宣言!「過去」からのしがらみの一掃の政策の一環として、入札改革に関して、
①業者と知事の癒着を防ぐために指名競争入札の縮小及び廃止を検討し、一般競争入札の活用や現行の条件付き一般競争入札の拡大を検討
②落札率の常時チェック(チェック組織の検討)を行い、日本一高い落札率の低下を促進
などを掲げておられます。
官製談合事件の反省から入札制度改革を進めるのは結構なことですが、それはFairnessが確保されないことが問題の本質であって、入札制度の改革によって、中小、零細建設業者が犠牲になるのは遺憾なことです。
弊センターも出版・情報提供を通じて、建設業に深く関わっており、上記のような雑感をもった次第です。
【ご参考】
全日本土木建築情報センター(春日書房)のHPはこちら












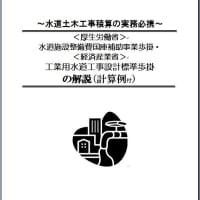
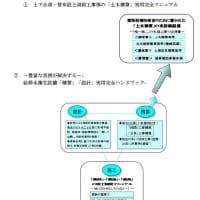
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます