 「豊臣秀次の群像」アマゾン電子書籍紹介。BOOK★WALKER電子書」
「豊臣秀次の群像」アマゾン電子書籍紹介。BOOK★WALKER電子書」
豊臣秀次(1568年~1595年)安土桃山時代の武将。豊臣秀吉の甥。通称孫七郎。父は三好吉房、母は秀吉の母の姉。1584年(天正12)小牧・長久手の戦に出陣し、敗れて有力家臣を失い、秀吉に叱咤された。しかし、翌年秀吉から近江に43万石の領知と山内一豊以下4名の宿老を付与され、八幡山に城を築いた。1590年秀吉の東国平定に際しては尾張清洲城に入り、宿老たちは東海道の要所に進出、豊臣政権の対東国最前線に配置された。実子に恵まれなかった秀吉が関白になると、羽柴秀長らとともに昇殿、1586年の右近衛中将から中納言、内大臣、左大臣と昇進。1591年には関白職を譲られ、後継者の地位についた。1593年(文禄2)秀頼が生まれると、実情は一変し、太閤として実権を握る秀吉と関白秀次権力との間に矛盾が表面化し、尾張の蔵入り地に太閤奉行衆の介入を受けるに至った。秀次に日本国の五分の四を与えるとか、秀次の娘と婚約など秀吉側から提案されたが、実現しないまま、1595年7月に謀反の罪で高野山に追放され、切腹させられた。妻子妾子女30余名も三条河原で悉く斬られた。秀次は調停に書籍を献上し、能の謠本百番の注釈など、作らせるなど、伝統文化の保存と継承した貢献した側面があった。正親町上皇の諒闇中に狩猟を行う軽率な性格があり、こうした結果を招いたといわれている。
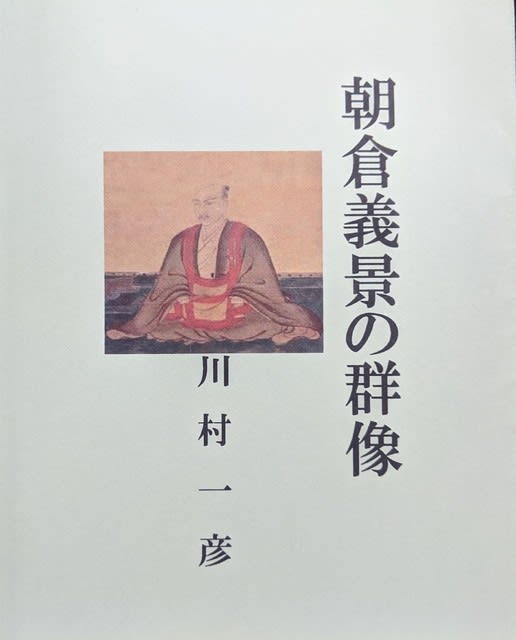 「朝倉義景の群像」アマゾン電子書籍紹介。BOOK★WALKER電子書」
「朝倉義景の群像」アマゾン電子書籍紹介。BOOK★WALKER電子書」
朝倉義景(1533年~1573年)越前の戦国大名、朝倉氏5代当主。孝景の長男、1548年(天文17年)に家督を継ぐ。延景と称したが、1552年に将軍足利義輝の一字を受けて改名。左衛門督。加賀一向一揆を攻撃してい、若狭の武田氏に支援の派兵している。他方では1561年(永禄4)に武威を誇示する大掛かりな犬追い物を催し、翌年には一乗谷に下向した元関白近衛尚通の子で大覚寺義俊を招いて曲水宴を開くなど、華美で文人風の儀礼を好んだ。1568年、前年に義景を頼って下向した足利義秋(義昭)の元服の役を務めている。この頃から本願寺とは和睦して織田信長と対立し、1573年(天正元)8月に近江で信長軍の追撃を受けて、越前大野に落ち延びたが、同月20日に自刃した。

「歴史の回想・長享延徳の乱」アマゾン電子書籍紹介。BOOK★WALKER電子書」
「長享・延徳の乱の起因」(ちょうきょう・えんとくのらん)とは、室町時代後期の長享元年(1487年)と延徳3年(1491年)の2度に亘って室町幕府が行った近江守護・六角行高(後の六角高頼)に対する親征で、六角征伐とも称される。
なお、1度目の出陣は近江国栗太郡鈎(まがり)(滋賀県栗東市)に在陣したため、別に鈎の陣とも称される。
文明9年(1477年)に応仁の乱が収束したのち、各地では守護や国人らが寺社領や公家の荘園などを押領して勢力を拡大していた。
旧西軍に属していた近江守護・六角行高も荘園や奉公衆の所領を押領していた。しかし、長享元年(1487年)7月、奉公衆の一色政具の訴訟案件が幕府に持ち込まれ、これをきっかけとして他の近江の奉公衆も六角行高に対し訴訟を起こした。さらに寺社本所領押領も発覚、幕府はその威信回復を企図して六角氏討伐の兵を挙げ近江に遠征した。
文明11年(1479年)11月、第9代将軍・足利義尚は判始を行ったが、先代将軍の足利義政は政務移譲を渋って対立し、文明17年(1485年)4月には奉公衆と奉行衆の諍いから、布施英基が義尚の小川御所にて奉公衆に殺害されている。
そして、長享元年(1487年)9月12日、足利義尚は、管領・細川政元をはじめ、若狭守護・武田国信等の守護大名、在京奉公衆、在国奉公衆、さらには公家衆も率いて近江坂本へ出陣した。この時、義尚は奉行衆も連れており、鈎の陣は実質的に幕府の政務も担ったが、奉行衆のうち義政側近であった伊勢貞宗、飯尾元連、松田数秀等は同行を許されず政務から外された。
義尚の遠征に対し、六角行高は観音寺城を放棄して撤退した。しかし、甲賀郡山間部でのゲリラ戦を展開し、戦闘は膠着状態に陥った。

「歴史の回想・本能寺の変」アマゾン電子書籍紹介。角川・BOOK★WALK」
本能寺の変は1582年(天正10年)織田信長が家臣のあ結光秀によって殺害された事件。信長は備中高松城(岡山市)を囲んで毛利軍と戦っている羽柴秀吉の応援のために、光秀に先鋒を命じた、自分は僅かな近臣を率いて四条坊門西洞院の本能寺に、嫡男の信忠は室町薬師町の妙覚寺に入った変の前日、信長は多くの公家や町衆から挨拶を受けて、茶の湯で接待し、夜は本因坊算砂らに碁を打たせて楽しんだ。信長は終日上機嫌で西国遠征の勝利を確信していた。光秀は1万余名の兵を率いて居城の丹波亀山城を出発、6月2日払晩本能寺を襲った。本能寺は一応の構えがあるが、東を西洞院川が流れるほか、残る三方は堀があったかどうかは不明。信長の警固は守蘭丸以下の小姓や中間数十人で、手練の馬廻衆は市中に分宿しておらず、信長はあえなく自刃した。信忠は妙覚寺が構えがないので、隣の二条御所に立て籠もり、駆け付けた馬廻り衆らを率いて戦たが、明智光秀の鉄砲隊にが撃破されて自刃。辺は終結されたが、明智光秀の謀反の理由が、怨恨説、立身絶望説、天下取り説などあるが、定説がない。光秀は山城、近江を平定したが、備中高松城で毛利と和睦して東上、大軍を山城山崎付近に集める中国大返しに成功した秀吉のために山崎の戦いに大敗し、野伏に討たれその天下が10日余りで終わった。
 「歴史の回想・乙丑の獄」アマゾン電子書籍紹介。角川・BOOK★WALK」
「歴史の回想・乙丑の獄」アマゾン電子書籍紹介。角川・BOOK★WALK」
乙丑の獄(いっちゅうのごく)は、1865年(乙丑年)に、福岡藩で起こった佐幕派による勤皇派弾圧事件。乙丑の変、または乙丑の政変と呼ぶ場合もある。
幕末の福岡藩、江戸時代末期、福岡藩は藩主黒田長溥の元「尊王佐幕」を掲げ、幕府を助けながら天皇を尊ぶ公武合体論に似た政治運動を進めていた。長溥自身非常に開明的で、城下に鉄鉱炉を建設し、また鉱山開発を進めるなど「蘭癖大名」と呼ばれるほどであった。また幕末の政治において「開国し政権が変わなければ日本の未来はないが、幕府は潰さず、朝廷と合同しそのまま改革すべし」という保守的な立場から幕府を助け、強い影響力を持つに至った。
これに対し家老加藤司書・藩士月形洗蔵・中村円太・平野国臣らを中心とする筑前勤王党は「攘夷を進め、幕府を打倒し政権を天皇の下へ戻すべし」という尊皇攘夷論を唱え、藩主に対し決意を迫っていた。そればかりか、彼らは上意を越え暴走を始める。福岡藩士の勤王派は土佐勤王、薩長の勤王派と連携しますます攘夷を進め藩佐幕派にばく進する中、藩主と思いは対立し行く中、藩主黒田長溥は勤王、佐幕と心は揺れ動き、勤王の藩士に弾圧を加える。勤王の藩士の末路は藩主の乙丑の獄を招き、切腹・加藤司書・斉藤五六郎・建部武彦・衣非茂記・尾崎惣左衛門・万代十兵衛・森安平・斬・・月形洗蔵・海津幸・鷹取養巴・森勤作・江上栄之進・伊藤清兵衛・安田喜八郎・今中祐十郎・今中作兵衛・中村哲蔵・瀬口三兵衛・佐座謙三郎・大神壱岐・伊丹信一郎・筑紫衛・流刑・野村望東尼・野村助作らの死によって福岡勤王党は終末を迎えた。









