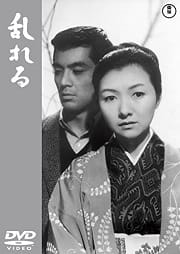■ YouTube Selection (songs & music)
 かれこれ40年近く前でしょうか、最初に観たのは。その後とんとお目にかかる機会もなく、しかしながら、「地下水道」というタイトルも、真っ暗で臭そうな下水道を必死で逃げる人たちの姿や、マンホールを上って地上に出たところで周りにはドイツ兵がうじゃうじゃなんていうシーンもずっと忘れずにいました。
かれこれ40年近く前でしょうか、最初に観たのは。その後とんとお目にかかる機会もなく、しかしながら、「地下水道」というタイトルも、真っ暗で臭そうな下水道を必死で逃げる人たちの姿や、マンホールを上って地上に出たところで周りにはドイツ兵がうじゃうじゃなんていうシーンもずっと忘れずにいました。今回はNHK-BSではアンジェイ・ワイダ監督のドキュメンタリーも同時期に放送していて、そちらも面白い内容でした。合わせて観ると、ドキュメンタリーで紹介されたポーランドの歴史により、描かれていない「地下水道」の政治的な背景も分かり感慨深いものがあります。撮影当時、社会主義体制でソ連の影響下にあったポーランドでは映画製作にも検閲があり(反ソ連的な表現は御法度であった為)、特に政治的なテーマが多いワイダ監督の苦労話も興味深いものでした。
「地下水道」は第二次世界大戦末期のポーランドが舞台。
NHKの解説では<第二次大戦末期のワルシャワほう起における対独レジスタンスの戦いを、全編の3分の2を占める地下水道を舞台とした悲惨な極限状況の中に描き出す。当時、弱冠31歳だったワイダによるドキュメンタリー・タッチのリアルで冷徹な映像は圧巻。カンヌ映画祭審査員特別賞受賞。>
ドキュメンタリーによれば、ワルシャワ蜂起の背景にはソ連軍のポーランド進駐=ドイツ軍の撤退という計画図があったようですが、ソ連軍はワルシャワのすぐ側まで来ていながら、レジスタンスと協調することなく、むしろドイツ軍に好き放題にさせた。そこにはスターリンの非情な思惑があり、結局、愛国心の強いポーランド人たちが20万人も見殺しになってしまったわけです。
「地下水道」にはそういう反ソ連的な思想も製作の裏側にはあったはずですが、出来上がったものは悲しい戦争の記録であり、反ソのムードは全然出ていません。
「灰とダイヤモンド」よりも登場人物の心情はわかりやすく、男女の恋愛も絡んでおり、タイトルから想像されるほど無味乾燥なドラマではありません。単調になりそうな下水道でのシーンも、逃げる人々を色合いの違う3班に分けて描いた為に緊張がとぎれないものとなっています。ちょっと、尻切れトンボ風のところもありますがね。
お薦め度は★★★から★★★★。
レジスタンスには民間人もおり、音楽家も出てきます。前半では彼が民家でピアノを弾くシーンもあり、まさに「戦場のピアニスト」でした。
ドキュメンタリーでは、カンヌで一躍注目された時の面白い話も出てきました。当時、西側の映画人たちは「地下水道」のストーリーを架空の話だと思っていたそうです。
(1956/アンジェイ・ワイダ監督/タデウシュ・ヤンツァー、テレサ・イジェフスカ、エミール・カレヴィッチ、ヴラデク・シェイバル/96分)
(1971/ダルトン・トランボ監督・脚本/ティモシー・ボトムズ、キャシー・フィールズ、ジェイソン・ロバーズ、マーシャ・ハント、ドナルド・サザーランド、ダイアン・ヴァーシ/112分)
<ネタバレあります>
封切時に観て、大変衝撃を受けた作品。但し、同時に翻訳本も読んだので、強い印象を残したのが映画のせいだったか、本のせいだったか、はたまた残酷な題材のせいか自分でも分からなくなっています。
今年、初めにNHKーBSの録画で再会しました。【原題:JOHNNY GOT HIS GUN】
 第一次世界大戦に参加したアメリカの若者が主人公。オープニング・タイトルのバックでは勇ましいドラムの音が鳴り続け、映画の開始早々、雨中の戦場の若者めがけて落下音と共に爆弾が落ちてくる。思わず、エッ!と絶句するが、次のシーンは病院の中だ。
第一次世界大戦に参加したアメリカの若者が主人公。オープニング・タイトルのバックでは勇ましいドラムの音が鳴り続け、映画の開始早々、雨中の戦場の若者めがけて落下音と共に爆弾が落ちてくる。思わず、エッ!と絶句するが、次のシーンは病院の中だ。
若者はベッドの上。横たわっているが、脚は見えない。お腹の上にカゴを被せたような形に布を膨らませて覆い、顔にも白い布が顔の表面から浮かすように被せてある。
若者のモノローグが始まる。
ここはどこだ? 周囲の状況を少しずつ確認していく。このプロセスが恐い。
若者には脚がない。爆弾に飛ばされたのだ。両腕もない。そして、なんと口もない、鼻もない。胴体と性器はあるようだが、口と一緒に喉も声帯も飛ばされちまったので、話すこともできない。(はっきり覚えてませんが、確か耳も聞こえないはずです)
想像してください。自分がそんな状態になったことを。身の回りを認識するのは、寝ているベッドを揺らす振動、それと肌に伝わる空気の感触だけです。
つまり意識はあるのです。前頭葉もしっかり残っているので、考えることも出来るのです。しかし、その事、自分には自分の状態が分かっているというその事を伝える術がないのです。むしろ、何も感じない方が幸せかも知れない、そう思ってしまいます。
この病院の担当医も、この若者にはすでに意識が無く、ただ息をしているだけ、時々動くのも神経の作用だと思っています。ただ一人、若者を担当している看護婦だけが、あることから彼には意識があり、コミュニケーションをとろうとしていることを知ります。
暗い部屋はイヤだ。夜中にネズミが顔の周りをうろつくような所はイヤだ。窓のカーテンも昼間は開けていて欲しい。そうすれば、“今”が昼なのか、夜なのかが分かるから。昼にはガラス越しに差し込む陽の光が額を暖めるから気持ちいいのだ。
しかし、看護婦から彼が意志を持っていることを聞かされた医者は、その事を公にしないように言う。公表するにはあまりに残酷だし、またとない研究材料なのだから・・・。
反戦映画ですな、明らかに。
ラストは、「ノー・マンズ・ランドド」のように、虚しく、苦しい思いだけが残り、戦争への怒りが沸々と湧いてくるわけです。
50年代の赤狩りによって、ハリウッドを追われた脚本家ダルトン・トランボが、自らの小説を生涯ただの一度だけ監督をした作品。1971年のカンヌ国際映画祭で、審査員特別グランプリを受賞したそうです。
現在の病院の中のシーンはモノクロ。ベッドの上の彼が思い出す、出征前の色々な思い出、幻想的な夢や空想はカラーで描かれています。
幻想のシーンには明らかにキリストをイメージさせる男(サザーランド)が出て来ますが何の救いにもならず、これは神の不在或いは無力を意味しているのでしょう。
過去の思い出では、出征前にぎこちなく彼女とベッドを共にしたこと、父親と魚釣りに行ったこと等を思い出します。
このまま生きて帰った時に、父親に見世物として晒される夢もみます。勿論、これは自虐的な夢で、父親はそんな事をするはずはありません。
数十年ぶりに今年観た印象は、モノクロとカラーを使い分けたり、幻想や夢のシーンを織り交ぜたりしているが、画の構成には技巧的なモノは見当たらなかったこと。それに正攻法の迫力を感じるか、物足りなさを感じるかで評価が別れるでしょう。
幻想シーンのエピソードは、それ程効果的ではなかったように感じました。
<ネタバレあります>
封切時に観て、大変衝撃を受けた作品。但し、同時に翻訳本も読んだので、強い印象を残したのが映画のせいだったか、本のせいだったか、はたまた残酷な題材のせいか自分でも分からなくなっています。
今年、初めにNHKーBSの録画で再会しました。【原題:JOHNNY GOT HIS GUN】
*
 第一次世界大戦に参加したアメリカの若者が主人公。オープニング・タイトルのバックでは勇ましいドラムの音が鳴り続け、映画の開始早々、雨中の戦場の若者めがけて落下音と共に爆弾が落ちてくる。思わず、エッ!と絶句するが、次のシーンは病院の中だ。
第一次世界大戦に参加したアメリカの若者が主人公。オープニング・タイトルのバックでは勇ましいドラムの音が鳴り続け、映画の開始早々、雨中の戦場の若者めがけて落下音と共に爆弾が落ちてくる。思わず、エッ!と絶句するが、次のシーンは病院の中だ。若者はベッドの上。横たわっているが、脚は見えない。お腹の上にカゴを被せたような形に布を膨らませて覆い、顔にも白い布が顔の表面から浮かすように被せてある。
若者のモノローグが始まる。
ここはどこだ? 周囲の状況を少しずつ確認していく。このプロセスが恐い。
若者には脚がない。爆弾に飛ばされたのだ。両腕もない。そして、なんと口もない、鼻もない。胴体と性器はあるようだが、口と一緒に喉も声帯も飛ばされちまったので、話すこともできない。(はっきり覚えてませんが、確か耳も聞こえないはずです)
想像してください。自分がそんな状態になったことを。身の回りを認識するのは、寝ているベッドを揺らす振動、それと肌に伝わる空気の感触だけです。
つまり意識はあるのです。前頭葉もしっかり残っているので、考えることも出来るのです。しかし、その事、自分には自分の状態が分かっているというその事を伝える術がないのです。むしろ、何も感じない方が幸せかも知れない、そう思ってしまいます。
この病院の担当医も、この若者にはすでに意識が無く、ただ息をしているだけ、時々動くのも神経の作用だと思っています。ただ一人、若者を担当している看護婦だけが、あることから彼には意識があり、コミュニケーションをとろうとしていることを知ります。
暗い部屋はイヤだ。夜中にネズミが顔の周りをうろつくような所はイヤだ。窓のカーテンも昼間は開けていて欲しい。そうすれば、“今”が昼なのか、夜なのかが分かるから。昼にはガラス越しに差し込む陽の光が額を暖めるから気持ちいいのだ。
しかし、看護婦から彼が意志を持っていることを聞かされた医者は、その事を公にしないように言う。公表するにはあまりに残酷だし、またとない研究材料なのだから・・・。
*
反戦映画ですな、明らかに。
ラストは、「ノー・マンズ・ランドド」のように、虚しく、苦しい思いだけが残り、戦争への怒りが沸々と湧いてくるわけです。
50年代の赤狩りによって、ハリウッドを追われた脚本家ダルトン・トランボが、自らの小説を生涯ただの一度だけ監督をした作品。1971年のカンヌ国際映画祭で、審査員特別グランプリを受賞したそうです。
現在の病院の中のシーンはモノクロ。ベッドの上の彼が思い出す、出征前の色々な思い出、幻想的な夢や空想はカラーで描かれています。
幻想のシーンには明らかにキリストをイメージさせる男(サザーランド)が出て来ますが何の救いにもならず、これは神の不在或いは無力を意味しているのでしょう。
過去の思い出では、出征前にぎこちなく彼女とベッドを共にしたこと、父親と魚釣りに行ったこと等を思い出します。
このまま生きて帰った時に、父親に見世物として晒される夢もみます。勿論、これは自虐的な夢で、父親はそんな事をするはずはありません。
数十年ぶりに今年観た印象は、モノクロとカラーを使い分けたり、幻想や夢のシーンを織り交ぜたりしているが、画の構成には技巧的なモノは見当たらなかったこと。それに正攻法の迫力を感じるか、物足りなさを感じるかで評価が別れるでしょう。
幻想シーンのエピソードは、それ程効果的ではなかったように感じました。
・お薦め度【★★★=強烈な反戦映画、一度は見ましょう】 

(1942/ウィリアム・ワイラー監督/グリア・ガーソン、ウォルター・ピジョン、テレサ・ライト、デイム・メイ・ウィッティ、レジナルド・オーウェン、ヘンリー・トラヴァース、リチャード・ネイ、ヘンリー・ウィルコクソン/134分)
何だか最近、ブログの記事も書き方がマンネリ気味で『何とかならんかいな』なんて思ったりもしてますが、なにせボキャブラリーが乏しいもんでね。例によって、いつもの調子です。ちょっと間が空いてしまったのですが、初鑑賞は1週間以上前。その後チラチラと家人が寝ているときに見直しております。
去年の大晦日に買った4枚の1コインDVDの一つ。なんとまあ、一年ぶりの鑑賞。いつでも観られると言う安心からか、オールドムーヴィー故軽んじたのか。しかしまあ、なんというか、ワイラー演出の細やかさは相変わらずウットリでありました。
ワイラー監督は12回アカデミー監督賞にノミネートされていますが、5回目にして初受賞した作品がこの「ミニヴァー夫人」です。
 第2次世界大戦の真っ最中に作られた作品で、話は1939年の英国参戦前の夏から始まります。
第2次世界大戦の真っ最中に作られた作品で、話は1939年の英国参戦前の夏から始まります。
ロンドンにほど近い平和な村。建築士の父親にはオックスフォード在学中の長男ヴィンと少し年の離れた長女と幼い次男がいる。映画の解説では中流家庭となっているが、料理人はいる、メイドはいる、しかも娘にはピアノの家庭教師もいる、そんなミニヴァー家です。
美人の奥さんは時々ロンドンに買い物に行っては自分の浪費癖を後悔しているが、決してお高くとまってなくて、地元のベルハム駅の駅長バラード氏は自身が育てた赤く美しいバラに「MRS. MINIVER」と名前を付けるほど。ソレを聞いた夫人も誇らしく感じるというよりは感謝するといった具合。まるで、武者小路実篤の本のような出来過ぎの善人たちばかりだが、全く不自然さを感じさせない作品でした。
この村では毎年、元領主のペルドン家の老女が主催する花の品評会があっていて、バラ部門は主宰者の老女が優勝することになっている。村人が元領主に遠慮して誰もバラ部門にエントリーしないからだが、バラードは今年は出品するつもりらしい。それ程の傑作なのだ。
いよいよ英国も大戦に参加し、ヴィンも軍隊に入る前に大学から帰ってくる。そんな折り、ペルドン家の孫娘がミニヴァー家を訪れる。“MRS. MINIVER”の評判を聞いて、祖母を悲しませたくないためにバラード氏に出品を取り止めてもらえないかとミニヴァー家へやって来たわけだ。階級意識に批判的なヴィンはそこでキャロルと論争となるが、その夜の村のダンスパーティーで二人は仲直りをしやがて恋に落ちる。
幸せな話はこの辺りまで。やがて、村にもドイツ軍の爆撃機が飛んでくるようになり、ヴィンは空軍へ、メイドの彼氏も海軍へ入隊する。灯火管制が始まり、付近に墜落した飛行機からはドイツ兵が逃亡し、付近に潜んでいるという噂も出てくる。
一週間の予定で帰ってきたヴィンに急に召集がかかり、その上真夜中の2時にミニヴァー氏にも自家用の船と共に緊急集会が開かれる。それは、ドイツ軍に追われてフランス、ダンケルク迄撤退してきた連合軍を助けに行くという民間人をも巻き込んだ事態だった・・・。
平和な5人家族の長男が軍隊に志願し、村の人々と共に一家も戦争に巻き込まれるという話は後年の「友情ある説得(1956)」に似ています。南北戦争が舞台だった「友情・・」はヒューマニズムがテーマとして確立していましたが、コチラは戦争中のこと故、ヒューマニズムを前面に出すことは控えられたようで、戦意昂揚を押しだそうとした終盤のまとめ方が、戦争の影が全くない平和な村と幸せな一家を描いた前半に対してちぐはぐな印象となってしまいました。「友情ある説得」はワイラー監督の密かなリベンジだったのかも知れませんな。
 1942年のアカデミー賞では、作品賞ほか12部門でノミネートされ、主演女優賞(ガーソン)など6部門で受賞したとのこと。
1942年のアカデミー賞では、作品賞ほか12部門でノミネートされ、主演女優賞(ガーソン)など6部門で受賞したとのこと。
グリア・ガースンと言えば、オールドファンには良妻賢母の代名詞的女優さんだったと思いますが、データでは1941年から5年連続主演オスカーにノミネートされるなど名女優さんでもあったようです。口髭に名前を残したロナルド・コールマンと共演したルロイ監督の「心の旅路(1942)」が有名ですな。
ワイラー演出は、例によってストーリーを追うだけではなく、個々のシーンでそれぞれの心の細かな動きを表す表情や動作の描き方が素晴らしく、何度も観てみたい気分にさせてくれます。
ベルハムのパブで男達が酒を飲んでいる時に、ラジオからナチスドイツの英語放送が流れていたのが印象的でした。『フランスが降伏したから、お前らも観念しろ』みたいな話。この時代のイギリス映画、もっと観たくなりましたね。
キャロルを演じたテレサ・ライトは、この映画でアカデミー助演女優賞を獲りましたが、昨年3月に86歳で亡くなりました。
封建的な精神を残したキャロルの祖母を演じたのは、デイム・メイ・ウィッティ。ヒチコックの「バルカン超特急」のミセス・フロイでした。そして、彼女に対抗して赤いバラの花を作った駅長は「素晴らしき哉、人生!」の落ちこぼれ天使ヘンリー・トラヴァースでした。
尚、この映画の日本初公開は49年5月だったようです。
何だか最近、ブログの記事も書き方がマンネリ気味で『何とかならんかいな』なんて思ったりもしてますが、なにせボキャブラリーが乏しいもんでね。例によって、いつもの調子です。ちょっと間が空いてしまったのですが、初鑑賞は1週間以上前。その後チラチラと家人が寝ているときに見直しております。
去年の大晦日に買った4枚の1コインDVDの一つ。なんとまあ、一年ぶりの鑑賞。いつでも観られると言う安心からか、オールドムーヴィー故軽んじたのか。しかしまあ、なんというか、ワイラー演出の細やかさは相変わらずウットリでありました。
ワイラー監督は12回アカデミー監督賞にノミネートされていますが、5回目にして初受賞した作品がこの「ミニヴァー夫人」です。
 第2次世界大戦の真っ最中に作られた作品で、話は1939年の英国参戦前の夏から始まります。
第2次世界大戦の真っ最中に作られた作品で、話は1939年の英国参戦前の夏から始まります。ロンドンにほど近い平和な村。建築士の父親にはオックスフォード在学中の長男ヴィンと少し年の離れた長女と幼い次男がいる。映画の解説では中流家庭となっているが、料理人はいる、メイドはいる、しかも娘にはピアノの家庭教師もいる、そんなミニヴァー家です。
美人の奥さんは時々ロンドンに買い物に行っては自分の浪費癖を後悔しているが、決してお高くとまってなくて、地元のベルハム駅の駅長バラード氏は自身が育てた赤く美しいバラに「MRS. MINIVER」と名前を付けるほど。ソレを聞いた夫人も誇らしく感じるというよりは感謝するといった具合。まるで、武者小路実篤の本のような出来過ぎの善人たちばかりだが、全く不自然さを感じさせない作品でした。
この村では毎年、元領主のペルドン家の老女が主催する花の品評会があっていて、バラ部門は主宰者の老女が優勝することになっている。村人が元領主に遠慮して誰もバラ部門にエントリーしないからだが、バラードは今年は出品するつもりらしい。それ程の傑作なのだ。
いよいよ英国も大戦に参加し、ヴィンも軍隊に入る前に大学から帰ってくる。そんな折り、ペルドン家の孫娘がミニヴァー家を訪れる。“MRS. MINIVER”の評判を聞いて、祖母を悲しませたくないためにバラード氏に出品を取り止めてもらえないかとミニヴァー家へやって来たわけだ。階級意識に批判的なヴィンはそこでキャロルと論争となるが、その夜の村のダンスパーティーで二人は仲直りをしやがて恋に落ちる。
幸せな話はこの辺りまで。やがて、村にもドイツ軍の爆撃機が飛んでくるようになり、ヴィンは空軍へ、メイドの彼氏も海軍へ入隊する。灯火管制が始まり、付近に墜落した飛行機からはドイツ兵が逃亡し、付近に潜んでいるという噂も出てくる。
一週間の予定で帰ってきたヴィンに急に召集がかかり、その上真夜中の2時にミニヴァー氏にも自家用の船と共に緊急集会が開かれる。それは、ドイツ軍に追われてフランス、ダンケルク迄撤退してきた連合軍を助けに行くという民間人をも巻き込んだ事態だった・・・。
平和な5人家族の長男が軍隊に志願し、村の人々と共に一家も戦争に巻き込まれるという話は後年の「友情ある説得(1956)」に似ています。南北戦争が舞台だった「友情・・」はヒューマニズムがテーマとして確立していましたが、コチラは戦争中のこと故、ヒューマニズムを前面に出すことは控えられたようで、戦意昂揚を押しだそうとした終盤のまとめ方が、戦争の影が全くない平和な村と幸せな一家を描いた前半に対してちぐはぐな印象となってしまいました。「友情ある説得」はワイラー監督の密かなリベンジだったのかも知れませんな。
 1942年のアカデミー賞では、作品賞ほか12部門でノミネートされ、主演女優賞(ガーソン)など6部門で受賞したとのこと。
1942年のアカデミー賞では、作品賞ほか12部門でノミネートされ、主演女優賞(ガーソン)など6部門で受賞したとのこと。グリア・ガースンと言えば、オールドファンには良妻賢母の代名詞的女優さんだったと思いますが、データでは1941年から5年連続主演オスカーにノミネートされるなど名女優さんでもあったようです。口髭に名前を残したロナルド・コールマンと共演したルロイ監督の「心の旅路(1942)」が有名ですな。
ワイラー演出は、例によってストーリーを追うだけではなく、個々のシーンでそれぞれの心の細かな動きを表す表情や動作の描き方が素晴らしく、何度も観てみたい気分にさせてくれます。
ベルハムのパブで男達が酒を飲んでいる時に、ラジオからナチスドイツの英語放送が流れていたのが印象的でした。『フランスが降伏したから、お前らも観念しろ』みたいな話。この時代のイギリス映画、もっと観たくなりましたね。
キャロルを演じたテレサ・ライトは、この映画でアカデミー助演女優賞を獲りましたが、昨年3月に86歳で亡くなりました。
封建的な精神を残したキャロルの祖母を演じたのは、デイム・メイ・ウィッティ。ヒチコックの「バルカン超特急」のミセス・フロイでした。そして、彼女に対抗して赤いバラの花を作った駅長は「素晴らしき哉、人生!」の落ちこぼれ天使ヘンリー・トラヴァースでした。
尚、この映画の日本初公開は49年5月だったようです。
・お薦め度【★★★★★=クラシックファンは、大いに見るべし!】 

(1984/ローランド・ジョフィ監督/サム・ウォーターストン、ハイン・S・ニョール、ジョン・マルコヴィッチ、ジュリアン・サンズ、クレイグ・T・ネルソン/141分)
何度観ても凄い映画である。
ドキュメンタリータッチが臨場感と緊迫感に於いて、これほど劇的な効果を生んだ例は他に記憶がない。クメール・ルージュの戦士達はほぼ100%客観的に描かれているので、まさに戦場にカメラを持ち込んで撮影したような感じ。いきなりカメラに向かって発砲するのではないかと錯覚するくらいだ。
カンボジア内戦のリポートでピューリッツア賞を受賞したアメリカ、ニューヨーク・タイムスの記者の体験を元に作られた、今から約30年前の実話であります。
 1973年8月。ベトナム戦争末期の隣国カンボジア。ここにも共産主義の勢力が力を伸ばしてきていて、やがてポルポトという狂人が支配する生き地獄が始まる頃、アメリカ人ジャーナリスト、シドニー・シャンバーグはディス・プランというカンボジア人の通訳兼ガイドと知り合う。
1973年8月。ベトナム戦争末期の隣国カンボジア。ここにも共産主義の勢力が力を伸ばしてきていて、やがてポルポトという狂人が支配する生き地獄が始まる頃、アメリカ人ジャーナリスト、シドニー・シャンバーグはディス・プランというカンボジア人の通訳兼ガイドと知り合う。
1975年4月。アメリカの支援を受けている現政府に対し、中国などに力を借りた共産勢力クメール・ルージュの攻勢は勢いを増していた。クメール・ルージュが政権を獲れば大虐殺があるとの噂が流れ、プランの家族は一足先にシドニーの計らいでアメリカ本土へ脱出する。プランはシドニーと共に取材活動を続けるが、首都プノンペンが陥落、僅かに残った外国人はフランス領事館に逃げ込む。プラン達カンボジア人にはタイへ国境を越える手があったが、パスポートを偽造することにより、プランはシドニー達と共に脱出出来るはずだった・・・。
パスポートがおりなかったプランは領事館を出ていき、シドニーと別れわかれになる。ココまでの上映時間約85分。この後の1時間弱でポルポト政権の異常な姿が露わになっていき、映画的にはプランの脱出劇がサスペンスフルに描かれる。
クメール・ルージュが支配するカンボジアの状況は悲惨きわまりない。十数年前、この映画を初めて観た後ネットで色々とポルポトについて調べたが、まさにカルト、極めて異常な共産原理主義者であります。映画とは直接関係ないのでこれ以上は書きませんが、映画でも子供が大人達を監視し、更には無慈悲にも殺していくシーンもあり、プランの置かれた情況の切迫さを感じさせるものとなっておりました。
あの時、大人を殺害した子供たちも現在生きているんでしょうが、あの子達がどうなっているか興味はありますな。
一部の映画ファンには、この映画はシドニーとプランとの友情物語として捉えられている。それも一つの側面だが、「ミッドナイト・エクスプレス(1978)」の製作者がそんなものの為だけに作るわけはなく、デヴィッド・パットナムの主題は人間の狂気や愚かさや暴力がどれだけ惨たらしい結果を招くかということにある。表向きにはオスカーを獲った「炎のランナー(1981)」がプロデューサーとしての代表作だろうが、個人的にはコチラの方が質も高いしスケールも大きい作品だと思っている。
1984年のアカデミー賞では、プラン役のハイン・S・ニョールが助演男優賞を受賞した他、撮影賞(クリス・メンゲス)、編集賞(ジム・クラーク)も受賞した。又、作品賞、主演男優賞(ウォーターストン)、監督賞、脚色賞(ブルース・ロビンソン)にもノミネートされた。
本人もカンボジアからの亡命者だというニョールの演技は鬼気迫るものがある。産婦人科医であった彼もプランと同じように知的労働者であることを隠し続け、4年もの間強制労働と拷問に耐えてきたとのことである。その間に妻と子供を亡くし、79年にタイに脱出、80年にアメリカに移住している。
これも既にご承知のことだろうが、96年ロサンゼルスの自宅で強盗により殺害されたとのことであります。
これがデビュー作のローランド・ジョフィの演出は迫力満点。再びパットナムと組んだ「ミッション(1986)」もカンヌ映画祭のグランプリを受賞したとのこと。寡作ですが、優れた作家のようであります。
▼(ネタバレ注意)
中盤以降はアメリカに無事亡命したプランの家族やプランの安否を探ろうとしているシドニーの活動も描かれ、脱出劇にシドニー側の状況を挿入したことでサスペンスが単調になるのが防げただろうし、ラストの再会シーンの感動にも繋がっている。上手い構成だった。
尚、二人の再会は79年10月。
タイの難民キャンプにシドニーが訪れての再会だった。ご存じ、ジョン・レノンの「♪イマジン」が流れるこのシーン、今回も涙してしまいました。
▲(解除)
何度観ても凄い映画である。
ドキュメンタリータッチが臨場感と緊迫感に於いて、これほど劇的な効果を生んだ例は他に記憶がない。クメール・ルージュの戦士達はほぼ100%客観的に描かれているので、まさに戦場にカメラを持ち込んで撮影したような感じ。いきなりカメラに向かって発砲するのではないかと錯覚するくらいだ。
カンボジア内戦のリポートでピューリッツア賞を受賞したアメリカ、ニューヨーク・タイムスの記者の体験を元に作られた、今から約30年前の実話であります。
*
 1973年8月。ベトナム戦争末期の隣国カンボジア。ここにも共産主義の勢力が力を伸ばしてきていて、やがてポルポトという狂人が支配する生き地獄が始まる頃、アメリカ人ジャーナリスト、シドニー・シャンバーグはディス・プランというカンボジア人の通訳兼ガイドと知り合う。
1973年8月。ベトナム戦争末期の隣国カンボジア。ここにも共産主義の勢力が力を伸ばしてきていて、やがてポルポトという狂人が支配する生き地獄が始まる頃、アメリカ人ジャーナリスト、シドニー・シャンバーグはディス・プランというカンボジア人の通訳兼ガイドと知り合う。1975年4月。アメリカの支援を受けている現政府に対し、中国などに力を借りた共産勢力クメール・ルージュの攻勢は勢いを増していた。クメール・ルージュが政権を獲れば大虐殺があるとの噂が流れ、プランの家族は一足先にシドニーの計らいでアメリカ本土へ脱出する。プランはシドニーと共に取材活動を続けるが、首都プノンペンが陥落、僅かに残った外国人はフランス領事館に逃げ込む。プラン達カンボジア人にはタイへ国境を越える手があったが、パスポートを偽造することにより、プランはシドニー達と共に脱出出来るはずだった・・・。
パスポートがおりなかったプランは領事館を出ていき、シドニーと別れわかれになる。ココまでの上映時間約85分。この後の1時間弱でポルポト政権の異常な姿が露わになっていき、映画的にはプランの脱出劇がサスペンスフルに描かれる。
クメール・ルージュが支配するカンボジアの状況は悲惨きわまりない。十数年前、この映画を初めて観た後ネットで色々とポルポトについて調べたが、まさにカルト、極めて異常な共産原理主義者であります。映画とは直接関係ないのでこれ以上は書きませんが、映画でも子供が大人達を監視し、更には無慈悲にも殺していくシーンもあり、プランの置かれた情況の切迫さを感じさせるものとなっておりました。
あの時、大人を殺害した子供たちも現在生きているんでしょうが、あの子達がどうなっているか興味はありますな。
一部の映画ファンには、この映画はシドニーとプランとの友情物語として捉えられている。それも一つの側面だが、「ミッドナイト・エクスプレス(1978)」の製作者がそんなものの為だけに作るわけはなく、デヴィッド・パットナムの主題は人間の狂気や愚かさや暴力がどれだけ惨たらしい結果を招くかということにある。表向きにはオスカーを獲った「炎のランナー(1981)」がプロデューサーとしての代表作だろうが、個人的にはコチラの方が質も高いしスケールも大きい作品だと思っている。
1984年のアカデミー賞では、プラン役のハイン・S・ニョールが助演男優賞を受賞した他、撮影賞(クリス・メンゲス)、編集賞(ジム・クラーク)も受賞した。又、作品賞、主演男優賞(ウォーターストン)、監督賞、脚色賞(ブルース・ロビンソン)にもノミネートされた。
本人もカンボジアからの亡命者だというニョールの演技は鬼気迫るものがある。産婦人科医であった彼もプランと同じように知的労働者であることを隠し続け、4年もの間強制労働と拷問に耐えてきたとのことである。その間に妻と子供を亡くし、79年にタイに脱出、80年にアメリカに移住している。
これも既にご承知のことだろうが、96年ロサンゼルスの自宅で強盗により殺害されたとのことであります。
これがデビュー作のローランド・ジョフィの演出は迫力満点。再びパットナムと組んだ「ミッション(1986)」もカンヌ映画祭のグランプリを受賞したとのこと。寡作ですが、優れた作家のようであります。
▼(ネタバレ注意)
中盤以降はアメリカに無事亡命したプランの家族やプランの安否を探ろうとしているシドニーの活動も描かれ、脱出劇にシドニー側の状況を挿入したことでサスペンスが単調になるのが防げただろうし、ラストの再会シーンの感動にも繋がっている。上手い構成だった。
尚、二人の再会は79年10月。
タイの難民キャンプにシドニーが訪れての再会だった。ご存じ、ジョン・レノンの「♪イマジン」が流れるこのシーン、今回も涙してしまいました。
▲(解除)
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】 

(1980/グェン・ホン・セン監督/グェン・トゥイ・アン、ラム・トイ/95分)
NHK衛星映画劇場での放送。
ベトナム映画は珍しいし、モスクワ映画祭金賞受賞作との事だったので録画して観た。予算の関係でしょうか、モノクロです。
ベトナム戦争時の対アメリカ戦をベトナム側から描いたもので、NHKのBSオンラインの説明はこうです。
<ベトナム戦争末期、戦地となった村でひっそりと暮らす若夫婦の愛情に満ちた生活が踏みにじられる様を通して、戦争の残酷さを静かに訴える感動作。ベトナム解放軍同士の連絡を断たせるため、アメリカ軍は南ベトナムのデルタ地帯のとある地区を無人にする作戦に出た。村人たちがすべて強制収容される中、解放軍の連絡員を努める一組の夫婦が幼い子供とともに残るが、やがてアメリカ軍に見つかり…。>
<村人たちがすべて強制収容される中・・・>とあるけれども、普通の村人は出てきません。出てくるベトナム人は全てゲリラ活動をしている人間で、強制収容されるシーンもありません。
若夫婦はメコンデルタの川面の上に枯れ木や草を集めて作ったような家で暮らしていて、半分水に浸かっているような水田ではお米も作っている。赤ん坊も一緒にいるから、あれは戦争前からそのようにして生活していたのでしょう。
赤ん坊を抱える若夫婦と彼らの置かれた状況を説明する前半はそれなりに観られたけど、後半の展開はモタモタしていたり、途中を端折ったようなシーンもあり、興ざめしてきた。それよりも、アメリカ軍側で出てくる人間が限られていて(ベトナム語をしゃべっているし)、まるで一昔前のマカロニ・ウェスタンの悪役のような描き方だったので笑ってしまいました。
作劇としても映像的な演出も同時代に観た欧米の映画とは比べものにならないものです。アジアでも、インドにはサタジット・レイという才人がいましたがね。
80年の作品だから、ソヴィエトの政治的な意図も有ってのモスクワ映画祭金賞受賞かもしれません。
ただ、アメリカ軍のヘリコプターが出てきて、若夫婦が川の中を歩いて逃げたり、草むらに隠れたりするシーンは、ドキュメンタリーを観ているような迫力がありました。いよいよ家が爆撃されるかも知れないという時には、赤ん坊も連れて逃げ、見つかりそうになる時には、赤ん坊をビニール袋にすっぽり入れて一緒に川の中に潜ったりする。
当時の報道写真を彷彿とさせるような画で、まるで、ベトナム版「地下水道」のようだと思いましたな。
ラストは、旦那さんの方がヘリコプターからの銃弾に倒れ、奥さんが旦那の銃で応戦。見事仇を討ち、ここに雄々しい女性戦士が生まれましたとさ・・・てな具合でした。
NHK衛星映画劇場での放送。
ベトナム映画は珍しいし、モスクワ映画祭金賞受賞作との事だったので録画して観た。予算の関係でしょうか、モノクロです。
ベトナム戦争時の対アメリカ戦をベトナム側から描いたもので、NHKのBSオンラインの説明はこうです。
<ベトナム戦争末期、戦地となった村でひっそりと暮らす若夫婦の愛情に満ちた生活が踏みにじられる様を通して、戦争の残酷さを静かに訴える感動作。ベトナム解放軍同士の連絡を断たせるため、アメリカ軍は南ベトナムのデルタ地帯のとある地区を無人にする作戦に出た。村人たちがすべて強制収容される中、解放軍の連絡員を努める一組の夫婦が幼い子供とともに残るが、やがてアメリカ軍に見つかり…。>
<村人たちがすべて強制収容される中・・・>とあるけれども、普通の村人は出てきません。出てくるベトナム人は全てゲリラ活動をしている人間で、強制収容されるシーンもありません。
若夫婦はメコンデルタの川面の上に枯れ木や草を集めて作ったような家で暮らしていて、半分水に浸かっているような水田ではお米も作っている。赤ん坊も一緒にいるから、あれは戦争前からそのようにして生活していたのでしょう。
赤ん坊を抱える若夫婦と彼らの置かれた状況を説明する前半はそれなりに観られたけど、後半の展開はモタモタしていたり、途中を端折ったようなシーンもあり、興ざめしてきた。それよりも、アメリカ軍側で出てくる人間が限られていて(ベトナム語をしゃべっているし)、まるで一昔前のマカロニ・ウェスタンの悪役のような描き方だったので笑ってしまいました。
作劇としても映像的な演出も同時代に観た欧米の映画とは比べものにならないものです。アジアでも、インドにはサタジット・レイという才人がいましたがね。
80年の作品だから、ソヴィエトの政治的な意図も有ってのモスクワ映画祭金賞受賞かもしれません。
ただ、アメリカ軍のヘリコプターが出てきて、若夫婦が川の中を歩いて逃げたり、草むらに隠れたりするシーンは、ドキュメンタリーを観ているような迫力がありました。いよいよ家が爆撃されるかも知れないという時には、赤ん坊も連れて逃げ、見つかりそうになる時には、赤ん坊をビニール袋にすっぽり入れて一緒に川の中に潜ったりする。
当時の報道写真を彷彿とさせるような画で、まるで、ベトナム版「地下水道」のようだと思いましたな。
ラストは、旦那さんの方がヘリコプターからの銃弾に倒れ、奥さんが旦那の銃で応戦。見事仇を討ち、ここに雄々しい女性戦士が生まれましたとさ・・・てな具合でした。
・お薦め度【★=お薦めしません】 

(1957/アンジェイ・ワイダ監督・共同脚本/ズビグニエフ・チブルスキー、エヴァ・クジジェフスカ、バクラフ・ザストルジンスキー/102分)
前回のチェコに続いて東欧の作品。チェコの隣国ポーランドの半世紀前のモノクロ映画。ワイダ監督の戦争三部作の3作目で彼の最高傑作といわれている。
子供の時に観たが殆ど忘れている。というか、子供の時には理解できなかっただろうし、今回も製作者の意図が分かったとはとても言えない。
同じように若くして事故死した事もあって、“ポーランドのジェームズ・ディーン”といわれた、ズビグニエフ・チブルスキーが若きテロリストに扮し、ラストシーンでは、虫けらのようにゴミ集積場で死んでいく。いつもかけているサングラスがニヒルな感じで、青春映画のように扱われたこともあったらしいが、中身はそんな甘っちょろいもんではない。
とても政治的な色彩が濃い映画だ。
主人公のマチェクが政治テロリストというだけでなく、地方都市の市長の秘書がテロリストを使っていたり、政治家同士の駆け引きのようなものも背景にあるようなので、ポーランドの歴史に疎い者にはちょっと分かりにくい。
更には、数年ぶりにソ連から帰ってきた東寄りの政治家(暗殺のターゲット)には息子が居るんだが、父親が居ない間に亡くなった奥さんの姉夫婦が育てていて、なんとこの姉夫婦が西側に協力的な人間だという、まことに色々な人物が複雑に絡まっている話なのだ。
そしてそして、暗殺の指令をだしていたのは、この義理の姉の旦那だったのだから、ややこしい。
 映画の冒頭でドイツ軍が全面降伏したニュースが流れる、時はまさに、第二次世界大戦の終戦直後。ポーランド国内には、戦中から西側にシンパシーを感じる一派と、ソヴィエトに追随しようとする一派とのつばぜり合いがあっていたようで、マチェクは西側一派に所属するテロリスト。映画は、ソヴィエト帰りのある大物政治家を暗殺するところから始まる。
映画の冒頭でドイツ軍が全面降伏したニュースが流れる、時はまさに、第二次世界大戦の終戦直後。ポーランド国内には、戦中から西側にシンパシーを感じる一派と、ソヴィエトに追随しようとする一派とのつばぜり合いがあっていたようで、マチェクは西側一派に所属するテロリスト。映画は、ソヴィエト帰りのある大物政治家を暗殺するところから始まる。
手引きしたのがその地の市長の秘書で、ところが、秘書が指示した相手はソ連帰りの一般労働者だった。暗殺成功の報告をしようと仲間と一緒にホテルに戻った所へ、本当のターゲットがチェックインに来て人違いに気付く。
テロリストの多くは元々ワルシャワ蜂起からのレジスタンス活動をしてきた仲間であり、母国の自由のためにテロを行ってきたわけだが、ドイツ軍が降伏し、戦争が終わったということで、マチェクは暗殺の必要性に疑問を持つ。暗殺が未遂であったために、とりあえずターゲットと同じホテルに宿泊し次の機会を待つことにする。ホテルのバーで働く美女と束の間の愛を交わす内に、新しい生活への望みも持ち始めるのだが・・・・。
な~んて、書いてはみましたが、実のところよく分かってないと思います。市長の秘書と暗殺の指令を出した人物との関係も掴み切れてないし、市長がこの後中央政界に進出が決まっているらしいのに、秘書が自暴自棄になっているのもよく分からない。ドイツ軍が降伏して戦争は終わったのに、どの人々もあんまり嬉しそうでないのも、この国の複雑な歴史が関係しているんでしょうけどねぇ。
映画としては、人間を絞ってもっと分かり易い話に組み立て直した方がよかったのでは、と思いましたな。見終わればマチェクが主人公の話だと分かるが、鑑賞中は群像劇を観ているようでした。多分、色々な事を言いたかったんでしょうがネ。
意図的な演出が随所に見られ、神に絡ませた象徴的なシーンもある。無信心な私には意味不明なシーン(突然出てくる白い馬)もあるし、チブルスキーの演技も昔の邦画を思い出させるようにややオーバーアクト気味。
さて、「大理石の男(1977)」も録画してるんだが、ソレをみれば少しは理解できるかな?
<追記>
他の方々の記事を読んでいる内に少しづつ疑問が解けてきたようです。
市長の秘書の件。
彼は反ソ派に加担しているが、市長は終戦後中央政界に出ることが決まっている。その頃は、ポーランドが共産主義国家になることは既定路線となっていたようで、反ソ連の立場である彼がヤケになるのはそういう事情だったのだろう。
マチェクが暗殺に消極的になっていったのは、国家の共産化が避けようがなかったことと、戦時下ではある意味正当化された殺人が、終戦後は単なる犯罪になってしまうのが分かったからではないか。
いずれにしても、この映画の登場人物の心情を理解するのは、なかなか難しい。
前回のチェコに続いて東欧の作品。チェコの隣国ポーランドの半世紀前のモノクロ映画。ワイダ監督の戦争三部作の3作目で彼の最高傑作といわれている。
子供の時に観たが殆ど忘れている。というか、子供の時には理解できなかっただろうし、今回も製作者の意図が分かったとはとても言えない。
同じように若くして事故死した事もあって、“ポーランドのジェームズ・ディーン”といわれた、ズビグニエフ・チブルスキーが若きテロリストに扮し、ラストシーンでは、虫けらのようにゴミ集積場で死んでいく。いつもかけているサングラスがニヒルな感じで、青春映画のように扱われたこともあったらしいが、中身はそんな甘っちょろいもんではない。
とても政治的な色彩が濃い映画だ。
主人公のマチェクが政治テロリストというだけでなく、地方都市の市長の秘書がテロリストを使っていたり、政治家同士の駆け引きのようなものも背景にあるようなので、ポーランドの歴史に疎い者にはちょっと分かりにくい。
更には、数年ぶりにソ連から帰ってきた東寄りの政治家(暗殺のターゲット)には息子が居るんだが、父親が居ない間に亡くなった奥さんの姉夫婦が育てていて、なんとこの姉夫婦が西側に協力的な人間だという、まことに色々な人物が複雑に絡まっている話なのだ。
そしてそして、暗殺の指令をだしていたのは、この義理の姉の旦那だったのだから、ややこしい。
 映画の冒頭でドイツ軍が全面降伏したニュースが流れる、時はまさに、第二次世界大戦の終戦直後。ポーランド国内には、戦中から西側にシンパシーを感じる一派と、ソヴィエトに追随しようとする一派とのつばぜり合いがあっていたようで、マチェクは西側一派に所属するテロリスト。映画は、ソヴィエト帰りのある大物政治家を暗殺するところから始まる。
映画の冒頭でドイツ軍が全面降伏したニュースが流れる、時はまさに、第二次世界大戦の終戦直後。ポーランド国内には、戦中から西側にシンパシーを感じる一派と、ソヴィエトに追随しようとする一派とのつばぜり合いがあっていたようで、マチェクは西側一派に所属するテロリスト。映画は、ソヴィエト帰りのある大物政治家を暗殺するところから始まる。手引きしたのがその地の市長の秘書で、ところが、秘書が指示した相手はソ連帰りの一般労働者だった。暗殺成功の報告をしようと仲間と一緒にホテルに戻った所へ、本当のターゲットがチェックインに来て人違いに気付く。
テロリストの多くは元々ワルシャワ蜂起からのレジスタンス活動をしてきた仲間であり、母国の自由のためにテロを行ってきたわけだが、ドイツ軍が降伏し、戦争が終わったということで、マチェクは暗殺の必要性に疑問を持つ。暗殺が未遂であったために、とりあえずターゲットと同じホテルに宿泊し次の機会を待つことにする。ホテルのバーで働く美女と束の間の愛を交わす内に、新しい生活への望みも持ち始めるのだが・・・・。
な~んて、書いてはみましたが、実のところよく分かってないと思います。市長の秘書と暗殺の指令を出した人物との関係も掴み切れてないし、市長がこの後中央政界に進出が決まっているらしいのに、秘書が自暴自棄になっているのもよく分からない。ドイツ軍が降伏して戦争は終わったのに、どの人々もあんまり嬉しそうでないのも、この国の複雑な歴史が関係しているんでしょうけどねぇ。
映画としては、人間を絞ってもっと分かり易い話に組み立て直した方がよかったのでは、と思いましたな。見終わればマチェクが主人公の話だと分かるが、鑑賞中は群像劇を観ているようでした。多分、色々な事を言いたかったんでしょうがネ。
意図的な演出が随所に見られ、神に絡ませた象徴的なシーンもある。無信心な私には意味不明なシーン(突然出てくる白い馬)もあるし、チブルスキーの演技も昔の邦画を思い出させるようにややオーバーアクト気味。
さて、「大理石の男(1977)」も録画してるんだが、ソレをみれば少しは理解できるかな?
<追記>
他の方々の記事を読んでいる内に少しづつ疑問が解けてきたようです。
市長の秘書の件。
彼は反ソ派に加担しているが、市長は終戦後中央政界に出ることが決まっている。その頃は、ポーランドが共産主義国家になることは既定路線となっていたようで、反ソ連の立場である彼がヤケになるのはそういう事情だったのだろう。
マチェクが暗殺に消極的になっていったのは、国家の共産化が避けようがなかったことと、戦時下ではある意味正当化された殺人が、終戦後は単なる犯罪になってしまうのが分かったからではないか。
いずれにしても、この映画の登場人物の心情を理解するのは、なかなか難しい。
・お薦め度【★★★=一度は見ましょう、ワイダだから】 

(1930/ルイス・マイルストン監督/リュー・エアーズ、ウィリアム・ベイクウェル、ラッセル・グリーソン、ルイス・ウォルハイム、スリム・サマーヴィル、ジョン・レイ、ウォルター・ブラウン・ロジャース、レイモンド・グリフィス、ベリル・マーサー/130分)
ずっと前からタイトルは知っていて、「オーシャンと11人の仲間(1960)」のルイス・マイルストン監督の作品としても気になっていた映画。75年前の作品だが、DVDが出ていたのでレンタルしてみた。最初の方は“雨が降っていて”デジタル・リマスターはされていなかったようだ。
「allcinema ONLINE」のデータでは100分の上映時間となっていたが、観たのは2時間10分くらいあった。【原題:ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT 】
 第一次世界大戦が舞台で、原作がエリッヒ・マリア・レマルク。そう、主人公はドイツの若者だ。学校の先生や周囲の大人にけしかけられて、お国のためにと軍に志願するも、戦争の悲惨さにうろたえ、傷つき、死んでいく若者たちが描かれている。
第一次世界大戦が舞台で、原作がエリッヒ・マリア・レマルク。そう、主人公はドイツの若者だ。学校の先生や周囲の大人にけしかけられて、お国のためにと軍に志願するも、戦争の悲惨さにうろたえ、傷つき、死んでいく若者たちが描かれている。
前半の若者達が味わう軍の非人間的な扱いを受けるシーンでは、昔観たTVドラマ、五味川純平の「人間の条件」を思い出した。
冒頭で生徒達に軍隊への志願をけしかける先生は、まさしくヒトラーを彷彿とさせる。ナチス党首のヒトラーが首相になったのは1933年で、この作品の後になるのだけど、すでにナチスは世界の脅威となっていたのでしょうか。
学生達が志願して行った軍隊の訓練所には、彼等の町で郵便配達をしていた男が訓練の指揮官となっている。顔なじみの大人を見つけて親しそうに話しかけるが、かつての郵便配達員は「愛と青春の旅だち(1982)」の指揮官のように厳しい。が、中身はあの鬼軍曹とは大違いで、いわゆる戦争バカのような男。20歳前の若者にイジメのような訓練を押しつけ、楽しんでいる。
後半、戦況がドイツ軍に危うくなってからは、このバカが前線にやって来るんだが、案の定戦闘が始まった途端に怖じ気づく。このキャラクターは面白いアクセントとなりました。
前半の戦闘シーンは75年前とは思えないほどの迫力で、まるでドキュメンタリーのような描写。「プライベート・ライアン」にも負けていません。突撃してきた兵隊が爆撃を受け、一瞬にして鉄条網にぶら下がった両手以外はどこかに消えてしまうシーンには驚きました。
原作はとても長い小説だそうで、3人の共作による脚本も後半はまとめ切らなかったのか、ちょっと散漫になったと感じました。「allcinema ONLINE」のデータにある100分の作品が存在するのなら、そちらの方が面白かったでしょう。
あまりに古くて、出演者は全然知らない人ばかり。後半、スポットライトが当たる若者はヘアスタイルもカッコよく、現在でもいそうな青年でした。
▼(ネタバレ注意)
彼が最後に戦死するシーンはとても有名ですな。塹壕から目の前にいる蝶々を見つけ、それに手を伸ばそうとして狙撃される。
▲(解除)
アカデミー賞の作品賞と監督賞をとり、脚本賞(マックスウェル・アンダーソン、デル・アンドリュース、ジョージ・アボット)と撮影賞(アーサー・エディソン)にもノミネートされたらしい。
データを調べていて気付いたこと。
レマルクの奥さんが、チャップリンの奥さんでもあったポーレット・ゴダード(「モダン・タイムス(1936)」)だったこと。
そして、マイルストンがロシア出身だったこと。アカデミー賞というのは、映画人の“出身”には拘らないんですなぁ・・・。
ずっと前からタイトルは知っていて、「オーシャンと11人の仲間(1960)」のルイス・マイルストン監督の作品としても気になっていた映画。75年前の作品だが、DVDが出ていたのでレンタルしてみた。最初の方は“雨が降っていて”デジタル・リマスターはされていなかったようだ。
「allcinema ONLINE」のデータでは100分の上映時間となっていたが、観たのは2時間10分くらいあった。【原題:ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT 】
 第一次世界大戦が舞台で、原作がエリッヒ・マリア・レマルク。そう、主人公はドイツの若者だ。学校の先生や周囲の大人にけしかけられて、お国のためにと軍に志願するも、戦争の悲惨さにうろたえ、傷つき、死んでいく若者たちが描かれている。
第一次世界大戦が舞台で、原作がエリッヒ・マリア・レマルク。そう、主人公はドイツの若者だ。学校の先生や周囲の大人にけしかけられて、お国のためにと軍に志願するも、戦争の悲惨さにうろたえ、傷つき、死んでいく若者たちが描かれている。前半の若者達が味わう軍の非人間的な扱いを受けるシーンでは、昔観たTVドラマ、五味川純平の「人間の条件」を思い出した。
冒頭で生徒達に軍隊への志願をけしかける先生は、まさしくヒトラーを彷彿とさせる。ナチス党首のヒトラーが首相になったのは1933年で、この作品の後になるのだけど、すでにナチスは世界の脅威となっていたのでしょうか。
学生達が志願して行った軍隊の訓練所には、彼等の町で郵便配達をしていた男が訓練の指揮官となっている。顔なじみの大人を見つけて親しそうに話しかけるが、かつての郵便配達員は「愛と青春の旅だち(1982)」の指揮官のように厳しい。が、中身はあの鬼軍曹とは大違いで、いわゆる戦争バカのような男。20歳前の若者にイジメのような訓練を押しつけ、楽しんでいる。
後半、戦況がドイツ軍に危うくなってからは、このバカが前線にやって来るんだが、案の定戦闘が始まった途端に怖じ気づく。このキャラクターは面白いアクセントとなりました。
前半の戦闘シーンは75年前とは思えないほどの迫力で、まるでドキュメンタリーのような描写。「プライベート・ライアン」にも負けていません。突撃してきた兵隊が爆撃を受け、一瞬にして鉄条網にぶら下がった両手以外はどこかに消えてしまうシーンには驚きました。
原作はとても長い小説だそうで、3人の共作による脚本も後半はまとめ切らなかったのか、ちょっと散漫になったと感じました。「allcinema ONLINE」のデータにある100分の作品が存在するのなら、そちらの方が面白かったでしょう。
あまりに古くて、出演者は全然知らない人ばかり。後半、スポットライトが当たる若者はヘアスタイルもカッコよく、現在でもいそうな青年でした。
▼(ネタバレ注意)
彼が最後に戦死するシーンはとても有名ですな。塹壕から目の前にいる蝶々を見つけ、それに手を伸ばそうとして狙撃される。
▲(解除)
アカデミー賞の作品賞と監督賞をとり、脚本賞(マックスウェル・アンダーソン、デル・アンドリュース、ジョージ・アボット)と撮影賞(アーサー・エディソン)にもノミネートされたらしい。
データを調べていて気付いたこと。
レマルクの奥さんが、チャップリンの奥さんでもあったポーレット・ゴダード(「モダン・タイムス(1936)」)だったこと。
そして、マイルストンがロシア出身だったこと。アカデミー賞というのは、映画人の“出身”には拘らないんですなぁ・・・。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 

(1951/ルネ・クレマン監督/ブリジット・フォッセー、ジョルジュ・プージュリー、シュザンヌ・クールタル、ジャック・マラン/87分)
フランス映画を語るときに、この作品を外すわけにはいきません。
一般に反戦映画と云われていますが、そのつもりで観たン十年前。確かに哀しいラストではありますが、それまでのストーリーは、少年ミシェルの子供時代の楽しかった思い出話の感覚で観れるので、“微笑ましい映画”との印象が強かったです。初恋話ではないけれど、突然現れた可愛い少女との束の間の生活は、ミシェルの心に楽しい思い出を残したのではないか。そんな風に捉えていたのですが・・・。
DVDが出ていたので久しぶりに観てみました。87分という短尺で、アッという間に終わってしまいました。
前回の印象は薄らいで、“禁じられた遊び”にのめり込んでいった子供たちを客観的に見ることが出来ました。光り輝くようなモノクロ画面ののどかな田園風景にサイレントの匂いをも感じましたね。役者の動きもそう。前回も感じましたが、ミシェルのドレ家とお隣さん(グアール家)とのいがみ合いはコミカルで牧歌的でさえある。その辺の設定もサイレント映画みたいでした。
出だしの疎開風景やドイツ軍の空襲シーンには、ドキュメンタリーを撮っていたルネ・クレマンらしいタッチがみられました。全体の雰囲気も、時々流れるギターのBGMだけの映像詩のようであります。
 1940年のフランスの田舎道。ドイツ軍の攻撃から逃れる為に、人や車、馬車などの長蛇の列が続いている。ポーレットも両親と一緒に車で移動していたが、そんな民間人の列にもドイツ軍の爆撃機は容赦なく爆弾を落とし、機銃掃射をくわえていた。
1940年のフランスの田舎道。ドイツ軍の攻撃から逃れる為に、人や車、馬車などの長蛇の列が続いている。ポーレットも両親と一緒に車で移動していたが、そんな民間人の列にもドイツ軍の爆撃機は容赦なく爆弾を落とし、機銃掃射をくわえていた。
飛び出した愛犬を追いかけていくポーレットを捕まえようとした両親は、背中を撃たれてあえなく死んでしまう。わずか4、5歳のポーレットには両親の死の意味が分からない。馬車で移動中の老夫婦が彼女を乗せてくれるが、小犬は死んでいるからと川に捨てられてしまう。先を急ぐ人々でごったがえす中、ポーレットは馬車を降り、流れていく小犬の死骸を追って河原を走る。
愛犬を拾うことが出来たポーレットをミシェルが見つける。ミシェルはこの近くの農家、ドレ家の末っ子坊主だ。ポーレットが先程の空爆で親を亡くした少女であることを理解したミシェルは、家に連れていく。
ドレ家では長男が大怪我をしたばかりだった。空爆で主人をなくした馬車が畑にやって来て、それを制しようとして馬に蹴られたのだ。医者は、空爆による傷病者の治療に出かけていて村には不在だった。
ミシェルとポーレットは小犬の埋葬をする。ポーレットはお墓には十字架を立てるということを教えてもらう。小犬が一人では可哀想だとモグラや虫の死体を集めて近くに埋葬しようと思う。そこは、二人だけの秘密の場所だった・・・。
▼(ネタバレ注意)
数日後、ミシェルの兄が亡くなる。
その葬式の日、墓地でたくさんの十字架をみたポーレットは、ミシェルにそれを欲しがる。いけないこととは知りながら、ポーレット可愛さに夜中に墓地へ行って十字架を盗むミシェル。大人が気付かないわけはない。司祭にミシェルの仕業だと教えられた父親は、ミシェルに盗んだ十字架の使い道を聞きだそうとするが、ミシェルはしゃべらない。14本も盗んでいたので、弁償するのも大変だ。次の日、警察がやって来る。ミシェルの父親はミシェルを見つけて十字架の場所を聞き出そうとするが、警察は実は、ポーレットを孤児院へ連れていこうと迎えに来ただけだった。
“お墓作り”が“禁じられた遊び”というわけだ。十字架を盗むことも勿論いけないことだから“禁じられ”ているが、としわもいかない小さな子供のすることだから、悪意はない。ポーレットは無意識のうちにパパとママのお墓作りをしていたのではないか。見終わってふとそんなことを考えましたな。
ラストシーンの切なさ。“微笑ましい映画”との印象が強かった前回はそれ程感じなかったのですが、今回はウルッとしてしまいました。戦争に翻弄されたいたいけな少女の話であることを思い知らされました。
▲(解除)
ポーレットを演じた天才少女ブリジット・フォッセーは、46年生まれだから当時5歳くらい。演技を感じさせない自然な表情が素晴らしい。15年後、「さすらいの青春(1966)」でカムバックしたのは雑誌で読んで知っていたが、この映画は観なかった。青春メロドラマとのこと。スチール写真では、現代劇ではない、ちょっと旧めの衣装を着ていたように記憶している。
ミシェルのジョルジュ・プージュリーは、「死刑台のエレベーター(1957)」に出ていた。犯人モーリス・ロネの車を盗む若いカップルの役だった。ン? ここでも盗みをやっていたのか。2000年に亡くなっていた。
『愛のロマンス』という、オープニングのタイトル・バックから流れているナルシソ・イエペスのギターは有名ですな。昔は、ギターを覚えたての頃は、誰もが一度は弾いていました。
・「禁じられた遊び」で気になった小ネタ
フランス映画を語るときに、この作品を外すわけにはいきません。
一般に反戦映画と云われていますが、そのつもりで観たン十年前。確かに哀しいラストではありますが、それまでのストーリーは、少年ミシェルの子供時代の楽しかった思い出話の感覚で観れるので、“微笑ましい映画”との印象が強かったです。初恋話ではないけれど、突然現れた可愛い少女との束の間の生活は、ミシェルの心に楽しい思い出を残したのではないか。そんな風に捉えていたのですが・・・。
DVDが出ていたので久しぶりに観てみました。87分という短尺で、アッという間に終わってしまいました。
前回の印象は薄らいで、“禁じられた遊び”にのめり込んでいった子供たちを客観的に見ることが出来ました。光り輝くようなモノクロ画面ののどかな田園風景にサイレントの匂いをも感じましたね。役者の動きもそう。前回も感じましたが、ミシェルのドレ家とお隣さん(グアール家)とのいがみ合いはコミカルで牧歌的でさえある。その辺の設定もサイレント映画みたいでした。
出だしの疎開風景やドイツ軍の空襲シーンには、ドキュメンタリーを撮っていたルネ・クレマンらしいタッチがみられました。全体の雰囲気も、時々流れるギターのBGMだけの映像詩のようであります。
*
 1940年のフランスの田舎道。ドイツ軍の攻撃から逃れる為に、人や車、馬車などの長蛇の列が続いている。ポーレットも両親と一緒に車で移動していたが、そんな民間人の列にもドイツ軍の爆撃機は容赦なく爆弾を落とし、機銃掃射をくわえていた。
1940年のフランスの田舎道。ドイツ軍の攻撃から逃れる為に、人や車、馬車などの長蛇の列が続いている。ポーレットも両親と一緒に車で移動していたが、そんな民間人の列にもドイツ軍の爆撃機は容赦なく爆弾を落とし、機銃掃射をくわえていた。飛び出した愛犬を追いかけていくポーレットを捕まえようとした両親は、背中を撃たれてあえなく死んでしまう。わずか4、5歳のポーレットには両親の死の意味が分からない。馬車で移動中の老夫婦が彼女を乗せてくれるが、小犬は死んでいるからと川に捨てられてしまう。先を急ぐ人々でごったがえす中、ポーレットは馬車を降り、流れていく小犬の死骸を追って河原を走る。
愛犬を拾うことが出来たポーレットをミシェルが見つける。ミシェルはこの近くの農家、ドレ家の末っ子坊主だ。ポーレットが先程の空爆で親を亡くした少女であることを理解したミシェルは、家に連れていく。
ドレ家では長男が大怪我をしたばかりだった。空爆で主人をなくした馬車が畑にやって来て、それを制しようとして馬に蹴られたのだ。医者は、空爆による傷病者の治療に出かけていて村には不在だった。
ミシェルとポーレットは小犬の埋葬をする。ポーレットはお墓には十字架を立てるということを教えてもらう。小犬が一人では可哀想だとモグラや虫の死体を集めて近くに埋葬しようと思う。そこは、二人だけの秘密の場所だった・・・。
▼(ネタバレ注意)
数日後、ミシェルの兄が亡くなる。
その葬式の日、墓地でたくさんの十字架をみたポーレットは、ミシェルにそれを欲しがる。いけないこととは知りながら、ポーレット可愛さに夜中に墓地へ行って十字架を盗むミシェル。大人が気付かないわけはない。司祭にミシェルの仕業だと教えられた父親は、ミシェルに盗んだ十字架の使い道を聞きだそうとするが、ミシェルはしゃべらない。14本も盗んでいたので、弁償するのも大変だ。次の日、警察がやって来る。ミシェルの父親はミシェルを見つけて十字架の場所を聞き出そうとするが、警察は実は、ポーレットを孤児院へ連れていこうと迎えに来ただけだった。
“お墓作り”が“禁じられた遊び”というわけだ。十字架を盗むことも勿論いけないことだから“禁じられ”ているが、としわもいかない小さな子供のすることだから、悪意はない。ポーレットは無意識のうちにパパとママのお墓作りをしていたのではないか。見終わってふとそんなことを考えましたな。
ラストシーンの切なさ。“微笑ましい映画”との印象が強かった前回はそれ程感じなかったのですが、今回はウルッとしてしまいました。戦争に翻弄されたいたいけな少女の話であることを思い知らされました。
▲(解除)
ポーレットを演じた天才少女ブリジット・フォッセーは、46年生まれだから当時5歳くらい。演技を感じさせない自然な表情が素晴らしい。15年後、「さすらいの青春(1966)」でカムバックしたのは雑誌で読んで知っていたが、この映画は観なかった。青春メロドラマとのこと。スチール写真では、現代劇ではない、ちょっと旧めの衣装を着ていたように記憶している。
ミシェルのジョルジュ・プージュリーは、「死刑台のエレベーター(1957)」に出ていた。犯人モーリス・ロネの車を盗む若いカップルの役だった。ン? ここでも盗みをやっていたのか。2000年に亡くなっていた。
『愛のロマンス』という、オープニングのタイトル・バックから流れているナルシソ・イエペスのギターは有名ですな。昔は、ギターを覚えたての頃は、誰もが一度は弾いていました。
・「禁じられた遊び」で気になった小ネタ
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】 

(2002/ロマン・ポランスキー監督/エイドリアン・ブロディ、トーマス・クレッチマン、エミリア・フォックス)
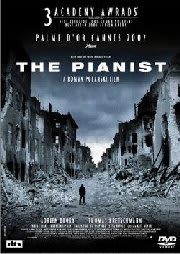 2002年度のアカデミー賞他たくさんの映画祭で賞賛された作品。米国アカデミーでは、監督賞と主演男優賞、脚色賞をとった。実在のユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンが第二次世界大戦の終戦直後に書いたといわれる回想録等を元に作られた。原題は「THE PIANIST」。ナチス・ドイツのユダヤ迫害を扱った映画だが、集団劇ではなく一人の男が戦争中の理不尽な迫害の中で生き延びていく姿を、彼の視点で描いている。途中から、ポルポト圧政下のカンボジアを描いた傑作「キリング・フィールド(1984)」を思い出した。あれも、実話だったなあ。
2002年度のアカデミー賞他たくさんの映画祭で賞賛された作品。米国アカデミーでは、監督賞と主演男優賞、脚色賞をとった。実在のユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンが第二次世界大戦の終戦直後に書いたといわれる回想録等を元に作られた。原題は「THE PIANIST」。ナチス・ドイツのユダヤ迫害を扱った映画だが、集団劇ではなく一人の男が戦争中の理不尽な迫害の中で生き延びていく姿を、彼の視点で描いている。途中から、ポルポト圧政下のカンボジアを描いた傑作「キリング・フィールド(1984)」を思い出した。あれも、実話だったなあ。
1939年のナチス・ドイツのワルシャワ侵攻から1944年の解放後までの6年余りの話で、時々入る年月の表示が、歴史をある程度分かっている人には効果的だったろう。原作の方が本人の心情などが詳しく表現されていて面白いらしい。しかし、実話なのにストーリーの展開に乱れはなく、先読みされてだれることもなく、それ故の脚色賞でしょう。
色調を抑えた美しい画面構成は、リアルだが「プライベート・ライアン」のように惨くはない。やっぱり、ポランスキーは優れた映画作家ですな。終盤の廃墟と化したワルシャワの街に漂う虚無感。戦後のユダヤ復興の原風景のような感じがしました。
ナチス・ドイツに制圧されたポーランド、ワルシャワでは、ユダヤ人への迫害が始まる。外出時にはユダヤ人であることを示す腕章をしなければいけなくなったり、カフェなどでも<ユダヤ人お断り>の看板が掲げられたりする。やがて、周囲に新設の壁を巡らしたユダヤ人のみの居住区(ゲットー)が定められ、大勢のユダヤ人が閉じこめられる。仕事もなく、食料の配給なども滞り、路上に死人が横たわる悲惨な状況となっていく。更に、強制収容所への移送が始まり、多数のユダヤ人が殺されていく。戦時下なので、ちょっと口答えしただけでも撃ち殺されたりする。この辺も「キリング・フィールド」に似ている。人間の狂気は、いつの時代も同じような顔をしている。
ゲットーの中のカフェでピアノを弾いているシュピルマン。やがて彼の家族も収容所へ送る貨物列車に乗せられることとなるが、知り合いのユダヤ人警察官に見つかった彼だけは奇跡的に助けられる。ナチス傘下に配置されたユダヤ人警察官が、強制収容所への移送にも手を貸していたというのは驚きだった。(アメリカ制圧下のイラクにもイラク人警察があるのとは、ちょっと違うか・・・)
生き残った若いユダヤ人達もドイツ軍の建設工事などにかりだされ、工事の進捗状況により、不要となりそうな数だけ無情にも殺されていく。「俺たち民族を抹殺するつもりだ」。誰かがつぶやく。そして、シュピルマンはゲットーからの脱出を決意するのだが・・・。
▼(ネタバレ注意)
この後は、色々なポーランド人に匿われていくわけだが、ポーランド人にもユダヤ迫害に手を貸す人もいたり、一歩間違えば殺されていただろう状況が何度も出てくる。結局この人は、戦時中一歩もワルシャワから出ることなく、敵の目の前で生き延びたんですな。ゲットーのユダヤ人とナチスの戦闘や、ポーランド人のレジスタンス闘争も目のあたりにしている。
最後は、皮肉にもドイツ軍将校に助けられる。原作本にはこのホーゼンフェルト大尉の日記も付けられていて、この人はシュピルマン以外のユダヤ人も数多く助けているらしいです。
▲(解除)
二度目の奥さん(シャロン・テート)がカルト集団に惨殺されたり、少女へのわいせつ行為で有罪判決などゴシップには事欠かないポランスキー監督は、「吸血鬼(1967)」、「チャイナタウン(1974)」等では俳優としても出てきて、ダスティン・ホフマン似の風貌を見せている。その他の日本公開作品は「フランティック(1988)」、「テス(1979)」、「マクベス(1971)」、「ローズマリーの赤ちゃん(1968)」、「袋小路(1965)」、「反撥(1964)」、「水の中のナイフ(1962)」など佳作揃い。70歳を前にして代表作ができましたな。
ところで、2003年のことだが、シュピルマンの実の息子さんが福岡市に在住されていて、彼がこの映画の関連で西日本新聞にインタビューを受けた時の記事が出ていた。その中で、今回のイラク戦争にもふれて『戦争はいけないことだが、平和主義者は結局、ヒトラーの暴走を止められなかった。フセインがヒトラーになるかどうかはわからないが。』というような主旨の発言をしていた。平和とはなにか。
こういう映画を見ると、イスラエルの強硬な対外軍事行動もわかるような気がするんだが・・・。平和とはなにか、考えさせられます。
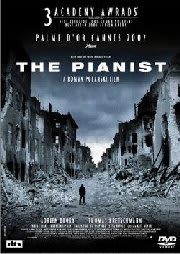 2002年度のアカデミー賞他たくさんの映画祭で賞賛された作品。米国アカデミーでは、監督賞と主演男優賞、脚色賞をとった。実在のユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンが第二次世界大戦の終戦直後に書いたといわれる回想録等を元に作られた。原題は「THE PIANIST」。ナチス・ドイツのユダヤ迫害を扱った映画だが、集団劇ではなく一人の男が戦争中の理不尽な迫害の中で生き延びていく姿を、彼の視点で描いている。途中から、ポルポト圧政下のカンボジアを描いた傑作「キリング・フィールド(1984)」を思い出した。あれも、実話だったなあ。
2002年度のアカデミー賞他たくさんの映画祭で賞賛された作品。米国アカデミーでは、監督賞と主演男優賞、脚色賞をとった。実在のユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンが第二次世界大戦の終戦直後に書いたといわれる回想録等を元に作られた。原題は「THE PIANIST」。ナチス・ドイツのユダヤ迫害を扱った映画だが、集団劇ではなく一人の男が戦争中の理不尽な迫害の中で生き延びていく姿を、彼の視点で描いている。途中から、ポルポト圧政下のカンボジアを描いた傑作「キリング・フィールド(1984)」を思い出した。あれも、実話だったなあ。1939年のナチス・ドイツのワルシャワ侵攻から1944年の解放後までの6年余りの話で、時々入る年月の表示が、歴史をある程度分かっている人には効果的だったろう。原作の方が本人の心情などが詳しく表現されていて面白いらしい。しかし、実話なのにストーリーの展開に乱れはなく、先読みされてだれることもなく、それ故の脚色賞でしょう。
色調を抑えた美しい画面構成は、リアルだが「プライベート・ライアン」のように惨くはない。やっぱり、ポランスキーは優れた映画作家ですな。終盤の廃墟と化したワルシャワの街に漂う虚無感。戦後のユダヤ復興の原風景のような感じがしました。
ナチス・ドイツに制圧されたポーランド、ワルシャワでは、ユダヤ人への迫害が始まる。外出時にはユダヤ人であることを示す腕章をしなければいけなくなったり、カフェなどでも<ユダヤ人お断り>の看板が掲げられたりする。やがて、周囲に新設の壁を巡らしたユダヤ人のみの居住区(ゲットー)が定められ、大勢のユダヤ人が閉じこめられる。仕事もなく、食料の配給なども滞り、路上に死人が横たわる悲惨な状況となっていく。更に、強制収容所への移送が始まり、多数のユダヤ人が殺されていく。戦時下なので、ちょっと口答えしただけでも撃ち殺されたりする。この辺も「キリング・フィールド」に似ている。人間の狂気は、いつの時代も同じような顔をしている。
ゲットーの中のカフェでピアノを弾いているシュピルマン。やがて彼の家族も収容所へ送る貨物列車に乗せられることとなるが、知り合いのユダヤ人警察官に見つかった彼だけは奇跡的に助けられる。ナチス傘下に配置されたユダヤ人警察官が、強制収容所への移送にも手を貸していたというのは驚きだった。(アメリカ制圧下のイラクにもイラク人警察があるのとは、ちょっと違うか・・・)
生き残った若いユダヤ人達もドイツ軍の建設工事などにかりだされ、工事の進捗状況により、不要となりそうな数だけ無情にも殺されていく。「俺たち民族を抹殺するつもりだ」。誰かがつぶやく。そして、シュピルマンはゲットーからの脱出を決意するのだが・・・。
▼(ネタバレ注意)
この後は、色々なポーランド人に匿われていくわけだが、ポーランド人にもユダヤ迫害に手を貸す人もいたり、一歩間違えば殺されていただろう状況が何度も出てくる。結局この人は、戦時中一歩もワルシャワから出ることなく、敵の目の前で生き延びたんですな。ゲットーのユダヤ人とナチスの戦闘や、ポーランド人のレジスタンス闘争も目のあたりにしている。
最後は、皮肉にもドイツ軍将校に助けられる。原作本にはこのホーゼンフェルト大尉の日記も付けられていて、この人はシュピルマン以外のユダヤ人も数多く助けているらしいです。
▲(解除)
二度目の奥さん(シャロン・テート)がカルト集団に惨殺されたり、少女へのわいせつ行為で有罪判決などゴシップには事欠かないポランスキー監督は、「吸血鬼(1967)」、「チャイナタウン(1974)」等では俳優としても出てきて、ダスティン・ホフマン似の風貌を見せている。その他の日本公開作品は「フランティック(1988)」、「テス(1979)」、「マクベス(1971)」、「ローズマリーの赤ちゃん(1968)」、「袋小路(1965)」、「反撥(1964)」、「水の中のナイフ(1962)」など佳作揃い。70歳を前にして代表作ができましたな。
ところで、2003年のことだが、シュピルマンの実の息子さんが福岡市に在住されていて、彼がこの映画の関連で西日本新聞にインタビューを受けた時の記事が出ていた。その中で、今回のイラク戦争にもふれて『戦争はいけないことだが、平和主義者は結局、ヒトラーの暴走を止められなかった。フセインがヒトラーになるかどうかはわからないが。』というような主旨の発言をしていた。平和とはなにか。
こういう映画を見ると、イスラエルの強硬な対外軍事行動もわかるような気がするんだが・・・。平和とはなにか、考えさせられます。
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】 











 ビデオジャケットに印刷された『2001年度アカデミー外国語映画賞受賞』、ボスニア・ヘルツェゴビナの内戦の話という紹介文に惹かれて見てみた。これは、非常によくできた反戦映画の秀作です。
ビデオジャケットに印刷された『2001年度アカデミー外国語映画賞受賞』、ボスニア・ヘルツェゴビナの内戦の話という紹介文に惹かれて見てみた。これは、非常によくできた反戦映画の秀作です。 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)