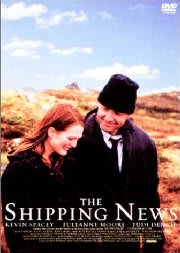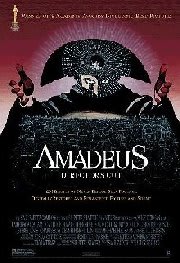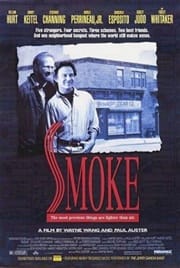(1953/ビリー・ワイルダー監督・製作・共同脚本/ウィリアム・ホールデン、ドン・テイラー、オットー・プレミンジャー、ロバート・ストラウス、ハーヴェイ・レンベック、ネヴィル・ブランド、ピーター・グレイヴス、シグ・ルーマン、リチャード・アードマン/119分)
お茶の間のテレビ(今でいう地上波)の吹き替えで洋画を観ていた頃、ワイルダーの名作と知りながらもなかなか放映されずに待ち続けた記憶がある映画だ。それでも何とか十代のうちに観たはずだが、とにかく昔の話なので今回が何十年ぶりかもわからないし、何回目なのかも覚えていない。多分2回目か3回目だろう。ドイツ軍の捕虜収容所が舞台の戦争の話と思って観ていたら、戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったという印象が残っている。さて、モノクロ・スタンダードサイズのスクリーンに繰り広げられるドラマは自粛中のモヤモヤを解消してくれるだろうか・・。
 オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。
オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。
語るのはC・H・クックと名乗る男。後で分かるが、この男はW・ホールデン扮するセフトン軍曹の相棒でなにかと補助をしてくれる弟分のような存在のクッキーの事だった。その彼がかつてドイツの捕虜収容所にいた頃の思い出を語っているという設定になっている。【原題:STALAG 17】
『戦争映画と言えば航空隊か潜水艦、或いはゲリラ戦の話ばかりでうんざりする。捕虜を描いた映画が観たいんだが、実は俺は乗っていた戦闘機をドイツ軍に撃墜されて1943年から2年半ほど捕虜収容所にいたんだ。その頃連合国の捕虜は4万人ほどいて、俺がいたドナウ川の近くにあった第十七捕虜収容所には630人くらい居た。収容所には敵側のスパイも居て色々ともめ事もあったんだ。あれは44年のクリスマス前の事だったか、同じ第4兵舎のアメリカ兵二人が脱走しようとしていたんだが・・・』
いきなり脱走のシーンになるが、ストーブをどけた後の床に穴が開いているというのは後年の「大脱走 (1963)」と同じだった。高床式の床下に潜り込んで、消灯後の共同洗面所まで行き、そこの簀の子の様な板を捲ると竪穴があり更に収容所の敷地外まで届いている横穴を這って行くのだ。この穴を伝って脱走するというのも「大脱走」と同じだった。ところが、これでひと安心と二人が立ち上がった所で前には機関銃を構えたドイツ兵が。あえなくハチの巣になる二人。兵舎の中で息を殺していた捕虜たちの耳にも銃声が聞こえてくる。
『何故だ?』
まるで待ち伏せしていたかのようなあっけない結末に驚く彼らだった。
第4兵舎にはおよそ70人のアメリカ兵がいるが全員空軍の軍曹らしい。
選挙で選ばれたであろうリーダーのホフィ(アードマン)と警務係のプライス(グレイブス)、血の気の多いデューク(ブランド)の三人が脱走の計画者の様である。
脱走のあった夜、二人が兵舎を出て行った後、セフトンはこの計画が失敗すると賭けを持ちかける。掛けたのはタバコ。その場にいた彼以外の全員が縁起の悪いことを言うなと成功に札をあげるが結果は前述の通り。デュークとセフトンは一発触発の状態になった。
セフトンは言った。
『脱走してなんになる。成功したって、また太平洋戦線へ送られるだけだ。運が良ければ今度は日本軍の捕虜になるかも知れん。俺はごめんだね。そんなに英雄になりたいのか。俺はそんな事よりもここでなるべく気楽に過ごしたい。それだけだ』
セフトンは他の兵隊達とは一線を画していた。
一見悲観論者に見えるが、彼の荷物箱の中身は綺麗に整理されていた。ストーブが脱走のカムフラージュに使われたので撤去されることになり、最後の温かい食事だとセフトンは目玉焼きを一人作って食べた。デュークには仲間を殺したドイツ人と取引したのかとなじられたがこう反論した。
『俺がココにやって来た時すぐに毛布と靴下を盗まれた。頼れるのは自分だけだと知った。だから例えドイツ人相手でも必要ならば取引もする』
セフトンは金儲けの才にも長けていた。
土日にはネズミを馬に見立てた競馬場を作って賭場を開くし、密造酒を作って煙草と交換したりする。少し離れた兵舎にロシアの女性兵士の捕虜が来た時には望遠鏡を作って有料で覗かせたりした。そんな事でせしめた煙草をドイツ兵との闇取引に使うのだ。それがまたデューク達の神経を逆なでする事になった。
セフトンに対するスパイ疑惑は燻っていたが、クリスマス直前についに爆発する事件が発生する。
新たに捕虜として連行されてきたダンパー中尉と軍曹の二人が、少し前のドイツ軍の弾薬列車爆破事件の実行者であり、その事が又してもドイツ軍に知られてしまったからだ。二人が事件を起した事は第4兵舎以外の人間は知らないはず。捕虜収容所の所長自ら中尉を連行に来て、これから拷問が始まると分かった捕虜たちはついにセフトンをリンチにかけるのだった・・・。
ドナルド・ビーヴァン、エドモンド・トルチンスキー共作戯曲のブロードウェイの舞台劇が元ネタだそうで、確かにサスペンスだけでなく捕虜たちの人間模様も描かれていて戦争映画の範疇に入れても違和感は無さそうである。
コメディリリーフを担当するのが、漫才コンビのようなアニマル(ストラウス)とハリー(レンベック)の二人。
その二人と何かと絡む第4兵舎担当のドイツ兵シュルツ軍曹(ルーマン)もユーモラスに描かれていた。スパイとの連絡役だからにっくき奴だが人間味が少し滲むシーンもあった。
その他、機械に強い金髪のブロンディとか、戦争体験から心の病におかされているジョーイ、各棟にニュースや郵便物等の配信、配達をする捕虜の兵隊などなど。
ダンパー中尉には「花嫁の父」でリズ・テイラーのフィアンセになったドンテイラー。
そして、収容所のシェルバッハ所長に扮したのは映画監督としても名高いオットー・プレミンジャーだった。冷酷なドイツ人将校を完璧に演じていたが、彼自身はオーストリア系のユダヤ人だそうである。
お薦め度は★四つ半。
終盤にはスパイが誰なのかもハッキリしてセフトンの容疑は晴れるし、ラストで中尉も無事に脱走出来てスカッとする。
1953年のアカデミー賞では監督賞、主演男優賞(ホールデン)、助演男優賞(ストラウス)にノミネートされ、ホールデンが初受賞したそうだ。
TVシリーズもあったはずと思っていたが、深夜放送しかされていなかったその番組は「0012捕虜収容所」というタイトルで、むしろ「大脱走」の影響でつくられた番組らしい。深夜帯での放送だったので当時子供だった僕は観ていない。
▼(ネタバレ注意)
最後にナチスの親衛隊に引き渡されそうになったダンパー中尉と共に脱走するのはセフトンだ。スパイを一人で暴き、危険な任務も引き受けるセフトンに、今までスパイと疑っていた連中も心の中で喝采を上げていたに違いない。宿舎のベッドの上でクッキーが口笛で鳴らした『♪ジョニーが凱旋するとき』がカッコいい。
戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったと書いているけど、実はスパイが誰だったか完全に忘れていた。
まさかTV「スパイ大作戦」のリーダー、フェルプス君だったとはねぇ~。
▲(解除)
お茶の間のテレビ(今でいう地上波)の吹き替えで洋画を観ていた頃、ワイルダーの名作と知りながらもなかなか放映されずに待ち続けた記憶がある映画だ。それでも何とか十代のうちに観たはずだが、とにかく昔の話なので今回が何十年ぶりかもわからないし、何回目なのかも覚えていない。多分2回目か3回目だろう。ドイツ軍の捕虜収容所が舞台の戦争の話と思って観ていたら、戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったという印象が残っている。さて、モノクロ・スタンダードサイズのスクリーンに繰り広げられるドラマは自粛中のモヤモヤを解消してくれるだろうか・・。
*
 オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。
オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。語るのはC・H・クックと名乗る男。後で分かるが、この男はW・ホールデン扮するセフトン軍曹の相棒でなにかと補助をしてくれる弟分のような存在のクッキーの事だった。その彼がかつてドイツの捕虜収容所にいた頃の思い出を語っているという設定になっている。【原題:STALAG 17】
『戦争映画と言えば航空隊か潜水艦、或いはゲリラ戦の話ばかりでうんざりする。捕虜を描いた映画が観たいんだが、実は俺は乗っていた戦闘機をドイツ軍に撃墜されて1943年から2年半ほど捕虜収容所にいたんだ。その頃連合国の捕虜は4万人ほどいて、俺がいたドナウ川の近くにあった第十七捕虜収容所には630人くらい居た。収容所には敵側のスパイも居て色々ともめ事もあったんだ。あれは44年のクリスマス前の事だったか、同じ第4兵舎のアメリカ兵二人が脱走しようとしていたんだが・・・』
いきなり脱走のシーンになるが、ストーブをどけた後の床に穴が開いているというのは後年の「大脱走 (1963)」と同じだった。高床式の床下に潜り込んで、消灯後の共同洗面所まで行き、そこの簀の子の様な板を捲ると竪穴があり更に収容所の敷地外まで届いている横穴を這って行くのだ。この穴を伝って脱走するというのも「大脱走」と同じだった。ところが、これでひと安心と二人が立ち上がった所で前には機関銃を構えたドイツ兵が。あえなくハチの巣になる二人。兵舎の中で息を殺していた捕虜たちの耳にも銃声が聞こえてくる。
『何故だ?』
まるで待ち伏せしていたかのようなあっけない結末に驚く彼らだった。
第4兵舎にはおよそ70人のアメリカ兵がいるが全員空軍の軍曹らしい。
選挙で選ばれたであろうリーダーのホフィ(アードマン)と警務係のプライス(グレイブス)、血の気の多いデューク(ブランド)の三人が脱走の計画者の様である。
脱走のあった夜、二人が兵舎を出て行った後、セフトンはこの計画が失敗すると賭けを持ちかける。掛けたのはタバコ。その場にいた彼以外の全員が縁起の悪いことを言うなと成功に札をあげるが結果は前述の通り。デュークとセフトンは一発触発の状態になった。
セフトンは言った。
『脱走してなんになる。成功したって、また太平洋戦線へ送られるだけだ。運が良ければ今度は日本軍の捕虜になるかも知れん。俺はごめんだね。そんなに英雄になりたいのか。俺はそんな事よりもここでなるべく気楽に過ごしたい。それだけだ』
セフトンは他の兵隊達とは一線を画していた。
一見悲観論者に見えるが、彼の荷物箱の中身は綺麗に整理されていた。ストーブが脱走のカムフラージュに使われたので撤去されることになり、最後の温かい食事だとセフトンは目玉焼きを一人作って食べた。デュークには仲間を殺したドイツ人と取引したのかとなじられたがこう反論した。
『俺がココにやって来た時すぐに毛布と靴下を盗まれた。頼れるのは自分だけだと知った。だから例えドイツ人相手でも必要ならば取引もする』
セフトンは金儲けの才にも長けていた。
土日にはネズミを馬に見立てた競馬場を作って賭場を開くし、密造酒を作って煙草と交換したりする。少し離れた兵舎にロシアの女性兵士の捕虜が来た時には望遠鏡を作って有料で覗かせたりした。そんな事でせしめた煙草をドイツ兵との闇取引に使うのだ。それがまたデューク達の神経を逆なでする事になった。
セフトンに対するスパイ疑惑は燻っていたが、クリスマス直前についに爆発する事件が発生する。
新たに捕虜として連行されてきたダンパー中尉と軍曹の二人が、少し前のドイツ軍の弾薬列車爆破事件の実行者であり、その事が又してもドイツ軍に知られてしまったからだ。二人が事件を起した事は第4兵舎以外の人間は知らないはず。捕虜収容所の所長自ら中尉を連行に来て、これから拷問が始まると分かった捕虜たちはついにセフトンをリンチにかけるのだった・・・。
*
ドナルド・ビーヴァン、エドモンド・トルチンスキー共作戯曲のブロードウェイの舞台劇が元ネタだそうで、確かにサスペンスだけでなく捕虜たちの人間模様も描かれていて戦争映画の範疇に入れても違和感は無さそうである。
コメディリリーフを担当するのが、漫才コンビのようなアニマル(ストラウス)とハリー(レンベック)の二人。
その二人と何かと絡む第4兵舎担当のドイツ兵シュルツ軍曹(ルーマン)もユーモラスに描かれていた。スパイとの連絡役だからにっくき奴だが人間味が少し滲むシーンもあった。
その他、機械に強い金髪のブロンディとか、戦争体験から心の病におかされているジョーイ、各棟にニュースや郵便物等の配信、配達をする捕虜の兵隊などなど。
ダンパー中尉には「花嫁の父」でリズ・テイラーのフィアンセになったドンテイラー。
そして、収容所のシェルバッハ所長に扮したのは映画監督としても名高いオットー・プレミンジャーだった。冷酷なドイツ人将校を完璧に演じていたが、彼自身はオーストリア系のユダヤ人だそうである。
お薦め度は★四つ半。
終盤にはスパイが誰なのかもハッキリしてセフトンの容疑は晴れるし、ラストで中尉も無事に脱走出来てスカッとする。
1953年のアカデミー賞では監督賞、主演男優賞(ホールデン)、助演男優賞(ストラウス)にノミネートされ、ホールデンが初受賞したそうだ。
TVシリーズもあったはずと思っていたが、深夜放送しかされていなかったその番組は「0012捕虜収容所」というタイトルで、むしろ「大脱走」の影響でつくられた番組らしい。深夜帯での放送だったので当時子供だった僕は観ていない。
▼(ネタバレ注意)
最後にナチスの親衛隊に引き渡されそうになったダンパー中尉と共に脱走するのはセフトンだ。スパイを一人で暴き、危険な任務も引き受けるセフトンに、今までスパイと疑っていた連中も心の中で喝采を上げていたに違いない。宿舎のベッドの上でクッキーが口笛で鳴らした『♪ジョニーが凱旋するとき』がカッコいい。
戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったと書いているけど、実はスパイが誰だったか完全に忘れていた。
まさかTV「スパイ大作戦」のリーダー、フェルプス君だったとはねぇ~。
▲(解除)
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし】 

(↓Twitter on 十瑠 から(一部修正あり))

 今朝、ロッセリーニの「無防備都市」を観る。何年ぶりだろう?50年以上かな。ドキュメンタリータッチと謳ってあるし、記憶もそんな感じだったけど、今の感覚では全然違うな。「アルジェの戦い」程度には描かれてると思ったけど、全然違う。ユーモアもあったしな。フェリーニが脚本に参加していた。
今朝、ロッセリーニの「無防備都市」を観る。何年ぶりだろう?50年以上かな。ドキュメンタリータッチと謳ってあるし、記憶もそんな感じだったけど、今の感覚では全然違うな。「アルジェの戦い」程度には描かれてると思ったけど、全然違う。ユーモアもあったしな。フェリーニが脚本に参加していた。
[ 7月 14日]
 12日に総合図書館で借りていた「無防備都市」を城南図書館に返却する。14日に何十年かぶりに観て、その後2回目を観る気が起きず、やっと一昨日に観た。
12日に総合図書館で借りていた「無防備都市」を城南図書館に返却する。14日に何十年かぶりに観て、その後2回目を観る気が起きず、やっと一昨日に観た。
[ 7月 25日 以下同じ]
 思えば、高校生になって「SCREEN」を読み始め「無防備都市」の記事に接した時にタイトルを思い出したんだから、映画は中学生か或は小学生の時に観たのかも知れない。ロッセリーニの名前もこの高校生の時に認識したのかも。あのイングリッド・バーグマンとの不倫ロマンスが有名な監督ですな。
思えば、高校生になって「SCREEN」を読み始め「無防備都市」の記事に接した時にタイトルを思い出したんだから、映画は中学生か或は小学生の時に観たのかも知れない。ロッセリーニの名前もこの高校生の時に認識したのかも。あのイングリッド・バーグマンとの不倫ロマンスが有名な監督ですな。
 第二次世界大戦時のイタリア、ローマが舞台。既にムッソリーニは失脚しているみたいで、ナチスドイツに支配されている時代のようだった。食糧難に苦しむ市民生活も描かれるが、大筋はナチスとイタリア、レジスタンス戦士との戦いが描かれている。
第二次世界大戦時のイタリア、ローマが舞台。既にムッソリーニは失脚しているみたいで、ナチスドイツに支配されている時代のようだった。食糧難に苦しむ市民生活も描かれるが、大筋はナチスとイタリア、レジスタンス戦士との戦いが描かれている。
 ゲシュタポのブラックリストに載っているレジスタンスの指導的立場の男が恋仲になった女優と撮った写真からローマにいる事がばれ追われるようになり、彼を匿う印刷工やその婚約者、婚約者の家族、更には彼らを支援する神父も出てきて前半はサスペンス劇のように進む。
ゲシュタポのブラックリストに載っているレジスタンスの指導的立場の男が恋仲になった女優と撮った写真からローマにいる事がばれ追われるようになり、彼を匿う印刷工やその婚約者、婚約者の家族、更には彼らを支援する神父も出てきて前半はサスペンス劇のように進む。
 戦時中とは言いながら教会の近くの路上でサッカーに興じている小学生の子供達も出てきて、中には爆弾による負傷だろうか片足の少年もいて、ひそかに爆弾作りをしていたり彼らなりに抵抗運動への準備をしていたことが分かる。
戦時中とは言いながら教会の近くの路上でサッカーに興じている小学生の子供達も出てきて、中には爆弾による負傷だろうか片足の少年もいて、ひそかに爆弾作りをしていたり彼らなりに抵抗運動への準備をしていたことが分かる。
 14日のツイートで『ユーモアもあったしな』と書いたのは主に神父と子供達との掛け合いの部分だったと思うけど、悲劇的なラストで前半の彼らのシーンが思い出されてくる。
14日のツイートで『ユーモアもあったしな』と書いたのは主に神父と子供達との掛け合いの部分だったと思うけど、悲劇的なラストで前半の彼らのシーンが思い出されてくる。
 前半はサスペンス劇だが、戦士が捕まった後の後半はゲシュタポの拷問が丁寧に描かれて彼らの残酷さが浮き彫りにされる。女優を利用するのに麻薬付けにしたりとか、拷問部屋の近くには酒やゲームに溺れる享楽的な部屋があったりと、ナチスの腐敗した姿も描かれている。
前半はサスペンス劇だが、戦士が捕まった後の後半はゲシュタポの拷問が丁寧に描かれて彼らの残酷さが浮き彫りにされる。女優を利用するのに麻薬付けにしたりとか、拷問部屋の近くには酒やゲームに溺れる享楽的な部屋があったりと、ナチスの腐敗した姿も描かれている。
 あのシーンを観ながらヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」を想像したんだけど、どうやら関係は無いみたい。ま、僕はアレは未見なので勝手な思い違いです。
あのシーンを観ながらヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」を想像したんだけど、どうやら関係は無いみたい。ま、僕はアレは未見なので勝手な思い違いです。
 出演者はほぼ知らない人ばかりですが、印刷工のフィアンセで子持ちの戦争未亡人ピーナを演じたのはアンナ・マニャーニでした。後にハリウッドに進出して主演オスカーも獲得したし、72年の「フェリーニのローマ」にも友情出演してましたね。
出演者はほぼ知らない人ばかりですが、印刷工のフィアンセで子持ちの戦争未亡人ピーナを演じたのはアンナ・マニャーニでした。後にハリウッドに進出して主演オスカーも獲得したし、72年の「フェリーニのローマ」にも友情出演してましたね。
 お薦め度は★四つ。ロッセリーニはこの後「戦火のかなた」、「ドイツ零年」と戦争ものが続く。前者はよりドキュメンタリータッチが顕著らしいし、後者は解説を読むと暗く厳しい作品らしい。尚、ロッセリーニは仏で支持され、ヌーヴェル・ヴァーグの父と呼ばれているらしい。
お薦め度は★四つ。ロッセリーニはこの後「戦火のかなた」、「ドイツ零年」と戦争ものが続く。前者はよりドキュメンタリータッチが顕著らしいし、後者は解説を読むと暗く厳しい作品らしい。尚、ロッセリーニは仏で支持され、ヌーヴェル・ヴァーグの父と呼ばれているらしい。
(1945/ロベルト・ロッセリーニ監督/アルド・ファブリッツィ、アンナ・マニャーニ、マルチェロ・パリエーロ、マリア・ミーキ/106分)

 今朝、ロッセリーニの「無防備都市」を観る。何年ぶりだろう?50年以上かな。ドキュメンタリータッチと謳ってあるし、記憶もそんな感じだったけど、今の感覚では全然違うな。「アルジェの戦い」程度には描かれてると思ったけど、全然違う。ユーモアもあったしな。フェリーニが脚本に参加していた。
今朝、ロッセリーニの「無防備都市」を観る。何年ぶりだろう?50年以上かな。ドキュメンタリータッチと謳ってあるし、記憶もそんな感じだったけど、今の感覚では全然違うな。「アルジェの戦い」程度には描かれてると思ったけど、全然違う。ユーモアもあったしな。フェリーニが脚本に参加していた。[ 7月 14日]
 12日に総合図書館で借りていた「無防備都市」を城南図書館に返却する。14日に何十年かぶりに観て、その後2回目を観る気が起きず、やっと一昨日に観た。
12日に総合図書館で借りていた「無防備都市」を城南図書館に返却する。14日に何十年かぶりに観て、その後2回目を観る気が起きず、やっと一昨日に観た。[ 7月 25日 以下同じ]
 思えば、高校生になって「SCREEN」を読み始め「無防備都市」の記事に接した時にタイトルを思い出したんだから、映画は中学生か或は小学生の時に観たのかも知れない。ロッセリーニの名前もこの高校生の時に認識したのかも。あのイングリッド・バーグマンとの不倫ロマンスが有名な監督ですな。
思えば、高校生になって「SCREEN」を読み始め「無防備都市」の記事に接した時にタイトルを思い出したんだから、映画は中学生か或は小学生の時に観たのかも知れない。ロッセリーニの名前もこの高校生の時に認識したのかも。あのイングリッド・バーグマンとの不倫ロマンスが有名な監督ですな。*
 第二次世界大戦時のイタリア、ローマが舞台。既にムッソリーニは失脚しているみたいで、ナチスドイツに支配されている時代のようだった。食糧難に苦しむ市民生活も描かれるが、大筋はナチスとイタリア、レジスタンス戦士との戦いが描かれている。
第二次世界大戦時のイタリア、ローマが舞台。既にムッソリーニは失脚しているみたいで、ナチスドイツに支配されている時代のようだった。食糧難に苦しむ市民生活も描かれるが、大筋はナチスとイタリア、レジスタンス戦士との戦いが描かれている。 ゲシュタポのブラックリストに載っているレジスタンスの指導的立場の男が恋仲になった女優と撮った写真からローマにいる事がばれ追われるようになり、彼を匿う印刷工やその婚約者、婚約者の家族、更には彼らを支援する神父も出てきて前半はサスペンス劇のように進む。
ゲシュタポのブラックリストに載っているレジスタンスの指導的立場の男が恋仲になった女優と撮った写真からローマにいる事がばれ追われるようになり、彼を匿う印刷工やその婚約者、婚約者の家族、更には彼らを支援する神父も出てきて前半はサスペンス劇のように進む。 戦時中とは言いながら教会の近くの路上でサッカーに興じている小学生の子供達も出てきて、中には爆弾による負傷だろうか片足の少年もいて、ひそかに爆弾作りをしていたり彼らなりに抵抗運動への準備をしていたことが分かる。
戦時中とは言いながら教会の近くの路上でサッカーに興じている小学生の子供達も出てきて、中には爆弾による負傷だろうか片足の少年もいて、ひそかに爆弾作りをしていたり彼らなりに抵抗運動への準備をしていたことが分かる。 14日のツイートで『ユーモアもあったしな』と書いたのは主に神父と子供達との掛け合いの部分だったと思うけど、悲劇的なラストで前半の彼らのシーンが思い出されてくる。
14日のツイートで『ユーモアもあったしな』と書いたのは主に神父と子供達との掛け合いの部分だったと思うけど、悲劇的なラストで前半の彼らのシーンが思い出されてくる。 前半はサスペンス劇だが、戦士が捕まった後の後半はゲシュタポの拷問が丁寧に描かれて彼らの残酷さが浮き彫りにされる。女優を利用するのに麻薬付けにしたりとか、拷問部屋の近くには酒やゲームに溺れる享楽的な部屋があったりと、ナチスの腐敗した姿も描かれている。
前半はサスペンス劇だが、戦士が捕まった後の後半はゲシュタポの拷問が丁寧に描かれて彼らの残酷さが浮き彫りにされる。女優を利用するのに麻薬付けにしたりとか、拷問部屋の近くには酒やゲームに溺れる享楽的な部屋があったりと、ナチスの腐敗した姿も描かれている。 あのシーンを観ながらヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」を想像したんだけど、どうやら関係は無いみたい。ま、僕はアレは未見なので勝手な思い違いです。
あのシーンを観ながらヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」を想像したんだけど、どうやら関係は無いみたい。ま、僕はアレは未見なので勝手な思い違いです。 出演者はほぼ知らない人ばかりですが、印刷工のフィアンセで子持ちの戦争未亡人ピーナを演じたのはアンナ・マニャーニでした。後にハリウッドに進出して主演オスカーも獲得したし、72年の「フェリーニのローマ」にも友情出演してましたね。
出演者はほぼ知らない人ばかりですが、印刷工のフィアンセで子持ちの戦争未亡人ピーナを演じたのはアンナ・マニャーニでした。後にハリウッドに進出して主演オスカーも獲得したし、72年の「フェリーニのローマ」にも友情出演してましたね。 お薦め度は★四つ。ロッセリーニはこの後「戦火のかなた」、「ドイツ零年」と戦争ものが続く。前者はよりドキュメンタリータッチが顕著らしいし、後者は解説を読むと暗く厳しい作品らしい。尚、ロッセリーニは仏で支持され、ヌーヴェル・ヴァーグの父と呼ばれているらしい。
お薦め度は★四つ。ロッセリーニはこの後「戦火のかなた」、「ドイツ零年」と戦争ものが続く。前者はよりドキュメンタリータッチが顕著らしいし、後者は解説を読むと暗く厳しい作品らしい。尚、ロッセリーニは仏で支持され、ヌーヴェル・ヴァーグの父と呼ばれているらしい。(1945/ロベルト・ロッセリーニ監督/アルド・ファブリッツィ、アンナ・マニャーニ、マルチェロ・パリエーロ、マリア・ミーキ/106分)
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 

ストーリー的には結構端折ってる部分があって、でもそれが観客の想像力を刺激する要因にもなってるデ・シーカ監督69歳の作品「ひまわり」。
そんな部分も含めて書き残してる所を徒然に記しておこうと思います。
主要な登場人物はほぼ三人。ジョバンナとアントニオと、もう一人リュドミラ・サベリーエワ扮するロシア人の奥さんですね。
この健気にも凍死寸前のイタリア兵を助けた少女の名前、劇中では語られなかったように思いますが、データによるとマーシャとなっていました。で、二人の間に生まれた女の子がカチューシャ。ロシアにはシャの付く人多いですよね。因みにサベリーエワがヒロインを演じたトルストイの「戦争と平和」の彼女の役名はナターシャでした。
このマーシャがアントニオを助けた理由も語られていないですね。
雪原で大勢行き倒れていた中でたまたま彼が息をしているのを見つけて救おうとしたと考えるのが妥当ですが、その後のアントニオとの関係の進展具合もほぼ観客の想像に任せられています。
そして、その間のアントニオの心中も描かれてはいません。この辺はサッカー場から駅へとジョバンナが追いかけて行った元イタリア兵の男の反応が答えと考えればいいんでしょう。極限のストレスの後遺症、つかの間の幸福を唯一の拠り所とせざるを得なかった異国の生活。なんとなく分かる気がします。
ジョバンナがソ連に行く前に「もう、スターリンも死んだことだし・・・」なんてセリフがありました。
スターリンが死んだのは1953年ですから、アントニオが出征して10年後くらいだったんですね。アントも40代半ばだったということです。
物足りないなと感じた部分は、ミラノに帰って行ったアントニオが母親について発言していない事。これはジョバンナも同じことですが、あの母親はどうなったんでしょうね。ストーリー的には大したことではないですがちょっと気になりました。
あと、とっても気になったのが、アントニオがミラノに舞い戻って来て再会した時に、すでに彼女にも幼子が居た事。
ジョバンナがショックから羽目を外して他の男とデートをしたりするシーンは確かにありましたが、子供を作るまでの時間が経っていたとは思えなかったですもの。時間経過の表現が曖昧だったのかなぁ。
最後に“ひまわり”について。
タイトルバックの向日葵畑の映像は途中にも出てきますが、あの向日葵の下には大勢のイタリア兵やロシア兵の捕虜、その地の老人や子供たちの遺体が眠っているんだそうです。
そして“ひまわり”はソヴィエトの国花の一つなんだそうです。
そんな部分も含めて書き残してる所を徒然に記しておこうと思います。
主要な登場人物はほぼ三人。ジョバンナとアントニオと、もう一人リュドミラ・サベリーエワ扮するロシア人の奥さんですね。
この健気にも凍死寸前のイタリア兵を助けた少女の名前、劇中では語られなかったように思いますが、データによるとマーシャとなっていました。で、二人の間に生まれた女の子がカチューシャ。ロシアにはシャの付く人多いですよね。因みにサベリーエワがヒロインを演じたトルストイの「戦争と平和」の彼女の役名はナターシャでした。
このマーシャがアントニオを助けた理由も語られていないですね。
雪原で大勢行き倒れていた中でたまたま彼が息をしているのを見つけて救おうとしたと考えるのが妥当ですが、その後のアントニオとの関係の進展具合もほぼ観客の想像に任せられています。
そして、その間のアントニオの心中も描かれてはいません。この辺はサッカー場から駅へとジョバンナが追いかけて行った元イタリア兵の男の反応が答えと考えればいいんでしょう。極限のストレスの後遺症、つかの間の幸福を唯一の拠り所とせざるを得なかった異国の生活。なんとなく分かる気がします。
ジョバンナがソ連に行く前に「もう、スターリンも死んだことだし・・・」なんてセリフがありました。
スターリンが死んだのは1953年ですから、アントニオが出征して10年後くらいだったんですね。アントも40代半ばだったということです。
物足りないなと感じた部分は、ミラノに帰って行ったアントニオが母親について発言していない事。これはジョバンナも同じことですが、あの母親はどうなったんでしょうね。ストーリー的には大したことではないですがちょっと気になりました。
あと、とっても気になったのが、アントニオがミラノに舞い戻って来て再会した時に、すでに彼女にも幼子が居た事。
ジョバンナがショックから羽目を外して他の男とデートをしたりするシーンは確かにありましたが、子供を作るまでの時間が経っていたとは思えなかったですもの。時間経過の表現が曖昧だったのかなぁ。
最後に“ひまわり”について。
タイトルバックの向日葵畑の映像は途中にも出てきますが、あの向日葵の下には大勢のイタリア兵やロシア兵の捕虜、その地の老人や子供たちの遺体が眠っているんだそうです。
そして“ひまわり”はソヴィエトの国花の一つなんだそうです。
(1970/ヴィットリオ・デ・シーカ監督/ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニ、リュドミラ・サベリーエワ、アンナ・カレナ/107分)
1970年は僕は高校生だったし映画に夢中だったからこの映画の事はよく覚えてますが、実は全体を通して観るのは今回が初なんですよね。双葉さんの評価が☆☆☆★★★(75点)の秀作だったから観るべきとの認識はあったと思いますが、当時はアメリカ映画の方が好きだったし、ソフィア・ローレンがビジュアル的に好みではなかったとか、第二次世界大戦絡みの内容にも今更感があったとか、そんな理由で後回しになったんだと思います。吹き替え放送も何回もあったでしょうけど、今回観て、やはり初見だったと確認しました。
オープニングクレジットのバックは広大な向日葵畑の映像。そこにもう何十年も忘れられないお馴染みのヘンリー・マンシーニの物悲しいテーマ曲のメロディーが・・・。
プロデューサーがソフィアの夫であるカルロ・ポンティだったということは周知の事ですが、今回アーサー・コーンも連名でクレジットされていたのに気づきました。コーンはデ・シーカの「女と女と女たち (1967)」とか「恋人たちの場所 (1968)」も手掛けていたんですね。
 第二次世界大戦さなかのイタリア、ミラノ。
第二次世界大戦さなかのイタリア、ミラノ。
主婦ジョバンナはロシア戦線に出たまま音信不通になっている夫アントニオの行方を尋ねようと義母と共に役所に出かけるが、役人は「行方不明」としか答えてくれない。「生きているんでしょ?」と詰め寄るも、軍隊からも本省からも行方不明としか回答がないと役人は繰り返すだけだった。
家に帰って一人の夕食。ジョバンナはアント(彼女はアントニオをこう呼んだ)と出会った頃を思い出す。
逢ったのはジョバンナの故郷ナポリ。浜辺で愛を確かめ合った若い頃、アントは32歳だった。結婚なんかしたくないと言ったアントだったが、婚姻で出征が12日延びると聞いてすぐに結婚をした。ナポリで式を挙げた後、アントの故郷ミラノに向かう列車の中でジョバンナはイアリングをプレゼントされた。
二人は12日間を殆ど家の中で過ごした。それほど二人は愛し合っていたのだ。
やがて休暇も終わる頃、離れがたい二人は一計を案じる。それはアントが気がふれた様に装って更に出征を免れようということだった。街中で刃物を振り回してジョバンナを追い掛け回し警察に捕まる。計略は上手くいったかに思えたが、直ぐにばれる事となった。
『脱走罪で懲役に服すか、ロシア戦線に行くか選びなさい』
戦地に向かうアントとの最期の別れは駅のトイレだった。
裁縫で生計を立てながらミラノで一人待つジョバンナ。
やがて戦争が終わり、ロシア戦線からの復員兵の列車が帰って来るというので、ジョバンナはアントの写真を持ってホームに立った。そこにはやはり同じように写真を抱えた人々が沢山居た。
一人の兵隊がアントの写真を見つけ『アントニオ』と応えた。
ジョバンナは男にアントの事を尋ねた。『生きてる?』
兵隊は人ごみを避けてしばらく歩き、おもむろに重い口を開いた。
『ドン河まではな・・・』
男の話は悲惨なものだった。
辺り一面雪に覆われたロシアの大地で敗色濃厚なイタリア軍は眠る時間もなく敗走を続けていた。四方八方からのロシア軍の攻撃もさることながら、立ち止まることが即ち凍死を意味する程の寒さだった。アントはその兵隊に助けられながら歩き続けたが、ドン河の手前でついに力尽きて倒れてしまったのだ。意識はあったが、アントは男に先に進むように目で合図をした。男は為すすべもなく再び前に向かって歩き出した。この時が男がアントニオを見た最後だった。
ジョバンナはアントを探しにロシアに向かう。外務省を訪ね、役人の支援を仰ぎながらアントが行方不明になった所の近くの村や、戦死したイタリア兵が多く眠る墓地にも行ったが、彼の消息を示すものは何処にも無かった。
記憶を失くしたイタリア人を見かけた事があると噂されたサッカー場にも行ってみたが、スタンドは広すぎて途方に暮れそうだった。試合の終了後に出入口で観客を待っていると、一人のらしき人物を見つけた。後をついていき『イタリア人でしょ?』と声を掛けたが『違う』とロシア語で返答された。
それでも駅の中にまで付いてくるジョバンナに根負けした彼はイタリア語で話しかけてくれた。やはりイタリア人だった。
『田舎は何処なの?』
『今はロシア人だ』
『何故、ここに居るの?』
『何故って?長い話さ。要するにこうなってしまった。それだけの事だ』
ジョバンナはアントニオの写真を見せたが、知らないと彼は言った。『俺もアルプス隊だから嘘はつかない』
『故郷へは?』
『故郷?』つまらぬ冗談を聞いた後のように、或いは何かを諦めたかのように片方の頬に笑みを浮かべながら男は電車に乗ってどこかへ帰って行った。
アントは絶対にどこかに居る。あの男のように、心に傷をもってこのロシアで暮らしているのだ。
ジョバンナは一人で村々を訪ね歩くことにした。すると、とある村で一組の母子がアントの写真に反応した。
その家はすぐ近くにあった。
小さな一軒家で、庭には大きなシーツや洋服などの洗濯物が。そして、洗濯物を取り入れる若い女。ジョバンナの表情に不安がよぎる。正に家庭の匂いがする家だった・・・。
高校生の頃は、多分にお涙頂戴映画の一つであると思っていた節があるのですが、後半の夫婦の二度の再会と別れのドラマには、背景にある戦争の残酷さが十分に感じられて、泣くというよりは胸を締め付けられる様でした。ジョバンナはアントニオをなかなか許せなかったみたいですけど、最後の最後には理解したようですね。
コメディのような明るい序盤と、マストロヤンニ、ソフィア・ローレンの悲痛な表情が対照的な後半。
戦闘シーンは殆どなく、当時の記録映像をコラージュのように編集していました。
ロシアの吉永小百合のようなリュドミラ・サベリーエワの哀し気な表情も切ないし、強気なナポリ女が雨の夜の再会前にかつて新婚旅行でプレゼントされたイヤリングを出してくるところも泣かせます。
お勧め度は★三つ半。
1970年のアカデミー賞で作曲賞(ヘンリー・マンシーニ)にノミネートされた音楽で★半分おまけです。
※ 追加記事、ネタバレ備忘録はコチラ。
1970年は僕は高校生だったし映画に夢中だったからこの映画の事はよく覚えてますが、実は全体を通して観るのは今回が初なんですよね。双葉さんの評価が☆☆☆★★★(75点)の秀作だったから観るべきとの認識はあったと思いますが、当時はアメリカ映画の方が好きだったし、ソフィア・ローレンがビジュアル的に好みではなかったとか、第二次世界大戦絡みの内容にも今更感があったとか、そんな理由で後回しになったんだと思います。吹き替え放送も何回もあったでしょうけど、今回観て、やはり初見だったと確認しました。
オープニングクレジットのバックは広大な向日葵畑の映像。そこにもう何十年も忘れられないお馴染みのヘンリー・マンシーニの物悲しいテーマ曲のメロディーが・・・。
プロデューサーがソフィアの夫であるカルロ・ポンティだったということは周知の事ですが、今回アーサー・コーンも連名でクレジットされていたのに気づきました。コーンはデ・シーカの「女と女と女たち (1967)」とか「恋人たちの場所 (1968)」も手掛けていたんですね。
*
 第二次世界大戦さなかのイタリア、ミラノ。
第二次世界大戦さなかのイタリア、ミラノ。主婦ジョバンナはロシア戦線に出たまま音信不通になっている夫アントニオの行方を尋ねようと義母と共に役所に出かけるが、役人は「行方不明」としか答えてくれない。「生きているんでしょ?」と詰め寄るも、軍隊からも本省からも行方不明としか回答がないと役人は繰り返すだけだった。
家に帰って一人の夕食。ジョバンナはアント(彼女はアントニオをこう呼んだ)と出会った頃を思い出す。
逢ったのはジョバンナの故郷ナポリ。浜辺で愛を確かめ合った若い頃、アントは32歳だった。結婚なんかしたくないと言ったアントだったが、婚姻で出征が12日延びると聞いてすぐに結婚をした。ナポリで式を挙げた後、アントの故郷ミラノに向かう列車の中でジョバンナはイアリングをプレゼントされた。
二人は12日間を殆ど家の中で過ごした。それほど二人は愛し合っていたのだ。
やがて休暇も終わる頃、離れがたい二人は一計を案じる。それはアントが気がふれた様に装って更に出征を免れようということだった。街中で刃物を振り回してジョバンナを追い掛け回し警察に捕まる。計略は上手くいったかに思えたが、直ぐにばれる事となった。
『脱走罪で懲役に服すか、ロシア戦線に行くか選びなさい』
戦地に向かうアントとの最期の別れは駅のトイレだった。
裁縫で生計を立てながらミラノで一人待つジョバンナ。
やがて戦争が終わり、ロシア戦線からの復員兵の列車が帰って来るというので、ジョバンナはアントの写真を持ってホームに立った。そこにはやはり同じように写真を抱えた人々が沢山居た。
一人の兵隊がアントの写真を見つけ『アントニオ』と応えた。
ジョバンナは男にアントの事を尋ねた。『生きてる?』
兵隊は人ごみを避けてしばらく歩き、おもむろに重い口を開いた。
『ドン河まではな・・・』
男の話は悲惨なものだった。
辺り一面雪に覆われたロシアの大地で敗色濃厚なイタリア軍は眠る時間もなく敗走を続けていた。四方八方からのロシア軍の攻撃もさることながら、立ち止まることが即ち凍死を意味する程の寒さだった。アントはその兵隊に助けられながら歩き続けたが、ドン河の手前でついに力尽きて倒れてしまったのだ。意識はあったが、アントは男に先に進むように目で合図をした。男は為すすべもなく再び前に向かって歩き出した。この時が男がアントニオを見た最後だった。
ジョバンナはアントを探しにロシアに向かう。外務省を訪ね、役人の支援を仰ぎながらアントが行方不明になった所の近くの村や、戦死したイタリア兵が多く眠る墓地にも行ったが、彼の消息を示すものは何処にも無かった。
記憶を失くしたイタリア人を見かけた事があると噂されたサッカー場にも行ってみたが、スタンドは広すぎて途方に暮れそうだった。試合の終了後に出入口で観客を待っていると、一人のらしき人物を見つけた。後をついていき『イタリア人でしょ?』と声を掛けたが『違う』とロシア語で返答された。
それでも駅の中にまで付いてくるジョバンナに根負けした彼はイタリア語で話しかけてくれた。やはりイタリア人だった。
『田舎は何処なの?』
『今はロシア人だ』
『何故、ここに居るの?』
『何故って?長い話さ。要するにこうなってしまった。それだけの事だ』
ジョバンナはアントニオの写真を見せたが、知らないと彼は言った。『俺もアルプス隊だから嘘はつかない』
『故郷へは?』
『故郷?』つまらぬ冗談を聞いた後のように、或いは何かを諦めたかのように片方の頬に笑みを浮かべながら男は電車に乗ってどこかへ帰って行った。
アントは絶対にどこかに居る。あの男のように、心に傷をもってこのロシアで暮らしているのだ。
ジョバンナは一人で村々を訪ね歩くことにした。すると、とある村で一組の母子がアントの写真に反応した。
その家はすぐ近くにあった。
小さな一軒家で、庭には大きなシーツや洋服などの洗濯物が。そして、洗濯物を取り入れる若い女。ジョバンナの表情に不安がよぎる。正に家庭の匂いがする家だった・・・。
*
高校生の頃は、多分にお涙頂戴映画の一つであると思っていた節があるのですが、後半の夫婦の二度の再会と別れのドラマには、背景にある戦争の残酷さが十分に感じられて、泣くというよりは胸を締め付けられる様でした。ジョバンナはアントニオをなかなか許せなかったみたいですけど、最後の最後には理解したようですね。
コメディのような明るい序盤と、マストロヤンニ、ソフィア・ローレンの悲痛な表情が対照的な後半。
戦闘シーンは殆どなく、当時の記録映像をコラージュのように編集していました。
ロシアの吉永小百合のようなリュドミラ・サベリーエワの哀し気な表情も切ないし、強気なナポリ女が雨の夜の再会前にかつて新婚旅行でプレゼントされたイヤリングを出してくるところも泣かせます。
お勧め度は★三つ半。
1970年のアカデミー賞で作曲賞(ヘンリー・マンシーニ)にノミネートされた音楽で★半分おまけです。
※ 追加記事、ネタバレ備忘録はコチラ。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 

(1965/ジッロ・ポンテコルヴォ監督/脚本:フランコ・ソリナス、撮影:マルチェロ・ガッティ、美術: セルジョ・カネヴァーリ、音楽:エンニオ・モリコーネ/122分)
(↓Twitter on 十瑠 から[一部修正アリ])

 図書館で借りた「アルジェの戦い」を観る。1965年のヴェネチアの金獅子賞でありますな。エイゼンシュタインを彷彿とさせるドキュメンタリータッチで、スケールも、小技も技術的には凌駕していると思うけど、好きかと聞かれればNOだな。
図書館で借りた「アルジェの戦い」を観る。1965年のヴェネチアの金獅子賞でありますな。エイゼンシュタインを彷彿とさせるドキュメンタリータッチで、スケールも、小技も技術的には凌駕していると思うけど、好きかと聞かれればNOだな。
[ 6月25日 以下同じ]
 僕は人間の葛藤を描いたドラマが好きなので、事件を描くのに終始したスタイルは好きじゃない。明らかにアルジェリア側の視点が強いんだが、両者の戦いを冷静に描いていて、かえって抵抗運動がただのテロリズムを描いたような印象もある。どっちもどっちと言いたいし、人間を描く視点としては弱いな。
僕は人間の葛藤を描いたドラマが好きなので、事件を描くのに終始したスタイルは好きじゃない。明らかにアルジェリア側の視点が強いんだが、両者の戦いを冷静に描いていて、かえって抵抗運動がただのテロリズムを描いたような印象もある。どっちもどっちと言いたいし、人間を描く視点としては弱いな。
 「アルジェの戦い」そろそろ返却しないといけない。昨日2回目を観て、やはり違和感は残った。フランス側とアルジェリアのゲリラ的解放戦線との戦いをイタリアが中立的に描いたように見えるが、弱者であるゲリラ側への視点の傾倒は隠せない。一般のフランス系市民への爆弾テロ描写は今は見せられないな。
「アルジェの戦い」そろそろ返却しないといけない。昨日2回目を観て、やはり違和感は残った。フランス側とアルジェリアのゲリラ的解放戦線との戦いをイタリアが中立的に描いたように見えるが、弱者であるゲリラ側への視点の傾倒は隠せない。一般のフランス系市民への爆弾テロ描写は今は見せられないな。
[ 7月 1日 以下同じ]
 物語構成は、ラストシークエンスの一部を最初に見せて、その後そこに至るまでの過程を綴るというワイルダーも使っている手法で作られていて巧い。映像とナレーションとの組み合わせも臨場感があるしネ。終盤の街中に戦車が登場する一連のシーンも、少し前のミャンマーを思い出してしまったよ。
物語構成は、ラストシークエンスの一部を最初に見せて、その後そこに至るまでの過程を綴るというワイルダーも使っている手法で作られていて巧い。映像とナレーションとの組み合わせも臨場感があるしネ。終盤の街中に戦車が登場する一連のシーンも、少し前のミャンマーを思い出してしまったよ。
1965年の製作ですが日本公開は67年、ということで当時映画館でまだ洋画を観てなかった僕は未見のまま。後に映画雑誌で双葉さんが85点(☆☆☆☆★)を付けられていたのを知り無性に観たいと思っておりました。政治的な題材故かレンタルにも見かけることもなく、半ば諦めておりましたら我が福岡市の総合図書館のビデオライブラリーに発見し(しかもDVDだし)、数十年ぶりに念願叶ったわけです。

オープニングがこの(↑)シーン。
右端の青年アリが暫定的な主人公で、次々と逮捕されていく解放戦線の中で唯一最後まで残っていた彼とその仲間が、フランス軍に追い詰められて隠れている所です。
お話の舞台はジャン・ギャバンの「望郷」でもお馴染みのカスバ。
ヤクザ者が隠れるには絶好の場所だったカスバは植民地支配からの脱却をもくろむゲリラ軍にもアジトとしてお誂えの場所だったわけです。
一方、彼らをテロリストとして封じ込めようとやって来たフランス精鋭部隊がコチラ(↓)であります。

先頭のサングラスの強面さんが、実行部隊のマシュー隊長。
第二次世界大戦も戦い抜いた強者で、冷静に相手を分析し、投降に応じない相手にはまさに先の大戦さながらに非情に対処していきます。
マスコミ対応も冷静です(↓)。

最初は、解放戦線はフランス人警官を辻斬りのように一人、二人と殺していくやり方でしたが、フランス本国から手ぬるい対処方法しか許可をもらえなかった現地警察は犯人らがいると思われた地域に爆弾を仕掛けます。つまり爆弾テロはフランス側が先に仕掛けたように描かれていますね。
で、怒った解放戦線も意表をついて、こんな人たち(↓)に爆弾テロをさせます。

彼女らが爆弾入りのバッグを置いて行ったのは、空港のロビーとかレストランとかダンスホール。
それらのシーンもじっくり描かれていますから、昨今の無差別自爆テロまで想起して怖かったですねぇ。
爆弾を使った応酬が始まり収拾がつかなくなりそうになったので、マシューさん達がやって来るのです。
彼らは警察じゃないですからね。軍隊ですから、こんなシーンも点描されます。

映画は1954年から1960年までのアルジェリア独立戦争のアルジェでの戦いを描いていて、一旦は解放軍は制圧されたけれど、その後民衆が蜂起し、エピローグでその2年後1962年に正式に独立したとナレーションされます。
ウィキを読むと分かりますが、130年に及ぶフランスからの植民地支配を覆したわけですから、この独立戦争はもっと複雑な勢力分布と其々の思惑が複雑に絡み合って動いていったと想像できます。ゲリラのやり方も今のイスラム過激派に近かったように記述されていますね。
映画を観る時に作者の視点が自分と合うと面白いと感じますよね。
中には作者の視点が何処にあるのか分からない映画もありますけど、視点を感じて、それが心地よいと何回でも観たくなったりします。
で、ポンテコルヴォのこの映画での視点はというと、言われているようにドキュメンタリー・タッチなのでクールで温かさは感じません。だけどこれでいいのかなぁって思う自分も居るんですよね。
コスタ=ガブラスの「Z」とか「ミッシング」とか、あとパットナムが作った「キリング・フィールド」とか、政治的な事変を描いた作品を幾つか観てますけど、それらの視点には人間への愛情が感じられるんですよね。どんなに惨いシーンがあったにしても、主人公として選んだ人に対しての愛情は感じるんです。
「アルジェの戦い」の視点は人々に対する愛情が薄い感じを受けるんですよねぇ。
ツイッターでの「違和感」というのはその事ですね。なので、お勧め度は世評よりは低くなっちゃいました。
1966年のヴェネチア国際映画祭で、サン・マルコ金獅子賞と国際映画評論家連盟賞を受賞。
米国アカデミー賞では1966年の外国語映画賞、1968年の監督賞と脚本賞にノミネートされるも無冠だったそうです。
※ トレーラーではフランス人はちゃんとフランス語をしゃべってましたけど、レンタルしたDVDでは彼らはイタリア語でした。イタリア製だからそうなのかなと思ってましたけど、どっちなの?
(↓Twitter on 十瑠 から[一部修正アリ])

 図書館で借りた「アルジェの戦い」を観る。1965年のヴェネチアの金獅子賞でありますな。エイゼンシュタインを彷彿とさせるドキュメンタリータッチで、スケールも、小技も技術的には凌駕していると思うけど、好きかと聞かれればNOだな。
図書館で借りた「アルジェの戦い」を観る。1965年のヴェネチアの金獅子賞でありますな。エイゼンシュタインを彷彿とさせるドキュメンタリータッチで、スケールも、小技も技術的には凌駕していると思うけど、好きかと聞かれればNOだな。[ 6月25日 以下同じ]
 僕は人間の葛藤を描いたドラマが好きなので、事件を描くのに終始したスタイルは好きじゃない。明らかにアルジェリア側の視点が強いんだが、両者の戦いを冷静に描いていて、かえって抵抗運動がただのテロリズムを描いたような印象もある。どっちもどっちと言いたいし、人間を描く視点としては弱いな。
僕は人間の葛藤を描いたドラマが好きなので、事件を描くのに終始したスタイルは好きじゃない。明らかにアルジェリア側の視点が強いんだが、両者の戦いを冷静に描いていて、かえって抵抗運動がただのテロリズムを描いたような印象もある。どっちもどっちと言いたいし、人間を描く視点としては弱いな。 「アルジェの戦い」そろそろ返却しないといけない。昨日2回目を観て、やはり違和感は残った。フランス側とアルジェリアのゲリラ的解放戦線との戦いをイタリアが中立的に描いたように見えるが、弱者であるゲリラ側への視点の傾倒は隠せない。一般のフランス系市民への爆弾テロ描写は今は見せられないな。
「アルジェの戦い」そろそろ返却しないといけない。昨日2回目を観て、やはり違和感は残った。フランス側とアルジェリアのゲリラ的解放戦線との戦いをイタリアが中立的に描いたように見えるが、弱者であるゲリラ側への視点の傾倒は隠せない。一般のフランス系市民への爆弾テロ描写は今は見せられないな。[ 7月 1日 以下同じ]
 物語構成は、ラストシークエンスの一部を最初に見せて、その後そこに至るまでの過程を綴るというワイルダーも使っている手法で作られていて巧い。映像とナレーションとの組み合わせも臨場感があるしネ。終盤の街中に戦車が登場する一連のシーンも、少し前のミャンマーを思い出してしまったよ。
物語構成は、ラストシークエンスの一部を最初に見せて、その後そこに至るまでの過程を綴るというワイルダーも使っている手法で作られていて巧い。映像とナレーションとの組み合わせも臨場感があるしネ。終盤の街中に戦車が登場する一連のシーンも、少し前のミャンマーを思い出してしまったよ。*
1965年の製作ですが日本公開は67年、ということで当時映画館でまだ洋画を観てなかった僕は未見のまま。後に映画雑誌で双葉さんが85点(☆☆☆☆★)を付けられていたのを知り無性に観たいと思っておりました。政治的な題材故かレンタルにも見かけることもなく、半ば諦めておりましたら我が福岡市の総合図書館のビデオライブラリーに発見し(しかもDVDだし)、数十年ぶりに念願叶ったわけです。

オープニングがこの(↑)シーン。
右端の青年アリが暫定的な主人公で、次々と逮捕されていく解放戦線の中で唯一最後まで残っていた彼とその仲間が、フランス軍に追い詰められて隠れている所です。
お話の舞台はジャン・ギャバンの「望郷」でもお馴染みのカスバ。
ヤクザ者が隠れるには絶好の場所だったカスバは植民地支配からの脱却をもくろむゲリラ軍にもアジトとしてお誂えの場所だったわけです。
一方、彼らをテロリストとして封じ込めようとやって来たフランス精鋭部隊がコチラ(↓)であります。

先頭のサングラスの強面さんが、実行部隊のマシュー隊長。
第二次世界大戦も戦い抜いた強者で、冷静に相手を分析し、投降に応じない相手にはまさに先の大戦さながらに非情に対処していきます。
マスコミ対応も冷静です(↓)。

最初は、解放戦線はフランス人警官を辻斬りのように一人、二人と殺していくやり方でしたが、フランス本国から手ぬるい対処方法しか許可をもらえなかった現地警察は犯人らがいると思われた地域に爆弾を仕掛けます。つまり爆弾テロはフランス側が先に仕掛けたように描かれていますね。
で、怒った解放戦線も意表をついて、こんな人たち(↓)に爆弾テロをさせます。

彼女らが爆弾入りのバッグを置いて行ったのは、空港のロビーとかレストランとかダンスホール。
それらのシーンもじっくり描かれていますから、昨今の無差別自爆テロまで想起して怖かったですねぇ。
爆弾を使った応酬が始まり収拾がつかなくなりそうになったので、マシューさん達がやって来るのです。
彼らは警察じゃないですからね。軍隊ですから、こんなシーンも点描されます。

映画は1954年から1960年までのアルジェリア独立戦争のアルジェでの戦いを描いていて、一旦は解放軍は制圧されたけれど、その後民衆が蜂起し、エピローグでその2年後1962年に正式に独立したとナレーションされます。
ウィキを読むと分かりますが、130年に及ぶフランスからの植民地支配を覆したわけですから、この独立戦争はもっと複雑な勢力分布と其々の思惑が複雑に絡み合って動いていったと想像できます。ゲリラのやり方も今のイスラム過激派に近かったように記述されていますね。
*
映画を観る時に作者の視点が自分と合うと面白いと感じますよね。
中には作者の視点が何処にあるのか分からない映画もありますけど、視点を感じて、それが心地よいと何回でも観たくなったりします。
で、ポンテコルヴォのこの映画での視点はというと、言われているようにドキュメンタリー・タッチなのでクールで温かさは感じません。だけどこれでいいのかなぁって思う自分も居るんですよね。
コスタ=ガブラスの「Z」とか「ミッシング」とか、あとパットナムが作った「キリング・フィールド」とか、政治的な事変を描いた作品を幾つか観てますけど、それらの視点には人間への愛情が感じられるんですよね。どんなに惨いシーンがあったにしても、主人公として選んだ人に対しての愛情は感じるんです。
「アルジェの戦い」の視点は人々に対する愛情が薄い感じを受けるんですよねぇ。
ツイッターでの「違和感」というのはその事ですね。なので、お勧め度は世評よりは低くなっちゃいました。
1966年のヴェネチア国際映画祭で、サン・マルコ金獅子賞と国際映画評論家連盟賞を受賞。
米国アカデミー賞では1966年の外国語映画賞、1968年の監督賞と脚本賞にノミネートされるも無冠だったそうです。
※ トレーラーではフランス人はちゃんとフランス語をしゃべってましたけど、レンタルしたDVDでは彼らはイタリア語でした。イタリア製だからそうなのかなと思ってましたけど、どっちなの?
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(2013/山崎貴:監督・共同脚本/岡田准一、井上真央、三浦春馬、吹石一恵、風吹ジュン、夏八木勲、濱田岳、橋爪功、新井浩文、田中泯、染谷将太、三浦貴大、上田竜也、山本學、平幹二朗、斉藤とも子、平岳大、駿河太郎、鈴木ちなみ/144分)
去年か一昨年だったか息子が友達と映画館で観て感激して帰ってきた作品で、この正月休みに帰省した時も、もう一度観ようと(或いは僕等に見せようとして)レンタルしてきたが、結局奴は観らずに名古屋に帰って行った。5日だったか娘が夜中に独りで観ていて、僕がトイレに起きてきたらキッチンで鉢合わせ、『後半号泣やった』と赤い目をしていた。映画関係のブログではそれ程好評でもないので期待は無かったが、返却日に時間が出来たので観ることにした。
 冒頭、敵艦の機銃掃射を海上すれすれの低空飛行で避けている零戦のショットが数秒続いた後、時代は太平洋戦争から現代に移る。
冒頭、敵艦の機銃掃射を海上すれすれの低空飛行で避けている零戦のショットが数秒続いた後、時代は太平洋戦争から現代に移る。
弁護士資格を望みながらもう4回も司法試験に落ち続けている佐伯健太郎(三浦)の祖母の葬儀のシーンが物語の幕開けだ。
喪主は夏八木勲扮する賢一郎で、直会(なおらい)の席で孫である健太郎は姉の慶子(吹石)、母の清子(風吹)から、お祖父ちゃんの賢一郎とは血縁関係がなく若くして戦死した実の祖父が別に居たことを聞かされる。
実の祖父の名は宮部久蔵(岡田)。
祖母松乃(井上)との結婚生活は4年足らず、26歳の若さで南太平洋で特攻隊員として亡くなっていた。
母の清子も久蔵について松乃から聞いた事が無く実の祖父について無知であった。清子に頼まれたこともあり、ルポライターを目指している慶子は健太郎にもバイト代を出すからと言って宮部久蔵の人生について調べることにした。ネットで戦友会のサイトをたよりに祖父を知っていそうな人物に手紙を書いたのだ。
最初に訪れた長谷川(平幹二朗)には、宮部は命を惜しんでばかりの男だったと言われた。片腕を戦争で無くしていた長谷川は祖父を憎んでもいたようである。その後に面会した人々からも祖父について良い話は聞かなかった。臆病者で、敵との戦いを避けてばかりいたなどとも言われた。
健太郎がこの調査にうんざりしてきた頃、見るからに世間の裏街道を歩んできたような男に会うことになった。男は景浦(田中)といった。健太郎は又しても祖父を罵倒されるかと思ったが、景浦は『(宮部を)臆病者という奴とは話をしない』と追い返された。
次に会ったのは末期がんで入院中の井崎(橋爪)だった。井崎には宮部さんは凄腕のパイロットだったと言われた。井崎は宮部の部下であり、身近に接していた男だった。宮部さんは飛行機乗りとしても戦闘員としても優秀だったが、その言動には違和感があったとも言った。
軍人は祖国の為に死ぬ事が立派だとされた時代に、宮部は生きて帰ることを願っていたからだ。それは周りの兵隊達にも感ぜられ、井崎は宮部と親しく接しないようにと忠告された。
やがて井崎は宮部が妻と生まれたばかりの娘の為に生きる事を優先している事を知る。宮部は戦闘訓練だけではなく、自身の身体の鍛錬も怠りなくやる男だった。しかも宮部は自己保身だけの男ではなかった。死ぬ事が惜しくないという井崎に、お前が死んで悲しむ人間がいるんじゃないのか、その人の為に生き抜く事を考えろと叱る上官だった。その姿勢はその後もずっと変わらなかった。
戦後の日本の為に我々は生き残るべきなんだ、そう宮部は言うのである・・・。

この映画の面白さの最大の要因は原作に由来するプロットの巧さでしょうな。つまり岡田扮する飛行機乗りを過去の話として、現代の彼の孫である三浦春馬がお爺ちゃんの過去を調べるという二重構造になっており、過去の調査が謎解きになっている事。
生きて家族の元に帰る事を念願していた宮部久蔵が、何故特攻隊員として散っていったのか?
謎解きは本でも映画でもサスペンスを生みますからな。
それと真珠湾攻撃などの特撮シーン(VFXというらしい)の違和感のない迫力は、かつてミニチュアを使った特撮を見せられたオジサンには大満足でした。戦闘機モノの漫画に夢中になった世代にはあの空中戦も大満足であります。
500万部に迫る大ベストセラーの百田尚樹の原作は読んでいませんが、多分映画と同じく登場人物に目新しい人物像は出てこないのではないでしょうか。
どれもどこかで見たことのある人物ばかりだし切り取り方も型通り。それでも2時間半近くを特段の緩みなく見せたのは先にも書いたように巧妙なプロットを生かしたスピーディーな語り口ゆえでしょう。
それにしても弁護士を目指しながら何度も司法試験を落ちているという三浦春馬扮する孫の存在感が薄いなぁ。とても重要な人間なのに演技力なのか雰囲気なのか分からんけれど、軽すぎる。
お勧め度は★二つ半。おまけして★三つにしときましょ。
▼(ネタバレ注意)
1回目の鑑賞の途中で、あれっ実のお祖父ちゃんの事を調べるならまず今のお祖父ちゃんに聞くのが先決でしょうと思っていたら、もう一度最初の方を見直すとちゃんと聞きに行ってましたな、実のお祖父ちゃんについて調べていいかと。賢一郎祖父ちゃんは宮部さんの事を調べるのは孫達にとっても良いことだと許しますが、自分が知っている過去の真実の告白はしませんでした。
賢一郎の知らない宮部像もあるかも知れないし、他人から聞くのもイイと判断したのかもしれません。なにせ、慶子は半分は仕事として着手していたのですから。
それと序盤のシーンを見直していたら葬儀場の案内に「大石松乃」と書かれていました。小説を読んだ人には当たり前ですが、未読の人にはネタバレでしたね。
ユーモアは皆無のこの映画で、唯一笑っちゃった所がありました。田中民扮するやくざの親分が再登場するエピソードで、別れ際に三浦君をハグして「俺は若い男が好きなんだ」と言う所です。あれって単純に人間として言っているのか、カミングアウトしているのか?僕は後者に感じちゃったんですよね。なんか変な感じ。
▲(解除)
ウィキを読んでいたら、否定的評価の段で<作家の石田衣良は、山田宗樹著『百年法』などと共に愛国心を強める作品として「右傾エンタメ」という造語を用いて批判し、「かわいそうというセンチメントだけで読まれている」「読者の心のあり方がゆったりと右傾化しているのでは」と主張した>と書かれていた。
僕らの子供の頃には「コンバット」とかの戦争ものが毎週のように放送されていましたが、誰も右傾化なんて言わなかったと思うけどなぁ。むしろ当時の小学校の担任からは、「コンバット」は観た方がいいとまで言われてた。先生はハードなヒューマニズムを評価していたんだと思うけど。
そして戦争を体験していない井筒和幸は<自身のラジオ番組で「見たことを記憶から消したくなる映画」と述べ、主人公の人物像についても「そんなわけない」と主張した。ストーリーや登場人物が実在しないのに、有り得ない内容で特攻隊を美化していると非難している>らしい。
同じウィキの肯定的評価の段では、元零戦搭乗員や特攻隊を拒否した戦争経験者が「宮部のような人物が確かにいた」と話しているのだが。
去年か一昨年だったか息子が友達と映画館で観て感激して帰ってきた作品で、この正月休みに帰省した時も、もう一度観ようと(或いは僕等に見せようとして)レンタルしてきたが、結局奴は観らずに名古屋に帰って行った。5日だったか娘が夜中に独りで観ていて、僕がトイレに起きてきたらキッチンで鉢合わせ、『後半号泣やった』と赤い目をしていた。映画関係のブログではそれ程好評でもないので期待は無かったが、返却日に時間が出来たので観ることにした。
*
 冒頭、敵艦の機銃掃射を海上すれすれの低空飛行で避けている零戦のショットが数秒続いた後、時代は太平洋戦争から現代に移る。
冒頭、敵艦の機銃掃射を海上すれすれの低空飛行で避けている零戦のショットが数秒続いた後、時代は太平洋戦争から現代に移る。弁護士資格を望みながらもう4回も司法試験に落ち続けている佐伯健太郎(三浦)の祖母の葬儀のシーンが物語の幕開けだ。
喪主は夏八木勲扮する賢一郎で、直会(なおらい)の席で孫である健太郎は姉の慶子(吹石)、母の清子(風吹)から、お祖父ちゃんの賢一郎とは血縁関係がなく若くして戦死した実の祖父が別に居たことを聞かされる。
実の祖父の名は宮部久蔵(岡田)。
祖母松乃(井上)との結婚生活は4年足らず、26歳の若さで南太平洋で特攻隊員として亡くなっていた。
母の清子も久蔵について松乃から聞いた事が無く実の祖父について無知であった。清子に頼まれたこともあり、ルポライターを目指している慶子は健太郎にもバイト代を出すからと言って宮部久蔵の人生について調べることにした。ネットで戦友会のサイトをたよりに祖父を知っていそうな人物に手紙を書いたのだ。
最初に訪れた長谷川(平幹二朗)には、宮部は命を惜しんでばかりの男だったと言われた。片腕を戦争で無くしていた長谷川は祖父を憎んでもいたようである。その後に面会した人々からも祖父について良い話は聞かなかった。臆病者で、敵との戦いを避けてばかりいたなどとも言われた。
健太郎がこの調査にうんざりしてきた頃、見るからに世間の裏街道を歩んできたような男に会うことになった。男は景浦(田中)といった。健太郎は又しても祖父を罵倒されるかと思ったが、景浦は『(宮部を)臆病者という奴とは話をしない』と追い返された。
次に会ったのは末期がんで入院中の井崎(橋爪)だった。井崎には宮部さんは凄腕のパイロットだったと言われた。井崎は宮部の部下であり、身近に接していた男だった。宮部さんは飛行機乗りとしても戦闘員としても優秀だったが、その言動には違和感があったとも言った。
軍人は祖国の為に死ぬ事が立派だとされた時代に、宮部は生きて帰ることを願っていたからだ。それは周りの兵隊達にも感ぜられ、井崎は宮部と親しく接しないようにと忠告された。
やがて井崎は宮部が妻と生まれたばかりの娘の為に生きる事を優先している事を知る。宮部は戦闘訓練だけではなく、自身の身体の鍛錬も怠りなくやる男だった。しかも宮部は自己保身だけの男ではなかった。死ぬ事が惜しくないという井崎に、お前が死んで悲しむ人間がいるんじゃないのか、その人の為に生き抜く事を考えろと叱る上官だった。その姿勢はその後もずっと変わらなかった。
戦後の日本の為に我々は生き残るべきなんだ、そう宮部は言うのである・・・。

この映画の面白さの最大の要因は原作に由来するプロットの巧さでしょうな。つまり岡田扮する飛行機乗りを過去の話として、現代の彼の孫である三浦春馬がお爺ちゃんの過去を調べるという二重構造になっており、過去の調査が謎解きになっている事。
生きて家族の元に帰る事を念願していた宮部久蔵が、何故特攻隊員として散っていったのか?
謎解きは本でも映画でもサスペンスを生みますからな。
それと真珠湾攻撃などの特撮シーン(VFXというらしい)の違和感のない迫力は、かつてミニチュアを使った特撮を見せられたオジサンには大満足でした。戦闘機モノの漫画に夢中になった世代にはあの空中戦も大満足であります。
500万部に迫る大ベストセラーの百田尚樹の原作は読んでいませんが、多分映画と同じく登場人物に目新しい人物像は出てこないのではないでしょうか。
どれもどこかで見たことのある人物ばかりだし切り取り方も型通り。それでも2時間半近くを特段の緩みなく見せたのは先にも書いたように巧妙なプロットを生かしたスピーディーな語り口ゆえでしょう。
それにしても弁護士を目指しながら何度も司法試験を落ちているという三浦春馬扮する孫の存在感が薄いなぁ。とても重要な人間なのに演技力なのか雰囲気なのか分からんけれど、軽すぎる。
お勧め度は★二つ半。おまけして★三つにしときましょ。
▼(ネタバレ注意)
1回目の鑑賞の途中で、あれっ実のお祖父ちゃんの事を調べるならまず今のお祖父ちゃんに聞くのが先決でしょうと思っていたら、もう一度最初の方を見直すとちゃんと聞きに行ってましたな、実のお祖父ちゃんについて調べていいかと。賢一郎祖父ちゃんは宮部さんの事を調べるのは孫達にとっても良いことだと許しますが、自分が知っている過去の真実の告白はしませんでした。
賢一郎の知らない宮部像もあるかも知れないし、他人から聞くのもイイと判断したのかもしれません。なにせ、慶子は半分は仕事として着手していたのですから。
それと序盤のシーンを見直していたら葬儀場の案内に「大石松乃」と書かれていました。小説を読んだ人には当たり前ですが、未読の人にはネタバレでしたね。
ユーモアは皆無のこの映画で、唯一笑っちゃった所がありました。田中民扮するやくざの親分が再登場するエピソードで、別れ際に三浦君をハグして「俺は若い男が好きなんだ」と言う所です。あれって単純に人間として言っているのか、カミングアウトしているのか?僕は後者に感じちゃったんですよね。なんか変な感じ。
▲(解除)
ウィキを読んでいたら、否定的評価の段で<作家の石田衣良は、山田宗樹著『百年法』などと共に愛国心を強める作品として「右傾エンタメ」という造語を用いて批判し、「かわいそうというセンチメントだけで読まれている」「読者の心のあり方がゆったりと右傾化しているのでは」と主張した>と書かれていた。
僕らの子供の頃には「コンバット」とかの戦争ものが毎週のように放送されていましたが、誰も右傾化なんて言わなかったと思うけどなぁ。むしろ当時の小学校の担任からは、「コンバット」は観た方がいいとまで言われてた。先生はハードなヒューマニズムを評価していたんだと思うけど。
そして戦争を体験していない井筒和幸は<自身のラジオ番組で「見たことを記憶から消したくなる映画」と述べ、主人公の人物像についても「そんなわけない」と主張した。ストーリーや登場人物が実在しないのに、有り得ない内容で特攻隊を美化していると非難している>らしい。
同じウィキの肯定的評価の段では、元零戦搭乗員や特攻隊を拒否した戦争経験者が「宮部のような人物が確かにいた」と話しているのだが。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(2008/キャスリン・ビグロー製作・監督/ジェレミー・レナー、アンソニー・マッキー、ブライアン・ジェラティ、レイフ・ファインズ、ガイ・ピアース、デヴィッド・モース/131分)
2009年のアカデミー賞で9部門にノミネート、作品賞、監督賞、脚本賞、編集賞、音響賞(編集)、音響賞(調整)の6部門で受賞した記憶されるべき作品ですが、この年はジェームズ・キャメロンの話題作「アバター」も9部門にノミネートされ、監督のキャスリン・ビグローがキャメロンの元妻だったこともあり元夫婦対決としてマスコミは面白がって書いておりました。
結果はご覧の通り、主要部門を今作品が獲って元妻の勝ち。しかしながら両作品を観た者から言わせて貰えば、劇場用映画としてのお薦め度は元夫の「アバター」に軍配を挙げたいですな。
 フセイン大統領を失脚させるべくアメリカが軍事介入したイラク戦争の開始から1年を過ぎたあたりの、2004年のバグダッドが舞台。自爆テロも含めてバグダッドでは爆弾を使った事件が多数発生しており、この映画は、アメリカ軍の爆弾処理部隊の活動をセミ・ドキュメンタリータッチで描いた作品であります。
フセイン大統領を失脚させるべくアメリカが軍事介入したイラク戦争の開始から1年を過ぎたあたりの、2004年のバグダッドが舞台。自爆テロも含めてバグダッドでは爆弾を使った事件が多数発生しており、この映画は、アメリカ軍の爆弾処理部隊の活動をセミ・ドキュメンタリータッチで描いた作品であります。
ドキュメンタリータッチの映画ということではカンボジア内戦が背景の「キリング・フィールド」を思い出しますが、あれに比べると明らかにこの映画の印象は弱い。というのも、「キリング・フィールド」には内戦状態に入った危険なカンボジアから米国のジャーナリストが無事に脱出できるかというスリルが前半にあり、後半にはジャーナリストの逃げ遅れた現地の友人のポルポト軍事政権下からの必死の逃避行があり、ドラマの軸がしっかり出来ているからです。観客もストーリーの流れを見失うことはない。
「ハート・ロッカー」が描いているのは、明日の予定も立てようがない爆弾処理部隊の日々で、あえてドラマチックな局面は作らないようにしている感がある。そういう意味ではドキュメンタリータッチの映像は狙いにマッチしているが、いかんせんそれだけでは2時間を超える上映時間を面白く見せるのは些か辛い。
シークエンスはあるがストーリーは無い。そんな感じの作品なのです。
ドキュメンタリー・タッチというのは主に映像の印象からくるものだと思うけど、一般ドラマで使われるドキュメンタリータッチは、この作品を観れば分かるように、概ねハンディカメラの揺れる映像で、激しいパンやズームアップ、ズームアウトが移動撮影と併せて多用されている。要するに、ニュース映像や個人的なビデオ撮影の映像に似ているから、生の事象の撮影に近いと感じるのでしょう。
主な登場人物は、オスカー主演男優賞にもノミネートされたジェレミー・レナー扮する爆弾処理の専門家ジェームズ軍曹と同じ部隊のサンポーン軍曹(マッキー)、それと同部隊の技術兵エルドリッジ(ジェラティ)。
冒頭で定石通りに爆弾処理の一幕があり、その時はガイ・ピアース扮するトンプソン軍曹が一般道路に仕掛けられた爆弾を爆発しないように処理するが、携帯電話を使った爆弾だったので、退避が間に合わずにトンプソンは死亡する。このトンプソンに替わってジェームズが赴任してくるわけです。「ダーティハリー」の冒頭の銀行強盗のシーンと同じく、主人公達を簡潔にして要領よく紹介しながら、併せて爆弾処理の難しさ、危険の大きさを感じさせ、その後の鑑賞者への影響を与える良いシーンでありました。
ジェームズ軍曹の爆弾処理は大胆だが、補佐するサンボーン達を無視するような態度をとるので幾度かは衝突もする。ストーリー的な楽しみを見出すとしたら、この三人の関係の進展具合でしょうか。そして、<ブラボー中隊、任務明けまで -○○日>と出る、時間経過の字幕。任務明けまでの日数が減っていくたびに、今日は彼等に何か起きるんではないか、そう思わせてしまう効果がありましたね。
ストーリーは無いと書いたけれど、中盤から後半にかけて、ジェームズが顔見知りになった基地の近くで海賊版のDVDを売っているサッカー好きの少年との絡みのエピソードがあって、ある局面だけ彼がまるでジャック・バウアーのような動きを見せる。ドキュメンタリータッチで描かれている中で少し違和感を感じさせるものでありました。
“戦闘での高揚感は、ときに激しい中毒となる。戦争は麻薬である”
ピューリッツア賞を受賞したアメリカのジャーナリスト、クリス・ヘッジズの言葉が冒頭で映し出されるけれど、ラストシーンは、任務明けから家族との束の間の休暇を過ごした後のジェームズが再びイラクで爆弾処理をしている所なので、つまりジェームズは中毒なのだといっているように見えます。
反戦映画には間違いないんでしょうが、ジェームズがヒーローに見えなくも無いので、作者の意図が何処まで実現できたのか疑問ではありますね。
いっそのこと爆弾処理班を取材したドキュメンタリー映画の方が面白いものが出来たんじゃないかとさえ思ってしまいました。現場の兵隊と、国際情勢を俯瞰で捉えたストーリーを絡めれば、反戦の意図も明確になったのではないかとも・・・。
2009年のアカデミー賞で9部門にノミネート、作品賞、監督賞、脚本賞、編集賞、音響賞(編集)、音響賞(調整)の6部門で受賞した記憶されるべき作品ですが、この年はジェームズ・キャメロンの話題作「アバター」も9部門にノミネートされ、監督のキャスリン・ビグローがキャメロンの元妻だったこともあり元夫婦対決としてマスコミは面白がって書いておりました。
結果はご覧の通り、主要部門を今作品が獲って元妻の勝ち。しかしながら両作品を観た者から言わせて貰えば、劇場用映画としてのお薦め度は元夫の「アバター」に軍配を挙げたいですな。
*
 フセイン大統領を失脚させるべくアメリカが軍事介入したイラク戦争の開始から1年を過ぎたあたりの、2004年のバグダッドが舞台。自爆テロも含めてバグダッドでは爆弾を使った事件が多数発生しており、この映画は、アメリカ軍の爆弾処理部隊の活動をセミ・ドキュメンタリータッチで描いた作品であります。
フセイン大統領を失脚させるべくアメリカが軍事介入したイラク戦争の開始から1年を過ぎたあたりの、2004年のバグダッドが舞台。自爆テロも含めてバグダッドでは爆弾を使った事件が多数発生しており、この映画は、アメリカ軍の爆弾処理部隊の活動をセミ・ドキュメンタリータッチで描いた作品であります。ドキュメンタリータッチの映画ということではカンボジア内戦が背景の「キリング・フィールド」を思い出しますが、あれに比べると明らかにこの映画の印象は弱い。というのも、「キリング・フィールド」には内戦状態に入った危険なカンボジアから米国のジャーナリストが無事に脱出できるかというスリルが前半にあり、後半にはジャーナリストの逃げ遅れた現地の友人のポルポト軍事政権下からの必死の逃避行があり、ドラマの軸がしっかり出来ているからです。観客もストーリーの流れを見失うことはない。
「ハート・ロッカー」が描いているのは、明日の予定も立てようがない爆弾処理部隊の日々で、あえてドラマチックな局面は作らないようにしている感がある。そういう意味ではドキュメンタリータッチの映像は狙いにマッチしているが、いかんせんそれだけでは2時間を超える上映時間を面白く見せるのは些か辛い。
シークエンスはあるがストーリーは無い。そんな感じの作品なのです。
ドキュメンタリー・タッチというのは主に映像の印象からくるものだと思うけど、一般ドラマで使われるドキュメンタリータッチは、この作品を観れば分かるように、概ねハンディカメラの揺れる映像で、激しいパンやズームアップ、ズームアウトが移動撮影と併せて多用されている。要するに、ニュース映像や個人的なビデオ撮影の映像に似ているから、生の事象の撮影に近いと感じるのでしょう。
主な登場人物は、オスカー主演男優賞にもノミネートされたジェレミー・レナー扮する爆弾処理の専門家ジェームズ軍曹と同じ部隊のサンポーン軍曹(マッキー)、それと同部隊の技術兵エルドリッジ(ジェラティ)。
冒頭で定石通りに爆弾処理の一幕があり、その時はガイ・ピアース扮するトンプソン軍曹が一般道路に仕掛けられた爆弾を爆発しないように処理するが、携帯電話を使った爆弾だったので、退避が間に合わずにトンプソンは死亡する。このトンプソンに替わってジェームズが赴任してくるわけです。「ダーティハリー」の冒頭の銀行強盗のシーンと同じく、主人公達を簡潔にして要領よく紹介しながら、併せて爆弾処理の難しさ、危険の大きさを感じさせ、その後の鑑賞者への影響を与える良いシーンでありました。
ジェームズ軍曹の爆弾処理は大胆だが、補佐するサンボーン達を無視するような態度をとるので幾度かは衝突もする。ストーリー的な楽しみを見出すとしたら、この三人の関係の進展具合でしょうか。そして、<ブラボー中隊、任務明けまで -○○日>と出る、時間経過の字幕。任務明けまでの日数が減っていくたびに、今日は彼等に何か起きるんではないか、そう思わせてしまう効果がありましたね。
ストーリーは無いと書いたけれど、中盤から後半にかけて、ジェームズが顔見知りになった基地の近くで海賊版のDVDを売っているサッカー好きの少年との絡みのエピソードがあって、ある局面だけ彼がまるでジャック・バウアーのような動きを見せる。ドキュメンタリータッチで描かれている中で少し違和感を感じさせるものでありました。
“戦闘での高揚感は、ときに激しい中毒となる。戦争は麻薬である”
ピューリッツア賞を受賞したアメリカのジャーナリスト、クリス・ヘッジズの言葉が冒頭で映し出されるけれど、ラストシーンは、任務明けから家族との束の間の休暇を過ごした後のジェームズが再びイラクで爆弾処理をしている所なので、つまりジェームズは中毒なのだといっているように見えます。
反戦映画には間違いないんでしょうが、ジェームズがヒーローに見えなくも無いので、作者の意図が何処まで実現できたのか疑問ではありますね。
いっそのこと爆弾処理班を取材したドキュメンタリー映画の方が面白いものが出来たんじゃないかとさえ思ってしまいました。現場の兵隊と、国際情勢を俯瞰で捉えたストーリーを絡めれば、反戦の意図も明確になったのではないかとも・・・。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(1956/ロベール・ブレッソン監督・脚本/フランソワ・ルテリエ、シャルル・ル・クランシュ、モーリス・ベアブロック、ローラン・モノー/100分)
高校に入学した頃から読み出した「SCREEN」で、滋野辰彦さんは双葉十三郎さんの次によく読んでいた評論家だった。演出についての考察が多く、「抵抗」も何度か取り上げられていたので当時から興味があったが、TVで放送されることはまず無かった。ロベール・ブレッソンの名前もこの「抵抗」という作品で初めて知ったと思う。そんな高校生の頃、製作より6年後に公開されたロバが主人公の「バルタザールどこへ行く(1964)」が「SCREEN」の批評家年間ベストテンで上位にランクインし、ブレッソンの名前は深く記憶に刻まれることになった。
「抵抗」は、第二次世界大戦中の実話を基にした映画で、ナチスドイツの占領下にあったフランスで、レジスタンス活動をしていたフランス人青年がゲシュタポに捕まり、収容された刑務所から脱獄する話です。
昔はただ「抵抗」というタイトルだけでしたが、最近は「抵抗(レジスタンス)-死刑囚の手記より-」と長たらしい名前になったようです。実際、原題は『死刑囚は逃げた、あるいは、風は己の望む所に吹く』との事。つまり脱獄は成功するってことです。そして『風は己の望む所に吹く』というのは、「天は自ら助くる者を助く」と同じ意味だと思われます。なんだか努力すれば夢は叶うみたいな話に聞こえますが・・・。
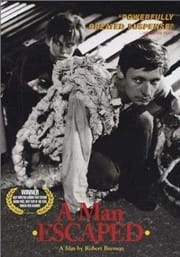 1943年、フランス第2の都市リヨン。ナチスドイツに抵抗するフランス軍中尉フォンテーヌは車で連行されるところだった。信号で止まった時に、あわよくば逃げようかと機会を狙っていたが、一旦は車を飛び出したものの後続車のゲシュタポに捕まり、拳銃で頭を殴られて刑務所に収容されることになった。
1943年、フランス第2の都市リヨン。ナチスドイツに抵抗するフランス軍中尉フォンテーヌは車で連行されるところだった。信号で止まった時に、あわよくば逃げようかと機会を狙っていたが、一旦は車を飛び出したものの後続車のゲシュタポに捕まり、拳銃で頭を殴られて刑務所に収容されることになった。
収容所でも拷問付きの尋問を受けて、担架で放り込まれるように独房に入れられた。両手には手錠が掛けられ、アチコチが痛み、頭からも出血していた。翌日、又も尋問を受けそうになったが、疲労困憊している風を装ったらそのままにしておいてくれた。ひょっとしたら、あのまま房を出て行ったら殺されていたかも知れない。
周りをコンクリートの壁で囲まれた小さな独房。トイレ用の大きなブリキの缶と洗面器代わりの小さな缶、粗末なベッドと毛布が与えられた。出入口とは反対側の壁の高い所に小さな窓があり、明かりはそこからしか届かなかった。
隣の囚人と壁を叩くことで会話が出来るようになり、手錠を安全ピン一つで外す方法も教えてもらった。高窓とベッドの中間あたりの壁に小さな台が付いており、その台に上ると窓から外を見ることが出来た。窓の外は刑務所の中庭であり、平服を着たフランス人の囚人が三人散歩をしていた。その内の一人と会話を交わし、安全ピンや紙、鉛筆を調達してもらった。
捕まって4日目。近くのホテルにあるゲシュタポ本部へ連行されて尋問を受け、刑務所に戻ると最上階の3階の独房107号室に移されることとなった。手錠も解かれ、4日ぶりに食べ物にもありつける事が出来たが、それは缶に入ったスープで、あっという間に無くなってしまった。
3階には大勢のフランス人が収容されていたが、彼等と会うのは、朝のひと時しかなかった。一列に並んで歩き、房から持ってきたバケツの排泄物を捨て、洗面所で顔を洗う。『しゃべるな!』とドイツ兵に言われるので、小声で手短に話すしかなかった。
隣の106号室は空室のようで、反対側の108号室には老人が居た。壁を叩いて合図を送ったが、老人からは反応がなかった。高窓越しに声を掛けてみたが、老人は生きる気力を無くしかけていた。
偶然からフォンテーヌは脱獄のきっかけを得る。暇をもてあまし、何の気なしに出入口の木製の扉を見ていた彼は、扉が小さな6枚の板が2段になって組み合わせられた物であることに気付き、継ぎ目を開いていけば人が通る事が出来るのではないかと思い始めたのだ。その巾は3枚分の板で十分だった。
毎回の食事にはスプーンが付いていたが、ある時、スプーンを忘れたふりをして缶だけを看守に返したら気付かれなかった。成功だ。スプーンの食物を掬う方を持って、反対側を床のコンクリートで削った。それはノミのように鋭くなり、木製扉の継ぎ目を削るのに丁度良い道具となった。幸いにして看守は1階にしか居なかったが、時に見回りに来ることもあり、物音には敏感にならざるを得なかった。こうして、フォンテーヌの命を懸けた抵抗が始まるのである・・・。
全編、主人公のモノローグでストーリーが進行される為、内面の葛藤がひしひしと伝わります。ロングショットは皆無に近く、殆どのショットがバストショット以上のアップで撮られているため、息を呑むような緊迫感が漂っています。映画で結末が分かっていては面白くないと言う人がいますが、映画は描写ですから、映像から伝わる緊張感、葛藤を素直に感じとればいいんです。
画面は主人公を中心に展開しており、敵方のドイツ兵の様子は殆ど描かれません。刑務所の描写もフォンテーヌが見れる範囲でしか描かれません。狭い視界。しかし、ドイツ兵の足音、中庭で行われているであろう銃殺刑での銃声等により、空間の広がりを感じさせるようになっています。終盤の脱出シーンでは、近くを通っているであろう列車の音が聞こえてきて、解放への望みが膨らんでいく気分になります。
1957年のカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞したモノクロ作品。現代の刺激的なカメラワークに慣らされた観客には、この品の良い感覚は物足りなさを感じるかもしれませんな。
(↓Twitter on 十瑠 より)
 9日に届いていたブレッソンの「抵抗」を午後のひと時に観る。この映画、以前観たのか、初見なのかあやふやなんだが(冒頭の車のシーンに既視感が)、とりあえず予想通りの印象だった。ブレッソンらしいシンプルでスマートな作り方。時にヒッチコックをも連想させた。台詞がなくても観れるな。
9日に届いていたブレッソンの「抵抗」を午後のひと時に観る。この映画、以前観たのか、初見なのかあやふやなんだが(冒頭の車のシーンに既視感が)、とりあえず予想通りの印象だった。ブレッソンらしいシンプルでスマートな作り方。時にヒッチコックをも連想させた。台詞がなくても観れるな。
[2月 23日 以下同じ]
 ブレッソンの「抵抗」、ロングショットはゼロに等しく、殆どがミディアムショット以上に対象に接近したカメラで綴られる。あのウディ・アレンの「インテリア」以上に、個性的な作り方。今、こんなに勇気のある作家がいるだろうか。何を描くかが明解だから出来たスタイルでしょう。
ブレッソンの「抵抗」、ロングショットはゼロに等しく、殆どがミディアムショット以上に対象に接近したカメラで綴られる。あのウディ・アレンの「インテリア」以上に、個性的な作り方。今、こんなに勇気のある作家がいるだろうか。何を描くかが明解だから出来たスタイルでしょう。
 そして、例えば脱獄の作業をしている時に看守が近づいてくるなんていうシーンがあるんだけど、ありきたりなパラレルシークエンスのカットバックなんていう手法はとっていない。近づいてくる看守は靴音だけで表現される。カメラの表現が取り上げられる事の多いブレッソンだが実は音の使い方も巧いんだ。
そして、例えば脱獄の作業をしている時に看守が近づいてくるなんていうシーンがあるんだけど、ありきたりなパラレルシークエンスのカットバックなんていう手法はとっていない。近づいてくる看守は靴音だけで表現される。カメラの表現が取り上げられる事の多いブレッソンだが実は音の使い方も巧いんだ。
 事前の予想との違いを言うと、主観ショットが少なく感じたこと。アップショットは対象の人物の内面を感じさせるが、主観ショットをもっと使えば、もっと主人公の心情が切実に感じられると思うんだが、もう一度観ないと実際のところは分からない。ブレッソンの意図はまた違うかもしれないし・・。
事前の予想との違いを言うと、主観ショットが少なく感じたこと。アップショットは対象の人物の内面を感じさせるが、主観ショットをもっと使えば、もっと主人公の心情が切実に感じられると思うんだが、もう一度観ないと実際のところは分からない。ブレッソンの意図はまた違うかもしれないし・・。
 終盤にそれまで独り部屋だった主人公の房に、若者が入ってくる。スパイの可能性もあるので、サスペンスが高まるんだが、この若者がマット・デーモンに似てて面白かった。それと、フランス人なのにドイツ側に付いていたという設定であり、ルイ・マルの「ルシアンの青春」の若者にも見えてきた。
終盤にそれまで独り部屋だった主人公の房に、若者が入ってくる。スパイの可能性もあるので、サスペンスが高まるんだが、この若者がマット・デーモンに似てて面白かった。それと、フランス人なのにドイツ側に付いていたという設定であり、ルイ・マルの「ルシアンの青春」の若者にも見えてきた。
 音の使い方で言えば、脱獄の際の列車の音なんていうのも巧いなぁ。そして、この作品は主人公のモノローグが使われている。内面と外界の音(銃殺刑の銃の音など)との対比。カメラの場所の限定は主人公の境遇を観客にも感じさせる意図が有るのではないかと思うが、音の扱いも同じでありましょうな。
音の使い方で言えば、脱獄の際の列車の音なんていうのも巧いなぁ。そして、この作品は主人公のモノローグが使われている。内面と外界の音(銃殺刑の銃の音など)との対比。カメラの場所の限定は主人公の境遇を観客にも感じさせる意図が有るのではないかと思うが、音の扱いも同じでありましょうな。
 「抵抗」の題材を平凡な作家が作ったとしたら、例えば、ナチスに捕まる前の主人公の様子をフラッシュバックで入れたりするかも知れない。刑務所中の別の囚人の部屋にカメラが入ったりするかもしれないし、ナチスの看守を悪役らしく描いたりするかもしれない。
「抵抗」の題材を平凡な作家が作ったとしたら、例えば、ナチスに捕まる前の主人公の様子をフラッシュバックで入れたりするかも知れない。刑務所中の別の囚人の部屋にカメラが入ったりするかもしれないし、ナチスの看守を悪役らしく描いたりするかもしれない。
 主人公の主観カメラで、例えば垢にまみれた主人公の掌だったり、格子窓から見える空のショットがあったらいいなぁ、なんて思ったんだけど、ブレッソンの解釈で、この主人公はそういう感傷的な人物ではないのかも知れない。だから、僕の期待したそういうショットがなかったのかも知れない。
主人公の主観カメラで、例えば垢にまみれた主人公の掌だったり、格子窓から見える空のショットがあったらいいなぁ、なんて思ったんだけど、ブレッソンの解釈で、この主人公はそういう感傷的な人物ではないのかも知れない。だから、僕の期待したそういうショットがなかったのかも知れない。
 今朝早くに「抵抗」の2回目を観る。あわよくば、紹介記事を書こうかとも思ったが、急に用事が色々と発生して、またもや後延ばしに。ったく。今月一杯は忙しそうだなぁ。「抵抗」のお薦め度は★四つ半くらい。もっとドラマチックな方が個人的にはお好みですからな。
今朝早くに「抵抗」の2回目を観る。あわよくば、紹介記事を書こうかとも思ったが、急に用事が色々と発生して、またもや後延ばしに。ったく。今月一杯は忙しそうだなぁ。「抵抗」のお薦め度は★四つ半くらい。もっとドラマチックな方が個人的にはお好みですからな。
[3月 1日 以下同じ]
 「抵抗」の主人公フォンテーヌ中尉さん。如何にもフランスの色っぽくてスラッと背の高いいい男。汚物入れのバケツも臭いがしないんじゃないかと思えるくらい。それにしても、も少し無精ひげが生えてる方がリアルだよね。ほんで、脱出途中でドイツ兵を殺すんだけど、死体の処理が大胆すぎないかなぁ。
「抵抗」の主人公フォンテーヌ中尉さん。如何にもフランスの色っぽくてスラッと背の高いいい男。汚物入れのバケツも臭いがしないんじゃないかと思えるくらい。それにしても、も少し無精ひげが生えてる方がリアルだよね。ほんで、脱出途中でドイツ兵を殺すんだけど、死体の処理が大胆すぎないかなぁ。
(お薦め度は★四つ半くらいですが、孤高の創作姿勢に敬意を表して★五つです)
高校に入学した頃から読み出した「SCREEN」で、滋野辰彦さんは双葉十三郎さんの次によく読んでいた評論家だった。演出についての考察が多く、「抵抗」も何度か取り上げられていたので当時から興味があったが、TVで放送されることはまず無かった。ロベール・ブレッソンの名前もこの「抵抗」という作品で初めて知ったと思う。そんな高校生の頃、製作より6年後に公開されたロバが主人公の「バルタザールどこへ行く(1964)」が「SCREEN」の批評家年間ベストテンで上位にランクインし、ブレッソンの名前は深く記憶に刻まれることになった。
*
「抵抗」は、第二次世界大戦中の実話を基にした映画で、ナチスドイツの占領下にあったフランスで、レジスタンス活動をしていたフランス人青年がゲシュタポに捕まり、収容された刑務所から脱獄する話です。
昔はただ「抵抗」というタイトルだけでしたが、最近は「抵抗(レジスタンス)-死刑囚の手記より-」と長たらしい名前になったようです。実際、原題は『死刑囚は逃げた、あるいは、風は己の望む所に吹く』との事。つまり脱獄は成功するってことです。そして『風は己の望む所に吹く』というのは、「天は自ら助くる者を助く」と同じ意味だと思われます。なんだか努力すれば夢は叶うみたいな話に聞こえますが・・・。
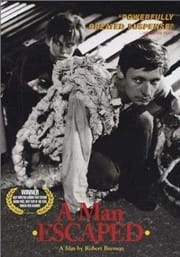 1943年、フランス第2の都市リヨン。ナチスドイツに抵抗するフランス軍中尉フォンテーヌは車で連行されるところだった。信号で止まった時に、あわよくば逃げようかと機会を狙っていたが、一旦は車を飛び出したものの後続車のゲシュタポに捕まり、拳銃で頭を殴られて刑務所に収容されることになった。
1943年、フランス第2の都市リヨン。ナチスドイツに抵抗するフランス軍中尉フォンテーヌは車で連行されるところだった。信号で止まった時に、あわよくば逃げようかと機会を狙っていたが、一旦は車を飛び出したものの後続車のゲシュタポに捕まり、拳銃で頭を殴られて刑務所に収容されることになった。収容所でも拷問付きの尋問を受けて、担架で放り込まれるように独房に入れられた。両手には手錠が掛けられ、アチコチが痛み、頭からも出血していた。翌日、又も尋問を受けそうになったが、疲労困憊している風を装ったらそのままにしておいてくれた。ひょっとしたら、あのまま房を出て行ったら殺されていたかも知れない。
周りをコンクリートの壁で囲まれた小さな独房。トイレ用の大きなブリキの缶と洗面器代わりの小さな缶、粗末なベッドと毛布が与えられた。出入口とは反対側の壁の高い所に小さな窓があり、明かりはそこからしか届かなかった。
隣の囚人と壁を叩くことで会話が出来るようになり、手錠を安全ピン一つで外す方法も教えてもらった。高窓とベッドの中間あたりの壁に小さな台が付いており、その台に上ると窓から外を見ることが出来た。窓の外は刑務所の中庭であり、平服を着たフランス人の囚人が三人散歩をしていた。その内の一人と会話を交わし、安全ピンや紙、鉛筆を調達してもらった。
捕まって4日目。近くのホテルにあるゲシュタポ本部へ連行されて尋問を受け、刑務所に戻ると最上階の3階の独房107号室に移されることとなった。手錠も解かれ、4日ぶりに食べ物にもありつける事が出来たが、それは缶に入ったスープで、あっという間に無くなってしまった。
3階には大勢のフランス人が収容されていたが、彼等と会うのは、朝のひと時しかなかった。一列に並んで歩き、房から持ってきたバケツの排泄物を捨て、洗面所で顔を洗う。『しゃべるな!』とドイツ兵に言われるので、小声で手短に話すしかなかった。
隣の106号室は空室のようで、反対側の108号室には老人が居た。壁を叩いて合図を送ったが、老人からは反応がなかった。高窓越しに声を掛けてみたが、老人は生きる気力を無くしかけていた。
偶然からフォンテーヌは脱獄のきっかけを得る。暇をもてあまし、何の気なしに出入口の木製の扉を見ていた彼は、扉が小さな6枚の板が2段になって組み合わせられた物であることに気付き、継ぎ目を開いていけば人が通る事が出来るのではないかと思い始めたのだ。その巾は3枚分の板で十分だった。
毎回の食事にはスプーンが付いていたが、ある時、スプーンを忘れたふりをして缶だけを看守に返したら気付かれなかった。成功だ。スプーンの食物を掬う方を持って、反対側を床のコンクリートで削った。それはノミのように鋭くなり、木製扉の継ぎ目を削るのに丁度良い道具となった。幸いにして看守は1階にしか居なかったが、時に見回りに来ることもあり、物音には敏感にならざるを得なかった。こうして、フォンテーヌの命を懸けた抵抗が始まるのである・・・。
全編、主人公のモノローグでストーリーが進行される為、内面の葛藤がひしひしと伝わります。ロングショットは皆無に近く、殆どのショットがバストショット以上のアップで撮られているため、息を呑むような緊迫感が漂っています。映画で結末が分かっていては面白くないと言う人がいますが、映画は描写ですから、映像から伝わる緊張感、葛藤を素直に感じとればいいんです。
画面は主人公を中心に展開しており、敵方のドイツ兵の様子は殆ど描かれません。刑務所の描写もフォンテーヌが見れる範囲でしか描かれません。狭い視界。しかし、ドイツ兵の足音、中庭で行われているであろう銃殺刑での銃声等により、空間の広がりを感じさせるようになっています。終盤の脱出シーンでは、近くを通っているであろう列車の音が聞こえてきて、解放への望みが膨らんでいく気分になります。
1957年のカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞したモノクロ作品。現代の刺激的なカメラワークに慣らされた観客には、この品の良い感覚は物足りなさを感じるかもしれませんな。
*
(↓Twitter on 十瑠 より)
 9日に届いていたブレッソンの「抵抗」を午後のひと時に観る。この映画、以前観たのか、初見なのかあやふやなんだが(冒頭の車のシーンに既視感が)、とりあえず予想通りの印象だった。ブレッソンらしいシンプルでスマートな作り方。時にヒッチコックをも連想させた。台詞がなくても観れるな。
9日に届いていたブレッソンの「抵抗」を午後のひと時に観る。この映画、以前観たのか、初見なのかあやふやなんだが(冒頭の車のシーンに既視感が)、とりあえず予想通りの印象だった。ブレッソンらしいシンプルでスマートな作り方。時にヒッチコックをも連想させた。台詞がなくても観れるな。[2月 23日 以下同じ]
 ブレッソンの「抵抗」、ロングショットはゼロに等しく、殆どがミディアムショット以上に対象に接近したカメラで綴られる。あのウディ・アレンの「インテリア」以上に、個性的な作り方。今、こんなに勇気のある作家がいるだろうか。何を描くかが明解だから出来たスタイルでしょう。
ブレッソンの「抵抗」、ロングショットはゼロに等しく、殆どがミディアムショット以上に対象に接近したカメラで綴られる。あのウディ・アレンの「インテリア」以上に、個性的な作り方。今、こんなに勇気のある作家がいるだろうか。何を描くかが明解だから出来たスタイルでしょう。 そして、例えば脱獄の作業をしている時に看守が近づいてくるなんていうシーンがあるんだけど、ありきたりなパラレルシークエンスのカットバックなんていう手法はとっていない。近づいてくる看守は靴音だけで表現される。カメラの表現が取り上げられる事の多いブレッソンだが実は音の使い方も巧いんだ。
そして、例えば脱獄の作業をしている時に看守が近づいてくるなんていうシーンがあるんだけど、ありきたりなパラレルシークエンスのカットバックなんていう手法はとっていない。近づいてくる看守は靴音だけで表現される。カメラの表現が取り上げられる事の多いブレッソンだが実は音の使い方も巧いんだ。 事前の予想との違いを言うと、主観ショットが少なく感じたこと。アップショットは対象の人物の内面を感じさせるが、主観ショットをもっと使えば、もっと主人公の心情が切実に感じられると思うんだが、もう一度観ないと実際のところは分からない。ブレッソンの意図はまた違うかもしれないし・・。
事前の予想との違いを言うと、主観ショットが少なく感じたこと。アップショットは対象の人物の内面を感じさせるが、主観ショットをもっと使えば、もっと主人公の心情が切実に感じられると思うんだが、もう一度観ないと実際のところは分からない。ブレッソンの意図はまた違うかもしれないし・・。 終盤にそれまで独り部屋だった主人公の房に、若者が入ってくる。スパイの可能性もあるので、サスペンスが高まるんだが、この若者がマット・デーモンに似てて面白かった。それと、フランス人なのにドイツ側に付いていたという設定であり、ルイ・マルの「ルシアンの青春」の若者にも見えてきた。
終盤にそれまで独り部屋だった主人公の房に、若者が入ってくる。スパイの可能性もあるので、サスペンスが高まるんだが、この若者がマット・デーモンに似てて面白かった。それと、フランス人なのにドイツ側に付いていたという設定であり、ルイ・マルの「ルシアンの青春」の若者にも見えてきた。 音の使い方で言えば、脱獄の際の列車の音なんていうのも巧いなぁ。そして、この作品は主人公のモノローグが使われている。内面と外界の音(銃殺刑の銃の音など)との対比。カメラの場所の限定は主人公の境遇を観客にも感じさせる意図が有るのではないかと思うが、音の扱いも同じでありましょうな。
音の使い方で言えば、脱獄の際の列車の音なんていうのも巧いなぁ。そして、この作品は主人公のモノローグが使われている。内面と外界の音(銃殺刑の銃の音など)との対比。カメラの場所の限定は主人公の境遇を観客にも感じさせる意図が有るのではないかと思うが、音の扱いも同じでありましょうな。 「抵抗」の題材を平凡な作家が作ったとしたら、例えば、ナチスに捕まる前の主人公の様子をフラッシュバックで入れたりするかも知れない。刑務所中の別の囚人の部屋にカメラが入ったりするかもしれないし、ナチスの看守を悪役らしく描いたりするかもしれない。
「抵抗」の題材を平凡な作家が作ったとしたら、例えば、ナチスに捕まる前の主人公の様子をフラッシュバックで入れたりするかも知れない。刑務所中の別の囚人の部屋にカメラが入ったりするかもしれないし、ナチスの看守を悪役らしく描いたりするかもしれない。 主人公の主観カメラで、例えば垢にまみれた主人公の掌だったり、格子窓から見える空のショットがあったらいいなぁ、なんて思ったんだけど、ブレッソンの解釈で、この主人公はそういう感傷的な人物ではないのかも知れない。だから、僕の期待したそういうショットがなかったのかも知れない。
主人公の主観カメラで、例えば垢にまみれた主人公の掌だったり、格子窓から見える空のショットがあったらいいなぁ、なんて思ったんだけど、ブレッソンの解釈で、この主人公はそういう感傷的な人物ではないのかも知れない。だから、僕の期待したそういうショットがなかったのかも知れない。 今朝早くに「抵抗」の2回目を観る。あわよくば、紹介記事を書こうかとも思ったが、急に用事が色々と発生して、またもや後延ばしに。ったく。今月一杯は忙しそうだなぁ。「抵抗」のお薦め度は★四つ半くらい。もっとドラマチックな方が個人的にはお好みですからな。
今朝早くに「抵抗」の2回目を観る。あわよくば、紹介記事を書こうかとも思ったが、急に用事が色々と発生して、またもや後延ばしに。ったく。今月一杯は忙しそうだなぁ。「抵抗」のお薦め度は★四つ半くらい。もっとドラマチックな方が個人的にはお好みですからな。[3月 1日 以下同じ]
 「抵抗」の主人公フォンテーヌ中尉さん。如何にもフランスの色っぽくてスラッと背の高いいい男。汚物入れのバケツも臭いがしないんじゃないかと思えるくらい。それにしても、も少し無精ひげが生えてる方がリアルだよね。ほんで、脱出途中でドイツ兵を殺すんだけど、死体の処理が大胆すぎないかなぁ。
「抵抗」の主人公フォンテーヌ中尉さん。如何にもフランスの色っぽくてスラッと背の高いいい男。汚物入れのバケツも臭いがしないんじゃないかと思えるくらい。それにしても、も少し無精ひげが生えてる方がリアルだよね。ほんで、脱出途中でドイツ兵を殺すんだけど、死体の処理が大胆すぎないかなぁ。(お薦め度は★四つ半くらいですが、孤高の創作姿勢に敬意を表して★五つです)
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】 

(1991/ガブリエレ・サルヴァトレス監督/クラウディオ・ビガリ、ディエゴ・アバタントゥオーノ、ジュゼッペ・チェデルナ、ヴァンナ・バルバ/90分)
ネタバレあります。
第二次世界大戦中の地中海。中尉と軍曹と落ちこぼれの兵隊ばかりを集めたイタリアの小隊が、偵察と通信の任務を負ってギリシャの孤島にやって来る。任期は4ヶ月。ところが、上陸してみると人の気配がない。港があり、家屋もたくさん立ち並んでいるのに、どの家も無人だった。どこかに潜んでいるのかも知れない。兵隊達は合い言葉を作って警戒を続けていたが、ちょっとしたドジから無線機を壊してしまい、仕方なく山育ちの兄弟兵士を島の高台に見張りにたてて様子を見ることにする。味方の船が現れたら拾ってもらおうというわけだ。
地中海の常夏のような陽気の中、ウトウトと昼寝をする彼らの前に突然大勢の子供たちが現れたのは、緊張感も薄らいだある日の事だった・・・。
1991年のアカデミー賞で外国語映画賞を受賞した作品。ですが、allcinemaの解説はかなり辛辣です。
<米アカデミー賞の外国語映画賞など、全く値打ちの無いものかもしれない。(中略)
大戦中の話なのに深刻な所はなに一つない。牧歌的なギリシャの小島に8人のイタリア兵が派遣されてくるが、サッカーをしたり娼婦のもとを訪ねたりする以外とりたててすることも無く、義務感に燃えていた若い隊長も教会のフレスコ画制作に夢中になる。>
どういうことかというと、つまりこの島の男たちはドイツ軍にさらわれていて年寄りと女子供しかおらず、イタリア兵も何をするか解らないのでしばらく隠れて様子を見ていたという次第。危険がなさそうなので島民も姿を現したわけですが、これが全く突然に、それまで何事もなかったかのような素振りで出て来るんですね。そこもちょっと首をひねるシーンでしたが、もっと変なのが、allcinemaの解説にあるように、島民が出て来て事情が判ったはイイものの、その後の兵隊達のやったことが<あまりにも現実逃避的>なことばかりで、村長の家を司令部として借りた以外は上の解説にあるような、まるで緊張感のない牧歌的な暮らしなんです。暮らしと言えるかどうかも疑問ですが(笑)。
イタリア兵達は本国との連絡も取れない状況だから郵便物も来ない。ということは、生きていく為には魚を捕ったり畑を耕したりしなければいけないだろうに、そういうシーンが全くないんですね。娼婦に支払うお金も無かったろうに、その辺には一切触れてない。
それに島民達はどうやって生き延びていたんでしょう。彼らの生活にも一切触れてないですね。
島の男の替わりに兵隊達が狩りをしたり農業をする。そういった生活の中で島民との様々なふれあいも発生したはずなのに、そういったエピソードは皆無なんです。
映画の後半でイタリアの戦闘機が偶然島に降り立って彼らを発見し、そのパイロットが本国に報せてくれて母国に帰れるわけですが、パイロットと兵隊達の会話で彼らが(なんと!)3年間もこの島で暮らしていたことが解ります。
3年も島の生活が続いたようには見えなかったし、なにしろ3年もあんな現実離れしたことだけに終始していたなんて実に馬鹿げています。
allcinemaの同作品の読者コメントは解説に対しての反対意見が殆どですが、私はツイッターにも書いたように(解説は)当たらずとも遠からずと思いますね。
<終戦で島を離れた彼らだが、本国で働き定年を迎え、再び吸い寄せられるように島へ帰ってくるのだった。あまりにも現実逃避的で、諷刺は病院の減塩メニューのように味気ない効き目。人生を頑張りすぎてると自負する人には慰めになるかも。そうでもない人には、ちょっとユルすぎる病人食のお粥みたいな映画。>
エピローグとして、年老いた中尉や軍曹が、娼婦と結婚をして逃亡兵として島に残った部下を訪ねてやって来ます。とってつけ足したような結末で、彼らの感慨に共感することは出来ませんね。
地中海の島が舞台で、長い時を隔てたエピローグがあることで「イル・ポスティーノ (1994)」を思い出しましたが、BGMの感じが似ているくらいで、見比べればラストの余韻の深みが全然違うことに気付くでしょう。
米国アカデミー外国語映画賞。なにを血迷ったんでしょうか?
ネタバレあります。
第二次世界大戦中の地中海。中尉と軍曹と落ちこぼれの兵隊ばかりを集めたイタリアの小隊が、偵察と通信の任務を負ってギリシャの孤島にやって来る。任期は4ヶ月。ところが、上陸してみると人の気配がない。港があり、家屋もたくさん立ち並んでいるのに、どの家も無人だった。どこかに潜んでいるのかも知れない。兵隊達は合い言葉を作って警戒を続けていたが、ちょっとしたドジから無線機を壊してしまい、仕方なく山育ちの兄弟兵士を島の高台に見張りにたてて様子を見ることにする。味方の船が現れたら拾ってもらおうというわけだ。
地中海の常夏のような陽気の中、ウトウトと昼寝をする彼らの前に突然大勢の子供たちが現れたのは、緊張感も薄らいだある日の事だった・・・。
1991年のアカデミー賞で外国語映画賞を受賞した作品。ですが、allcinemaの解説はかなり辛辣です。
<米アカデミー賞の外国語映画賞など、全く値打ちの無いものかもしれない。(中略)
大戦中の話なのに深刻な所はなに一つない。牧歌的なギリシャの小島に8人のイタリア兵が派遣されてくるが、サッカーをしたり娼婦のもとを訪ねたりする以外とりたててすることも無く、義務感に燃えていた若い隊長も教会のフレスコ画制作に夢中になる。>
どういうことかというと、つまりこの島の男たちはドイツ軍にさらわれていて年寄りと女子供しかおらず、イタリア兵も何をするか解らないのでしばらく隠れて様子を見ていたという次第。危険がなさそうなので島民も姿を現したわけですが、これが全く突然に、それまで何事もなかったかのような素振りで出て来るんですね。そこもちょっと首をひねるシーンでしたが、もっと変なのが、allcinemaの解説にあるように、島民が出て来て事情が判ったはイイものの、その後の兵隊達のやったことが<あまりにも現実逃避的>なことばかりで、村長の家を司令部として借りた以外は上の解説にあるような、まるで緊張感のない牧歌的な暮らしなんです。暮らしと言えるかどうかも疑問ですが(笑)。
イタリア兵達は本国との連絡も取れない状況だから郵便物も来ない。ということは、生きていく為には魚を捕ったり畑を耕したりしなければいけないだろうに、そういうシーンが全くないんですね。娼婦に支払うお金も無かったろうに、その辺には一切触れてない。
それに島民達はどうやって生き延びていたんでしょう。彼らの生活にも一切触れてないですね。
島の男の替わりに兵隊達が狩りをしたり農業をする。そういった生活の中で島民との様々なふれあいも発生したはずなのに、そういったエピソードは皆無なんです。
映画の後半でイタリアの戦闘機が偶然島に降り立って彼らを発見し、そのパイロットが本国に報せてくれて母国に帰れるわけですが、パイロットと兵隊達の会話で彼らが(なんと!)3年間もこの島で暮らしていたことが解ります。
3年も島の生活が続いたようには見えなかったし、なにしろ3年もあんな現実離れしたことだけに終始していたなんて実に馬鹿げています。
allcinemaの同作品の読者コメントは解説に対しての反対意見が殆どですが、私はツイッターにも書いたように(解説は)当たらずとも遠からずと思いますね。
<終戦で島を離れた彼らだが、本国で働き定年を迎え、再び吸い寄せられるように島へ帰ってくるのだった。あまりにも現実逃避的で、諷刺は病院の減塩メニューのように味気ない効き目。人生を頑張りすぎてると自負する人には慰めになるかも。そうでもない人には、ちょっとユルすぎる病人食のお粥みたいな映画。>
エピローグとして、年老いた中尉や軍曹が、娼婦と結婚をして逃亡兵として島に残った部下を訪ねてやって来ます。とってつけ足したような結末で、彼らの感慨に共感することは出来ませんね。
地中海の島が舞台で、長い時を隔てたエピローグがあることで「イル・ポスティーノ (1994)」を思い出しましたが、BGMの感じが似ているくらいで、見比べればラストの余韻の深みが全然違うことに気付くでしょう。
米国アカデミー外国語映画賞。なにを血迷ったんでしょうか?
・お薦め度【★=お薦めはしません】 

(1956/ロバート・アルドリッチ製作・監督/ジャック・パランス、エディ・アルバート、リー・マーヴィン、ウィリアム・スミサーズ、ロバート・ストラウス、バディ・イブセン、ペーター・ヴァン・アイク/108分)
 60年代のお茶の間の人気番組だった戦争ドラマ「コンバット」にも多分有ったに違いないと思わせる、臆病で統率能力のない中隊長と、規律を重んじながらも部下を無駄死にさせたくない小隊長との対立を描いた作品。
60年代のお茶の間の人気番組だった戦争ドラマ「コンバット」にも多分有ったに違いないと思わせる、臆病で統率能力のない中隊長と、規律を重んじながらも部下を無駄死にさせたくない小隊長との対立を描いた作品。
骨太の男性的作風の作品が多いが、「何がジェーンに起ったか? (1962)」や「ふるえて眠れ (1965)」などの異常心理を描くこともあったアルドリッチ(オルドリッチとも言う)の、両方の特色が生かされた映画でありましょう。
中隊長のクーニー大尉には「ローマの休日」でグレゴリー・ペックの同僚の人の良いカメラマンを演じたエディ・アルバート。
冒頭、ドイツ軍の拠点を攻めようとするも反撃にあって敗走を始めた部下の為に小隊長が援護射撃を要請するも、躊躇するばかりで、ついには無線機の受話器を放り出してしまうほどに気弱な中隊長として登場します。彼には同郷の上司がおり、その中佐は彼の父親とも懇意にしていて、この中佐のご機嫌さえ損なわなければなんとかなると思っている。戦時の縦社会に情を持ち込んで、部下の命など省みない馬鹿な男なんですね。終盤で、こんなロクデナシが出来上がった背景の一端が暴露されますが、家庭の偏った躾が生んだ歪んだ人生でありました。
『今度、臆病風を吹かせて部下を一人でも見捨てたら貴様を殺す!』とまで言ってのけた小隊長のコスタ中尉には、「シェーン」で黒ずくめの情け無用のガンマンを演じたジャック・パランス。
「コンバット」のサンダース軍曹を思わせる熱くて冷静な男です。
クーニーの上司、バートレット中佐を演じるのが、アルドリッチのご贔屓俳優リー・マーヴィン。
中佐はクーニーの無能ぶりを知っているのに、彼を更迭しようとはしない。何故か?
中佐は戦争が終われば、故郷で政治家になろうとしており、故郷で判事をしているクーニーの父親の人脈が欲しいのです。既に戦争は末期を迎えていたし、クーニーについてはとにかく表沙汰になるような問題が起こさなければそれで良いと思っているわけです。
コスタの同僚に別の小隊を率いているウッドラフ中尉(スミサーズ)もおり、彼もクーニーには憤りを覚えているが、直接クーニーに怒りをぶつけることはせず、バートレットにクーニーを本部付けの事務官にするようにと直訴します。
クーニーの父親の性格を知っているバートレットは、あくまでも最前線にクーニーをおいて置くと、ウッドラフの意見を退けるが、戦争は9分9厘終わった様なモノなので、これ以上クーニーに悩まされることはないだろうと付け加える。
ところが、その舌の根も乾かない内に、新たな攻撃命令が出されるのでした・・・。
序盤でクーニーの無能ぶりを紹介して観客を驚かせた後、その後バートレット、コスタ、ウッドラフを含めた4者の関係も紹介して、コスタとクーニーの一触即発のハラハラな関係を見せつけ、更にはクーニーの更迭が無くなった為に冒頭のような危険がもう一度起こるであろう事を予感させる。この予感は見事に的中し、新しい戦闘作戦がクライマックスへの序章になります。
その作戦は、戦火にまみれているある町を占拠するべく侵攻するというモノで、ドイツ軍が待ち伏せしている可能性もある。コスタの小隊が先陣を切って攻め入ろうとするが、いざ突撃となる直前で町の中で待ち伏せしているドイツ兵のショットを入れるというショック演出が上手いです。
この戦闘で又してもクーニーはコスタを裏切り、終盤へと繋がっていく。
町で待ち伏せしていたドイツ軍は大量の戦車や大砲を使って、クーニー等が待機している町まで反撃にやって来て、その場所は死守しなければいけないのに、クーニーは最大限の臆病風を吹かせて、ついにはバートレットにも殴られてしまう。
この終盤は、攻め入るドイツ軍との戦闘とコスタのクーニーへの復讐がミックスされた怒濤の展開となる期待を抱かせますが、展開がモタモタした感があり、いまいち乗り切れません。ここで★一つ減点となりました。
ヴェネチア国際映画祭でイタリア批評家賞を受賞。
 60年代のお茶の間の人気番組だった戦争ドラマ「コンバット」にも多分有ったに違いないと思わせる、臆病で統率能力のない中隊長と、規律を重んじながらも部下を無駄死にさせたくない小隊長との対立を描いた作品。
60年代のお茶の間の人気番組だった戦争ドラマ「コンバット」にも多分有ったに違いないと思わせる、臆病で統率能力のない中隊長と、規律を重んじながらも部下を無駄死にさせたくない小隊長との対立を描いた作品。骨太の男性的作風の作品が多いが、「何がジェーンに起ったか? (1962)」や「ふるえて眠れ (1965)」などの異常心理を描くこともあったアルドリッチ(オルドリッチとも言う)の、両方の特色が生かされた映画でありましょう。
中隊長のクーニー大尉には「ローマの休日」でグレゴリー・ペックの同僚の人の良いカメラマンを演じたエディ・アルバート。
冒頭、ドイツ軍の拠点を攻めようとするも反撃にあって敗走を始めた部下の為に小隊長が援護射撃を要請するも、躊躇するばかりで、ついには無線機の受話器を放り出してしまうほどに気弱な中隊長として登場します。彼には同郷の上司がおり、その中佐は彼の父親とも懇意にしていて、この中佐のご機嫌さえ損なわなければなんとかなると思っている。戦時の縦社会に情を持ち込んで、部下の命など省みない馬鹿な男なんですね。終盤で、こんなロクデナシが出来上がった背景の一端が暴露されますが、家庭の偏った躾が生んだ歪んだ人生でありました。
『今度、臆病風を吹かせて部下を一人でも見捨てたら貴様を殺す!』とまで言ってのけた小隊長のコスタ中尉には、「シェーン」で黒ずくめの情け無用のガンマンを演じたジャック・パランス。
「コンバット」のサンダース軍曹を思わせる熱くて冷静な男です。
クーニーの上司、バートレット中佐を演じるのが、アルドリッチのご贔屓俳優リー・マーヴィン。
中佐はクーニーの無能ぶりを知っているのに、彼を更迭しようとはしない。何故か?
中佐は戦争が終われば、故郷で政治家になろうとしており、故郷で判事をしているクーニーの父親の人脈が欲しいのです。既に戦争は末期を迎えていたし、クーニーについてはとにかく表沙汰になるような問題が起こさなければそれで良いと思っているわけです。
コスタの同僚に別の小隊を率いているウッドラフ中尉(スミサーズ)もおり、彼もクーニーには憤りを覚えているが、直接クーニーに怒りをぶつけることはせず、バートレットにクーニーを本部付けの事務官にするようにと直訴します。
クーニーの父親の性格を知っているバートレットは、あくまでも最前線にクーニーをおいて置くと、ウッドラフの意見を退けるが、戦争は9分9厘終わった様なモノなので、これ以上クーニーに悩まされることはないだろうと付け加える。
ところが、その舌の根も乾かない内に、新たな攻撃命令が出されるのでした・・・。
序盤でクーニーの無能ぶりを紹介して観客を驚かせた後、その後バートレット、コスタ、ウッドラフを含めた4者の関係も紹介して、コスタとクーニーの一触即発のハラハラな関係を見せつけ、更にはクーニーの更迭が無くなった為に冒頭のような危険がもう一度起こるであろう事を予感させる。この予感は見事に的中し、新しい戦闘作戦がクライマックスへの序章になります。
その作戦は、戦火にまみれているある町を占拠するべく侵攻するというモノで、ドイツ軍が待ち伏せしている可能性もある。コスタの小隊が先陣を切って攻め入ろうとするが、いざ突撃となる直前で町の中で待ち伏せしているドイツ兵のショットを入れるというショック演出が上手いです。
この戦闘で又してもクーニーはコスタを裏切り、終盤へと繋がっていく。
町で待ち伏せしていたドイツ軍は大量の戦車や大砲を使って、クーニー等が待機している町まで反撃にやって来て、その場所は死守しなければいけないのに、クーニーは最大限の臆病風を吹かせて、ついにはバートレットにも殴られてしまう。
この終盤は、攻め入るドイツ軍との戦闘とコスタのクーニーへの復讐がミックスされた怒濤の展開となる期待を抱かせますが、展開がモタモタした感があり、いまいち乗り切れません。ここで★一つ減点となりました。
ヴェネチア国際映画祭でイタリア批評家賞を受賞。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

■ YouTube Selection (予告編)
■ Information&Addition
※gooさんからの告知です:<「トラックバック機能」について、ご利用者数の減少およびスパム利用が多いことから、送受信ともに2017年11月27日(月)にて機能の提供を終了させていただきます>[2017.11.12]
●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。
●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。
●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。
◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
*
●映画の紹介、感想、関連コラム、その他諸々綴っています。
●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。
●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。
●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。
*
◆【管理人について】
HNの十瑠(ジュール)は、あるサイトに登録したペンネーム「鈴木十瑠」の名前部分をとったもの。由来は少年時代に沢山の愛読書を提供してくれたフランスの作家「ジュール・ヴェルヌ」を捩ったものです。
◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。
*
 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)