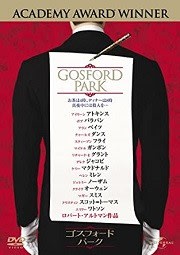(1961/スタンリー・キューブリック監督/ジェームズ・メイソン、スー・リオン、シェリー・ウィンタース、ピーター・セラーズ/153分)
スタンリー・キューブリックの「ロリータ【原題 LOLITA】」を観る。
数年前に確かブック・オフの1コイン・コーナーで見つけたDVDで、キューブリック作品と知っていたので迷わず買ったが、実は内容については知らなかった。
“ロリコン”=“ロリータ・コンプレックス”の語源となった小説の映画化でありますな。原作者はロシア系アメリカ人のウラジミール・ナボコフ。この映画の脚本もナボコフが書いています。事前の印象ではキューブリックにロリコンは似合わないと思っていたけれど、中盤以降の毒気の出し方にはキューブリックらしさを感じましたな。
「スパルタカス」の翌年、「博士の異常な愛情」の3年前の作品であります。
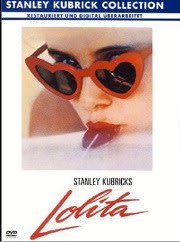 主人公はジェームス・メイスン扮するヨーロッパの文芸作家ハンバート・ハンバート。苗字と名前が同じという変な奴だが、フランスの詩集の英訳が評判となりアメリカの大学に講師として呼ばれた中年男であります。
主人公はジェームス・メイスン扮するヨーロッパの文芸作家ハンバート・ハンバート。苗字と名前が同じという変な奴だが、フランスの詩集の英訳が評判となりアメリカの大学に講師として呼ばれた中年男であります。
大学が始まるまでの間、避暑の出来る地方の町に下宿を探しているシーンからストーリーは始まります。
ハンバートが訪ねたのがシェリー・ウィンタース扮するシャーロット・ヘイズの一軒家で、若いシェリーさん、まだまだ往年のようには太っていなくてセクシーであります。
このシャーロットさん、妙に馴れ馴れしくて身体を摺り寄せてくるので変な空気になるがハンバートもまんざらではない様子。ハンバーㇳは一年前に離婚、シャーロットは七年前に未亡人になってお互いに独り身であることが分かり、ますます艶笑喜劇みたいな感じになっていきます。
でもなんといってもハンバートが下宿先をココに決めたのは、突然現れたシャーロットの高校生の娘ドローレス、愛称ロリータの魅力的な水着姿の日光浴を見たから。完全なるロリコン男ハンバーㇳはロリータに恋をしてしまうのです。
ストーリーの始まりは下宿探しのシーンからと書きましたが、実はその前に153分の結末部分が数分流れます。そこではハンバートがとある屋敷に入って行って、家主のピーター・セラーズに銃をぶっ放すシーンがありまして、その後「その4年前のこと・・・」と字幕が入って過去話としてロリータとのあれこれが語られるのです。
原作では刑務所に繋がれたハンバーㇳが我が罪について告白をするシーンから始まるらしいので映画もそれに倣ったんでしょうな。
セラーズ扮するテレビ作家クィルティが、ロリータをハンバーㇳよりも先に弄んだのかなと推測してしまいますが、お話の軸はハンバートの恋物語なので、ロリータとクィルティの関係は曖昧なままなんですよね。クィルティが神出鬼没でキャラクターも謎すぎるのでも少しクィルティのシーンを削ったら映画も締まったんじゃないでしょうかね。
お薦め度は★二つ半。クィルティのシーンだけじゃなく、全体的にも長すぎますね。
60年以上前の映画だけどスー・リオン扮するロリータは現代の娘と云われてもオジサンには違和感無し。
wikiによると97年のエイドリアン・ラインのリメイクの方が原作に忠実らしいけど、ナボコフが脚本を書いたのはこっちなのにね。
DVDのジャケットはカラーですが、本編はオズワルド・モリスの美しいモノクロ映像でした。
2006年にシェリーさんの訃報を記事にしてますが、その中で既に観ている作品名にこの「ロリータ」が入っていました。18年前の記憶の方が正しいでしょうから、観ていたんでしょう。う~ン、・・消えてる・・。
スタンリー・キューブリックの「ロリータ【原題 LOLITA】」を観る。
数年前に確かブック・オフの1コイン・コーナーで見つけたDVDで、キューブリック作品と知っていたので迷わず買ったが、実は内容については知らなかった。
“ロリコン”=“ロリータ・コンプレックス”の語源となった小説の映画化でありますな。原作者はロシア系アメリカ人のウラジミール・ナボコフ。この映画の脚本もナボコフが書いています。事前の印象ではキューブリックにロリコンは似合わないと思っていたけれど、中盤以降の毒気の出し方にはキューブリックらしさを感じましたな。
「スパルタカス」の翌年、「博士の異常な愛情」の3年前の作品であります。
*
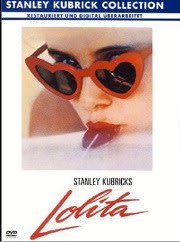 主人公はジェームス・メイスン扮するヨーロッパの文芸作家ハンバート・ハンバート。苗字と名前が同じという変な奴だが、フランスの詩集の英訳が評判となりアメリカの大学に講師として呼ばれた中年男であります。
主人公はジェームス・メイスン扮するヨーロッパの文芸作家ハンバート・ハンバート。苗字と名前が同じという変な奴だが、フランスの詩集の英訳が評判となりアメリカの大学に講師として呼ばれた中年男であります。大学が始まるまでの間、避暑の出来る地方の町に下宿を探しているシーンからストーリーは始まります。
ハンバートが訪ねたのがシェリー・ウィンタース扮するシャーロット・ヘイズの一軒家で、若いシェリーさん、まだまだ往年のようには太っていなくてセクシーであります。
このシャーロットさん、妙に馴れ馴れしくて身体を摺り寄せてくるので変な空気になるがハンバートもまんざらではない様子。ハンバーㇳは一年前に離婚、シャーロットは七年前に未亡人になってお互いに独り身であることが分かり、ますます艶笑喜劇みたいな感じになっていきます。
でもなんといってもハンバートが下宿先をココに決めたのは、突然現れたシャーロットの高校生の娘ドローレス、愛称ロリータの魅力的な水着姿の日光浴を見たから。完全なるロリコン男ハンバーㇳはロリータに恋をしてしまうのです。
ストーリーの始まりは下宿探しのシーンからと書きましたが、実はその前に153分の結末部分が数分流れます。そこではハンバートがとある屋敷に入って行って、家主のピーター・セラーズに銃をぶっ放すシーンがありまして、その後「その4年前のこと・・・」と字幕が入って過去話としてロリータとのあれこれが語られるのです。
原作では刑務所に繋がれたハンバーㇳが我が罪について告白をするシーンから始まるらしいので映画もそれに倣ったんでしょうな。
セラーズ扮するテレビ作家クィルティが、ロリータをハンバーㇳよりも先に弄んだのかなと推測してしまいますが、お話の軸はハンバートの恋物語なので、ロリータとクィルティの関係は曖昧なままなんですよね。クィルティが神出鬼没でキャラクターも謎すぎるのでも少しクィルティのシーンを削ったら映画も締まったんじゃないでしょうかね。
お薦め度は★二つ半。クィルティのシーンだけじゃなく、全体的にも長すぎますね。
60年以上前の映画だけどスー・リオン扮するロリータは現代の娘と云われてもオジサンには違和感無し。
wikiによると97年のエイドリアン・ラインのリメイクの方が原作に忠実らしいけど、ナボコフが脚本を書いたのはこっちなのにね。
DVDのジャケットはカラーですが、本編はオズワルド・モリスの美しいモノクロ映像でした。
2006年にシェリーさんの訃報を記事にしてますが、その中で既に観ている作品名にこの「ロリータ」が入っていました。18年前の記憶の方が正しいでしょうから、観ていたんでしょう。う~ン、・・消えてる・・。
・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】 

(1986/ウディ・アレン監督・脚本・出演/ミア・ファロー(=ハンナ)、ダイアン・ウィースト(=ホリー)、バーバラ・ハーシー(=リー)、マイケル・ケイン(=エリオット)、マックス・フォン・シドー(=フレデリック)、キャリー・フィッシャー(=エイプリル)、モーリン・オサリヴァン、ロイド・ノーラン、ダニエル・スターン、サム・ウォーターストン/107分)
 2006年にTV放映された「ギター弾きの恋 (1999)」が面白くて、それまで食わず嫌いだったウディ・アレンが気になる人になった。滑らかな語り口はどんな題材でもいけるだろうと3か月後にはツタヤで「インテリア (1978)」を借りて、これで完全に御贔屓監督になった。以来何作か観てきたけれど、僕の最高の御贔屓監督ウィリアム・ワイラーのようには全ての作品が良いと思わせるまでにはいかず、ときたま何の感慨も残さない作品にもお目にかかる。
2006年にTV放映された「ギター弾きの恋 (1999)」が面白くて、それまで食わず嫌いだったウディ・アレンが気になる人になった。滑らかな語り口はどんな題材でもいけるだろうと3か月後にはツタヤで「インテリア (1978)」を借りて、これで完全に御贔屓監督になった。以来何作か観てきたけれど、僕の最高の御贔屓監督ウィリアム・ワイラーのようには全ての作品が良いと思わせるまでにはいかず、ときたま何の感慨も残さない作品にもお目にかかる。
「ハンナとその姉妹」は双葉評で☆四つの傑作で、好きな「カイロの紫のバラ (1985)」の翌年の作品なのでかなり期待していたが、その次の年に作られた「ラジオ・デイズ (1987)」のようにその饒舌さが邪魔になった映画だった。女性監督の作品には色々とエピソードを詰め込み過ぎて印象がばらける嫌いがあるが、そんな感じかな。

 ニューヨークに住む三姉妹の話。三姉妹と両親が出てくるので「インテリア」みたいだが、今作はあんなシリアスなムードではなく三姉妹と其々の夫や恋人を絡ませたコメディタッチのお話だ。「インテリア」のストーリーの軸は神経質な一家の母親だったのに対して、ここでは姉の夫とややこしい関係になる妹やら、姉の元夫と付き合いだす妹だったりと、男女関係の危うさがテーマになっている。ハラハラしてしまう局面もあるが、まだ「ブルージャスミン」や「女と男の観覧車」のような毒気を放つまでにはいたってない。画面外から登場人物のモノローグが随所に流れてくるのが特徴で、そこにユーモアも生まれている。
ニューヨークに住む三姉妹の話。三姉妹と両親が出てくるので「インテリア」みたいだが、今作はあんなシリアスなムードではなく三姉妹と其々の夫や恋人を絡ませたコメディタッチのお話だ。「インテリア」のストーリーの軸は神経質な一家の母親だったのに対して、ここでは姉の夫とややこしい関係になる妹やら、姉の元夫と付き合いだす妹だったりと、男女関係の危うさがテーマになっている。ハラハラしてしまう局面もあるが、まだ「ブルージャスミン」や「女と男の観覧車」のような毒気を放つまでにはいたってない。画面外から登場人物のモノローグが随所に流れてくるのが特徴で、そこにユーモアも生まれている。
 三姉妹の両親は共に役者。しかしスターと呼べる程のレベルではなく、長女の言う所によると子供は作っても育てるのには興味のない親だったらしい。親族が集まるパーティーでは仲良くしているが、仲裁を長女に頼むほどの口喧嘩も絶えない夫婦だった。因みに母親役のモーリン・オサリヴァンはミア・ファローの実の母親だ。
三姉妹の両親は共に役者。しかしスターと呼べる程のレベルではなく、長女の言う所によると子供は作っても育てるのには興味のない親だったらしい。親族が集まるパーティーでは仲良くしているが、仲裁を長女に頼むほどの口喧嘩も絶えない夫婦だった。因みに母親役のモーリン・オサリヴァンはミア・ファローの実の母親だ。
 ミア・ファロー扮する長女ハンナは女優で三姉妹の中で一番の成功者。夫のエリオットは投資顧問のアナリストで夫婦仲は良いんだが、エリオットはハンナの末の妹のリーの容姿がお気に入りで、映画の冒頭、感謝祭で親戚一同が集まっているパーティーのシーンではリーに寄せる切ない恋心を語るエリオットのモノローグが聞こえてくる。エリオットとリーの関係はこの後発展していき、この映画の最も重要なシークエンスを形成していく。
ミア・ファロー扮する長女ハンナは女優で三姉妹の中で一番の成功者。夫のエリオットは投資顧問のアナリストで夫婦仲は良いんだが、エリオットはハンナの末の妹のリーの容姿がお気に入りで、映画の冒頭、感謝祭で親戚一同が集まっているパーティーのシーンではリーに寄せる切ない恋心を語るエリオットのモノローグが聞こえてくる。エリオットとリーの関係はこの後発展していき、この映画の最も重要なシークエンスを形成していく。
 次女のホリーも女優を目指しているがオーディションには落ちっぱなし。同じく女優志願の友人エイプリルとケータリングの食べ物屋を始める。あるパーティーで知り合った建築家のデヴィッドにデートに誘われるも後にエイプリルに横取りされ、おまけにホリーが落ちたミュージカルのオーディションにエイプリルが受かってしまう。再び一人になった彼女はハンナに脚本家になると宣言する。
次女のホリーも女優を目指しているがオーディションには落ちっぱなし。同じく女優志願の友人エイプリルとケータリングの食べ物屋を始める。あるパーティーで知り合った建築家のデヴィッドにデートに誘われるも後にエイプリルに横取りされ、おまけにホリーが落ちたミュージカルのオーディションにエイプリルが受かってしまう。再び一人になった彼女はハンナに脚本家になると宣言する。
 三女のリーは仕事も結婚もしてなくて、フレデリックという歳の離れた画家と同棲している。彼は人間嫌いの気難しい男でリーの家族の集まりにも寄り付かないが、感謝祭のパーティーから帰って来た彼女の話を聞いてエリオットは君を狙っているとさらりと言う。リーもエリオットの事が嫌いではないので気にするようになり、その後エリオットとリーの関係は断続的に語られていく。顧客にフレデリックの絵を紹介すると言いながらリーに近づいていったエリオットは、ハンナとの生活が行き詰っており近い内に離婚すると言って強引にリーと逢瀬を重ねるようになっていく。
三女のリーは仕事も結婚もしてなくて、フレデリックという歳の離れた画家と同棲している。彼は人間嫌いの気難しい男でリーの家族の集まりにも寄り付かないが、感謝祭のパーティーから帰って来た彼女の話を聞いてエリオットは君を狙っているとさらりと言う。リーもエリオットの事が嫌いではないので気にするようになり、その後エリオットとリーの関係は断続的に語られていく。顧客にフレデリックの絵を紹介すると言いながらリーに近づいていったエリオットは、ハンナとの生活が行き詰っており近い内に離婚すると言って強引にリーと逢瀬を重ねるようになっていく。
 ウディ・アレンが扮するのはハンナの最初の夫ミッキーで、病気に異常に神経質なテレビ・ディレクターの役。
ウディ・アレンが扮するのはハンナの最初の夫ミッキーで、病気に異常に神経質なテレビ・ディレクターの役。
ある日片方の聴力に疑問を持ったミッキーは医者通いを始め、最後には脳腫瘍の疑い迄もってしまうが、最終的には異常無しと結論が出る。人生の儚さに目覚めたミッキーは哲学書を読み漁り、次には宗教に生きる意味を見出そうとする。
この辺りはアレンお得意のコメディ演技が観られますな。
元々ユダヤ教だったのにキリスト教に改宗、更には仏教にも手を出すが神様は答えてくれない。自殺に失敗した彼は街を彷徨い歩き一軒の映画館に入るのだが・・・。
▼(ネタバレ注意)
 ミッキーとハンナの関係についてネタバレ補足しておきましょう。
ミッキーとハンナの関係についてネタバレ補足しておきましょう。
新婚時代、子供が出来ないので病院に行くとミッキーの方に問題が有り子供は出来ないと言われる。どうしても子供が欲しいハンナはミッキーの友人夫婦から精子を貰い体外受精で双子を産む。二人で考えた方法だったが、子供の事で次第に二人の間に隙間風が吹くようになったのが離婚の原因だった。ミッキーは子供達を認知しているし誕生日にはプレゼントを持ってくるんだが、養育費は払っていないらしい。
大喧嘩をして別れた訳ではないので、その後も二人は友達関係を続けている。ハンナは妹のホリーをミッキーに紹介するが、当時薬物に溺れていた彼女とはうまくいかなかった。
数年後にホリーが脚本を書いた後、二人は街で再会する。
 ミッキーが観た映画はマルクス兄弟のコメディだった。人生の意味を考え続けて行きついた先はそれには答えは無い事、神がいようがいまいが映画の様に人生は楽しめる事だった。再会したホリーとミッキーは結婚をする。
ミッキーが観た映画はマルクス兄弟のコメディだった。人生の意味を考え続けて行きついた先はそれには答えは無い事、神がいようがいまいが映画の様に人生は楽しめる事だった。再会したホリーとミッキーは結婚をする。
 エリオットとリーの関係は最終的には誰にもバレずに収束する。いつまでも離婚をしない彼に業を煮やしたリーがフレデリックとの関係も清算し、大学に通い始め、新しいボーイフレンドを見つけるのだ。
エリオットとリーの関係は最終的には誰にもバレずに収束する。いつまでも離婚をしない彼に業を煮やしたリーがフレデリックとの関係も清算し、大学に通い始め、新しいボーイフレンドを見つけるのだ。
エリオットも自分が思っている以上にハンナを愛していることに気付く。
 終盤で一番面白いエピソードは、ある年の感謝祭でホリーが書いた脚本をハンナに見せるシーン。読んだハンナはそこに出てくる夫婦が自分達であるし、夫婦しか知らない事が書かれていると怒るのだ。
終盤で一番面白いエピソードは、ある年の感謝祭でホリーが書いた脚本をハンナに見せるシーン。読んだハンナはそこに出てくる夫婦が自分達であるし、夫婦しか知らない事が書かれていると怒るのだ。
『なんでこんなことをあなたが知ってるの?』
勿論、寝物語でエリオットがリーに聞かせ、それをリーがホリーに喋ったのだ。
ハンナはエリオットに『ホリーかリーに相談したの?!』と問い詰める。
ここは不倫がバレてしまうかとハラハラするシーンでした。
 オープニングも感謝祭のパーティーのシーンだったが、ラストシーンも感謝祭の夜だった。
オープニングも感謝祭のパーティーのシーンだったが、ラストシーンも感謝祭の夜だった。
リーは人妻となり、エリオットはハンナと幸せな夫婦に戻っている。
少し遅れてきたホリーを再びパーティーに参加するようになったミッキーが迎えキスをする。
ホリーが言う。
『妊娠したわ』
幸せな驚きが二人を包み、再び熱いキスを交わすのでした。
▲(解除)
 お薦め度は★三つ半。ミッキーのエピソードが全体のアクセントにはなっていても、特別な相乗効果は生まれてない事がマイナスに感じました。ベルイマン的なテーマをアレン流に語ったんでしょうが、映画で救われるというのは今となっては平凡なオチでしょうか。
お薦め度は★三つ半。ミッキーのエピソードが全体のアクセントにはなっていても、特別な相乗効果は生まれてない事がマイナスに感じました。ベルイマン的なテーマをアレン流に語ったんでしょうが、映画で救われるというのは今となっては平凡なオチでしょうか。
封切り当時に観たとしたら★一つ分は増えたでしょうけどネ。
 2006年にTV放映された「ギター弾きの恋 (1999)」が面白くて、それまで食わず嫌いだったウディ・アレンが気になる人になった。滑らかな語り口はどんな題材でもいけるだろうと3か月後にはツタヤで「インテリア (1978)」を借りて、これで完全に御贔屓監督になった。以来何作か観てきたけれど、僕の最高の御贔屓監督ウィリアム・ワイラーのようには全ての作品が良いと思わせるまでにはいかず、ときたま何の感慨も残さない作品にもお目にかかる。
2006年にTV放映された「ギター弾きの恋 (1999)」が面白くて、それまで食わず嫌いだったウディ・アレンが気になる人になった。滑らかな語り口はどんな題材でもいけるだろうと3か月後にはツタヤで「インテリア (1978)」を借りて、これで完全に御贔屓監督になった。以来何作か観てきたけれど、僕の最高の御贔屓監督ウィリアム・ワイラーのようには全ての作品が良いと思わせるまでにはいかず、ときたま何の感慨も残さない作品にもお目にかかる。「ハンナとその姉妹」は双葉評で☆四つの傑作で、好きな「カイロの紫のバラ (1985)」の翌年の作品なのでかなり期待していたが、その次の年に作られた「ラジオ・デイズ (1987)」のようにその饒舌さが邪魔になった映画だった。女性監督の作品には色々とエピソードを詰め込み過ぎて印象がばらける嫌いがあるが、そんな感じかな。
*

 ニューヨークに住む三姉妹の話。三姉妹と両親が出てくるので「インテリア」みたいだが、今作はあんなシリアスなムードではなく三姉妹と其々の夫や恋人を絡ませたコメディタッチのお話だ。「インテリア」のストーリーの軸は神経質な一家の母親だったのに対して、ここでは姉の夫とややこしい関係になる妹やら、姉の元夫と付き合いだす妹だったりと、男女関係の危うさがテーマになっている。ハラハラしてしまう局面もあるが、まだ「ブルージャスミン」や「女と男の観覧車」のような毒気を放つまでにはいたってない。画面外から登場人物のモノローグが随所に流れてくるのが特徴で、そこにユーモアも生まれている。
ニューヨークに住む三姉妹の話。三姉妹と両親が出てくるので「インテリア」みたいだが、今作はあんなシリアスなムードではなく三姉妹と其々の夫や恋人を絡ませたコメディタッチのお話だ。「インテリア」のストーリーの軸は神経質な一家の母親だったのに対して、ここでは姉の夫とややこしい関係になる妹やら、姉の元夫と付き合いだす妹だったりと、男女関係の危うさがテーマになっている。ハラハラしてしまう局面もあるが、まだ「ブルージャスミン」や「女と男の観覧車」のような毒気を放つまでにはいたってない。画面外から登場人物のモノローグが随所に流れてくるのが特徴で、そこにユーモアも生まれている。 三姉妹の両親は共に役者。しかしスターと呼べる程のレベルではなく、長女の言う所によると子供は作っても育てるのには興味のない親だったらしい。親族が集まるパーティーでは仲良くしているが、仲裁を長女に頼むほどの口喧嘩も絶えない夫婦だった。因みに母親役のモーリン・オサリヴァンはミア・ファローの実の母親だ。
三姉妹の両親は共に役者。しかしスターと呼べる程のレベルではなく、長女の言う所によると子供は作っても育てるのには興味のない親だったらしい。親族が集まるパーティーでは仲良くしているが、仲裁を長女に頼むほどの口喧嘩も絶えない夫婦だった。因みに母親役のモーリン・オサリヴァンはミア・ファローの実の母親だ。 ミア・ファロー扮する長女ハンナは女優で三姉妹の中で一番の成功者。夫のエリオットは投資顧問のアナリストで夫婦仲は良いんだが、エリオットはハンナの末の妹のリーの容姿がお気に入りで、映画の冒頭、感謝祭で親戚一同が集まっているパーティーのシーンではリーに寄せる切ない恋心を語るエリオットのモノローグが聞こえてくる。エリオットとリーの関係はこの後発展していき、この映画の最も重要なシークエンスを形成していく。
ミア・ファロー扮する長女ハンナは女優で三姉妹の中で一番の成功者。夫のエリオットは投資顧問のアナリストで夫婦仲は良いんだが、エリオットはハンナの末の妹のリーの容姿がお気に入りで、映画の冒頭、感謝祭で親戚一同が集まっているパーティーのシーンではリーに寄せる切ない恋心を語るエリオットのモノローグが聞こえてくる。エリオットとリーの関係はこの後発展していき、この映画の最も重要なシークエンスを形成していく。 次女のホリーも女優を目指しているがオーディションには落ちっぱなし。同じく女優志願の友人エイプリルとケータリングの食べ物屋を始める。あるパーティーで知り合った建築家のデヴィッドにデートに誘われるも後にエイプリルに横取りされ、おまけにホリーが落ちたミュージカルのオーディションにエイプリルが受かってしまう。再び一人になった彼女はハンナに脚本家になると宣言する。
次女のホリーも女優を目指しているがオーディションには落ちっぱなし。同じく女優志願の友人エイプリルとケータリングの食べ物屋を始める。あるパーティーで知り合った建築家のデヴィッドにデートに誘われるも後にエイプリルに横取りされ、おまけにホリーが落ちたミュージカルのオーディションにエイプリルが受かってしまう。再び一人になった彼女はハンナに脚本家になると宣言する。 三女のリーは仕事も結婚もしてなくて、フレデリックという歳の離れた画家と同棲している。彼は人間嫌いの気難しい男でリーの家族の集まりにも寄り付かないが、感謝祭のパーティーから帰って来た彼女の話を聞いてエリオットは君を狙っているとさらりと言う。リーもエリオットの事が嫌いではないので気にするようになり、その後エリオットとリーの関係は断続的に語られていく。顧客にフレデリックの絵を紹介すると言いながらリーに近づいていったエリオットは、ハンナとの生活が行き詰っており近い内に離婚すると言って強引にリーと逢瀬を重ねるようになっていく。
三女のリーは仕事も結婚もしてなくて、フレデリックという歳の離れた画家と同棲している。彼は人間嫌いの気難しい男でリーの家族の集まりにも寄り付かないが、感謝祭のパーティーから帰って来た彼女の話を聞いてエリオットは君を狙っているとさらりと言う。リーもエリオットの事が嫌いではないので気にするようになり、その後エリオットとリーの関係は断続的に語られていく。顧客にフレデリックの絵を紹介すると言いながらリーに近づいていったエリオットは、ハンナとの生活が行き詰っており近い内に離婚すると言って強引にリーと逢瀬を重ねるようになっていく。 ウディ・アレンが扮するのはハンナの最初の夫ミッキーで、病気に異常に神経質なテレビ・ディレクターの役。
ウディ・アレンが扮するのはハンナの最初の夫ミッキーで、病気に異常に神経質なテレビ・ディレクターの役。ある日片方の聴力に疑問を持ったミッキーは医者通いを始め、最後には脳腫瘍の疑い迄もってしまうが、最終的には異常無しと結論が出る。人生の儚さに目覚めたミッキーは哲学書を読み漁り、次には宗教に生きる意味を見出そうとする。
この辺りはアレンお得意のコメディ演技が観られますな。
元々ユダヤ教だったのにキリスト教に改宗、更には仏教にも手を出すが神様は答えてくれない。自殺に失敗した彼は街を彷徨い歩き一軒の映画館に入るのだが・・・。
▼(ネタバレ注意)
 ミッキーとハンナの関係についてネタバレ補足しておきましょう。
ミッキーとハンナの関係についてネタバレ補足しておきましょう。新婚時代、子供が出来ないので病院に行くとミッキーの方に問題が有り子供は出来ないと言われる。どうしても子供が欲しいハンナはミッキーの友人夫婦から精子を貰い体外受精で双子を産む。二人で考えた方法だったが、子供の事で次第に二人の間に隙間風が吹くようになったのが離婚の原因だった。ミッキーは子供達を認知しているし誕生日にはプレゼントを持ってくるんだが、養育費は払っていないらしい。
大喧嘩をして別れた訳ではないので、その後も二人は友達関係を続けている。ハンナは妹のホリーをミッキーに紹介するが、当時薬物に溺れていた彼女とはうまくいかなかった。
数年後にホリーが脚本を書いた後、二人は街で再会する。
 ミッキーが観た映画はマルクス兄弟のコメディだった。人生の意味を考え続けて行きついた先はそれには答えは無い事、神がいようがいまいが映画の様に人生は楽しめる事だった。再会したホリーとミッキーは結婚をする。
ミッキーが観た映画はマルクス兄弟のコメディだった。人生の意味を考え続けて行きついた先はそれには答えは無い事、神がいようがいまいが映画の様に人生は楽しめる事だった。再会したホリーとミッキーは結婚をする。 エリオットとリーの関係は最終的には誰にもバレずに収束する。いつまでも離婚をしない彼に業を煮やしたリーがフレデリックとの関係も清算し、大学に通い始め、新しいボーイフレンドを見つけるのだ。
エリオットとリーの関係は最終的には誰にもバレずに収束する。いつまでも離婚をしない彼に業を煮やしたリーがフレデリックとの関係も清算し、大学に通い始め、新しいボーイフレンドを見つけるのだ。エリオットも自分が思っている以上にハンナを愛していることに気付く。
 終盤で一番面白いエピソードは、ある年の感謝祭でホリーが書いた脚本をハンナに見せるシーン。読んだハンナはそこに出てくる夫婦が自分達であるし、夫婦しか知らない事が書かれていると怒るのだ。
終盤で一番面白いエピソードは、ある年の感謝祭でホリーが書いた脚本をハンナに見せるシーン。読んだハンナはそこに出てくる夫婦が自分達であるし、夫婦しか知らない事が書かれていると怒るのだ。『なんでこんなことをあなたが知ってるの?』
勿論、寝物語でエリオットがリーに聞かせ、それをリーがホリーに喋ったのだ。
ハンナはエリオットに『ホリーかリーに相談したの?!』と問い詰める。
ここは不倫がバレてしまうかとハラハラするシーンでした。
 オープニングも感謝祭のパーティーのシーンだったが、ラストシーンも感謝祭の夜だった。
オープニングも感謝祭のパーティーのシーンだったが、ラストシーンも感謝祭の夜だった。リーは人妻となり、エリオットはハンナと幸せな夫婦に戻っている。
少し遅れてきたホリーを再びパーティーに参加するようになったミッキーが迎えキスをする。
ホリーが言う。
『妊娠したわ』
幸せな驚きが二人を包み、再び熱いキスを交わすのでした。
▲(解除)
 お薦め度は★三つ半。ミッキーのエピソードが全体のアクセントにはなっていても、特別な相乗効果は生まれてない事がマイナスに感じました。ベルイマン的なテーマをアレン流に語ったんでしょうが、映画で救われるというのは今となっては平凡なオチでしょうか。
お薦め度は★三つ半。ミッキーのエピソードが全体のアクセントにはなっていても、特別な相乗効果は生まれてない事がマイナスに感じました。ベルイマン的なテーマをアレン流に語ったんでしょうが、映画で救われるというのは今となっては平凡なオチでしょうか。封切り当時に観たとしたら★一つ分は増えたでしょうけどネ。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(2000/マイケル・カレスニコ監督・脚本/ケネス・ブラナー、ロビン・ライト・ペン、リン・レッドグレーヴ、スージー・ホフリヒター、ジャレッド・ハリス/108分)
借りる人が少なかったんでしょう、何年か前にレンタルショップで売りに出されていた中古DVDで、ジャケットに書かれていた「製作総指揮 ロバート・レッドフォード」という文句に惹かれて購入しました。
ジャケットのデザインとタイトルでウディ・アレンが絡んでいると勝手に思い込みましたが全く関係ないようです。主人公が劇作家で台詞が多いし下ネタギャグも出てくるので1回目の鑑賞ではウディ・アレン作品の雰囲気も“確かに”感じましたがね。
脚本家として活躍していたマイケル・カレスニコの初監督作品との事で、今作の脚本も勿論彼です。
 LAに住むイギリス人劇作家ピーター・マクガウェン。80年代にはヒット作を連発して時代の寵児ともてはやされたが、90年代に入ってからは失敗作が続いていた。
LAに住むイギリス人劇作家ピーター・マクガウェン。80年代にはヒット作を連発して時代の寵児ともてはやされたが、90年代に入ってからは失敗作が続いていた。
家族は元ダンサーで今は子供向けのバレエ教室を開いている妻のメラニーと、少し痴呆症がでてきた彼女の母親エドナ。ピーターは新しい舞台の準備に入っていたが、ゲイの若い演出家の演出プランが掴めずに筆が進んでいなかった。
メラニーは子供を欲しがっていたが元々子供嫌いのピーターは排卵日の告知もストレスなのに、隣の移民の家が犬を飼い始めて夜吠えるのでますますストレス過多で不眠症になっていた。更には反対側のお隣りにシングルマザーと幼い娘が引っ越して来て、メラニーがお付き合いを始めてしまうのでそれも気に食わなかった。その少女エイミーは脳性麻痺によって片脚に障害があり運動が苦手のようだった。
新作の舞台稽古ではピーターの本にも注文が入ってくるが、登場する子供の台詞にリアリティが無いと言われた。
丁度その頃、メラニーがエイミーを預かることになり、一人ままごとをするエイミーをこっそり観察していたピーターは成り行きでままごとに付き合う事になるのだが・・・。
新しい芝居のスタッフやキャスト、TVの情報番組でのインタビュー、家族、隣人、そして近所でピーターと同姓同名を名乗って夜中に徘徊する男。それらに関連するエピソードがピーターを中心にしてスケッチ風に描かれている作品です。予想外のタイミングで切り替わるし、芝居のエピソードには劇中劇もでてくるのでコラージュの様な編集にも感じますね。しかし軽いタッチの語りなので嫌味はないです。編集はこの後「リトル・ミス・サンシャイン」を手掛けるパメラ・マーティンでした。
エピソードのメインはエイミーとピーターの関係で、偏屈な作家がうざいと思っていた子供とのふれ合いが意外に面白いことに気付いていく過程がさりげなく描かれ温かい気持ちになっていきます。少女によってピーターは子供嫌いを克服し、子育てについても考えるようになっていく。新作の芝居の本も皆が納得する形で完成される。なによりエイミーとの間に生まれた友情というか、疑似親子の愛情というか、それが感動的でもありますね。
ハンドルを持つとつい悪態をついてしまっていた彼が歩行者に道をゆずるようになるというシーンもさりげなく挿入されていました。
ピーターにはイギリス人俳優ケネス・ブラナー。妻のメラニーにはロビン・ライト・ペン。
二人共好演でしたし、お似合いでしたが、個人的にはこのメラニーさんはユーモアと豊かな共感性をもった理想の奥さんだったような気がしています。
メラニーの母親エドナにはヴァネッサ・レッドグレーヴの妹のリン。まだ50代なので、ちょっと老けさせたメイクでしたね。
小学三年生くらいに見えたエイミーには11歳のスージー・ホフリヒター。特典映像の記者会見では役者を続けるって言ってたけど、IMDbには2009年の作品名までしか出てなかった。
偽ピーター役にはジャレッド・ハリス。ピーターが英国人なので彼も英国訛りのロンドンっ子。なんとリチャード・ハリスの息子なんだって!
原題は【HOW TO KILL YOUR NEIGHBOR'S DOG】
▼(ネタバレ注意)
原題はピーターのヒット作品の一つだと映画の中で紹介されていたけれど、悲しいことに隣家の犬は映画の終盤に偽ピーターによって射殺される。
ピーターが不眠症をその犬のせいにして語っていたからだが、一時はピーターが犯人ではないかと疑われる。
軽いコメディタッチの作品なのに、含まれている数少ない毒の一つでした。
もう一つのシリアスなエピソードは、終盤のエイミーとの別れ。
引っ込み思案だったエイミーはピーター夫妻と触れ合う事によって活動的になっていくが、彼女の母親は逆の考え方をする人間で、なるべくエイミーを人目にさらしたくないと思っている。それは娘の事を思ってのことかも知れないが、ピーターにはその考えはエイミーの可能性を奪っていくものだと思っている。
終盤、エイミーはメラニーに教わったダンスを母親の前で披露するが途中で脚を縺(もつ)らせてよろけてしまう。母親はエイミーの意思を無視して止めさせようとし、それに怒ったピーターが噛み付く。すると母親はそれまで溜まっていたものを吐き出すように、子供のいないカップルが障害のある子供を笑い者にしようとしていると反論し二人はヒートアップする。
メラニーはエイミーの母親がそういう人間である事は分かっていたはず、あそこで怒りに身を任せていけなかったわとピーターを諫めるが時すでに遅し。しかも別居していた夫とよりが戻った母親はエイミーを連れて再び何処かへ引っ越していく。
お引越しの日にはエイミーとピーターの別れのシーンがあるけれど、最後母親の手を振り切ってお隣の小父さんに駆け寄っていく少女には、この数週間が将来にきっと良い影響をもたらすと信じたいですね。
▲(解除)
借りる人が少なかったんでしょう、何年か前にレンタルショップで売りに出されていた中古DVDで、ジャケットに書かれていた「製作総指揮 ロバート・レッドフォード」という文句に惹かれて購入しました。
ジャケットのデザインとタイトルでウディ・アレンが絡んでいると勝手に思い込みましたが全く関係ないようです。主人公が劇作家で台詞が多いし下ネタギャグも出てくるので1回目の鑑賞ではウディ・アレン作品の雰囲気も“確かに”感じましたがね。
脚本家として活躍していたマイケル・カレスニコの初監督作品との事で、今作の脚本も勿論彼です。
*
 LAに住むイギリス人劇作家ピーター・マクガウェン。80年代にはヒット作を連発して時代の寵児ともてはやされたが、90年代に入ってからは失敗作が続いていた。
LAに住むイギリス人劇作家ピーター・マクガウェン。80年代にはヒット作を連発して時代の寵児ともてはやされたが、90年代に入ってからは失敗作が続いていた。家族は元ダンサーで今は子供向けのバレエ教室を開いている妻のメラニーと、少し痴呆症がでてきた彼女の母親エドナ。ピーターは新しい舞台の準備に入っていたが、ゲイの若い演出家の演出プランが掴めずに筆が進んでいなかった。
メラニーは子供を欲しがっていたが元々子供嫌いのピーターは排卵日の告知もストレスなのに、隣の移民の家が犬を飼い始めて夜吠えるのでますますストレス過多で不眠症になっていた。更には反対側のお隣りにシングルマザーと幼い娘が引っ越して来て、メラニーがお付き合いを始めてしまうのでそれも気に食わなかった。その少女エイミーは脳性麻痺によって片脚に障害があり運動が苦手のようだった。
新作の舞台稽古ではピーターの本にも注文が入ってくるが、登場する子供の台詞にリアリティが無いと言われた。
丁度その頃、メラニーがエイミーを預かることになり、一人ままごとをするエイミーをこっそり観察していたピーターは成り行きでままごとに付き合う事になるのだが・・・。
新しい芝居のスタッフやキャスト、TVの情報番組でのインタビュー、家族、隣人、そして近所でピーターと同姓同名を名乗って夜中に徘徊する男。それらに関連するエピソードがピーターを中心にしてスケッチ風に描かれている作品です。予想外のタイミングで切り替わるし、芝居のエピソードには劇中劇もでてくるのでコラージュの様な編集にも感じますね。しかし軽いタッチの語りなので嫌味はないです。編集はこの後「リトル・ミス・サンシャイン」を手掛けるパメラ・マーティンでした。
エピソードのメインはエイミーとピーターの関係で、偏屈な作家がうざいと思っていた子供とのふれ合いが意外に面白いことに気付いていく過程がさりげなく描かれ温かい気持ちになっていきます。少女によってピーターは子供嫌いを克服し、子育てについても考えるようになっていく。新作の芝居の本も皆が納得する形で完成される。なによりエイミーとの間に生まれた友情というか、疑似親子の愛情というか、それが感動的でもありますね。
ハンドルを持つとつい悪態をついてしまっていた彼が歩行者に道をゆずるようになるというシーンもさりげなく挿入されていました。
ピーターにはイギリス人俳優ケネス・ブラナー。妻のメラニーにはロビン・ライト・ペン。
二人共好演でしたし、お似合いでしたが、個人的にはこのメラニーさんはユーモアと豊かな共感性をもった理想の奥さんだったような気がしています。
メラニーの母親エドナにはヴァネッサ・レッドグレーヴの妹のリン。まだ50代なので、ちょっと老けさせたメイクでしたね。
小学三年生くらいに見えたエイミーには11歳のスージー・ホフリヒター。特典映像の記者会見では役者を続けるって言ってたけど、IMDbには2009年の作品名までしか出てなかった。
偽ピーター役にはジャレッド・ハリス。ピーターが英国人なので彼も英国訛りのロンドンっ子。なんとリチャード・ハリスの息子なんだって!
原題は【HOW TO KILL YOUR NEIGHBOR'S DOG】
▼(ネタバレ注意)
原題はピーターのヒット作品の一つだと映画の中で紹介されていたけれど、悲しいことに隣家の犬は映画の終盤に偽ピーターによって射殺される。
ピーターが不眠症をその犬のせいにして語っていたからだが、一時はピーターが犯人ではないかと疑われる。
軽いコメディタッチの作品なのに、含まれている数少ない毒の一つでした。
もう一つのシリアスなエピソードは、終盤のエイミーとの別れ。
引っ込み思案だったエイミーはピーター夫妻と触れ合う事によって活動的になっていくが、彼女の母親は逆の考え方をする人間で、なるべくエイミーを人目にさらしたくないと思っている。それは娘の事を思ってのことかも知れないが、ピーターにはその考えはエイミーの可能性を奪っていくものだと思っている。
終盤、エイミーはメラニーに教わったダンスを母親の前で披露するが途中で脚を縺(もつ)らせてよろけてしまう。母親はエイミーの意思を無視して止めさせようとし、それに怒ったピーターが噛み付く。すると母親はそれまで溜まっていたものを吐き出すように、子供のいないカップルが障害のある子供を笑い者にしようとしていると反論し二人はヒートアップする。
メラニーはエイミーの母親がそういう人間である事は分かっていたはず、あそこで怒りに身を任せていけなかったわとピーターを諫めるが時すでに遅し。しかも別居していた夫とよりが戻った母親はエイミーを連れて再び何処かへ引っ越していく。
お引越しの日にはエイミーとピーターの別れのシーンがあるけれど、最後母親の手を振り切ってお隣の小父さんに駆け寄っていく少女には、この数週間が将来にきっと良い影響をもたらすと信じたいですね。
▲(解除)
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(1961/ジョシュア・ローガン監督・製作/レスリー・キャロン、ホルスト・ブッフホルツ、モーリス・シュヴァリエ、シャルル・ボワイエ、ヴィクター・フランセン、ライオネル・ジェフリーズ/137分)
先日新しい映画を借りようかとツタヤに行きまして、新作コーナー、準新作コーナーを見ていたら、コレ発見しました。数十年前の十代の頃にNHKの字幕スーパーで観て気に入ってた映画ですが、その後殆ど観た記憶が無いんですよね。レンタルにも無かったし。
「午前十時の映画祭」もそうですが、旧い映画でも新しくDVD化されたりするとツタヤさんは新作扱いにしてくれるので、たまにはこのコーナーにも行かなくちゃです。
フランスの劇作家マルセル・パニョルの戯曲を元ネタに、ウィリアム・ホールデン主演の「ピクニック (1955)」、マリリン・モンロー主演の「バス停留所 (1956)」などの人情劇がお得意のジョシュア・ローガンが製作を兼ねて監督をしています。ネット情報によりますと、ブロードウェイでミュージカルとしてヒットしていたそうで、その舞台の演出を手掛けたのもローガンだったそうです。
成る程。それを今度はミュージカルではなく、地元の俳優を集めて人情コメディとして作ったわけですね。
物語の舞台はフランスの地中海沿岸の港町マルセイユ。でもハリウッド作品なので全編英語です。但し、レスリー・キャロンに加えてモーリス・シュヴァリエ、シャルル・ボワイエというフランスの大御所も参加しているので、雰囲気は伝わります。
 ファニーには「巴里のアメリカ人」のレスリー・キャロン。
ファニーには「巴里のアメリカ人」のレスリー・キャロン。
港で採れたての魚介類を売っている恰幅の良い母親と二人暮らしのファニーは18歳。いつもは母親の仕事を手伝っている。
幼馴染の19歳の若者マリウスには「荒野の七人」のホルスト・ブッフホルツ。
マリウスの方は父親のセザールと二人暮らしで父親の小さな居酒屋を手伝っている。お店にはセザールの友人たちが毎日のように集っては、カードゲームをしたり、通行人をからかったりして呑気に暮らしていた。マルセイユの湾内を航行するタクシー代わりの小舟の船長や帆船の帆や潜水具などの海洋商品の販売をしているパニース等が友人だが、パニースは4か月前に奥さんを亡くしたばかりだった。
その日、18回目の誕生日を迎えたファニーは母親に休みをもらいマリウスの店に遊びに来た。ファニーは彼が好きで、精一杯おめかしもしてきたのにマリウスは全然そんな気持ちを察してくれなかった。
マリウスもファニーが好きなんだが、それ以上に若者らしい屈託を抱えていた。毎日毎日小さな居酒屋でお馴染みさんを相手にする生まれ育った港町での暮らしに飽き飽きしていたのだ。時々港に入ってくる大きな船を眺めては、一緒に乗り込んで外洋へ出、世界中を旅してみたい。いつしかそんな夢を持つようになっていたのだ。
船乗りに憧れ過ぎて年がら年中仕事もせずに港で船を見ている“提督”と呼ばれる男だけにはマリウスは自分の夢を語っていた。
ファニーをお気に入りのパニースが彼女をテーブルに呼ぶので、ファニーはマリウスに嫉妬させようとワザと親密なふりをした。案の定マリウスは危うくパニースに喧嘩を売る所だったが、そこに“提督”がやって来た。港に入ってくる大きな船を発見したからだ。
その船は海洋調査船で、地球を5年かけて廻る船だった。以前より憧れていた船で、いつでも乗船できるようにマリウスは荷造り等の準備はしていた。
“提督”の手配で件の調査船の乗組員と接触したマリウスはいよいよ明日船に乗ることが出来るようになったが、反対するに決まっている父親のセザールには言えなかった。
その夜、店を閉めようとしたところにファニーがやって来た。話があるという。
二人は港の桟橋で落ちあい、話をした。18歳になったファニーは、マリウスへの恋心を告白した。勿論、二人は相思相愛なのだ。
マリウスはファニーを想う気持ちを隠さなかったが、航海への憧れ、このまま故郷の生活に埋もれていくのが我慢できない事も話した。
ファニーの母親は急用で遠くの親戚の家に出かけて行って今夜は居ない。
愛を認め合った若い二人はファニーの家に入っていくのだが・・・。
「シェルブールの雨傘」を思い出す設定もありまして、その他にも如何にも何時の時代にも何処の国にもありそうな下世話な話ですが、色恋だけでなく人生の展望が貧しい故の若気の至りとか、父と息子とか、(今の時代には受け入れがたいでしょうが)女性の幸せとか、老いとか、ドラマの要素は色々と入っているので観て損はないです。
そして出てくる人々がどれも心根の悪い人は居なくて、綺麗事と片付けられるかもしれませんが、こんな世界があってもいいじゃないかと十代の時も今回も思いました。
モーリス・シュヴァリエがパニースで、シャルル・ボワイエがセザール。
どっちも流石の好演でしたね。
『永遠の少女』レスリー・キャロンは当時30歳。色気のある18歳に見えなくもないのがなんというか・・。
漠然とモノクロと思い込んでいましたら、カラーでした。カメラはジャック・カーディフ。港の風景は美しいし、時折入る人物の顔のアップが的確な心情描写になっていました。
1961年のアカデミー賞で、作品賞、主演男優賞(ボワイエ)、撮影賞(カラー)、劇・喜劇映画音楽賞(ハリー・サックマン、モリス・W・ストロフ)、編集賞(William H.Reynolds)にノミネートされたそうです。
先日新しい映画を借りようかとツタヤに行きまして、新作コーナー、準新作コーナーを見ていたら、コレ発見しました。数十年前の十代の頃にNHKの字幕スーパーで観て気に入ってた映画ですが、その後殆ど観た記憶が無いんですよね。レンタルにも無かったし。
「午前十時の映画祭」もそうですが、旧い映画でも新しくDVD化されたりするとツタヤさんは新作扱いにしてくれるので、たまにはこのコーナーにも行かなくちゃです。
フランスの劇作家マルセル・パニョルの戯曲を元ネタに、ウィリアム・ホールデン主演の「ピクニック (1955)」、マリリン・モンロー主演の「バス停留所 (1956)」などの人情劇がお得意のジョシュア・ローガンが製作を兼ねて監督をしています。ネット情報によりますと、ブロードウェイでミュージカルとしてヒットしていたそうで、その舞台の演出を手掛けたのもローガンだったそうです。
成る程。それを今度はミュージカルではなく、地元の俳優を集めて人情コメディとして作ったわけですね。
物語の舞台はフランスの地中海沿岸の港町マルセイユ。でもハリウッド作品なので全編英語です。但し、レスリー・キャロンに加えてモーリス・シュヴァリエ、シャルル・ボワイエというフランスの大御所も参加しているので、雰囲気は伝わります。
*
 ファニーには「巴里のアメリカ人」のレスリー・キャロン。
ファニーには「巴里のアメリカ人」のレスリー・キャロン。港で採れたての魚介類を売っている恰幅の良い母親と二人暮らしのファニーは18歳。いつもは母親の仕事を手伝っている。
幼馴染の19歳の若者マリウスには「荒野の七人」のホルスト・ブッフホルツ。
マリウスの方は父親のセザールと二人暮らしで父親の小さな居酒屋を手伝っている。お店にはセザールの友人たちが毎日のように集っては、カードゲームをしたり、通行人をからかったりして呑気に暮らしていた。マルセイユの湾内を航行するタクシー代わりの小舟の船長や帆船の帆や潜水具などの海洋商品の販売をしているパニース等が友人だが、パニースは4か月前に奥さんを亡くしたばかりだった。
その日、18回目の誕生日を迎えたファニーは母親に休みをもらいマリウスの店に遊びに来た。ファニーは彼が好きで、精一杯おめかしもしてきたのにマリウスは全然そんな気持ちを察してくれなかった。
マリウスもファニーが好きなんだが、それ以上に若者らしい屈託を抱えていた。毎日毎日小さな居酒屋でお馴染みさんを相手にする生まれ育った港町での暮らしに飽き飽きしていたのだ。時々港に入ってくる大きな船を眺めては、一緒に乗り込んで外洋へ出、世界中を旅してみたい。いつしかそんな夢を持つようになっていたのだ。
船乗りに憧れ過ぎて年がら年中仕事もせずに港で船を見ている“提督”と呼ばれる男だけにはマリウスは自分の夢を語っていた。
ファニーをお気に入りのパニースが彼女をテーブルに呼ぶので、ファニーはマリウスに嫉妬させようとワザと親密なふりをした。案の定マリウスは危うくパニースに喧嘩を売る所だったが、そこに“提督”がやって来た。港に入ってくる大きな船を発見したからだ。
その船は海洋調査船で、地球を5年かけて廻る船だった。以前より憧れていた船で、いつでも乗船できるようにマリウスは荷造り等の準備はしていた。
“提督”の手配で件の調査船の乗組員と接触したマリウスはいよいよ明日船に乗ることが出来るようになったが、反対するに決まっている父親のセザールには言えなかった。
その夜、店を閉めようとしたところにファニーがやって来た。話があるという。
二人は港の桟橋で落ちあい、話をした。18歳になったファニーは、マリウスへの恋心を告白した。勿論、二人は相思相愛なのだ。
マリウスはファニーを想う気持ちを隠さなかったが、航海への憧れ、このまま故郷の生活に埋もれていくのが我慢できない事も話した。
ファニーの母親は急用で遠くの親戚の家に出かけて行って今夜は居ない。
愛を認め合った若い二人はファニーの家に入っていくのだが・・・。
*
「シェルブールの雨傘」を思い出す設定もありまして、その他にも如何にも何時の時代にも何処の国にもありそうな下世話な話ですが、色恋だけでなく人生の展望が貧しい故の若気の至りとか、父と息子とか、(今の時代には受け入れがたいでしょうが)女性の幸せとか、老いとか、ドラマの要素は色々と入っているので観て損はないです。
そして出てくる人々がどれも心根の悪い人は居なくて、綺麗事と片付けられるかもしれませんが、こんな世界があってもいいじゃないかと十代の時も今回も思いました。
モーリス・シュヴァリエがパニースで、シャルル・ボワイエがセザール。
どっちも流石の好演でしたね。
『永遠の少女』レスリー・キャロンは当時30歳。色気のある18歳に見えなくもないのがなんというか・・。
漠然とモノクロと思い込んでいましたら、カラーでした。カメラはジャック・カーディフ。港の風景は美しいし、時折入る人物の顔のアップが的確な心情描写になっていました。
1961年のアカデミー賞で、作品賞、主演男優賞(ボワイエ)、撮影賞(カラー)、劇・喜劇映画音楽賞(ハリー・サックマン、モリス・W・ストロフ)、編集賞(William H.Reynolds)にノミネートされたそうです。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 


トーキー時代に作られたサイレント映画ならではの音に関するチャレンジがあると「アーティスト」の記事に書きました。
それはトーキーで作られた映画の試写を見た後の、ジョージの楽屋での一コマでした。
ドレッサーの前でコップをテーブルに置くと「コツン」と音がするんですね。これは字幕ではなく実際音がするんです。で、びっくりした彼が鏡の前の化粧道具をテーブルに倒してみると、やはり「カタコト」と音がする。しかし、自分の声は聞こえないんですね。部屋の中の椅子を動かすとやはり音がするけど自分の叫び声は聞こえない。ドアを開けて外に出ると、歩いている撮影所の人々の話し声も聞こえてくる。えーっ!とジョージが天を仰いだところで・・・ベッドの上の冷や汗をかいた彼の顔。
つまり、楽屋のシーンは彼の悪夢だったというオチ。
トーキーをせせら笑うほど馬鹿にしていた彼だったけど、内心はどこかで怯えていたということでしょうか。それにしちゃ、トーキーへのチャレンジが遅かったなぁ。
*
序盤の新作映画の上映シーンで、ルビッチを参考にしたテクニックが披露されていると書いた部分について。
敵の組織に捕らわれの身になっているヒーロー役のジョージの所に愛犬のジャックが助けに来るシーンでした。
主人公が自由の身になるには見張りの男の目を欺き、縛られている縄も外さなければならないけれど、如何に対処しているかは見せないままに、スクリーンを観ている大勢の観客の反応を見せながら彼の脱出が上手くいっているのを表現し、次のカットでは彼が捕らわれていた部屋の外に出てドアを閉めている。
ルビッチの「ニノチカ (1939)」に、同じようにストーリーの対象を直接写さずに登場人物のリアクションで内容を表現するシーンがあったことを思い出しました。
*
さて、ネタバレついでに後半の展開についても書いておこうと思いましたが、ウィキに適当な記述があったので必要部分をコピペします。
<妻も出て行き、落ちぶれたジョージは執事を解雇し、家財道具などの全てをオークションで売り払う。それらを密かに買い取ったのはペピーだった。彼女は愛するジョージを助けたい一心で陰ながら彼を見守っていたのだ。執事も自分の家で働かせていた。
酒に溺れ、荒んだ生活を送るジョージは、ある日、酔った勢いで自分が出演した映画のフィルムに部屋の中で火を放つ。煙にまかれ、焼け死ぬところを寸前で救ったのは愛犬ジャックだった。 かつてのスターが火事を起こして焼け死ぬ寸前だったという事件は新聞紙上を飾る。その記事をたまたま目にしたペピーは撮影を放り出して病院に駆けつける。そして、火事の中でもジョージが抱きしめて決して放そうとしなかったというフィルムが、かつてペピーがエキストラとして出演したジョージの主演映画のものであることを知ったペピーはジョージを引き取って自宅で療養させることにする。
ペピーの屋敷で穏やかな療養生活を送り始めていたジョージだったが、自分がオークションで売り払った家財道具などを買い取っていたのがペピーであることを知ってしまう。プライドを傷つけられたジョージは火事の後片付けも済んでいない自宅に戻り、拳銃で自殺をしようとする。一方、ジョージが全てを知って屋敷を出て行ってしまったことを知ったペピーは自ら慣れない運転でジョージの下に向う。ジョージが拳銃の引き金を引く。“BANG!”その瞬間、ペピーの運転する車がジョージの自宅前の立ち木に激突して止まる。ジョージの下に駆けつけるペピー。ジョージを傷つけるつもりは毛頭なく、ただ助けたかっただけだったと涙ながらに謝罪するペピーをジョージは抱きしめる。
ペピーはジョージを俳優として映画界に復帰させるアイデアがあると言う。 映画会社の社長の前でペアダンスを披露するジョージとペピー。社長は感激し、2人の主演でミュージカル映画を撮ることになる>
オークションでペピーが競り落としていたのは直後に観客に明かされるので、終盤のジョージのショックは観客には伝わらない。ここは、観客にも内緒にしていた方が良かったでしょうね。
そうそう、ラストシーンはトーキーのミュージカルの撮影に入るところで、そこにも撮影所内の音がスクリーンから聞こえていました、サイレントではなく。ここは、いよいよ本格的にトーキーの時代に入ったという表現なんでしょうね。

(2011/ミシェル・アザナヴィシウス監督・脚本・共同編集/ジャン・デュジャルダン、ベレニス・ベジョ、ジョン・グッドマン、ジェームズ・クロムウェル、エド・ローター、マルコム・マクダウェル/101分)
ご存じ、2011年の米国アカデミー賞で作品賞他4部門でオスカーを受賞した作品であります。フランス製なんですけど、ハリウッドを舞台にしたからか、英語圏向けのバージョンがスタンダードだったせいなのか知りませんが・・。
最大の話題はその創作スタイル。サイレント時代のハリウッドを描くという事で、モノクロ・スタンダードサイズで、しかも無声映画なのでした。1971年に50年代を舞台にした「ラスト・ショー」がモノクロ画面で作られ話題になりましたが、ストーリー当時の雰囲気を出す為に採用するにしても21世紀にサイレントで作るってと、びっくりしたもんです。「アーティスト」は大凡一世紀前のムードを持ってこようとしたわけですネ。
 時は1927年のハリウッド。
時は1927年のハリウッド。
無声映画の大スター、ジョージ・ヴァレンティンが、愛犬ジャックと共に新作の舞台挨拶に登場するのがオープニング。共演女優とは仲がよろしくないようで、ジョージが彼女の観客への紹介を遅らせたりと意地悪をする所がユーモラスに描写されるのが、かつてのサイレント映画らしい雰囲気であります。
その後劇場の外で記者やカメラマンに囲まれてインタビューを受けるのも恒例だが、大勢のファンの中には女優の卵であるペピー・ミラーもいて、群衆に押されたペピーはジョージとぶつかってしまう。一瞬記者たちも凍り付くが、ジョージは怒ることもせずに笑顔で対応してくれた。
次の日、仕事を探しに撮影所にやって来たペピーは、ジョージ主演の映画に踊りの出来る女の子の役で採用された。勿論エキストラだ。撮影所内の物陰でダンスの練習をしていると、偶然に見えた彼女の綺麗な脚元が気に入ったジョージが声を掛け、二人は再会する。主演男優とエキストラのはずなのに二人が腕を組んで踊るシーンもあり、テイクを重ねていく間に妙な親近感が湧いてくるのだった。
出番の終わったペピーはお礼を言おうとジョージの楽屋を訪ねるも不在。つい部屋に残してあった彼の洋服に腕を通したりしているところを、帰ってきたジョージに見られ恥ずかしい思いもするが、大スターは女優の卵に優しくアドバイスをする。成功したいんなら個性を持たなきゃと、口元に付けぼくろを描いてやるのだった。
時代はサイレントからトーキー(発声映画)に移行する頃。
ジョージが所属する会社もこれからはサイレント映画は作らない方針となったが、トーキーに将来は無いと信じているジョージは会社を辞めて自身で無声映画を作ることにした。一方のペピーは徐々に知名度を上げ、ついにはトーキー映画の主役に躍り出るようになった。
恐慌の嵐が吹き、ジョージの財産も危うくなり、頼みの綱は新作映画のヒットだけだったが、皮肉な事に彼の新作の公開日はペピーの新作公開と重なることになった。はたして、埋まった客席がまばらなジョージの映画に対して、ペピーのトーキー新作は映画館の表の道路上にまで切符を買い求める観客が列をなしている状態だった・・・。
44歳で監督賞を獲ったミシェル・アザナヴィシウスについてウィキにこう書かれてました。
<監督のミシェル・アザナヴィシウスはサイレント映画時代の映画製作者を賞賛し、自身も長年サイレント映画を作ろうとしていた。・・・アザナヴィシウスは、全盛期のサイレント映画の多くはメロドラマであると考え、本作をメロドラマにすることにした。彼は1920年代のハリウッドに関して詳しい調査を行い、また、大量の字幕を使わずに物語を理解させるテクニックを見つけるためにサイレント映画を勉強した>
確かに少ない字幕でもストーリーはよく分かるし、字幕の入れ方もそつが無かったですね。個人的には後半の主人公の心情については、もう少し字幕なりが欲しいシーンもあったような気がしてます。
序盤のBGMはチャップリン映画でよく聴いたメロディーだったので懐かしかったし、愛犬ジャック君の演技も最高で、これもチャップリンを思い出しました。
序盤の劇中劇ともいえる新作映画の上映シーンで、観客の反応でストーリーを進めるテクニックが披露されていて、これはルビッチを参考にしたのかなぁとオールドファンは嬉しくなりましたね。
実はチャップリンの「モダン・タイムス (1936)」もトーキー時代に作られたサイレント映画で、建前はサイレントなのにトーキーならではのチャレンジもしていて、例えばちょっとした音やチャップリンの唄声を聞かせるというシーンがある。あれに挑戦したんでしょうか、この映画にもちょっとした音出しのシーンがありました。どんなものかは後日ネタバレ記事があるかも。
お薦め度は★三つ半。
後半の悩める主人公のシークエンスが長すぎると感じました。明らかにハッピーエンドで終わるはずの物語で暗い展開がしつこくないかと。それならそれでもう少し意外性のある展開が欲しいと思いましたね。
タイトルが「アーティスト」だからジョージが主人公だけど、予告編を観ると二人の恋物語とみるのが自然。その割にはヒロインの描写がバランス的には不足していると感じましたネ。それに個人的にはヒロインの魅力がいまいちかなと。新人さんの設定ですからね。ベレニス・ベジョは監督の奥さんだそうです。
でもま、クラシック映画への興味を広げてくれたんではないかと、おまけして★四つです。
脇役にも意外な人が出てて面白かったです。
ペピーの最初のお抱え運転手にエド・ローター。
ペピーのオーディションの時に隣に座ってた白髪のおじいさんはマルコム・マクダウェルでした。
ご存じ、2011年の米国アカデミー賞で作品賞他4部門でオスカーを受賞した作品であります。フランス製なんですけど、ハリウッドを舞台にしたからか、英語圏向けのバージョンがスタンダードだったせいなのか知りませんが・・。
最大の話題はその創作スタイル。サイレント時代のハリウッドを描くという事で、モノクロ・スタンダードサイズで、しかも無声映画なのでした。1971年に50年代を舞台にした「ラスト・ショー」がモノクロ画面で作られ話題になりましたが、ストーリー当時の雰囲気を出す為に採用するにしても21世紀にサイレントで作るってと、びっくりしたもんです。「アーティスト」は大凡一世紀前のムードを持ってこようとしたわけですネ。
*
 時は1927年のハリウッド。
時は1927年のハリウッド。無声映画の大スター、ジョージ・ヴァレンティンが、愛犬ジャックと共に新作の舞台挨拶に登場するのがオープニング。共演女優とは仲がよろしくないようで、ジョージが彼女の観客への紹介を遅らせたりと意地悪をする所がユーモラスに描写されるのが、かつてのサイレント映画らしい雰囲気であります。
その後劇場の外で記者やカメラマンに囲まれてインタビューを受けるのも恒例だが、大勢のファンの中には女優の卵であるペピー・ミラーもいて、群衆に押されたペピーはジョージとぶつかってしまう。一瞬記者たちも凍り付くが、ジョージは怒ることもせずに笑顔で対応してくれた。
次の日、仕事を探しに撮影所にやって来たペピーは、ジョージ主演の映画に踊りの出来る女の子の役で採用された。勿論エキストラだ。撮影所内の物陰でダンスの練習をしていると、偶然に見えた彼女の綺麗な脚元が気に入ったジョージが声を掛け、二人は再会する。主演男優とエキストラのはずなのに二人が腕を組んで踊るシーンもあり、テイクを重ねていく間に妙な親近感が湧いてくるのだった。
出番の終わったペピーはお礼を言おうとジョージの楽屋を訪ねるも不在。つい部屋に残してあった彼の洋服に腕を通したりしているところを、帰ってきたジョージに見られ恥ずかしい思いもするが、大スターは女優の卵に優しくアドバイスをする。成功したいんなら個性を持たなきゃと、口元に付けぼくろを描いてやるのだった。
時代はサイレントからトーキー(発声映画)に移行する頃。
ジョージが所属する会社もこれからはサイレント映画は作らない方針となったが、トーキーに将来は無いと信じているジョージは会社を辞めて自身で無声映画を作ることにした。一方のペピーは徐々に知名度を上げ、ついにはトーキー映画の主役に躍り出るようになった。
恐慌の嵐が吹き、ジョージの財産も危うくなり、頼みの綱は新作映画のヒットだけだったが、皮肉な事に彼の新作の公開日はペピーの新作公開と重なることになった。はたして、埋まった客席がまばらなジョージの映画に対して、ペピーのトーキー新作は映画館の表の道路上にまで切符を買い求める観客が列をなしている状態だった・・・。
*
44歳で監督賞を獲ったミシェル・アザナヴィシウスについてウィキにこう書かれてました。
<監督のミシェル・アザナヴィシウスはサイレント映画時代の映画製作者を賞賛し、自身も長年サイレント映画を作ろうとしていた。・・・アザナヴィシウスは、全盛期のサイレント映画の多くはメロドラマであると考え、本作をメロドラマにすることにした。彼は1920年代のハリウッドに関して詳しい調査を行い、また、大量の字幕を使わずに物語を理解させるテクニックを見つけるためにサイレント映画を勉強した>
確かに少ない字幕でもストーリーはよく分かるし、字幕の入れ方もそつが無かったですね。個人的には後半の主人公の心情については、もう少し字幕なりが欲しいシーンもあったような気がしてます。
序盤のBGMはチャップリン映画でよく聴いたメロディーだったので懐かしかったし、愛犬ジャック君の演技も最高で、これもチャップリンを思い出しました。
序盤の劇中劇ともいえる新作映画の上映シーンで、観客の反応でストーリーを進めるテクニックが披露されていて、これはルビッチを参考にしたのかなぁとオールドファンは嬉しくなりましたね。
実はチャップリンの「モダン・タイムス (1936)」もトーキー時代に作られたサイレント映画で、建前はサイレントなのにトーキーならではのチャレンジもしていて、例えばちょっとした音やチャップリンの唄声を聞かせるというシーンがある。あれに挑戦したんでしょうか、この映画にもちょっとした音出しのシーンがありました。どんなものかは後日ネタバレ記事があるかも。
お薦め度は★三つ半。
後半の悩める主人公のシークエンスが長すぎると感じました。明らかにハッピーエンドで終わるはずの物語で暗い展開がしつこくないかと。それならそれでもう少し意外性のある展開が欲しいと思いましたね。
タイトルが「アーティスト」だからジョージが主人公だけど、予告編を観ると二人の恋物語とみるのが自然。その割にはヒロインの描写がバランス的には不足していると感じましたネ。それに個人的にはヒロインの魅力がいまいちかなと。新人さんの設定ですからね。ベレニス・ベジョは監督の奥さんだそうです。
でもま、クラシック映画への興味を広げてくれたんではないかと、おまけして★四つです。
脇役にも意外な人が出てて面白かったです。
ペピーの最初のお抱え運転手にエド・ローター。
ペピーのオーディションの時に隣に座ってた白髪のおじいさんはマルコム・マクダウェルでした。
・お薦め度【★★★★=真の映画好きの、友達にも薦めて】 

(1950/ヴィンセント・ミネリ監督/スペンサー・トレイシー、ジョーン・ベネット、エリザベス・テイラー、ドン・テイラー、レオ・G・キャロル、ラスティ・タンブリン/93分)
allcinemaの解説氏も触れていますが、1971年に作られたボグダノヴィッチの「ラスト・ショー」の冒頭の映画館のシーンで流れている映画ですね。四十数年前の「ラスト・ショー」を観る前から知ってはいたものの未見だったし、それ以降もずっと食指の動かない作品でした。最近ちょっと訳がありまして観てみることにしました。
愛娘が彼氏にプロポーズされたと告白してから嫁に出すまでの、凡そ3か月間の父親の苦労話を人情味を交えながら面白おかしく描いたコメディであります。
観てて驚いたのが、半世紀以上前のアメリカでは結婚式や披露宴の費用は花嫁側の負担だという事。式場選びや披露宴の段取りも全て花嫁側の裁量で行われる。最近はそうでもないらしいですが、当時はそういう事らしいです。嫁取り婿取りの儀式ではなく、嫁に送り出すお祝いという意味なんでしょうか。前提条件としてこれは頭に入れておいた方が話はすんなり入って来るでしょう。
映画の前年度にベストセラーになったエドワード・ストリーターの小説が原作。ストリーターは軍隊物のユーモア小説で有名なのだそうです。
 舞台はハッキリしないが東地区のニューヨークに近い町でしょう。緑の芝生が美しい住宅街の一家のお話です。
舞台はハッキリしないが東地区のニューヨークに近い町でしょう。緑の芝生が美しい住宅街の一家のお話です。
スペンサー・トレイシー扮する父親の名はスタンリー・バンクス。自身の事務所を構えている弁護士ですがベラボーに裕福というわけではなく、一戸建ての家のローンも少しだがまだ残っている状況です。
母親はジョーン・ベネット扮するエリー・バンクス。良妻賢母を絵にかいたような奥さんであります。
そして夫婦には三人の子供がいて、長女にして唯一の女の子がキャサリン。扮するは当時18歳のエリザベス・テイラー。
キャサリンは愛称ケイ。20歳という設定でしたが、リズさんの違和感ない色気がかえって初々しさを損なってる感じがしないでもないです。勿論これは個人的感想ですが。
あと男の子は工学部の学生という長男と中学生くらいの次男坊。次男坊トミーを演じていたのは「ウエストサイド物語」等のラス・タンブリンで、当時はラスティと云っていたようです。この男の子たちはそんなに出番がありませんがね。
さて、もう一人の重要な役ケイのフィアンセはというと、偶然にもエリザベスさんと同じ姓のドン・テイラー扮するどこにでもいる(多分)金髪碧眼の青年バックリー・ダンストン。序盤でスタンリーが今までケイが連れてきたボーイフレンド達を回想するシーンがありますが、“オツムの軽い筋肉マン”として紹介された青年でした。
そうそう、この作品は結婚披露宴が終わって散らかり放題の我が家で (この頃は披露宴は自宅でするのが普通の様です) スタンリーが回想している所から始まるのですが、途中途中にも彼のモノローグが入るスタイルになっています。
彼氏の品定めから、彼の実家を訪れての両親への挨拶 (当然、家庭環境の調査も兼ねております) 、そして冒頭にも書いたように結婚式を何処でやるかとか、招待客の選定とか、披露宴の準備とか、花嫁の親としてやるべき事柄をこなしていく。
小津安二郎作品のような肉親間の人情の襞を味わおうとすると物足りないけれど、あちらにはあちらなりの苦労があるんだなぁという事は分かるようになっていますね。それをユーモアを交えながら、さもありなんと思わせるエピソードにしています。経費を抑えるために20年前に作ったモーニングを無理やり着たら破けちゃったとかネ。
あちらには婚約披露パーティなんちゅうのもあるみたいで、これもスタンリーの自宅でやっていて、この時は父親がお客の飲み物をサービスする係となるのですが、本人はスピーチを用意していたのに結局お酒作りばかりに縛られて、気が付いたら殆どの客が帰ってしまっていたというオチがあったりします。

脚本を書いたのは、アルバート・ハケットとフランセス・グッドリッチの夫婦。この夫婦は「素晴らしき哉、人生! (1946)」や「略奪された七人の花嫁 (1954)」、「アンネの日記 (1959)」等を書いた名コンビです。
お勧め度は★三つ。
父親と娘との思い違いや言葉不足の為の葛藤が殆ど口喧嘩で始っていて、収まり方も形式的で、親子の情愛というのが表面的な感じがしたこと等もマイナス要因でしょうか。
アカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、脚色賞にノミネート。
因みにバックリー役のドン・テイラーは後に演出家になったそうですが、「新・猿の惑星 (1971)」の監督ドン・テイラーが彼だったとは・・・。
allcinemaの解説氏も触れていますが、1971年に作られたボグダノヴィッチの「ラスト・ショー」の冒頭の映画館のシーンで流れている映画ですね。四十数年前の「ラスト・ショー」を観る前から知ってはいたものの未見だったし、それ以降もずっと食指の動かない作品でした。最近ちょっと訳がありまして観てみることにしました。
愛娘が彼氏にプロポーズされたと告白してから嫁に出すまでの、凡そ3か月間の父親の苦労話を人情味を交えながら面白おかしく描いたコメディであります。
観てて驚いたのが、半世紀以上前のアメリカでは結婚式や披露宴の費用は花嫁側の負担だという事。式場選びや披露宴の段取りも全て花嫁側の裁量で行われる。最近はそうでもないらしいですが、当時はそういう事らしいです。嫁取り婿取りの儀式ではなく、嫁に送り出すお祝いという意味なんでしょうか。前提条件としてこれは頭に入れておいた方が話はすんなり入って来るでしょう。
映画の前年度にベストセラーになったエドワード・ストリーターの小説が原作。ストリーターは軍隊物のユーモア小説で有名なのだそうです。
*
 舞台はハッキリしないが東地区のニューヨークに近い町でしょう。緑の芝生が美しい住宅街の一家のお話です。
舞台はハッキリしないが東地区のニューヨークに近い町でしょう。緑の芝生が美しい住宅街の一家のお話です。スペンサー・トレイシー扮する父親の名はスタンリー・バンクス。自身の事務所を構えている弁護士ですがベラボーに裕福というわけではなく、一戸建ての家のローンも少しだがまだ残っている状況です。
母親はジョーン・ベネット扮するエリー・バンクス。良妻賢母を絵にかいたような奥さんであります。
そして夫婦には三人の子供がいて、長女にして唯一の女の子がキャサリン。扮するは当時18歳のエリザベス・テイラー。
キャサリンは愛称ケイ。20歳という設定でしたが、リズさんの違和感ない色気がかえって初々しさを損なってる感じがしないでもないです。勿論これは個人的感想ですが。
あと男の子は工学部の学生という長男と中学生くらいの次男坊。次男坊トミーを演じていたのは「ウエストサイド物語」等のラス・タンブリンで、当時はラスティと云っていたようです。この男の子たちはそんなに出番がありませんがね。
さて、もう一人の重要な役ケイのフィアンセはというと、偶然にもエリザベスさんと同じ姓のドン・テイラー扮するどこにでもいる(多分)金髪碧眼の青年バックリー・ダンストン。序盤でスタンリーが今までケイが連れてきたボーイフレンド達を回想するシーンがありますが、“オツムの軽い筋肉マン”として紹介された青年でした。
そうそう、この作品は結婚披露宴が終わって散らかり放題の我が家で (この頃は披露宴は自宅でするのが普通の様です) スタンリーが回想している所から始まるのですが、途中途中にも彼のモノローグが入るスタイルになっています。
彼氏の品定めから、彼の実家を訪れての両親への挨拶 (当然、家庭環境の調査も兼ねております) 、そして冒頭にも書いたように結婚式を何処でやるかとか、招待客の選定とか、披露宴の準備とか、花嫁の親としてやるべき事柄をこなしていく。
小津安二郎作品のような肉親間の人情の襞を味わおうとすると物足りないけれど、あちらにはあちらなりの苦労があるんだなぁという事は分かるようになっていますね。それをユーモアを交えながら、さもありなんと思わせるエピソードにしています。経費を抑えるために20年前に作ったモーニングを無理やり着たら破けちゃったとかネ。
あちらには婚約披露パーティなんちゅうのもあるみたいで、これもスタンリーの自宅でやっていて、この時は父親がお客の飲み物をサービスする係となるのですが、本人はスピーチを用意していたのに結局お酒作りばかりに縛られて、気が付いたら殆どの客が帰ってしまっていたというオチがあったりします。

脚本を書いたのは、アルバート・ハケットとフランセス・グッドリッチの夫婦。この夫婦は「素晴らしき哉、人生! (1946)」や「略奪された七人の花嫁 (1954)」、「アンネの日記 (1959)」等を書いた名コンビです。
お勧め度は★三つ。
父親と娘との思い違いや言葉不足の為の葛藤が殆ど口喧嘩で始っていて、収まり方も形式的で、親子の情愛というのが表面的な感じがしたこと等もマイナス要因でしょうか。
アカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、脚色賞にノミネート。
因みにバックリー役のドン・テイラーは後に演出家になったそうですが、「新・猿の惑星 (1971)」の監督ドン・テイラーが彼だったとは・・・。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

「ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅」の記事で、ラストシーンは親孝行の良い話になって嬉しい気持ちになりますと書いていますが、この辺りを書き残しておこうと思います。
無論勿論、本編未見の方には“ネタバレ注意”です。
町の皆にウディの宝くじが偽物と分かるのは、ウディの二人の甥っ子が宝くじが当たったと知らせてきた手紙をクジごと強奪したからで、デイビッドとウディが酒場から出てくるところを似たような体型の二人がマスクをつけて待ち伏せるショットが情けないやら可笑しいやら。
伯父の家に戻るとバカ甥二人は偽物のくじなんか捨てたとあっさり白状、ウディとデイビッドは酒場の近くに戻って探す事になるが、ひと休みにと入った酒場で、誰かに拾われたその手紙をエド・ピグラムが嘲笑を交えて披露している所に出くわす。
若い時から人に頼まれごとをすると嫌と言えない性分だったウディ。エドがバカにしているのは明らかなのに、ウディは黙って大事そうにその手紙を受け取るのだ。
つい先日まで、ウディの宝くじの恩恵にあずかろうと脅迫めいた事までのたまっていたエド。ウディの代わりに睨み返したデイビッドはついに彼を殴り倒す。
酒場を出た二人は外灯の近くでしゃがみ込み話す。デイビッドには父親の真意が分からなかったのだ。夫婦二人で暮らしていくのには充分な蓄えがあるのに何故そんなに大金を欲しがるのか?
『新品のトラックが買いたいんだ』
『トラックなんか100万ドルも要らないじゃないか。残りはどうするの?』
『残りはお前たちにやる』
酒を飲んでばかりで、息子たちの面倒もそれ程みてこなかった。ウディにはその事に後悔があったのだ。せめて何かを残したい、息子たちの為に。それが100万ドルを欲しがる理由だったのだ。
一旦は100万ドルを諦めたかにみえたウディだが、最終的にはデイビッドは父親をリンカーンの件の手紙を出した会社に連れて行く。
ケイトが帰りしなに言ったように、この後ウディが家族のせいで大金を逃したかのように思い込んでしまったら大変だと思ったのかもしれない。
読者獲得の為に出した手紙に付いていたくじの番号は、100万ドルの当選番号とは一致しなかったために、ウディには残念賞の(賞金獲得者というロゴ入りの)キャップだけが渡される。
助手席でガックリうなだれるウディ。
そんな父親の姿を見た息子は一計を講じる。
『父さん、モンタナに帰るよ。でもその前に2、3寄る所がある』
『好きにしろ』
デイビッドが考えた親孝行。
それは、ウディが100万ドルが当たったらやりたいと言っていた、トラックを買うこととコンプレッサーを手に入れる事でした。
モンタナから乗ってきた日本製の乗用車と中古だけど新品同様のピックアップトラックを中古車屋で交換し、途中の機械屋さんで新品のコンプレッサーを買う。
ウディの名義で登録したトラックを走らせるデイビッド。
ホーソーンの入口では運転席をウディと入れ替わり、父親に運転をさせた。
デイビッドを助手席の下に潜り込ませ、まるで一人のようにドライブするウディ。
『かっこいいぞ、ウディ』と声を掛ける昔なじみ。片頬にデイビッドに殴られた跡が残るエド・ピグラムはあっけにとられた表情。
ケイトが現れるまではウディの元カノだった、地元の新聞社の発行人のおばあちゃんが見送る顔には、ウディの方が驚いた様でしたが・・・。
無論勿論、本編未見の方には“ネタバレ注意”です。
町の皆にウディの宝くじが偽物と分かるのは、ウディの二人の甥っ子が宝くじが当たったと知らせてきた手紙をクジごと強奪したからで、デイビッドとウディが酒場から出てくるところを似たような体型の二人がマスクをつけて待ち伏せるショットが情けないやら可笑しいやら。
伯父の家に戻るとバカ甥二人は偽物のくじなんか捨てたとあっさり白状、ウディとデイビッドは酒場の近くに戻って探す事になるが、ひと休みにと入った酒場で、誰かに拾われたその手紙をエド・ピグラムが嘲笑を交えて披露している所に出くわす。
若い時から人に頼まれごとをすると嫌と言えない性分だったウディ。エドがバカにしているのは明らかなのに、ウディは黙って大事そうにその手紙を受け取るのだ。
つい先日まで、ウディの宝くじの恩恵にあずかろうと脅迫めいた事までのたまっていたエド。ウディの代わりに睨み返したデイビッドはついに彼を殴り倒す。
酒場を出た二人は外灯の近くでしゃがみ込み話す。デイビッドには父親の真意が分からなかったのだ。夫婦二人で暮らしていくのには充分な蓄えがあるのに何故そんなに大金を欲しがるのか?
『新品のトラックが買いたいんだ』
『トラックなんか100万ドルも要らないじゃないか。残りはどうするの?』
『残りはお前たちにやる』
酒を飲んでばかりで、息子たちの面倒もそれ程みてこなかった。ウディにはその事に後悔があったのだ。せめて何かを残したい、息子たちの為に。それが100万ドルを欲しがる理由だったのだ。
*
一旦は100万ドルを諦めたかにみえたウディだが、最終的にはデイビッドは父親をリンカーンの件の手紙を出した会社に連れて行く。
ケイトが帰りしなに言ったように、この後ウディが家族のせいで大金を逃したかのように思い込んでしまったら大変だと思ったのかもしれない。
読者獲得の為に出した手紙に付いていたくじの番号は、100万ドルの当選番号とは一致しなかったために、ウディには残念賞の(賞金獲得者というロゴ入りの)キャップだけが渡される。
助手席でガックリうなだれるウディ。
そんな父親の姿を見た息子は一計を講じる。
『父さん、モンタナに帰るよ。でもその前に2、3寄る所がある』
『好きにしろ』
デイビッドが考えた親孝行。
それは、ウディが100万ドルが当たったらやりたいと言っていた、トラックを買うこととコンプレッサーを手に入れる事でした。
モンタナから乗ってきた日本製の乗用車と中古だけど新品同様のピックアップトラックを中古車屋で交換し、途中の機械屋さんで新品のコンプレッサーを買う。
ウディの名義で登録したトラックを走らせるデイビッド。
ホーソーンの入口では運転席をウディと入れ替わり、父親に運転をさせた。
デイビッドを助手席の下に潜り込ませ、まるで一人のようにドライブするウディ。
『かっこいいぞ、ウディ』と声を掛ける昔なじみ。片頬にデイビッドに殴られた跡が残るエド・ピグラムはあっけにとられた表情。
ケイトが現れるまではウディの元カノだった、地元の新聞社の発行人のおばあちゃんが見送る顔には、ウディの方が驚いた様でしたが・・・。
(2013/アレクサンダー・ペイン監督/ブルース・ダーン、ウィル・フォーテ、ジューン・スキッブ、ステイシー・キーチ、ボブ・オデンカーク/115分)
しばらく旧い作品が続いたのでレンタルショップで比較的新しい映画を借りてきました。4年前のどこが新しいんだと言われる方もおられるでしょうが、テアトル十瑠としては新作の範疇でありますぞ。
「サイドウェイ」で名前を覚えたアレクサンダー・ペインの作品ですね。「サイドウェイ」と同じくロード・ムーヴィーで、それもずっと旅を追っていくのではなく旅先でのアレコレが主な話と言うのも似ております。
2013年のアカデミー賞で作品賞他5部門にノミネートされた作品で、なんとモノクロ画面。地平線が印象的なアメリカ中西部を旅するロード・ムーヴィーでモノクロ作品、といえば僕らの世代では「ペーパー・ムーン」を思い出しますが、あちらがレトロな雰囲気を醸し出すスタンダードサイズだったのに対して、こちらは大地の広さを感じさせるワイドサイズで撮られておりました。
ジョン・フォードの西部劇を彷彿とするような抜けるような青空(モノクロなのにそんな感じ)と白い雲と、とにかく風景が美しい。撮影はフェドン・パパマイケル。「サイドウェイ」も撮ったパパマイケルさんはこの作品でオスカーにノミネートされたようです。
 モンタナ州に住む老人ウディ・グラント。元々口数が少ないのに、口うるさい妻のケイトの前では余計に会話も無くなり、ケイトからはボケ老人の様に見られ始めている。
モンタナ州に住む老人ウディ・グラント。元々口数が少ないのに、口うるさい妻のケイトの前では余計に会話も無くなり、ケイトからはボケ老人の様に見られ始めている。
突然届いた100万ドルの1等宝くじに当選したというダイレクトメールを信用した彼は、当選金を受け取るべくネブラスカ州リンカーンに向かおうとするが、高齢の為に運転免許証を返納しており、歩いて高速道路にまで入っていくのでパトカーに捕まってしまう。
何度目かの警察沙汰に根負けした次男デイビッドは、仕事を休んで父親に付き合う事にした。老い先短い父親の気のすむようにしてやろうと思ったのだ。ネブラスカ州まではモンタナからワイオミング、サウスダコタを越えて千キロ以上の長旅。途中の宿泊先で酒を飲んで転んで頭にケガをしたウディは一時入院することになり、週内にはリンカーンに行けなくなってしまう。
リンカーンの手前の町ホーソーンは実はウディの生まれ故郷。土日を兄レイの家に滞在することになったウディは酒場で昔なじみに会う事になるが、彼がふと漏らした宝くじ当選の噂は一晩にして小さな町中に知れ渡ってしまう・・・。
主役はボケ老人のウディになっていますが、ドラマの軸は次男のデイビッドといっていいですね。タイトルの「ふたつの心」とは当然この親子の事であります。
父親の故郷で初めて知る父親の過去。重い話ではないですが、大酒呑みで家族を顧みなかった父親が昔なじみにどう思われているかを知ることによって、父親の人生に思いをはせる息子を描いた映画と思いました。
日曜日にはケイトや長男のロスもホーソーンにやってきて何十年ぶりかの親族の再会パーティーが開かれるが、親族にも宝くじの件はばれており、いくらケイト達がウディの勘違いだと否定しても却って隠そうとしていると誤解されるのが可笑しいやら怖いやら。急に有名人になった人々に親戚が増えるのと似ていて、コチラはにわか長者に対してホントか嘘かもわからない過去の借金の返済を迫る人々が出てくるって事。小言ばかりの婆さんだと思われたケイトが、ピシッと言いがかりを撥ね付けるのが気持ちよかったです。
偽の宝くじ当選話の決着は如何に?
ラストシーンは親孝行の良い話になって嬉しい気持ちになりますが、似たようなBGMで思い出した「ストレイト・ストーリー」の感慨深さには及びませんでした。
ウディを演じたのはローラ・ダーンの父親ブルース。「華麗なるギャツビー (1974)」、「ファミリー・プロット (1976)」の頃しか覚えてないので、事前情報がなければ彼とウディは結びつかないでしょうね。ウディのよたよた歩き、お見事です。
そして、オープニング・クレジットで気づいたステイシー・キーチ。役はウディのかつての仕事仲間エド・ピグラム。
知り合いが大金持ちになりそうだと知った人間がどう変化するか。歳をとってもやっぱり憎たらしい男がお似合いですな。
アカデミー賞以外にも、ゴールデン・グローブ、英国アカデミー賞、カンヌ国際映画祭、LA批評家協会賞などで複数の部門でノミネートされた佳作です。
僕のお薦め度は★三つ半。★四つにするだけのおまけが見つかりませんでした。
※ネタバレ備忘録はコチラです。
しばらく旧い作品が続いたのでレンタルショップで比較的新しい映画を借りてきました。4年前のどこが新しいんだと言われる方もおられるでしょうが、テアトル十瑠としては新作の範疇でありますぞ。
「サイドウェイ」で名前を覚えたアレクサンダー・ペインの作品ですね。「サイドウェイ」と同じくロード・ムーヴィーで、それもずっと旅を追っていくのではなく旅先でのアレコレが主な話と言うのも似ております。
2013年のアカデミー賞で作品賞他5部門にノミネートされた作品で、なんとモノクロ画面。地平線が印象的なアメリカ中西部を旅するロード・ムーヴィーでモノクロ作品、といえば僕らの世代では「ペーパー・ムーン」を思い出しますが、あちらがレトロな雰囲気を醸し出すスタンダードサイズだったのに対して、こちらは大地の広さを感じさせるワイドサイズで撮られておりました。
ジョン・フォードの西部劇を彷彿とするような抜けるような青空(モノクロなのにそんな感じ)と白い雲と、とにかく風景が美しい。撮影はフェドン・パパマイケル。「サイドウェイ」も撮ったパパマイケルさんはこの作品でオスカーにノミネートされたようです。
*
 モンタナ州に住む老人ウディ・グラント。元々口数が少ないのに、口うるさい妻のケイトの前では余計に会話も無くなり、ケイトからはボケ老人の様に見られ始めている。
モンタナ州に住む老人ウディ・グラント。元々口数が少ないのに、口うるさい妻のケイトの前では余計に会話も無くなり、ケイトからはボケ老人の様に見られ始めている。突然届いた100万ドルの1等宝くじに当選したというダイレクトメールを信用した彼は、当選金を受け取るべくネブラスカ州リンカーンに向かおうとするが、高齢の為に運転免許証を返納しており、歩いて高速道路にまで入っていくのでパトカーに捕まってしまう。
何度目かの警察沙汰に根負けした次男デイビッドは、仕事を休んで父親に付き合う事にした。老い先短い父親の気のすむようにしてやろうと思ったのだ。ネブラスカ州まではモンタナからワイオミング、サウスダコタを越えて千キロ以上の長旅。途中の宿泊先で酒を飲んで転んで頭にケガをしたウディは一時入院することになり、週内にはリンカーンに行けなくなってしまう。
リンカーンの手前の町ホーソーンは実はウディの生まれ故郷。土日を兄レイの家に滞在することになったウディは酒場で昔なじみに会う事になるが、彼がふと漏らした宝くじ当選の噂は一晩にして小さな町中に知れ渡ってしまう・・・。
*
主役はボケ老人のウディになっていますが、ドラマの軸は次男のデイビッドといっていいですね。タイトルの「ふたつの心」とは当然この親子の事であります。
父親の故郷で初めて知る父親の過去。重い話ではないですが、大酒呑みで家族を顧みなかった父親が昔なじみにどう思われているかを知ることによって、父親の人生に思いをはせる息子を描いた映画と思いました。
日曜日にはケイトや長男のロスもホーソーンにやってきて何十年ぶりかの親族の再会パーティーが開かれるが、親族にも宝くじの件はばれており、いくらケイト達がウディの勘違いだと否定しても却って隠そうとしていると誤解されるのが可笑しいやら怖いやら。急に有名人になった人々に親戚が増えるのと似ていて、コチラはにわか長者に対してホントか嘘かもわからない過去の借金の返済を迫る人々が出てくるって事。小言ばかりの婆さんだと思われたケイトが、ピシッと言いがかりを撥ね付けるのが気持ちよかったです。
偽の宝くじ当選話の決着は如何に?
ラストシーンは親孝行の良い話になって嬉しい気持ちになりますが、似たようなBGMで思い出した「ストレイト・ストーリー」の感慨深さには及びませんでした。
ウディを演じたのはローラ・ダーンの父親ブルース。「華麗なるギャツビー (1974)」、「ファミリー・プロット (1976)」の頃しか覚えてないので、事前情報がなければ彼とウディは結びつかないでしょうね。ウディのよたよた歩き、お見事です。
そして、オープニング・クレジットで気づいたステイシー・キーチ。役はウディのかつての仕事仲間エド・ピグラム。
知り合いが大金持ちになりそうだと知った人間がどう変化するか。歳をとってもやっぱり憎たらしい男がお似合いですな。
アカデミー賞以外にも、ゴールデン・グローブ、英国アカデミー賞、カンヌ国際映画祭、LA批評家協会賞などで複数の部門でノミネートされた佳作です。
僕のお薦め度は★三つ半。★四つにするだけのおまけが見つかりませんでした。
※ネタバレ備忘録はコチラです。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(1964/スタンリー・キューブリック監督・共同脚本/ピーター・セラーズ、ジョージ・C・スコット、スターリング・ヘイドン、スリム・ピケンズ、キーナン・ウィン、ジェームズ・アール・ジョーンズ、トレイシー・リード/93分)
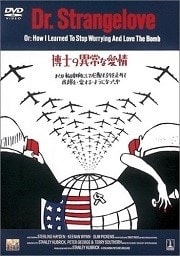 スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅 (1968)」の前作でありますな。そしてその前が「ロリータ (1961)」になる。寡作だけど実に多彩な題材であります。時々難解な作風になることもあるけれど、これは分かりやすかった。いわゆる風刺ブラックコメディで、今作の風刺の矛先は戦争だ。
スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅 (1968)」の前作でありますな。そしてその前が「ロリータ (1961)」になる。寡作だけど実に多彩な題材であります。時々難解な作風になることもあるけれど、これは分かりやすかった。いわゆる風刺ブラックコメディで、今作の風刺の矛先は戦争だ。
ピーター・ジョージってイギリスの作家の原作があって、原題は【Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb】。この長いのは日本語タイトルにもなっていて、『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』なんて表記することもある。
Dr. Strangeloveはピーター・セラーズ扮する、ドイツからアメリカにやって来た科学者の名前なんだけど、かといってこの博士が主役というわけでもない。なんでこんなタイトルになったんだろう?ひょっとして原作は博士による記述みたいなスタイルになっているのかな?
脚本はこのジョージさんとキューブリック、そして風刺と言えばこの人って感じのテリー・サザーンの三人共作であります。
製作年が1964年だから、米ソ冷戦時代でありますな。北極海のある島でソ連が新兵器の開発をしているらしいというナレーションの後、オープニングタイトルバックでは、アメリカ空軍の戦闘機が飛行しながらの給油を受けている映像が流れていて、そのBGMがまるで『♪ジェットストリーム~』という城達也の甘い声が聞こえてきそうなストリングスの曲。ラストのエンディング・ロールもこのオープニングに呼応するように、画面は衝撃的な映像なのにBGMは女性ボーカルのラブソングが流れるという洒落た作りになっておりました。洒落たというか、背筋が凍るようなキツイ皮肉なんですけどね。
さて、物語の発端はアメリカ空軍ナンバー2の准将が嘘の攻撃命令を出すところから。冷戦時代だからソ連の周りには三十有余機のアメリカ軍の爆撃機が常時飛び回っているんだけど、准将は本土がソ連の攻撃を受けた場合の反撃を記したR作戦の実行指令を勝手に出しちゃうんですね。勿論アメリカは攻撃されてないのに。
スターリング・ヘイドン扮するこの准将は、祖国が共産主義者に侵されているという勝手な妄想に取付かれていて、反撃計画は大統領の確認なんか待ってる暇はないから准将の判断で実行できるって所に乗っかっちゃったわけ。准将は空軍のナンバー2だけど、空軍基地のトップに座っている人物なので可能なんだ。
後でおいおい分かるんだけど、彼の名前がジャック・リッパーって言うから笑っちゃうよね。この名前で直ぐに彼が狂人だというのが分かる。
ソ連に向かう空軍機は、第三次世界大戦級の話だから一応指令を出した基地に確認するけど、基地の連中もトップ命令でラジオが没収されていてニュースも聞けない状況にされていたので、そのまま攻撃続行になってしまうんだ。
驚いた政府はリッパー准将に連絡を取ろうとするけれど当然音信は不通。ペンタゴンに大統領以下政府の要人、陸海空軍のトップも揃って核戦争勃発を回避するべく対策会議が開かれる。
空軍のトップに扮するのがジョージ・C・スコット。この軍人も秘書と懇ろになっているってシーンが出てきたり、会議の流れではこのままソ連を攻撃しちゃいましょうよ、なんて物騒なことをしゃべるといういい加減な人間として描かれている。
一方、空軍基地ではリッパーの異変にいち早く気付いた副官であるマンダレイク大佐が、彼を諫めようとするが逆に司令官室に監禁されてしまう。このマンダレイクに扮するのがピーター・セラーズで、同盟国のイギリスから派遣されているという設定。後には、ペンタゴンの指令でリッパー制圧に陸軍がやって来るんだけど、マンダレイクもリッパーの籠城につき合わされることになる。彼の運の悪さが笑いを誘う所であります。
映画は、この空軍基地のリッパーとマンダレイクのやり取り、ペンタゴンの会議の行方、そして嘘の指令を受けてソ連攻撃に向かう一機の爆撃機の様子をパラレルに描いています。
ペンタゴンの会議中にはソ連の駐米大使が出て来たリ、ソ連の首相に直接電話を掛けたりしてまして、はてホットラインはもう有ったのかなと思ったら、キューバ危機の後だからもう出来てたんですね。電話でしか出てこないあの首相(声も聞こえなくて、大統領の受け答えでしかわからないんだけど)も、酔っぱらいのヒステリー持ちの変な奴だった。
ピーター・セラーズは一人三役で、マンダレイク大佐とドイツからやって来た科学者ストレンジラブ博士とペンタゴンの会議に出席しているアメリカ大統領を演じています。
大佐も大統領も賢明で善良な人物でしたけど、博士は不気味な怪演でありました。
爆撃機の乗組員の一人に若き日のジェームズ・アール・ジョーンズが出ていたのが懐かしかったです。
スリム・ピケンズは、最後までソ連の攻撃目標に向かっていく爆撃機の機長キングコング少佐の役でした。常識人に見えた少佐が徐々に狂気を帯びていく所も怖かったです。
ツイッターにも書いたけど、ジョージ・C・スコットの演技は強面の割にはハシャギ過ぎの印象が残ったな。
1964年のアカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、監督賞、脚色賞にノミネート。
NY批評家協会賞では監督賞を受賞。
英国アカデミー賞でも、作品賞と美術賞(モノクロ)を獲得したそうです。
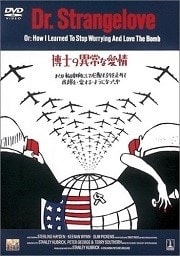 スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅 (1968)」の前作でありますな。そしてその前が「ロリータ (1961)」になる。寡作だけど実に多彩な題材であります。時々難解な作風になることもあるけれど、これは分かりやすかった。いわゆる風刺ブラックコメディで、今作の風刺の矛先は戦争だ。
スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅 (1968)」の前作でありますな。そしてその前が「ロリータ (1961)」になる。寡作だけど実に多彩な題材であります。時々難解な作風になることもあるけれど、これは分かりやすかった。いわゆる風刺ブラックコメディで、今作の風刺の矛先は戦争だ。ピーター・ジョージってイギリスの作家の原作があって、原題は【Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb】。この長いのは日本語タイトルにもなっていて、『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』なんて表記することもある。
Dr. Strangeloveはピーター・セラーズ扮する、ドイツからアメリカにやって来た科学者の名前なんだけど、かといってこの博士が主役というわけでもない。なんでこんなタイトルになったんだろう?ひょっとして原作は博士による記述みたいなスタイルになっているのかな?
脚本はこのジョージさんとキューブリック、そして風刺と言えばこの人って感じのテリー・サザーンの三人共作であります。
製作年が1964年だから、米ソ冷戦時代でありますな。北極海のある島でソ連が新兵器の開発をしているらしいというナレーションの後、オープニングタイトルバックでは、アメリカ空軍の戦闘機が飛行しながらの給油を受けている映像が流れていて、そのBGMがまるで『♪ジェットストリーム~』という城達也の甘い声が聞こえてきそうなストリングスの曲。ラストのエンディング・ロールもこのオープニングに呼応するように、画面は衝撃的な映像なのにBGMは女性ボーカルのラブソングが流れるという洒落た作りになっておりました。洒落たというか、背筋が凍るようなキツイ皮肉なんですけどね。
さて、物語の発端はアメリカ空軍ナンバー2の准将が嘘の攻撃命令を出すところから。冷戦時代だからソ連の周りには三十有余機のアメリカ軍の爆撃機が常時飛び回っているんだけど、准将は本土がソ連の攻撃を受けた場合の反撃を記したR作戦の実行指令を勝手に出しちゃうんですね。勿論アメリカは攻撃されてないのに。
スターリング・ヘイドン扮するこの准将は、祖国が共産主義者に侵されているという勝手な妄想に取付かれていて、反撃計画は大統領の確認なんか待ってる暇はないから准将の判断で実行できるって所に乗っかっちゃったわけ。准将は空軍のナンバー2だけど、空軍基地のトップに座っている人物なので可能なんだ。
後でおいおい分かるんだけど、彼の名前がジャック・リッパーって言うから笑っちゃうよね。この名前で直ぐに彼が狂人だというのが分かる。
ソ連に向かう空軍機は、第三次世界大戦級の話だから一応指令を出した基地に確認するけど、基地の連中もトップ命令でラジオが没収されていてニュースも聞けない状況にされていたので、そのまま攻撃続行になってしまうんだ。
驚いた政府はリッパー准将に連絡を取ろうとするけれど当然音信は不通。ペンタゴンに大統領以下政府の要人、陸海空軍のトップも揃って核戦争勃発を回避するべく対策会議が開かれる。
空軍のトップに扮するのがジョージ・C・スコット。この軍人も秘書と懇ろになっているってシーンが出てきたり、会議の流れではこのままソ連を攻撃しちゃいましょうよ、なんて物騒なことをしゃべるといういい加減な人間として描かれている。
一方、空軍基地ではリッパーの異変にいち早く気付いた副官であるマンダレイク大佐が、彼を諫めようとするが逆に司令官室に監禁されてしまう。このマンダレイクに扮するのがピーター・セラーズで、同盟国のイギリスから派遣されているという設定。後には、ペンタゴンの指令でリッパー制圧に陸軍がやって来るんだけど、マンダレイクもリッパーの籠城につき合わされることになる。彼の運の悪さが笑いを誘う所であります。
映画は、この空軍基地のリッパーとマンダレイクのやり取り、ペンタゴンの会議の行方、そして嘘の指令を受けてソ連攻撃に向かう一機の爆撃機の様子をパラレルに描いています。
ペンタゴンの会議中にはソ連の駐米大使が出て来たリ、ソ連の首相に直接電話を掛けたりしてまして、はてホットラインはもう有ったのかなと思ったら、キューバ危機の後だからもう出来てたんですね。電話でしか出てこないあの首相(声も聞こえなくて、大統領の受け答えでしかわからないんだけど)も、酔っぱらいのヒステリー持ちの変な奴だった。
ピーター・セラーズは一人三役で、マンダレイク大佐とドイツからやって来た科学者ストレンジラブ博士とペンタゴンの会議に出席しているアメリカ大統領を演じています。
大佐も大統領も賢明で善良な人物でしたけど、博士は不気味な怪演でありました。
爆撃機の乗組員の一人に若き日のジェームズ・アール・ジョーンズが出ていたのが懐かしかったです。
スリム・ピケンズは、最後までソ連の攻撃目標に向かっていく爆撃機の機長キングコング少佐の役でした。常識人に見えた少佐が徐々に狂気を帯びていく所も怖かったです。
ツイッターにも書いたけど、ジョージ・C・スコットの演技は強面の割にはハシャギ過ぎの印象が残ったな。
1964年のアカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、監督賞、脚色賞にノミネート。
NY批評家協会賞では監督賞を受賞。
英国アカデミー賞でも、作品賞と美術賞(モノクロ)を獲得したそうです。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 

■ YouTube Selection (予告編)
■ Information&Addition
※gooさんからの告知です:<「トラックバック機能」について、ご利用者数の減少およびスパム利用が多いことから、送受信ともに2017年11月27日(月)にて機能の提供を終了させていただきます>[2017.11.12]
●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。
●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に暫定的に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。
●2025年2月にブログ名を「テアトル十瑠」から「::: テアトル十瑠 :::」に変えました。
●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。
◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
*
●映画の紹介、感想、関連コラム、その他諸々綴っています。
●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。
●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に暫定的に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。
●2025年2月にブログ名を「テアトル十瑠」から「::: テアトル十瑠 :::」に変えました。
●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。
*
◆【管理人について】
HNの十瑠(ジュール)は、あるサイトに登録したペンネーム「鈴木十瑠」の名前部分をとったもの。由来は少年時代に沢山の愛読書を提供してくれたフランスの作家「ジュール・ヴェルヌ」を捩ったものです。
◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。
*
 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)