世界一の長生き大国日本、長寿の陰にボケ老人確実に増加中
なんて題名・・・イヤだねえ^
その仲間にはいるやもしれない我が身としては・・・
長寿かならずしも嬉しからずや・・・・・
寝たきりで10年なんてひとも。
しかし、本当の健康長寿ならだれも文句言えやしないのだが・・・
20年前の本ですので、当たり外れも多いかと思いますが
そこは賢明なアナタの取捨選択眼にかかております。はい。
松本英聖著 「21世紀の医学革命へ」より
20年前の本ですよ。1995年?
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
10P
医療・年金@の急増で日本経済は崩壊
バブル崩壊と円高で日本経済は今なお低迷しているが、しかし、一方では、「医療・年金」など社会保障費が急増。総額の伸び率は、この十年間で七倍増となった。この伸び率は国民所得の伸び率(三倍)の二倍以上というハイ・ペース。
現に今、公的年金制度が将来国民に支払うことを約束している年金総額は、実に五二九兆円(国民年金一〇〇兆円、厚生年金三二〇兆円、共済年金一〇九兆円)という天文学的な金額。しかも現在支給中の分は除いた金額である。この金額は現在のGNP(国民総生産)の二倍であるから、飲まず食わずに只働きしても二年間かかる大変な金額である。
これに対して、資産(積立金)の方は三者を全部合わせても約四〇兆円。従って、資産の十三倍もの約束手形を振り出していることになる。一方毎年の収入(保険料)は三者全合計で八・四兆円、支出(給付金)は四二兆円で、差し引き不足の三三・六兆円をどうするか。資産を全部喰い潰しても一年ともたないから、結局は次世代からの税金に頼らざるを得ない。昨今、結婚を嫌うシングルが増えているが、この人たちの年金は誰が負担するのか。結局は他人の子におんぶするわけだから、こんな虫の良い話が通用するはずがない。やがて、欧米並に子育ての人数に応じた掛け金負担になるだろう。
現に経済審議会のレポート『二千年の日本』によれば、西暦二千年(平成十二年)の年金受給者は四・八倍にふくれあがる。そこで一九九一年から積立金を取り崩しにかかると、一九九八年には積立金はゼロとなる。つまり不渡り手形となるわけ。そこで年金制度の見直しとなった。このまま推移すれば、年金制度自体が破綻することは明らかであるからだ。
一例を示そう。四二万人の職員が加入していた旧国鉄共済年金では、現役十人でOB十二人分の年金を負担していた。これではパンクするのが当然で、民営化したJRではこのツケが大きな足カセとなり、そのシワ寄せをどうするのか。
しかも年金だけではない。これに追い打ちをかけるのが医療費急増の重圧。厚生省試算では西暦二千年の医療費を四四兆円(現在の約二倍)と見積もっているが、沖中記念成人病研
究所の予測ではGNPの一七%(約五八兆円・現在の三倍)と弾いている。
いずれにせよ、医療費膨張は今後十年間に二~三倍にふくらむ勘定で、すでに日本経済は「医療・年金」の両面から崩壊し始めているのだ。〝福祉に追い付く稼ぎなし〟 -、と思えてならない。
しかも無気味なことは、次代を背負う若者たちの健康状態が急速に悪化していることだ。
118P
崩れた長寿神話 - 平成元年は早老・早死元年!?
以上が西丸説の概要であるが、平均寿命の算出に当たって、現在の生活条件の悪化を折り込んだ点が極めて合理的であり、自然医学の立場からも大いに参考になる意見である。ところで、現在の平均寿命の伸びをもって医学・栄養学の進歩とする考え方については、かねてから多くの批判が出されていた。筆者も昭和三八年に 「ニッポン放送・療養講座シリーズ」でこの問題を取り上げたことがあるが、当時は時期尚早で全く問題にされなかった。ところが、十数年たってから、カナダ政府が政府刊行物『健康展望』で、平均寿命の統計的カラクリを批判する論文を掲載。その後、アメリカ上院・栄養問題特別委員会において、リー博士(カリフォルニア大学健康政策教授)とスタムラー博士(国際心臓病会議議長)の二人が、「平均寿命の伸びだけを強調することは統計上の錯覚を招き、国民の正しい判断を誤らせて、結果的に国民を騙すことになる」と激しく警告して大きな話題を呼んだ。
指摘された問題点を纏(まと)めると、
一、零歳(および乳幼児)の平均余命(平均寿命は零歳の平均余命)が伸びたことは正しい。
しかし、
二、中・高年層の平均余命はほんの僅かしか伸びておらず、むしろ縮む傾向が見られ、近い将来急速に短命化する惧れがあること(西丸説と同じ)。
三、国民(特に老人)の有病率が増加し、医療費が急増していること。
四、これらの原因は、今の食事が誤っているためで、その改善を図らないかぎり、短命化は避けられない。
ということで、いまや長寿神話は揺らぎ、このまま進めば間もなく早老・短命化時代が出現することになろう。
この意味において、先程紹介した簡易生命表が、各年代とも一斉に平均余命の対前年比がマイナスに転じていることは極めて象徴的であり、短命化時代への転機を示す兆しと言えよう。
栄耀栄華(えいようえいが)と長寿の夢を追い続けた物質万能時代は終わりを告げ、次代は精神文明を基調にして、自然と共に生かされる〝天寿全う時代〟へと転換するであろう。
119p
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
その前の項
再掲になるかな?
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
105P
第九章、 早老・早死時代の到来
--回避の道は素食・小食のみ・-
欧米の三倍の速さで高齢化社会へ突入
人生僅か五十年 -。
かつて歌にも謡われた時代に比べて、今、日本人の寿命は大幅に伸び、人生八十年時代が出現した。
長い人間の歴史の中で、平均寿命が七十歳を超えたのはつい五十年ほど前のこと。この水準に到達するまでにヨ-ロッパでは三百年かかったが、日本では明治以来百二十年で欧米を抜き世界一の超高齢化社会に突入した。欧米に比べて、実に三倍の猛スピード。特に戦後四十年間で三十年も寿命が伸びた(図1)。
この数字を見れば、誰しも近代科学、特に医学・栄養学の進歩のお陰とその成果を誇り、この分で進めば人生百年時代の出現も間近いことと思うであろう。
では日本人の寿命はこの先どれぐらい伸びると予想されているのだろうか。
106P
弾きだされた平均寿命の限界
厚生省の試算では、三十年後(西暦二千二五年)の日本人の平均寿命は男性七七・八七歳、女性八三・八五歳と見積もられている。
この試算に対して、厚生省で十一年間人口統計にたずさわったこの道の専門家、菱沼従伊氏(現第百生命専務)は、「人間の寿命には限界がある」との見地から計算し直した結果、男性七七・四一歳、女性八一・七〇歳が日本人の平均寿命の限界と弾きだしている。
どちらの数字が正しいかはさておき、日本人の寿命もそろそろ頭打ちというのが現状。すでにその兆しは最近の人口調査で現われてきた。
男女とも平均寿命が短縮
次表は、昭和六三年度の各年代の平均余命を示したものである。
この数字を見る限り、女性の平均寿命は八一、三〇歳で依然として世界第一位であり、男性のそれは七五・五四歳であって、やはりトップクラスである。しかし、よく見ると前年度に比べると女性は〇・〇九歳、男性は〇・〇七歳寿命が縮まっている。特に五五歳以上の平均余命は、男性では〇・一六歳、女性は〇・二一歳と大幅に縮まっている。平均余命とは年令ごとに前年度の死亡率が変わらないものとして、あと何年生きられるかを計算したもの。零歳児の平均余命が国民の平均寿命となる。
このように男女とも平均寿命が短縮した理由として、厚生省では「昨年二月のインフルエンザ流行が直接、間接に影響した」と分析、「来年は再び伸びに転じる」と強気の説明をしている。
だが、果たしてそうなのだろうか。 表をよく見ると分かるように、各年代とも平均余命の前年度比は一斉に縮んでいる。実は、中年すぎの平均余命はずっと以前から伸び悩んでいたのだが、今回のように一斉に縮んだことは初めて。しかもこの他にも憂慮すべき現象が見られるから、むしろ短命化の始まりと見るべきなのだが……。
この問題はあとでもう一度取り上げることにして、話を先に進めよう。
108P
有病率が高く実際は〝長寿地獄″
「お年寄り(六五歳以上)の半数は病気もち」 ーー、厚生省が毎年発表する『国民健康調査』の結果である。因みに国民全体の有病率は、人口千人当たり一三八・二人(八人に一人の割合)。調査を始めた昭和二十八年当時に比べて三倍も増え、六五歳以上では実に六倍に及んでいる。しかも毎年着実に増え続けているから不気味。一億総半病人時代と言われる所以である。
こんな国は世界中探してもどこにもなく、要介護老人の国際比較では欧米の三倍にもなっているのだ。
つまり、世界一の長寿国と言っても名ばかり。その実態は病人だらけで、むしろ〝長寿地獄〟と言った方がふさわしい。
この状態が今後とも続けば、一体どうなるのだろうか。
専業主婦を上回るボケ・寝たきり老人
ボケ老人 二二三万人、寝たきり老人 二〇二万人ーー、
日大・人口研が予測(昭和六一年十二月三日)した西暦二千二五年(平成三七年)の日本の姿である。
現在、日本の総人口は約一億二千万人、老年人口(六五歳以上)は千二百万人で、このうちボケ老人は六九万人、寝たきり老人は六八万人である。これが三十年後(西暦二千二五年)には総人口一億三千二百万人に対して、老年人口は約二・五倍の三千二百万人(総人口の四分の一)に増え、この時ボケ老人と寝たきり老人は現在の三倍(二倍になるのは二十年後)に増えると予測されているわけだ(図2)。
今でさえボケ老人や寝たきり老人が大きな社会問題となっているのに、この先二倍、三倍と増えたらどうなるのか。
仮に四五~五五歳の専業主婦がそのお世話をするとすれば、二十年後には主婦一人当たり一人のボケ老人や寝たきり老人をかかえる計算になり、三十年後には一人当たり一二一三人の割合となって、完全に専業主婦の数を上回ることになる。
また五十年前(戦前)は若者十三人で一人の老人を養っていたが、いまでは半分の六人、十年後には四人、三十年後には二人で一人の老人を養わねばならなくな
る。
つまり長寿国とは若者にとって高負担な社会であり、長生きのツケはすべて次代の孫子に負わされるわけだ。
今消費税の増額をめぐって大騒ぎしているが、十年後にはどうなるか、事態はきわめて深刻なのだ。
長生きは大いに結構。だがそのためには〝健康は自分で守る〟ことが鉄則。人に迷惑をかけない ー という自覚と責任をもたなければ、長生きをする資格はないことを銘記すべきであろう。
国連WHOがPHC(プライマリ-・ヘルスケアー)政策を掲げ、〝健康は自分で守る〟政策を真剣に呼び掛けているのはこのためである。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
さて、ボケ老人は増えたのだろうか? あれから20年
あ、ボク?
よくワカンナ~~イ (だって、ボケ本人には分からないわけね)












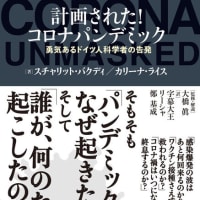
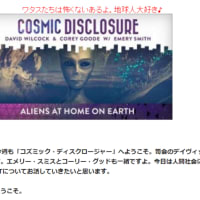
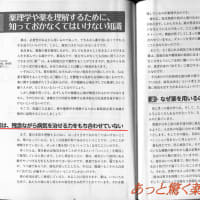
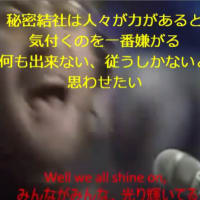
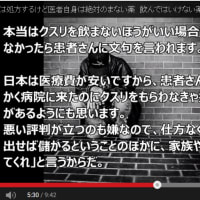

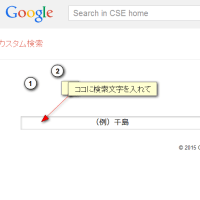
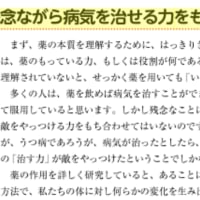







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます