長い間当たり前のように行われていた盲腸の切除手術(本当は虫垂の切除)が見直されて来たと言います。
無用な存在(存在理由が分からない医学が不要としただけのことだったが)
が、今は有用だとわかってきた (生物学の進歩によってだが)そうです。
現代医学では「虫垂の手術など朝飯前」くらいの軽い手術だったようですが、これも医学が全然人体の機能を理解できなかっただけの事でした。
世間で言われている「手術の進歩」を「医学の進歩」と錯覚していることに気づかない人が多すぎますが、虫垂にしても扁桃腺にしても(昔は簡単に切り取ったというほど、不要なものにしていた)簡単に人体を切り刻むことが現代医学の進歩のように思い込んできたのです。
だが、進歩すればするほど「退歩していた事に気づく」という皮肉な話です。
最近は、医学の進歩によって手術の数が増えたと言われていますが、じつは岡田茂吉氏は「手術の進歩は、技術の進歩であって医学の進歩では無い」と述べていました。
そこで古い(昭和18(1943)年 ながらもお役に立つかも知れないと思いますので。
岡田茂吉医学論文より
ーーーーーーーーーー以下転載ーーーーーー
扁桃腺炎、盲腸炎、手術・病患と医学の誤謬
『明日の医術(再版)第二編』昭和18(1943)年2月5日発行
病患と医学の誤謬
西洋医学における誤謬は、事実を基礎として理論的には充分説いたつもりであるが、なお重(おも)なる病気に対し、実証的に検討してみよう。
一、扁桃腺炎、盲腸炎、手術
現代医学の診断において、誤謬の頗る多い事は、多数の患者を取扱われた経験豊富の医家はよく知っているはずである。
何よりも医科大学において、診断と解剖の結果とを照合してみれば、思半(なか)ばに過ぎるであろう。
まずそれらについて、事実によって順次解説してみよう。
近来、最も多い病気として扁桃腺炎なるものがある。
この病気は大抵の人は経験しているはずであるから、まずこれから採り上げてみよう。
元来、この扁桃腺なる機能はいかなる役目をしているものであるか、又扁桃腺炎なるものは、いかなる理由によって発病するものであるか、恐らく医学においては未だ不明であろう。
何となれば、手術によって除去するのを最上の方法としている位だからである。
そうして手術の理由としては、扁桃腺は不必要であるばかりではなく、反って有害な存在であるとしている。
故にもし医学で言うごときものとすれば、それは人間を造った程の偉大なる造物主が、無益にして有害なる機能を造ったという訳である。
医学が不必要視するものを、造物主は必要とされたのである。
――という事はまことに不可解極まる話ではあるまいか。
仮にそうだとすれば、造物主の頭脳よりも医学者の頭脳の方が優れているという事になる。
造物主即ち神よりも、人間である現代の医学者の方が上位であるとは驚くべき潜〔僭〕越である。
しかるに実は、医学者といえども、造物主に造られたのではないか。
医学者がいかに学理を以てするも、一本の睫(まつげ)一ミリの皮膚さえ造り出す事は到底不可能であろう。
故に、扁桃腺が不必要というのは、その存在理由が未だ判明しないに関わらず、判明したように錯覚した結果が手術を生んだというべきであろう。
しからば、扁桃腺なるものは何が故に存在するのであるか、私の発見によれば、非常に重要なる使命を果しているのである。
それは人体において、最も毒素が集溜し易いのは頸部淋巴(リンパ)腺付近である。
そうしてこの集溜毒素は、浄化作用によって排泄されなければならないので、さきに説いたごとく、第一浄化作用によって一旦扁桃腺に毒素が集溜し、凝結し、それが第二浄化作用の発熱によって溶解し、液体となって排泄せらるるのである。
即ち、扁桃腺は、毒素の排泄口である。
この理によって、扁桃腺の起った場合、放置しておけば、浄化作用が順調に行われ、普通二三日で治癒するのである。
しかるに医療はこの場合、ルゴールの塗布や氷冷、湿布、下熱剤等よって浄化作用の停止を行うから、浄化作用とその停止との摩擦を起し、治癒までに相当の時日を要するという事になる。
そうして一時治癒したとしても、実は真の治癒ではなく、浄化発生以前に還元させたまでであるから、扁桃腺固結は依然としている。
しかしそればかりではない。
その後に集溜する毒素が加わって、固結は漸次増大する。
再び浄化が起る。
また浄化を停止し還元させる。
かような事を繰返すにおいて慢性症となり、固結はいよいよ膨大する。
これを扁桃腺肥大症というのである。
そうして、手術除去をすすめるのであるが、何ぞ知らん、除去しなければならない程に膨大させたのは、医療の結果であるのである。
そうして、この様に膨大した扁桃腺は、発病するや激烈なる浄化作用が起るから、高熱は勿論の事、患部の腫脹はなはだしく、喉頭は閉鎖され、はなはだしきは、水一滴さえも飲下する能(あた)わざる程になるのである。
かような悪性扁桃腺炎を恐るるが故、除去を勧むるという事になるのである。
しかるに自然治癒によれば、扁桃腺炎は、一回より二回、二回より三回というように、漸次軽症となり、ついに全く扁桃腺炎は発病しない事になるのである。
ここで、脳貧血について一応説明しておこう。
これは扁桃腺炎に関係があるからである。
それは仮に、頸部淋巴腺に集溜する毒素が、その排泄口である扁桃腺が失(な)いとしたならどうなるであろう。
それはそのまま淋巴腺付近に停溜固結する。
その固結が頭脳に送血する血管を圧迫するから、頭脳の血液が不足する。
それが脳貧血であり、神経衰弱でもある。
頭脳が朦朧(もうろう)として圧迫感や不快感等の患者が、近年非常に多いのは全く右のごときが原因であることもすくなくないである。
そればかりではない。
扁桃腺を固結させるか、又は除去した場合、淋巴腺集溜毒素は出口を他に求めるの止むなきに至る。
それは、反対の方向に流進して排泄されようとする。
即ち耳下腺を通って中耳に到り、鼓膜(こまく)を破って排泄されようとするのである。
その際、高熱によって液体化した毒素は耳骨を穿孔(せんこう)しようとする。
その痛みと発熱を中耳炎というのである。
近来、中耳炎患者の増加したのも全く右の原因による事もあろう。
扁桃腺炎なら、軽症で済むべきものを、医療はより重症である中耳炎にまで発展させる訳である。
そうして中耳炎の場合必ず氷冷法を行うから、液体毒素は方向を転換するのである。
即ち中耳に向って流進していたのが、頭脳に向って転進するのである。
これを医師は“中耳炎に因る脳膜炎”というのである。
かように扁桃腺炎を中耳炎に発展させ、ついに脳膜炎まで起させるというのは全く驚くべきである。
次に、盲腸炎について説明してみよう。
これも近来非常に多い病気であって、扁桃腺炎と同じく手術除去を奨めるのである。
そうして医学では多く食物に原因を置いている。
彼(か)の、葡萄の種が原因という学説であるが、私はいつも嗤(わら)うのである。
葡萄の種位で盲腸炎が起るとすれば、柿の種や魚の骨など嚥下(えんか)したら即死するであろう――と。
そうして医療においては、最初氷冷によって浄化を停止し、還元させようとするかないしは直ちに手術を行うのである。
そうして速かに手術せざれば化膿し、虫状〔様〕突起が破れて急性腹膜炎を起すというが、これも誤りである。
そうして、盲腸手術の結果予後良好で、健康時の状態となったとしても、慢性腹膜炎及腎臓病が起り易くなるのである。それらは、いかなる訳であるか。
左に詳説してみよう。
そもそも、盲腸炎の原因は何であるかというとそれにはまず、盲腸なる機能の役目から説かねばならない。
身体不断の浄化作用によって下半身の毒素溜結個所として、盲腸部は上半身の扁桃腺と同じ様な意味である。
即ち、第一浄化作用によって盲腸部へ毒素が溜結するのである。
その際同部を指頭にて圧診すれば、大小の痛みを感ずるのである。
そうして重痛は毒素溜結が強度に達し、盲腸炎即ち第二浄化作用の近づいた徴候であって、軽痛は、毒素の溜結が軽度又は少量なる為である。
又その際盲腸部以外の腹部を圧診する時、痛苦があれば腹膜にも毒素溜結があって、急性腹膜炎合併症の前兆である。
しかしながらここで面白いのは、全身的に衰弱している時は第二浄化作用は起り得ないもので、第二浄化作用が起り得るのは活力旺盛であるからである。
故に過激な運動を行った後など起り易い事と、青壮年時に起り易いという事はそういう意味である。
又第二浄化作用が起るまでに毒素が溜結するには、大抵数年ないし十数年の長時日を要するものであるから、幼児又は小児にはほとんどないにみても明かである。
右のごとき理によるのであるから、盲腸炎発生の際は放任しておけば容易に治癒するのである。
即ち高熱によって溜結毒素が液体化し両三日経て下痢となって排泄せられ治癒するのである。
右の毒素溶解を医学では化膿といって恐れるのであるが、実は化膿するから治癒するのである。
即ち化膿した時は下痢の一歩手前であるから半ば治癒したと見なしてよいのである。
故に、盲腸炎発生時の養生法としては、一日断食、二日目三日目は流動物、四日目五日目は粥、六日目から普通食で差しつかえないまでに治癒するのである。
そうして自然療法による時には、激痛は半日ないし一日位軽痛二日間位で、四日目からは室内歩行が出来る位になるから、何ら恐るべき病気ではないのである。
そうして、盲腸炎の根本原因としては、右側腎臓部に硬度の毒素溜結があり、その為の萎縮腎による余剰尿が盲腸部に溜結したのであるから、右の毒結を解消するにおいて決して再発はないのである。
又、腹膜炎併発は盲腸に直接関係はないのであって、これは、腹膜部の毒素溜結が同時に浄化作用を起す為である。
その際医療は手術をすすめる事もあるが、これは予後不良である。
故に医師によっては手術を避け、他の療法によって浄化作用を停止し、還元させようとするのであるが、それには非常に長時日を要するので、その結果は漸次腹部の毒素は固結し、板のごとくなり、その圧迫によって胃腸障碍を起し食欲不振となり、衰弱はなはだしく多くは斃(たお)れるのである。
これは、自然療法によるも、三日間位は激痛を堪え忍ばなければならないし、その間絶食のやむなきに至るのである。
しかし、医療によって生命の危険に曝(さら)すよりも、必ず治癒するのであるから、三日や五日位の忍苦は何でもないであろう。
そうしてその結果、猛烈なる下痢を起し、完全に治癒するので、普通二三週間位で治癒し、勿論再発の憂は絶無である。
ここで、手術について一言を挿(さしはさ)む事とする。
今日医学の進歩をいう時、必ず手術の進歩を誇るのである。
これは一寸聞くともっとものようであるが、実は大いに間違っている。
何となれば患部の機能を除去するという事は、人体における重要機能を消失させるので、他に悪影響を及ぼすのは当然である。
なるほど手術後一時的ある期間は安全であるが、浄化作用の機関が失くなるとすれば、毒素は他のあらゆる機能を犯す事になるからである。
それは不自然な方法が齎(もたら)す結果としてそうあるべきである。
最も高級で微妙極まる人体の組織であるから、たとえいささかの毀損(きそん)も全体に悪影響を及ぼさぬはずはないのである。
これをたとえていえば、いかなる名画といえども、画面の一部が毀損さるれば、それは全体の毀損であり、価値は大いに低下するであろう。
又家屋にしても、一本の柱、一石の土台を除去したとしたら、直に倒れないまでも、その家屋の安全性はそれだけ減殺される訳である。
そうして手術は、病気の除去ではない。
病気と共に機能を除去するのであるから、いかに理由づけようとしても、医術の進歩とはならないであろう。
私は真の医術とは、病気そのものだけを除去して、機能は以前のまま、生れたままの本来の姿でなくてはならないと思うのである。
そうして手術は外部即ち指一本を除去するとすれば不具者として恐れられるが、内臓なるがため直接不自由と外観に影響しないので左程恐れられないのである。
故に私は惟(おも)う、手術が進歩するという事は、医学が進歩しないという事である。
即ちメスによって患部を欠損させ治療の目的を達するというまことに原始的方法を以て唯一としているからである。
この意味において、今日称(とな)うる手術の進歩とは、医術の進歩ではなく“技術の進歩”であると、私は言いたいのである。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
全部を鵜呑みにする必要はありませんが、この手術のなかでも長い間当たり前のように行われてきた「盲腸の切除手術」 は実は誤りであった・・・と、ようやく気づいてきたのが生物学のようです。
じつは盲腸(虫垂)は切り取ってはいけない。不要どころか有用な器官だったと言うのです。
医学の方ではどうなっているのでしょうか? 医学は生物学を基礎として成り立っているわけですから、この生物学を無視してはいけないわけです。
近代医学がいかに間違っているかに気づくのはまだまだ時間がかかるかと思いますが、本当に進歩の暁には、なんと!「ほとんどの医療が「やらない方が益しだった」と気づく時が来る」と・・
そんな事をど素人が言うな!! とお怒りでしょうが、全部とは言わずとも盲腸切除(本当は虫垂の切除と言うのでしょうが、一般的には盲腸と言われているので)を例にとってみると、気づくのになんと時間がかかったのだろうかと思うわけです。
そこで、ネット上から盲腸(本式は虫垂のことだろうが、一般的に盲腸としました)についての記事を参考に。
TITLE:盲腸は医学の盲点
- 原典聖書研究 - Yahoo!ブログ -
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/semidalion/49669839.html
より以下転載・・・・・ーーーーーーーーーーー
最近は虫垂炎なんていう病気は見かけなくなりましたよね。その原因をご存じでしょうか?
本当の原因は何とバリウム検査です。次が抗生剤の投与による腸内細菌の消滅と腐敗菌
の腸内異状繁殖と便通の阻害によるいわゆる糞詰まりによる虫垂内の逆流便腐敗です。
だから虫垂炎は全て医原病という次第です。
さて問題はこの虫垂は人の免疫機能を司る最重要器官の一つで切除などはとんでもな
い蛮行です。 まあ世界人類の医学は未開人のレベルですから医者がそんな嘘に騙された
りそれを真に受けて摘出していますがそれはとんでもない犯罪という事になります。
以下は最近になって漸く西洋医学も虫垂の重要性に気づき始めた事を報じる未開人の
ネットニュースです。
そうそう、虫垂の免疫器官としての重要性は最近ちゅうもくされている「あなたの身体は9割りが
細菌」とか「人の命は腸が9割り」 「身体の中の外界 腸の不思議」 「大便通」 「脳はバカ、腸は賢い」
などという最新の免疫関係著書を是非お読みください。
盲腸の手術で不要と切除されてきた虫垂、実は進化した器官で役立っているらしい
人体に不要なものなんてないんです!
進化の世界において、虫垂ほど科学者たちを悩ませてきた器官はないそうです。かの有名なチャールズ・ダーウィンは、昔、霊長類が樹上生活をしていたころ、木の葉を食べて消化するために使われていた器官だと主張。不要になってから、ずいぶんと長い歴史を経てきたものの、いまだに人体に虫垂として残り続けていると説かれもしてきました。
(中略)
ところが、このほど電子ジャーナルの「Comptes Rendus Palevol」に発表された論文によれば、虫垂は進化に逆行するどころか、身体に必要なものとして進化を遂げてきた重要な器官だと説明されています。虫垂なんて不要と盲腸の手術で切除してしまうと、かえって人体にはダメージがおよぶとも指摘されていますよ。
同論文の発表のもととなる研究には、欧米各国および南アフリカの大学の研究者たちが参加。世界各地で533の哺乳類を調べ、虫垂の働きを調査しました。虫垂をもたない哺乳類も少なくはないものの、1つの種のなかに虫垂を有する個体が出ると、種の繁栄に伴って虫垂が消えることは殆どないことが判明したそうです。
また、虫垂を有する哺乳類と虫垂をもたない哺乳類を比較してみると、虫垂を有する哺乳動物のほうが、盲腸内にリンパ組織による高い免疫系が整っていることが明らかだったそう。虫垂のリンパ組織は、特定の良性バクテリアの成長を活性化させ、腸内細菌の培養に役立っていると説明されています。
免疫を高めるうえで、虫垂が重要な役割を果たしているということは、盲腸の手術なんかで切除してしまったらいけないのでしょうか? 通常の生活に支障をきたすことはないそうですが、今回の発表論文では、虫垂切除後に若干の免疫力低下は避けられないと警告されていますよ。病気の快復に、少しですが周囲より時間がかかるといった傾向も観察されているんだとか。虫垂の役割と盲腸の手術における扱いが、見直されることになりそうですよね…。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
もうひとつ
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
虫垂は腸に免疫細胞を供給、虫垂むやみに取らないで、
腸内細菌のバランスを保つために
TITLE:虫垂は腸に免疫細胞を供給、虫垂むやみに取らないで、腸内細菌のバランスを保つために -
URL:http://www.menekiplaza.com/column/tyusui.html
盲腸と虫垂を同じものだと思っている人が多くいます。盲腸炎と言うのは古い言い方で、最近は虫垂炎というのが正しいと思っていませんか? 当然、盲腸炎と虫垂炎は異なるものです。
盲腸は小腸と大腸の境目にあり、盲腸の先端にぶら下がるようにくっついている袋状の突起、これが虫垂です。長さは5~10cmで、直径は1㎝にも満たない小さな臓器です。
さて進化の過程で、盲腸そのものを退化させてしまった動物さえ多くいるのに、わずかの痕跡程度ですが、まかり間違えば命さえ危ない「虫垂」が、人の体に何故残っているのでしょう。
虫垂、免疫細胞を供給・腸の免疫力を保つそれはこれまでの研究で知られている通り、免疫の役割が虫垂にあるからです。腸の内壁は極めて薄く養分を吸収しやすい分、異物や細菌にも侵入されやすく、そのために腸の各所に免疫細胞を配置させておく必要から、特に虫垂にその免疫力の任を集中させました。
このように、この小さな虫垂は、大切な働きをしています。虫垂は非常に発達したリンパ組織を持っており、腸内の免疫機能をコントロールしています。
私たちの腸の中には、およそ300種類の腸内細菌が100兆個以上いるといわれていますが、これらの細菌は、互いにバランスを取りながら、腸内の抵抗力を高めたり、消化吸収を助けるなどの役割を果たしています。しかし、腸内細菌のバランスが崩れることもあり、ここで、虫垂のリンパ組織は、バランスを崩そうとしている細菌をすぐさま察知し、白血球を使って攻撃を行います。虫垂は、こうして、腸内の免疫機能を維持しています。
にもかかわらず、これまで、虫垂炎の手術で虫垂をとってしまっても、それで体が弱くなるという事はなく、虫垂が免疫力の機能はあるものの、現代医学はそれを上回る機能を持っている(?)ことから、現代では特に必要としないものとして軽んじて来ました。
しかしここへきて、新たな研究の結果、免疫力を保ち、腸内細菌のバランスを保つ上でも、虫垂をむやみに取らないように、阪大の研究チームが提言しています。
下記の記事は、日本経済新聞の2014/4/11付朝刊「虫垂むやみに取らないで」「腸内細菌のバランス保つ」「 阪大など、治療に応用期待」と言う記事の転載です。
体に必要ない組織と考えられていた虫垂が腸に免疫細胞を供給し腸内細菌のバランスを保っていることを大阪大などのチームがマウスで明らかにし、10日付の英科学誌ネイチャーコミュニケーションズ電子版に発表した。
チームの竹田潔大阪大教授(免疫学)は「バランスが悪くなると食中毒も起こしやすい。虫垂をむやみに取らない方がよい」と話す。腸内細菌のバランスが崩れて発症する潰瘍性大腸炎やクローン病の新しい治療法開発も期待される。
虫垂は盲腸の端から伸びる細長い組織。体内に侵入した病原体などを攻撃する免疫細胞を作る働きを持つ。だが虫垂炎を起こすことがあり、他の病気の開腹手術の際、大きな影響が出ないとして切除されることがある。
チームは虫垂を切除したマウスと、していないマウスを比較。切除したマウスの大腸内では、腸内細菌のバランス維持を担う抗体を作る免疫細胞が半分になっており、バランスも崩れていた。虫垂でできた免疫細胞が大腸と小腸に移動していることも確かめており、虫垂が腸内細菌のバランスを保つのに役立っていることが分かった。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
チュウ吸い やっぱり必要だったのですね~
チュウチュウチュウ ああ 吸いたい
ところで
昔はドンドン切り取って(∋_∈)シマッタ 扁桃腺 ですが・・・どうなったんでしょうね。
今はもう「必要」だと気づいたのでしょうか? 現代医学ではどうなってんでしょうね?
ね?
・・・・・・・・・・・・・
へんとうせん・・・・












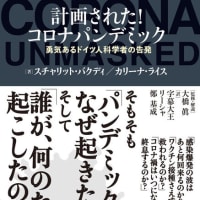
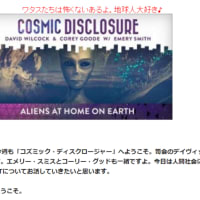
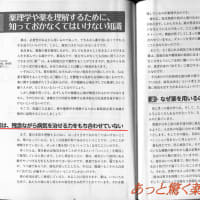
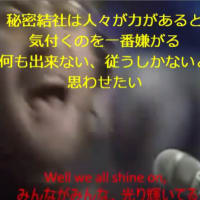
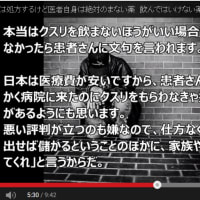

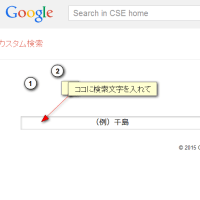
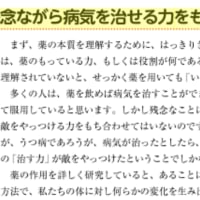







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます